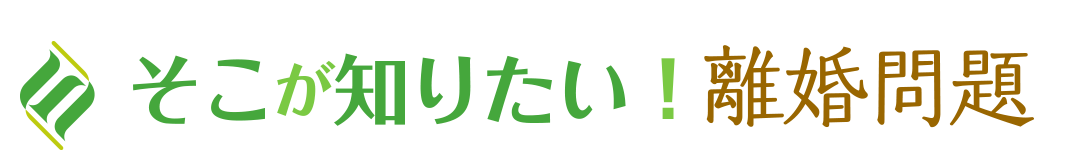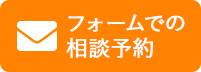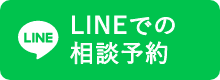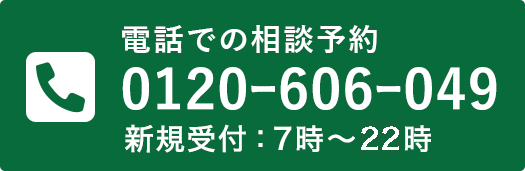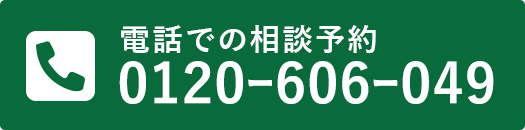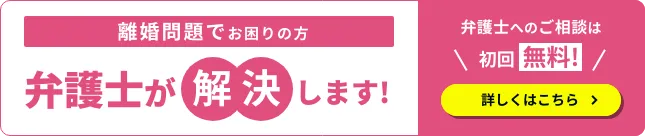

- 監護権とは?
- 監護権を変更することはできる?
- 監護権を変更する方法とは?
【Cross Talk 】離婚後に監護権者を変更することはできますか?
離婚してから監護権者を変更することはできますか?
離婚後であっても監護権者を変更することはできます。
離婚後の監護権の変更について詳しく教えてください。
離婚後、子どもと暮らす「監護権者」は、一度決まれば二度と変更できないというものではありません。監護環境の変化や、子どもの成長に伴う状況の変化により、監護権者の変更が必要となることがあります。この記事では、監護権の基本的な意味から、その変更が可能かどうか、そして具体的な変更方法や考慮されるべきポイントなどについて、弁護士が解説していきます。
監護権とは?

- 親権と監護権の違いとは?
- 親権者と監護権者を分けることはできる?
監護権とはどのようなものなのでしょうか?
ここでは、監護権の概要について解説していきます。
監護権とは?
監護権とは、未成年の子どもの生活を実際に世話し、教育を行う親の権利と義務を指します。具体的には、子どもと一緒に生活し、衣食住を提供したり、学校に通わせたり、しつけをしたりといった、日常的な世話や健全な成長を促すための活動全般が含まれます。
監護権の主な内容としては、以下のようなものがあります。
監護権と親権の違い
監護権と混同されやすいものに親権がありますが、両者には明確な違いがあります。
親権とは、未成年のお子さんを監護・教育し、その財産を管理する親の包括的な権利義務全体を指します。親権は、大きく分けて「身上監護権(監護権)」と「財産管理権」の2つの要素から構成されています。
身上監護権(監護権)は、上述の通り、子どもの身の回りの世話や教育に関する権利義務であるのに対して、財産管理権は、子ども名義の財産を管理し、契約などに対して同意を与える権利義務です。
つまり、監護権は親権の一部であり、親権に含まれる権利の一つという関係にあります。通常、親権を持つ親が監護権も行使し、子どもと一緒に生活することになります。
関連記事:親権と監護権はどっちが強い?違いや分けるデメリットを解説
親権者と監護権者を分けることはできる?
原則として、親権者が監護権も行使し、お子さんと同居して世話をするのが一般的ですが、例外的に親権者と監護権者を分離することも可能です。
例えば、離婚時に親権を巡る争いが激しく、話し合いがまとまらない場合に、時間の短縮や子の福祉を優先するために、財産管理能力のある親を親権者としつつ、実際に子どもの世話をしてきた親を監護権者とすることなどが考えられます。また、親権者となった親が海外転勤などで子どもと同居できない事情がある場合、もう一方の親が監護権者としてお子さんと暮らすこともあります。
ただし、親権者と監護権者が異なる場合、例えば監護権者には子どもの財産を管理する権限はないため、財産管理に関する手続きなどでは親権者の同意や協力が必要となるなど、不便が生じることもあります。
そのため、両者を分離する際には、お子さんの利益を最優先に、慎重に検討し、後々のトラブルを防ぐために明確な取り決めを行うことが重要です。
監護権者を変更することはできる?

- 監護権者を変更することはできる?
- 監護者の変更は父母の話し合いでできる
あとから監護権者を変更することはできるのでしょうか?
ここでは、事後的に監護権者を変更することの可否について解説していきます。
監護権者は、一度定められた後でも、状況の変化に応じて変更することが可能です。
子どもの健やかな成長と利益のため、監護の現状が適切でないと判断される場合、その変更が検討されます。
まず、最も望ましいのは、父母が話し合いによって監護権者の変更に合意することです。この場合、家庭裁判所の手続きを経る必要はありません。市区町村役場への届出も不要であるため、当事者間の合意が成立すれば、速やかに監護者を変更できます。しかし、父母間の話し合いで合意が得られない場合や、一方の親が監護に不適切な状況にあるといった問題がある場合には、家庭裁判所に監護者変更の調停または審判を申立てる必要があります。
監護者の変更が認められやすい場合としては、現在の監護権者が育児を放棄していたり、現在の監護権者が重い病気で子どもの面倒を見ることができなかったりなどです。
また、監護権者が子どもに対して身体的・精神的な虐待を行っている事実が明らかになった場合や、子どもがある程度の年齢に達し、現在の監護者とは別の親との生活を強く希望する場合も、事後的に監護者を変更が認められる可能性があるでしょう。
監護権者を変更する方法

- 監護権者を変更する方法とは?
- 協議が調わない場合には調停・審判を申立てる
監護権者を変更するにはどうすればいいのでしょうか?
ここでは、監護権者を変更する方法について具体的に解説していきます。
父母の話し合いによる監護権者の変更
監護者を変更する方法として最も簡単なのは、父母の話し合いによる合意に基づき監護権者を変更する方法です。
親権者の変更には家庭裁判所の関与が必須ですが、監護権者の変更は、父母双方の合意があれば、家庭裁判所での手続きは不要です。また、戸籍の記載事項ではないため、市区町村役場への届出も必要ありません。
この方法の最大のメリットは、時間や費用をかけずにスムーズに手続きを進められる点です。
ただし、後々の認識のずれやトラブルを防ぐためにも、口約束で終わらせるのではなく、監護権者を変更する旨、その理由、変更後の監護体制などを具体的に記載した離婚協議書や合意書などを作成し、公正証書として残しておくことをおすすめします。
調停による監護権者の変更
父母間の話し合いで監護権者の変更について合意に至らない場合は、家庭裁判所に監護者変更の調停を申立てることができます。
調停では、裁判官1名と2名の調停委員からなる調停委員会が間に入り、父母双方の意見を聴きながら、話し合いによる解決を目指します。調停委員会は、子どもの監護状況、現在の監護権者の監護能力、申立人の監護能力、お子さんの意思などを総合的に考慮し、子の利益を最優先に考えた解決策を模索します。
調停で合意が成立した場合は、「調停調書」が作成されます。この調停調書は確定判決と同じ法的効力を持つため、記載された内容は守る義務が生じる公文書となります。しかし、あくまで話し合いがベースの制度であるため、双方が合意に至らず調停が不成立となることもあります。その場合は、自動的に次の審判手続きへと移行します。
審判による監護権者の変更
調停が不成立となった場合、または緊急性が高く調停手続きを経る時間がないと判断されるような場合には、家庭裁判所の審判によって監護権者の変更が決定されることがあります。
審判では、調停のように話し合いで解決を目指すのではなく、裁判官が提出された資料や当事者の主張、家庭裁判所調査官による調査結果など、あらゆる事情を考慮して、最終的な判断を下します。この判断基準も、民法第766条1項に示されている「子の利益」が最も重視されます。
審判によって監護権者の変更が決定されると、「審判書」という公文書が作成され、これには法的拘束力があります。審判の結果に不服がある場合は、原則として2週間以内に不服申立て(即時抗告)を行うことができます。審判が確定した場合でも、戸籍の届出は不要です。
監護権者を変更するためのポイント

- 監護権者を変更するポイントとは?
- 監護権者側の事情と子ども側の事情を考慮する
監護権者を変更する際には何が重要ですか?
ここでは、監護権者を変更するポイントを解説していきます。
親の監護能力や監護実績
監護権者の変更は、子どもの生活環境や精神状態に大きな影響を与えるため、その判断は非常に慎重に行われます。父母の話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所の調停や審判で判断がなされますが、いずれの場合も「子どもの利益のために変更が必要であるか」という観点が最も重視されます。
監護権者の変更を検討する際、まず評価されるのは、現在の監護権者、そして変更を希望する親それぞれの「監護能力」と「監護実績」です。
離婚後、実際にどちらの親が主としてお子さんの世話や教育を行ってきたかという実績は、非常に重視されます。これは、慣れ親しんだ環境や生活リズムを継続できるかどうかが、子どもの安定に繋がると考えられるためです。
また、子どもの教育費や生活費を安定して賄える収入があるか、親が心身ともに健康であり、日常的に子どもの世話や教育を行える体力・精神力があるか、子どもが安心して生活できる住居環境や、学校・地域との連携が適切に保てるか、といった点が考慮されることになります。
子どもの状況・意思
監護権者を変更する際、子ども自身の状況や意思も非常に重要なポイントとなります。
子どもの年齢が幼いほど、特に母親との生活の継続性が重視される傾向があります(母性優先の原則)。
また、現在の生活環境に子どもがどの程度適応しているか、そして監護者が変更された場合に、新しい環境にスムーズに適応できるかどうかも考慮されます。頻繁な環境の変化は子どもの養育上好ましくないため、現在の環境の継続性も重視される傾向にあります。
さらに、子どもがどちらの親と生活したいかという意思は、年齢が上がるにつれてより強く尊重されるようになります。監護権者の変更の審判をする場合、家庭裁判所には15歳以上の子の意見を聴取する義務がありますが、10歳前後の子どもであれば、判断能力があるとみなされ、その意向が尊重される傾向があります。
まとめ
監護権は、子どもの具体的な世話や教育を行う親の権利であり、親権の一部です。一度定められた監護権者も、子どもの利益のために必要と判断されれば、変更が可能です。
変更には、父母間の話し合いによる合意が最も望ましいですが、合意が得られない場合は家庭裁判所の調停や審判を通じて決定されます。
裁判所は、親の監護能力や監護実績、お子さんの状況や意思などを総合的に考慮し、子どもとって最善の選択を行います。
監護権の変更についてお悩みの際は、ぜひ当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。