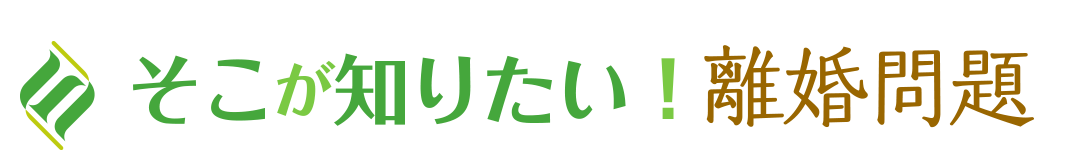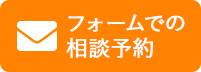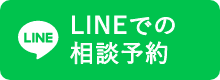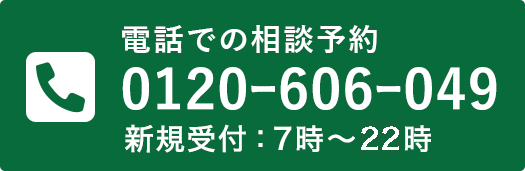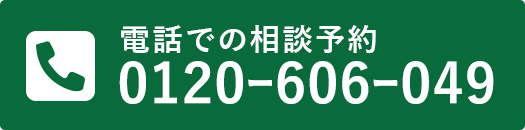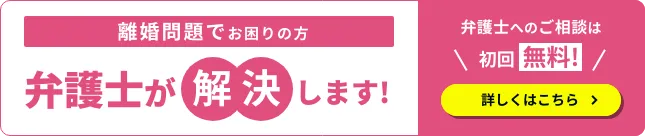

- 面会交流の平均時間はどのくらい?
- 面会交流の時間や回数は増やせる?
- 面会交流の変更は弁護士に相談すべき?
【Cross Talk 】面会交流の平均的な実施時間はどのくらいなのでしょうか?
離れて暮らす子どもとの面会交流の時間はどのくらいが一般的なのでしょうか?
面会交流の平均的な時間は、子どもの年齢によって異なります。
面会交流が実施される時間について、詳しく教えてください。
離婚が成立すると、夫婦関係は終了することになりますが、離婚したからといって親子関係が消滅するわけではありません。離婚して離れて暮らす親も法的に子どもの親であることは変わりません。そして、非監護親が子どもと交流することができる貴重な機会が面会交流です。それでは、面会交流とはどのようなもので、その実施時間はどれくらいなのでしょうか?また、面会交流の時間や回数は事後的に増やすことができるのでしょうか?
この記事では、このような疑問点について弁護士が解説していきます。
面会交流とは?

- 面会交流の意義とは?
- 面会交流の実施は子どもの利益を最優先に考慮して判断される
そもそも、面会交流とはどのような制度なのでしょうか?
ここでは、面会交流の意義や制度の趣旨について解説していきます。
「面会交流」とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと直接会ったり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。面会交流は、子どもの健全な成長を促すために重要な機会であり、子どもが両親から愛されていると感じられるようにするための貴重な機会です。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは両親間で話し合い、子どもの年齢、性別、性格、生活リズム、生活環境などを考慮して、子どもの精神的な負担にならないように柔軟に決めることが大切です。一般的には、月に1~2回程度、日中の数時間、自宅や外出先で子どもと会い、一緒に遊んだり食事をしたりする場合が多く見られますが、面会交流の時間や回数は子どもの発育状態に応じて異なります。
面会交流は、子どもが成人するまで継続することが望ましいと考えられていますが、2022年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたため、基本的には18歳までです。
しかし、子どもの年齢が上がるにつれて、子どもの意思が尊重されるようになるため、必ずしも成人まで継続する必要はありません。
面会交流は、子どものためのものであり、子どもの利益(幸せ)を最優先に考慮する必要があります。両親間の感情的な対立に巻き込まれることなく、子どもの福祉・利益に資するよう、冷静な話し合いをすることが求められます。
面会交流の時間はどのくらい?

- 面会交流の実施時間はどのくらい?
- 面会交流の時間は子どもの発育状態によって異なる
子どもとの面会交流の時間はどのくらいですか?
面会交流の実施時間は子どもの発育状態に応じて異なります。
面会交流の時間の決め方
面会交流の時間を決める際には、子どもの年齢や発達段階、体調、非監護親との関係性、面会交流の場所や方法などを考慮する必要があります。子どもの成長は日々変化するため、その都度子どもの状況に合わせて柔軟に時間を決めることが望ましいでしょう。しかし、両親が協力し合うことが難しい場合は、事前に具体的な時間を決めておくことで、面会交流をスムーズに実施することができます。
以下では、子どもが「乳児~幼児の場合」、「小学生の場合」、「中学生以上の場合」に分けて面会交流の実施時間について解説していきます。
子どもが乳児~幼児の場合
乳児(1歳未満)の場合は、監護親と離れることに強い不安を感じるため、10分~1時間程度の短時間から始めることが多いです。幼児(1歳~小学校就学まで)の場合は、30分~半日程度が目安となります。
特に、子どもと非監護親の交流が長期間途絶えていた場合は、短時間から始め、子どもの様子を見ながら徐々に時間を延ばしていくと良いでしょう。3歳くらいになれば、公園や遊び場で一緒に遊んだり、食事をしたりすることも可能です。
一方で、乳幼児期前期の子どもは、肉体的にも精神的にも未熟であるため、監護親の同席が必要になることが多いでしょう。非監護親は、ミルクや離乳食の与え方やおむつ交換など、監護親のサポートが必要になる場合も想定されます。監護親と同席での面会交流が難しい場合には、祖父母などの第三者の協力を得て行うなどの工夫も必要です。
子どもが小学生の場合
小学生の子どもとの面会交流は、行動範囲や体力も広がり、できることが増えるため、より柔軟な計画が可能になります。時間帯としては、日中の時間を活用し、「午前9時頃から午後5時頃まで」といった、ほぼ一日を共に過ごすことが可能になります。学校の授業や宿題の時間を考慮し、週末や長期休暇を利用することが一般的です。
例えば、テーマパークや水族館など、子どもが楽しめる場所に一緒に出かけるという面会交流も可能となります。学年や体力にもよりますが、遠方へのお出かけや、宿泊を伴う面会交流も可能になる場合があります。
宿泊を伴う場合は、事前に宿泊場所やスケジュールについて、子どもとよく話し合い、同意を得ることが重要です。宿泊中は、子どもの安全に十分配慮し、規則正しい生活リズムを保つように心がけましょう。
子どもが中学生以上の場合
中学生以上の子どもとの面会交流は、子どもの自主性を尊重し、柔軟な対応が求められます。時間帯としては、部活動や塾などで忙しくなるため、2~3時間での交流となることが多いです。
交流方法としては、子ども自身が非監護親と連絡を取り、会う場所や時間を決める場合が増えてきます。子どもの生活リズムを尊重し、柔軟に時間を決めることが大切です。夕食を一緒に食べる、映画を観るなど、子どもの興味や関心に合わせた過ごし方ができるようになります。
一方で、一緒にキャンプに行ったり、泊りがけで遠方に旅行したりすることもできるようになり、宿泊付きの面会交流が充実することもあります。
面会交流の時間や回数は増やせる?

- 面会交流の時間や回数を増やすには?
- 面会交流調停・審判を活用する
一度決まった面会交流の時間や回数を増やすことはできますか?
面会交流の取り決めを変更する場合には、調停や審判を活用することができます。
父母間で話し合いを行う
離婚時に取り決めた面会交流の条件は、その後の状況変化によって見直しが必要となる場合があります。
面会交流の時間や回数を増やしたい場合には、まずは両親間で直接話し合いを行い、合意形成を目指しましょう。
子どもの成長や生活環境の変化、両親の生活リズムの変化などを考慮し、子どもにとって最適な面会交流の形を話し合います。子どもが意見を表明できる年齢であれば、子どもの意見も尊重する姿勢が重要です。
感情的な対立が予想される場合は、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。弁護士に相談すれば、両者の意見を冷静に整理し、子どもの利益を最優先に考えた解決策を提案してもらうことができます。
関連記事:祖父母は孫と面会交流できる?実現するためのポイントを紹介
面会交流調停・審判を申立てる
両親間の話し合いで合意に至らない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が両者の意見を聴き取り、合意形成をサポートします。
調停でも合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が面会交流の条件を決定します。審判では、子どもの年齢、生活環境、両親の状況などを総合的に考慮し、子どもの利益を最優先に裁判所が判断を下します。
近年では、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することも増えています。ADRは、裁判所の手続きによらず、専門家が間に入って話し合いをサポートする手続きです。面会交流の時間についてのみ、柔軟な話し合いをしたい場合には、ADRも選択肢の一つとなります。
どのような手段を選ぶべきかについては、個々の状況によって異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
面会交流時間の悩みを弁護士に相談すべきメリット

- 面会交流の悩みを弁護士に相談するメリットとは?
面会交流の時間に関する悩みは弁護士に相談すべきなのでしょうか?
ここでは、面会交流の悩みを弁護士に相談するメリットについて解説していきます。
面会交流の方法について悩んだとき、弁護士に相談することをおすすめします。
まず、弁護士に依頼することで、面会交流時間や頻度、方法について適切なアドバイスを受けられ、代わりに交渉を進めてもらえるため、精神的な負担を軽減してくれます。
また、面会交流調停や審判に発展した場合においても、弁護士に裁判対応を任せておくことができます。
調停では、子どもの生活や精神的な負担に配慮した面会交流ができるよう、調停委員を介して相手方と話し合いを進めます。調停や審判手続きを有利に進めるためには、弁護士のサポートが不可欠です。
離婚トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談することで、より良い結果が期待できます。
さらに、面会交流時間などの条件変更についても、弁護士に対応を依頼できます。
一度取り決めた条件も、子どもの成長や状況の変化によって再協議が必要になることがあります。弁護士に依頼することで、法的な見解に基づいた適切な主張を行い、相手方を説得し、現実的な条件を定めることが期待できます。
このように、面会交流に関する悩みは、弁護士に相談することで多くのメリットを得ることができます。
まとめ
「面会交流」とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと直接会ったり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。面会交流の時間や回数については、子どもの年齢や発達段階、体調、非監護親との関係性、面会交流の場所や方法などを考慮して、両親が話し合って決めることができます。そして、一度決められていた面会交流の時間や回数についても、事後的に増やすこともできます。
面会交流の時間や回数について悩まれている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に対応を任せれば、面会交流の取り決めを変更できる可能性があります。お悩みの方は当事務所の弁護士にぜひご相談ください。