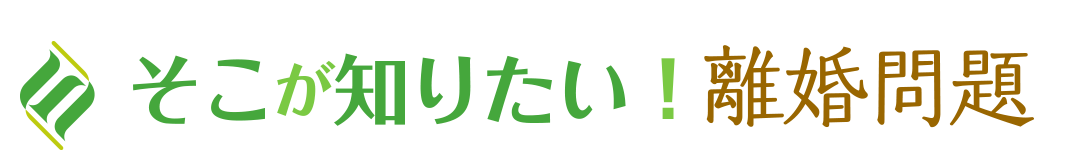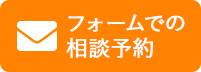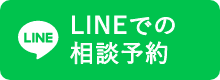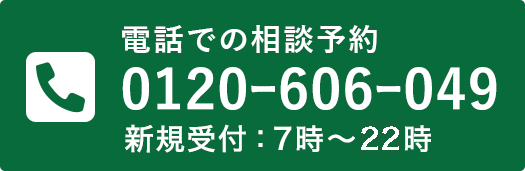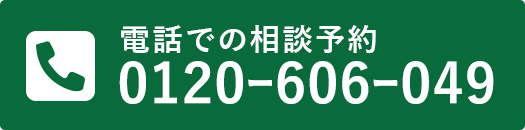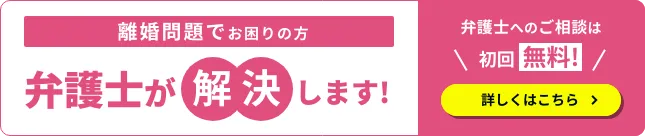

- 原則として面会交流は拒否できない
- 正当な理由があれば、面会交流を拒否できる
- 子どものために面会交流の負担を軽減するためのポイントとは?
【Cross Talk 】子どもが嫌がった場合には面会交流を拒否できますか?
子どもが嫌がった場合には面会交流を拒否できますか?
面会交流は、正当な理由があれば拒否できる可能性があります。
子どものために面会交流を拒否することについて、詳しく教えてください。
離婚後に子どもと離れて暮らす親(非監護親)が定期的に子どもに会って交流する「面会交流」は、子どもの健やかな成長のために非常に重要です。しかし、「子どもが相手親に会いたがらない」、「会わせたくない」という場合、面会交流を拒否することができるのでしょうか?この記事では、面会交流を拒否できる場合や、子どものために面会交流の負担を軽減する方法、面会交流のトラブルを弁護士に相談するメリットなどを、弁護士が解説していきます。
面会交流は拒否できる?

- 面会交流の概要について
- 原則として面会交流は拒否できない
面会交流を拒否することはできるのでしょうか?
ここでは、面会交流の基本的な考え方について解説していきます。
面会交流とは子どもが別居する親と交流する権利のこと
「面会交流」とは、親の離婚や別居によって、離れて暮らす親(非監護親)と子どもが定期的に会って話をしたり、一緒に過ごしたり、手紙や電話などで交流したりすることです。これは、民法第766条および第771条で定められており、協議離婚だけでなく、調停や訴訟によって離婚する場合にも、その方法を定めるよう規定されています。
面会交流が法律で定められている理由は、たとえ夫婦が離婚して他人同士になったとしても、子どもにとって別居中の親もまた親であることに変わりはないからです。子どもが両方の親から愛情を受けて育つことは、精神的な安定や健全な成長に不可欠と考えられています。
しかし、面会交流は非監護親の権利という側面と、「子ども自身の権利」という側面があることを理解しておく必要があります。面会交流について決定する際には、子どもの利益を考慮する必要があるため、面会交流は親の都合ではなく、子どもの都合や希望、そして何よりも子どもに与える影響を最優先に考慮して行う必要があるのです。
面会交流は原則として拒否できない
「子どもを会わせたくない」「面会交流に気が進まない」と感じる親権者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、前述の通り、面会交流は「子どもの利益」を最優先に考えるべきものです。このような制度の趣旨から、基本的に面会交流は拒否できないと考えるべきでしょう。
面会交流を拒否できるのは、後述のように、あくまで面会交流が子どもにとって不利益であると明確に判断される場合に限られます。
以下のような理由では、原則として面会交流を拒否することはできません。
特に、子どもが「会いたくない」と言っている場合でも、その理由が上記のような子どもの気持ちに起因するものであれば、必ずしも拒否できるとは限りません。子どもが親に気を遣って、本心を言えない場合が少ないためです。
あくまで「子どもにとってプラスになるかどうか」が判断基準になることを意識しておく必要があります。
子どもが嫌がっている場合は面会交流を拒否できる

- 子どもが嫌がった場合、面会交流を拒否できる?
- 面会交流を拒否できる正当な理由とは?
子どもが嫌がっている場合、面会交流を拒否できますか?
ここでは、面会交流を拒否できる正当な理由について解説していきます。
正当な理由があれば拒否できる
まず、子どもの意思は尊重されるべきですが、その意思が「真意」であるかどうかの見極めが重要です。特に幼い子どもや小学生の場合、同居している親に気を遣って「会いたくない」と言っていることも少なくありません。
家庭裁判所の調査官が子どもの真意を確かめた結果、「同居親に遠慮しているだけ」と判断されれば、面会交流が認められることがあります。
面会交流を拒否する正当な理由とは?
子どもが面会交流を嫌がる場合以外にも、面会交流を拒否する正当な理由として認められる場合があります。家庭裁判所は、子どもの利益に反する「特段の事情」がない限り面会交流を認める傾向があるものの、以下のような事情があると、面会交流を実施すべきではないと判断される可能性があります。
これらの事情がある場合は、子どもの利益を保護するために面会交流を制限することが適切であると判断されることがあります。ただし、これらの理由を主張する際には、客観的な証拠や具体的な状況を明確に提示することが重要となります。
関連記事:面会交流は拒否できる?拒否した場合のリスクなどについて解説
子どものために面会交流の負担を軽減するためのポイント

- 子どものために面会交流の負担を軽減するポイントとは?
- 第三者機関の利用を検討する
子どものために面会交流の負担を軽減するにはどうすればいいのでしょうか?
父母間の話し合いが難しい場合には、第三者機関の利用を検討してください。
父母同士で話し合い、実施回数や面会方法を変更する
面会交流を円滑に進めるためには、何よりも父母間の建設的な話し合いが不可欠です。もし現在の面会交流が子どもにとって負担になっていると感じる場合、まずは別居親にその状況を冷静に伝え、実施回数や面会方法の見直しを提案してみましょう。感情的にならず、「子どもの利益」を最優先に考える姿勢が大切です。
具体的には、面会の頻度を減らしたり、面会時間を短縮したりすることを検討すべきでしょう。また、特定の場所での面会が子どもにとってストレスになっているのであれば、公園や児童館、子どもの自宅付近など子どもがよりリラックスできる場所に変更することを検討してください。さらに、直接会う面会交流が難しい場合は、電話や手紙、メール、オンライン通話(ビデオチャット)などを活用することで、離れた非監護親と交流することができます。
第三者機関を利用する
父母間での話し合いが難しい場合や、感情的な対立が解消されない場合には、第三者機関の利用を検討することも非常に有効な手段です。利用できる主な第三者機関としては、以下の選択肢があります。
当事者だけでは面会交流に関する合意形成が困難な場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。調停委員が父母双方の意見を丁寧に聞き取り、子どもの状況や意向も踏まえながら、具体的な面会交流の方法について合意形成をサポートしてくれます。
また、面会交流支援団体は、面会交流の日時・場所の調整、子どもの受け渡し、面会時の立ち会い、面会場所の提供などをサポートしてくれます。父母間の直接の接触を避けられるため、DVの懸念がある場合には有効な選択肢となります。
さらに、法律の専門家である弁護士に相談することで、あなたの代わりに相手方との交渉や裁判手続きを進めてもらえます。そのため、感情的な対立を避けて、適切な面会交流の実現が期待できます。
面会交流の問題は弁護士に相談すべき

- 面会交流の問題を弁護士に相談するメリットとは?
- 相手との交渉や裁判手続きを一任できる
面会交流の問題は、弁護士に相談すべきなのでしょうか?
ここでは、面会交流の問題を弁護士に相談するメリットを解説していきます。
法的な観点から適切なアドバイスを受けられる
弁護士に相談することで、あなたの個別の状況に応じて、法的な観点から適切なアドバイスを受けられます。「面会交流を拒否できる正当な理由があるか」といった判断は、法律の専門家でなければ難しい場面が多くあります。
弁護士は、過去の判例や家庭裁判所の実務を踏まえ、子どもの年齢や性格、学校・習い事のスケジュール、父母間の関係性などを総合的に考慮し、子どもにとって本当に望ましい面会交流のルールを策定するためのアドバイスをしてくれます。
相手方との話し合いや交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、相手方と面会交流の条件に関する交渉を任せることができます。弁護士が間に入ることで、感情的なやり取りを避け、法的な根拠に基づいた冷静な話し合いが期待できます。
これにより、あなたの精神的な負担が大幅に軽減され、スムーズな合意形成に繋がる可能性が高まります。また、相手方が弁護士を立てている場合でも、専門家同士で建設的な話し合いを進めることができます。
調停手続きについても一任できる
弁護士に依頼すれば、調停や、もし調停が不成立になった場合の審判手続きについても全面的に任せることができます。裁判所に提出する書類の作成から、調停期日での適切な主張、そして家庭裁判所調査官による調査への対応まで、煩雑な手続きをスムーズに進めてくれます。
これにより、あなたは安心して手続きを弁護士に任せ、子どもの生活やご自身の日常に集中することができます。
まとめ
面会交流は、離婚や別居によって離れて暮らす親と子どもが交流を持つ、子どものための大切な権利です。原則として面会交流は拒否できませんが、子どもが強く嫌がっている場合や、別居親に虐待や連れ去りの危険があるなど、子どもの利益を著しく害する正当な理由がある場合には、面会交流の制限や拒否が認められることがあります。
面会交流に関する問題は、感情的な対立が絡むことが多く、当事者だけで解決するのは非常に困難です。当事務所には、面会交流の問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。