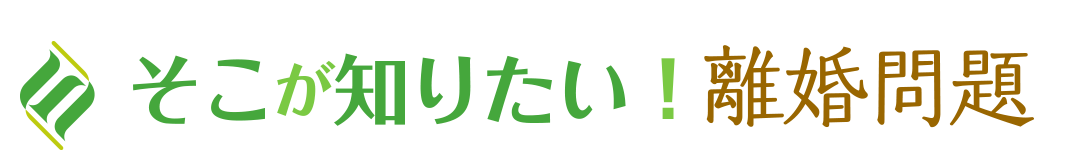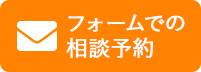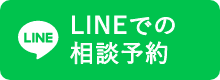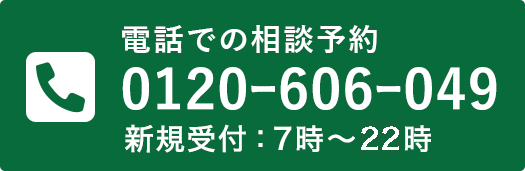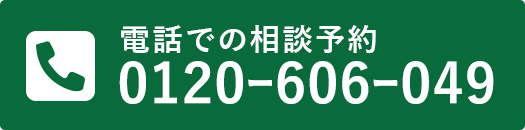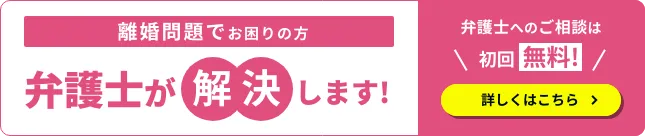

- 親権とは?
- 親権者の決定に子どもの意思はどの程度考慮される?
- 親権を獲得するためのポイントとは?
【Cross Talk 】離婚に際して、親権者を子ども自身が決めることはできますか?
離婚の際、子どもが親権者を選ぶことはできるのでしょうか?
親権者の決定に際して子どもの意思も重要な考慮要素となります。
親権者の決定と子どもの意思について、詳しく教えてください。
離婚に際し、子どもの親権をどちらが持つかは、夫婦にとって重要な決断です。子どもが一方の親と住みたいといっている場合、子ども自身が親権者を決められるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、親権の基本的な考え方から、子どもの意思が親権者の決定にどのように影響するのか、そして親権を得るための重要なポイントなどについて、弁護士が解説していきます。
親権とは?

- 親権とは?
- 身上監護権と財産管理権
そもそも親権とはどのようなものなのでしょうか?
親権は身上監護権と財産管理権のことを指します。
身上監護権
親権とは、未成年である子どもの成長と幸福のために、親が負う責任と義務のことであり、子どもが成人するまで行使されます。民法では、婚姻中は父母が共同で親権を行使すると定められていますが、離婚する際にはどちらか一方を親権者として定めなければ、離婚自体が成立しません。
この親権は、大きく分けて「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権利から構成されています。
まず、身上監護権とは、子どもの身体的・精神的な成長を促すために、親が子どもを監護・養育する権利と義務を指します。具体的には、以下のような内容が含まれます。
一般的に「監護権」という言葉は、この身上監護権を意味することが多いといえるでしょう。
関連記事:
親権と監護権を分けるメリット・デメリットとは?養育費はどうなる?
財産管理権
財産管理権とは、未成年である子どもの財産を管理し、その財産に関する法律行為を子どもに代わって行う権利と義務を指します。
例えば、子ども名義の預貯金を管理したり、子どもが不動産の賃貸契約を結ぶ際に同意を与えたりする行為などがこれに該当します。未成年の子どもは単独では契約などの法律行為ができないため、親権者が法定代理人としてその役割を担います。
親権から監護権だけを分離することも可能
原則として、親権者が身上監護権も行使しますが、法律上は親権者と監護権者を分離することも可能です。これは、親権者ではない方が子どもと一緒に生活し、具体的な世話や教育を行う場合を指します。
ただし、親権と監護権の分離は、子どもの養育に混乱や葛藤を生じさせる可能性もあるため、慎重に検討する必要があります。実際に分離する場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、その内容を明確に記載した離婚協議書などの書面を作成しておくことが重要です。
親権者を子どもが決めることはできる?

- 親権者を決め方とは?
- 子どもの意思で親権者を決めることはできる?
子どもの意思で親権者を決めることはできるのでしょうか?
ここでは、親権者を定める際の考慮事項を解説していきます。
親権の決定で考慮される要素
離婚時の親権者決定は、子どもの将来に大きな影響を与えるため、慎重に行われる必要があります。子ども自身の意思も重要な要素ではありますが、子どもが親権者を最終的に決定する権利を持つわけではありません。
親権者の決定においては、子どもの利益を最優先に、様々な要素が総合的に考慮されます。裁判所が親権者を決定する際に最も重視するのは、「子どもの利益」に適うかどうかという点です。
これを判断するために、以下の要素が総合的に考慮されます。
・これまでの養育実績
・離婚後の養育環境
・離婚後の親権者の生活や経済状況
・親権者の健康状態
・子どもの意向 など
子どもが15歳以上の場合
家庭裁判所は、子どもが15歳以上である場合、親権や監護に関する審判を行う前に、子どもの意見を聴くことが義務付けられています(家事事件手続法第169条2項)。これは、子どもの意思を尊重し、その意見を親権者決定に反映させるための重要な手続きです。
家庭裁判所調査官が子どもと面談し、その意向を確認します。この際、子どもが「父親(母親)と暮らしたい」と明確な意思表示をすれば、その意向が親権者の決定に大きく影響する可能性があります。
しかし、子どもの意見が唯一の決定要素ではなく、これまでの養育実績や離婚後の生活環境なども含め、総合的に判断されるという点には注意が必要です。
子どもが15歳未満の場合
子どもが15歳未満の場合でも、その意思が全く考慮されないわけではありません。家庭裁判所の実務では、10歳前後であれば、自分の意思を表明できると考えられ、意向の確認が行われることがあります。
特に、子どもが特定の親との生活を強く望む意思を示した場合、裁判所はその真意を慎重に探ります。
家庭裁判所調査官による面談や、場合によっては家庭・学校訪問、心理テストなどを通じて、子どもの心の状態や真の意向を把握しようとします。
幼い子どもは、親の顔色をうかがったり、本心とは違うことを言ったりする可能性もあるため、表面的な言葉だけでなく、その背景にある真意が重視されるのです。
関連記事:
親権は何歳まで行使する?養育費との関係は?
親権を得るためのポイント

- 親権を得るためのポイントとは?
- 養育実績や生活状況が考慮される
離婚の際に子どもの親権を得るためにはどのような点が重要なのでしょうか?
ここでは、親権を獲得するためのポイントについて解説していきます。
養育実績
離婚に際して親権を争うことになった場合、裁判所は「子どもの利益」を最も重視し、様々な角度から親権者としての適格性を判断します。そして、これまでの養育実績は、親権者を判断する上で極めて重要な要素です。
子どもが幼い頃からどちらの親が主に世話をしてきたか、学業や習い事、精神的なケアにどれだけ関わってきたかなど、具体的な養育への貢献度が問われます。
もし夫婦が既に別居している場合、現在子どもを監護している親の方が、その実績が評価され、親権獲得に有利に働く傾向があります。子どもが慣れ親しんだ環境や生活リズムを維持できることも、子どもの利益に繋がると考えられるためです。
離婚後の生活・経済状況の安定
親権者となった後、子どもに安定した生活環境を提供できるかどうかも重要なポイントです。
子どもが安心して生活できる住居があるか(居住環境)、子どもの学校生活に支障がないか、転校の必要性があるか(学業環境)、子どもの教育費や生活費を安定的に賄える収入があるか(経済状況)といった点が考慮されます。
もちろん、収入が多ければ良いというわけではありません。たとえ相手よりも収入が低かったとしても、養育費によって不足分を補える場合や、無理なく子どもの養育ができる程度の収入があれば、必ずしも不利になるわけではありません。しかし、借金が多い、浪費癖があるなど、経済観念に問題があると判断される場合は、親権者としての適格性が否定される可能性もあります。
子どもとの十分な時間を取れること
子どもが健全に成長するためには、親との十分な時間と心の交流が不可欠です。特に幼い子どもの場合、親が傍にいて日常的な世話や精神的なサポートができる時間がどれだけ確保できるかが重視されます。
例えば、仕事が忙しく、常に子どもを祖父母や他人に預けるような状況では、子どもと過ごす時間が短くなり、親権獲得が難しくなる可能性があります。
仕事との両立を図りながらも、子どもの送迎、学校行事への参加、休日の過ごし方など、積極的に子どもと関わってきた実績や、今後もその時間を確保できる見込みがあることを具体的に示すことが重要です。
関連記事:
親権を取り返すことは可能?離婚後の親権者変更について弁護士が解説
親権の問題は弁護士に相談すべき

- 親権問題を弁護士に相談すべき理由とは?
- 相手との交渉や必要な手続きを一任できる
親権問題は弁護士に相談すべきなのでしょうか?
ここでは、親権問題を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。
相手との交渉を有利に進められる
親権に関する話し合いは、感情的になりやすく、ご自身だけで相手方と交渉を進めるのは困難を伴います。弁護士は、あなたの代理人として、冷静かつ専門的な視点から交渉を進めることができます。
弁護士は、親権獲得のためにどのような主張が法的に有効か、どのような証拠を揃えるべきかなど、具体的なアドバイスを提供します。また、相手方の主張に対し、法的な根拠に基づいて反論したり、より有利な条件を引き出すための戦略を立てたりすることで、交渉を有利に進めることが可能になるでしょう。
養育費や面会交流などについても適切に取り決められる
親権の決定と並行して、養育費や面会交流など、離婚後の子どもの生活に関わる重要な事柄を取り決める必要があります。これらの取り決めは、単に金額や頻度を決めるだけでなく、子どもの成長段階や将来を見据えた、きめ細やかな配慮が求められます。
弁護士に依頼することで、これらの付随的な問題についても、法的な知識に基づき、あなたにとって不利益にならないよう適切な取り決めができるようサポートしてくれます。
関連記事:
面会交流調停を有利に進めるポイントは?弁護士費用の相場も紹介
調停や訴訟などを任せられる
夫婦間の話し合いで親権の問題が解決しない場合、家庭裁判所での調停や審判、あるいは離婚訴訟へと移行します。これらの法的手続きは、専門的な知識と多くの時間、精神的な負担を伴います。申立書の作成、主張書面の提出、期日への出頭など、不慣れな手続きをご自身で行うのは非常に大変です。
弁護士に依頼すれば、これら全ての法的手続きを代理して行ってもらえます。書類作成から裁判所への出頭、調停委員や裁判官への効果的な主張まで、法律の専門家による強力なサポートを受けることができます。
まとめ
親権は、未成年のお子さんの成長と幸福に直結する大切な権利義務です。離婚に際し、親権者を子ども自身が最終的に決定する権利を有するわけではありませんが、裁判所はお子さんの年齢や発達段階に応じて、その意向を慎重に考慮します。特に15歳以上のお子さんの意見は法的に聴取されることが義務付けられています。
親権者を決定する際には、これまでの養育実績、離婚後の生活・経済状況の安定性、そしてお子さんとの時間を十分に確保できるかなど、様々な要素が総合的に判断されます。親権の問題は複雑であり、ご自身で解決しようとすると大きな負担がかかる可能性があります。
親権に関するお悩みは、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。