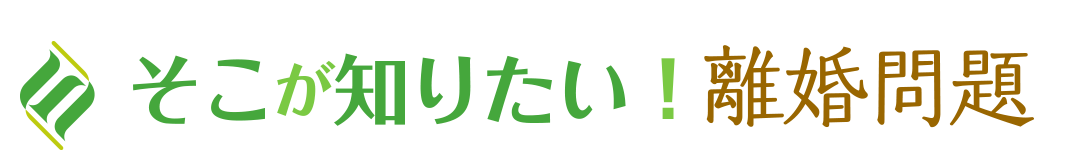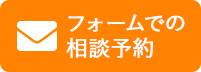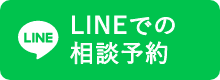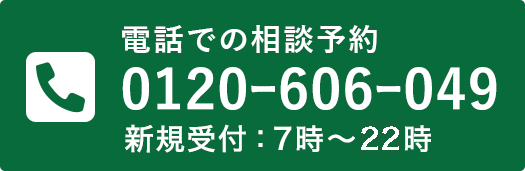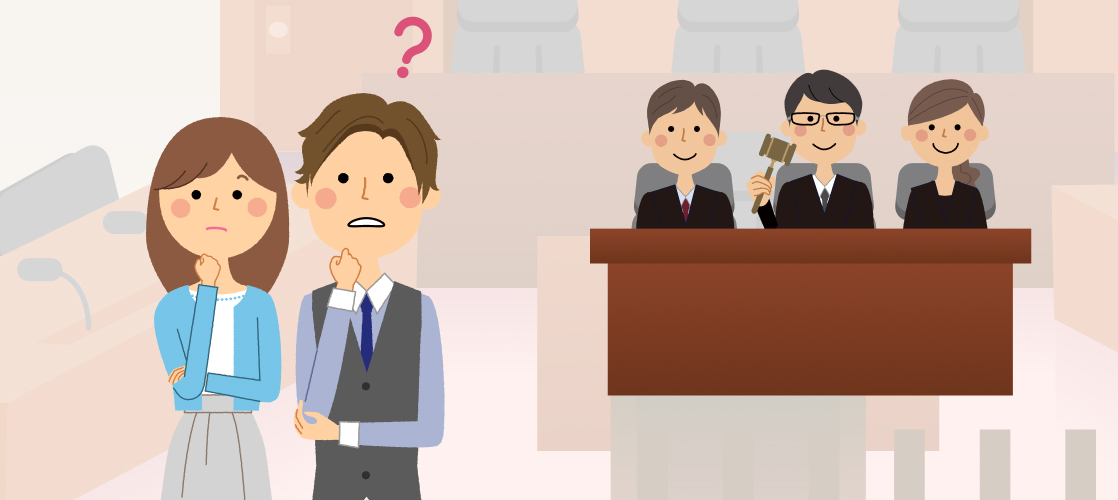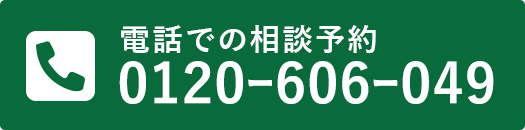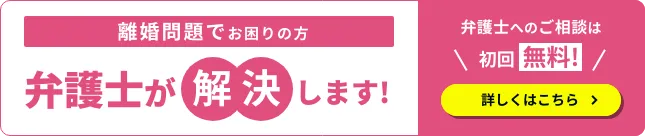

- 離婚調停で申立人が聞かれることとは?
- 離婚調停で相手方が聞かれることとは?
- 離婚調停で聞かれたことに答える際のポイントとは?
【Cross Talk 】離婚調停ではどのようなことが聞かれるのでしょうか?
離婚調停手続きで聞かれることはどのようなことですか?
離婚調停では、調停に至る経緯や離婚条件などについて聞かれることが一般的です。
離婚調停で聞かれることについて、詳しく教えてください。
夫婦は話し合いで離婚するかどうかや、離婚条件について話し合うことができます。話し合いでは離婚できない場合、離婚調停を家庭裁判所に申立てることができます。離婚調停では、離婚の可否や離婚条件などに関して調停委員から聞かれることが一般的です。
この記事では、離婚調停で当事者が聞かれることや、聞かれたことに答える際のポイント、離婚調停の手続きの流れなどについて、弁護士が解説していきます。
離婚調停で聞かれること

- 離婚調停で聞かれることとは?
- 一般的に、離婚の理由や離婚条件、離婚後の生活について聞かれる
離婚調停ではどのようなことが聞かれるのでしょうか?
ここでは、一般的に調停委員から聞かれることについて、具体的に解説していきます。
離婚したい理由や経緯
まず、調停委員は「なぜ離婚したいのか」という理由や経緯を確認します。
結婚に至った経緯や結婚後の生活状況、夫婦関係の変化や悪化の原因、そして離婚を決意するまでの過程について説明する必要があります。
特に、離婚の原因としてDVやモラハラ、不貞行為がある場合は、証拠を準備することが重要です。時系列に沿って冷静かつ端的に説明することで、調停委員に状況を正確に伝えることができます。
関連記事:離婚調停とはどのようなものか・費用・期間・有利にすすめるコツなどを紹介
子どもの監護
未成年の子どもがいる場合、親権や養育費、面会交流について細かく質問されます。
調停委員は「子の福祉」を最優先に考えるため、現在どちらが子どもの世話をしているのか、子どもの生活環境(学校、習い事、交友関係など)について説明することが求められます。
また、別居中であれば、子どもとの関わりや面会交流の有無と頻度についても聞かれることが一般的です。
離婚後の親権や養育費、面会交流についての希望を明確に伝えることが重要です。特に親権争いが発生する場合は、子どもの生活を安定させるための具体的な計画を示すことも重要です。
関連記事:面会交流は何歳まで?子どもや元配偶者が拒否する場合の対処法も
財産分与や慰謝料
離婚に伴う財産分与や慰謝料についても、調停委員から聞かれます。
特に金銭面の争いは長期化しやすいため、調停では夫婦共有財産のリストを整理し、不動産や預貯金、車、保険、年金などの分け方を話し合う必要があります。
財産分与に関する意向を具体的に伝え、必要であれば根拠を示す資料を用意することが望ましいです。慰謝料を請求する場合は、請求の有無や証拠の提示、具体的な金額の妥当性についても説明する必要があります。養育費に関しては、金額や支払い方法について具体的に伝えることが求められます。
離婚後の生活
離婚後の生活についても、調停委員から聞かれることがあります。特に、専業主婦の方が申立人である場合には経済的な自立が可能かどうか聞かれることがあります。
離婚後の住まいが決まっているか、収入や就職の見込みがあるか、無職の場合は再就職の計画があるかを聞かれることがあります。また、特に未成年の子どもがいる場合には、子どもの養育環境の維持についても説明が求められ、転校の有無や生活リズムの変化にどのように対応するかなどを示すことが求められます。
公的支援の活用についても考慮し、児童扶養手当や生活保護などの制度を利用する計画がある場合は、その点についても伝えることが大切です。
離婚調停で相手方が聞かれること

- 離婚調停で相手方が聞かれることは?
- 一般的に、申立人への反論や離婚意思の有無などが聞かれる
離婚調停を申立てられた場合に聞かれることはどのようなことですか?
ここでは、離婚調停の相手方が聞かれることを解説していきます。
申立人の主張への反論
相手方に対して最初に聞かれるのは、申立人の主張に対する反論です。
離婚問題では、夫婦それぞれの言い分が異なることが多いため、調停委員は一方の主張だけで判断せず、同じ内容について相手方の意見を確認します。
例えば、申立人が「相手の不貞や暴力が原因で離婚を決意した」と主張した場合、相手方にはその事実があるのか、またはどのように認識しているのかが問われます。相手方が「そのような事実はない」と否定する場合、調停委員は証拠や状況を総合的に判断しながら進めていきます。
また、離婚に至るまでの経緯について争いがある場合には、この点についても、相手方の視点から詳しく説明を求められます。夫婦関係がどのように変化していったのか、申立人の主張する問題がいつから生じたのか、相手方がどのような対応をしてきたのかといった点です。
離婚する意思の有無
離婚調停では、相手方が離婚に応じる意思があるかどうかが重要なポイントです。
離婚が成立するためには双方の合意が必要となるため、相手方が離婚に同意するかどうかを明確にする必要があります。相手方が離婚に応じる意思がない場合、その理由についても詳しく聞かれます。
離婚を拒否する理由として、夫婦関係の修復が可能と考えている場合や、離婚による経済的な影響を懸念している場合が挙げられます。また、子どものために夫婦関係を維持したいと考えることもあり、調停委員は関係修復の可能性についても探ることになります。
一方で、相手方が条件次第では離婚に応じる、という意思がある場合、離婚の条件について具体的な話し合いが進められます。
離婚する場合の条件
離婚調停では、相手方にも離婚条件について詳しく質問されます。離婚後の生活に関わる重要な取り決めとなるため、財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流のルールについて具体的に意見を求められます。
財産分与に関しては、夫婦で築いた財産をどのように分けるかが焦点です。
預貯金や不動産、車、保険、年金などの資産がどのように分配されるのかについて、双方の意見を調整していきます。また、慰謝料については、申立人が請求している場合、その請求の妥当性を判断するために相手方の意見が求められます。相手方が支払いを拒否する場合、その理由や根拠が必要です。
また、相手方が親権を主張する場合、育児の実績や子どもとの関係、生活環境を維持するための具体的な計画を説明する必要があります。養育費についても、支払いの有無や金額について話し合います。
また、面会交流についても、離婚後にどの程度の頻度で子どもと会うことができるのか、どのような方法で面会を行うのかが話し合われます。
離婚調停で聞かれたことに答える際のポイント

- 離婚調停で聞かれたことに答える際のポイントとは?
- 事前に伝えたいポイントや反論を準備しておくことが重要
離婚調停で聞かれたことに答えるためには、どうすればいいのでしょうか?
ここでは、離婚調停で聞かれたことに答える際のポイントについて解説していきます。
事前に話す内容をまとめておく
調停では、感情的になってしまいうまく話せなくなることがあるため、事前に話す内容を整理し、伝えたいポイントを明確にしておくことが重要です。
調停委員に対して、どのような事実を伝えたいのか、どのような条件を望んでいるのかを事前にメモなどにまとめておくと、調停期日でも落ち着いて話すことができます。
嘘はつかず事実に基づいて話す
調停の場では、誠実に事実を伝えることが求められます。自分にとって不利な内容であっても、正直に答えることが大切です。
調停委員や調停官は、あくまで中立な立場で双方の話を聞きますので、嘘をついてしまうと信用を失い、逆に不利な状況に陥る可能性があります。また、相手方が証拠を持っている場合、嘘が明らかになれば、こちらの主張そのものの信憑性が疑われてしまうことにもなります。その場しのぎの発言ではなく、誠実な態度で調停に臨むことが、最終的には有利に働くことにつながります。
相手方の反応を予想して代替案を用意しておく
調停は裁判所を間に挟んで、話し合いによって合意を目指す場です。そのため、相手方の反応をある程度予測し、妥協点を考えておくことが重要になります。
例えば、慰謝料の支払いについて相手が拒否する可能性がある場合、財産分与を多めにもらうなど別の条件を提示できるよう準備しておくと、調停がスムーズに進むことがあります。
相手方がどのような主張をしてくるかを考え、それに対する柔軟な対応をシミュレーションしておくことで、無用な対立を避けることができるでしょう。
離婚調停の流れ

- 離婚調停手続きの流れとは?
離婚調停はどのような流れで進んでいくのでしょうか?
ここでは、離婚調停の手続きの流れを解説していきます。
離婚調停の申立て
離婚調停を開始するためには、まず家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行う必要があります。申立人は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出しますが、双方の合意があれば別の家庭裁判所を選ぶことも可能です。
申立書の提出には、戸籍謄本や収入印紙、郵便切手などを添付する必要があります。申立てが受理されると、家庭裁判所から申立人と相手方に調停期日が通知されます。
調停期日
調停期日には、申立人と相手方が家庭裁判所に出頭し、話し合いが行われます。
調停委員が双方の意見を別々に聞き取って話し合いを進めるため、当事者同士が直接顔を合わせることはありません。
1回の調停期日は通常2時間程度で、調停委員が交互に事情を聴取し、それを数回繰り返します。1回の調停で解決することは少なく、一般的には1ヵ月~1ヵ月半ごとに1回のペースで行われ、1~5回程度の期日を経て合意に至ることが多いでしょう。
調停の成立または不成立
調停期日を重ねた結果、双方が離婚やその条件について合意すれば、調停は成立します。合意内容は調停調書にまとめられ、これは確定判決と同じ効力を持つため、後に一方が合意を破った場合でも、強制執行が可能となります。調停成立後、10日以内に調停調書を持参して市区町村役場に離婚届を提出しなければなりません。
一方で、調停を重ねても合意に至らなかった場合、調停は不成立となります。調停が不成立になると、当事者同士での話し合いに戻るか、家庭裁判所に離婚訴訟を提起するかを選択することになります。離婚調停は自動的に審判へ移行することはなく、裁判を行う場合には新たに手続きを進める必要があります。
まとめ
離婚調停を申立てた場合には、調停委員から、離婚に至った経緯や離婚条件、離婚後の生活などについて聞かれることになります。あらかじめ聞かれる内容を整理して、ご自身の回答をまとめておくことで、聞かれたことに適切に答えることができます。
離婚調停への対応に不安がある方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。当事務所には離婚事件の経験豊富な弁護士が在籍しているため、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。