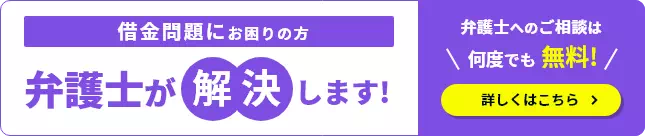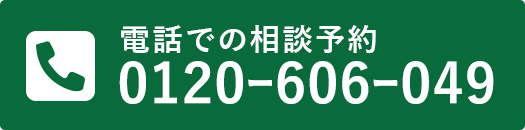- 破産者が悪意で加えた不法行為や人の生命または身体を害する不法行為の損害賠償は免除されない
- 非免責債権があっても自己破産はできる
- 免責不許可事由に該当すると裁量免責が認められない限り借金の支払い義務がなくならない
【Cross Talk 】自己破産すれば損害賠償責任はなくなる?
損害賠償責任を負っているのですが、自己破産すれば免責されるのでしょうか。
債務の性質によっては免責されない場合があるので一概にはいえません。
では、どのような場合に免責されないのかを詳しく知りたいです。
自己破産は債務の免責を受けられる制度ですが、全ての債務が免責されるわけではありません。損害賠償責任については、その性質や発生原因によって免責されるかどうかが変わります。
本記事では、自己破産した場合の損害賠償責任の取り扱いについて、非免責債権の説明と合わせて詳しく解説します。
自己破産すると損害賠償責任はなくなる?

- 自己破産手続きを行い、免責許可を得ることができれば、借金がゼロになる
- 債務には、免責が認められるものと、認められないものがある
自己破産をしても免責されない損害賠償責任があるのというのは、本当でしょうか。
はい。ただし、それを理解するためにはまず、自己破産や損害賠償責任について正しく理解する必要があります。
では、自己破産とは何か、損害賠償責任とは何かについて、詳しく教えてください。
自己破産とは
自己破産とは、支払不能にある債務者が裁判所に破産申し立てを行い、破産手続終了後、免責手続きによって債務を免責する制度です。免責が認められると借金の返済義務がなくなりますが、必ずしもすべての債務について免責が認められるとは限りません。
まず自己破産するためには、債務者が支払不能状態にあることが必要です。支払不能とは、法律上「債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11項)とされており、預金や給料その他の収入を合わせても借金を返せない状態のことをいいます。
支払不能状態にあり、破産手続開始決定が出ても、破産法252条に定められている「免責不許可事由」に該当すると、免責が認められないことがあります。例えば、浪費や賭博など著しく不誠実な行為によって債務を増加させた場合などが、これに該当します。
関連記事:
自己破産ってどんなもの?メリット・デメリットとは?
損害賠償責任とは
損害賠償責任は、主に債務不履行と不法行為という2つの原因によって発生します。債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです。例えば、売買契約において売主が約束した期日に商品を引き渡さないなどの行為が債務不履行にあたります。
一方、不法行為というのは他人の権利を違法に侵害する行為のことです。例えば、他人の所有物を壊したり、交通事故でケガをさせたりする行為などがこれに該当します。
次で述べる通り、一部の不法行為に基づく損害賠償責任は非免責債権に該当し、自己破産をしても免責されないため、支払い義務を免れることができません。
非免責債権は自己破産をしても免除されない

- 非免責債権は、債権の性質上自己破産によって免責されない債権
- 非免責債権にあたる損害賠償責任は、自己破産の免責対象にならない
自己破産をしても免責されない損害賠償責任とは、どのようなものですか?
損害賠償責任のうちでも非免責債権にあたるものは、自己破産しても免責を受けられません。
では非免責債権について詳しく教えてください。
非免責債権とは、その性質上自己破産によって免責されない債権のことです(破産法253条但書き)。破産者の債務の中に非債免責債権がある場合、自己破産の申立てが認められても免責が受けられません。
非債免責債権の具体例は、以下のとおりです。
1.税金などの租税公課
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4.次に掲げる義務に係る請求権
a.夫婦間の協力及び扶助の義務
b.婚姻から生ずる費用の分担の義務
c.子の監護に関する義務
d.a~cに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7.罰金等の請求権
上記2、3に該当する損害賠償請求権は、非債免責債権であるため、破産者がこれらの債務を負っている場合、自己破産をしても損害賠償責任はなくなりません。
非免責債権にあたる損害賠償請求権

- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権には積極的な害意が必要
- 人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は故意又は重大な過失が必要
非免責債権にあたる損害賠償請求権について、より詳しく知りたいです。
では、先ほど紹介した2つの損害賠償請求権についてさらに詳しく解説します。
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
法律上、「悪意」とは事実を知っていること意味しますが、ここでいう「悪意で加えた不法行為」とは、積極的な害意を要する状態を意味するとされています。つまり、単に故意に行われた不法行為ではなく、積極的に相手の利益を害する目的で行った不法行為がこれに該当します。
例えば、個人的な恨みから相手に傷害を負わせた場合、これは積極的な害意を持った不法行為と判断される可能性があります。このような場合、加害者が自己破産しても、この傷害行為によって生じた損害賠償債務は非免責債権となり、免責の対象にはなりません。
破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
自己破産により、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権が免責されると被害者保護の観点から問題があるため、このような場合も非債免責債権とされます。
交通事故などで他人の生命または身体を害した場合、それによって生じた損害賠償請求権は非債免責債権となる可能性があります。
なお、「悪意で加えた不法行為」では積極的な害意が必要とされるのに対し、こちらは「故意又は重大な過失」が要件となっていることにも留意が必要です。「重大な過失」とは、単なる過失よりも、重い注意義務違反がある場合をいいます。
非免責債権があっても自己破産できる

- 非債免責債権は自己破産しても返済義務が残る
- 自己破産前に非債免責債権がないかを確認することが重要
債務の中に非債免責債権があると、自己破産できなくなってしまうのでしょうか。
いいえ、非債免責債権があっても自己破産はできます。
そうなんですね。そのあたりがまだよくわからないので、もう少し詳しく教えてください。
前述のとおり、非免責債権とは債権の性質上自己破産をしても免責されない債権のことです。つまり、自己破産をしても非債免責債権は免責の対象から除外されるということであり、非債免責債権の存在が自己破産自体を妨げるわけではありません。そのため、非免責債権があっても自己破産は可能です。
例えば、破産者が悪意による不法行為や生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務を負っていた場合、自己破産をしてもその損害賠償債務は免責されません。しかし、その他の非債免責債権に該当しない債務は免責を受けられるので、自己破産をする意味はあります。
自己破産を検討する際は、どの債務が免責されるかを事前に確認しておきましょう。もし債務の大部分を非債免責債権が占めているのであれば、自己破産をしても経済的な負担があまり変わらないため、自己破産すべきかどうかを考え直すという選択肢もあります。
自己破産の手続をする上での注意点

- 免責不許可事由があると裁量免責が認められない限り、債務が免責されない
- 裁量免責が認められれば免責不許可事由があっても債務が免責される
その他に何か自己破産をする上での注意点はありますか?
免責不許可事由があると、自己破産申立をしても、裁量免責されない限り債務が免責されなくなってしまうので、この点には注意が必要です。
では免責不許可事由についても詳しく教えてください。
免責不許可事由があると裁量免責が認められない限り、債務が免責されない
免責不許可事由とは、法律によって定められた免責が認められない事情のことです。破産法には免責不許可事由が列挙されており(破産法252条)、以下に該当する事実がある場合には免責が認められないできません。
いくつか具体例を挙げると、まず「浪費やギャンブルによる財産の費消」とは、例えば返済能力を超えた浪費や、パチンコ・競馬・オンラインカジノなどのギャンブルに費やして財産を減少させる行為です。
「詐術を用いた信用取引」は、返済能力がないことを隠して融資を受けるなど、嘘や騙しによって信用取引をする行為を指します。
「特定の債権者に利益を与える行為」は、親族や知人など特定の債権者だけに債務を返済し、他の債権者の利益を害する行為です。
関連記事:
ギャンブルの借金って破産できる?借金の種類で自己破産に影響あるの?
裁量免責を得る方法
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められる場合があり(破産法第252条第2項)、これを「裁量免責」といいます。裁量免責の要件は明確に定められているわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して決定されます。
例えば、浪費やギャンブルで借金を作ったものの真摯に反省し更生への意欲を見せれば、裁量免責は認められる可能性があります。また、家族からのサポートが得られたり、安定した収入が得られる職に就いたりと、更生の可能性を示すことも裁量免責を判断するうえでプラスに働くと考えられます。
逆に、破産手続きへの妨害行為を繰り返したり、短期間で何度も破産を繰り返したりしていた場合、裁量免責が得られる可能性は低くなります。
まとめ
自己破産をしても、「破産者が悪意で加えた不法行為」「故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為」に基づく損害賠償請求権は、非債免責債権であるため免責を受けられません。
また、免責不許可事由がある場合は原則として免責が認められませんが、事情によっては裁判所の裁量によって免責が認められる可能性もあります。
自己破産を検討する際は、自分の抱える債務がどのような性質であり、非免責債権に該当するのかどうか、借金が膨らんでしまった原因に、免責不許可事由にあたる行為があるかを事前に確認することが重要です。適切な判断と手続きを行うことで、自己破産後の生活再建への道が開かれます。

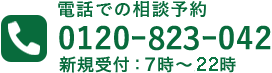
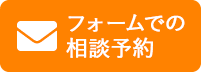


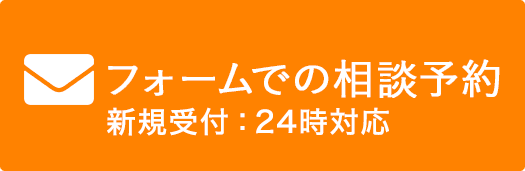
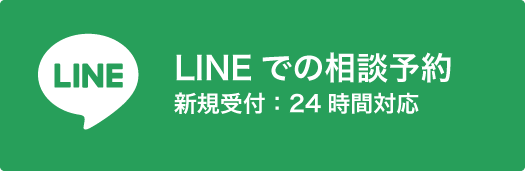
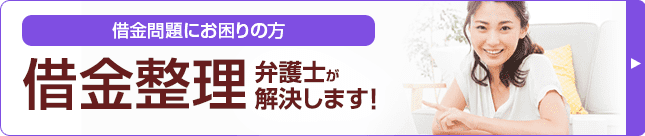
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください