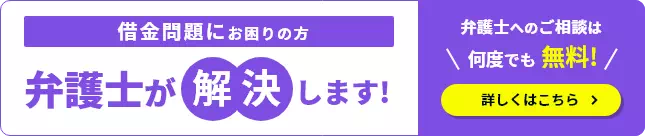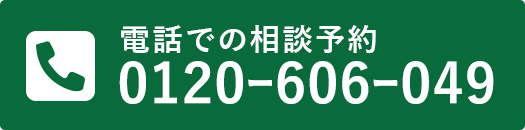- 自己破産すると借金を返す義務がなくなる!
- デメリットとしては財産が処分される、ローンが組めなくなる、更には生命保険の解約もされてしまう可能性があること等です。
- 弁護士に相談して自分に合った債務整理の方法を選びましょう。
【Cross Talk】借金の支払義務がなくなる!?自己破産!
借金が多すぎてとても払いきれません!なんとかなりませんか!?
それなら、自己破産という手続がありますよ!免責を受ければ、借金を返さなくて済みます!
え!?借金を返さなくてよくなるのですか!?その自己破産について教えてください!
借金(債務)整理手続は様々な種類・方法があります。その中でも、借金の支払義務がなくなる自己破産とはどのような手続きなのか、メリット・デメリットは何なのか、解説したいと思います。
自己破産とは

- 自己破産のイメージは全てキレイにする!借金と財産を清算するのが自己破産!
自己破産とはどのような手続なのですか?
自己破産とは、債務の支払いができなくなった債務者が裁判所に申立てをし、処分できる財産があれば処分して債権者に弁済・配当をし、それでも残った債務の責任を免除してもらう手続です。
債務整理には、債権者と個別に交渉する任意整理、裁判所の手続によって債務を大幅に減額したうえで残額を一定期間で分割弁済する個人再生といった手続がありますが、これらの手続と自己破産との大きな違いは、税金など一部の例外を除いて債務が免責される点です。
ただし、そのような債務者にとって大きなメリットがある反面、不動産等の価値のある財産があれば処分して債権者に配当する必要があり、財産をほとんど残すことができないというデメリットもあります。
自己破産の手続き

- 自己破産は大きく分けて管財手続と同時廃止手続の2種類がある
- 管財手続には通常の管財手続と少額管財手続の2種類がある
自己破産の手続には種類があるのですか?
自己破産の手続は、大きく分けて裁判所が破産管財人を選任する「管財手続」と管財人を選任しない「同時廃止」という手続の2種類があります。また、管財手続については、一部の裁判所では通常の管財手続のほかに手続が簡略化された「少額管財手続」という運用を行っているところもあります。
管財手続
破産手続とは「債務者の財産」を「清算する手続」と定めています。
破産手続の申立てがあった場合に、裁判所が破産手続開始の原因となる事実(支払不能など)があると認めたときは、破産手続開始の決定とともに債務者の財産を清算するための破産管財人が選任されます。
裁判所に選任された破産管財人は、債務者の財産を調査、管理し、換価(売却)できるものは換価して債権者に配当(弁済)をします。
その後、裁判所が債務者の残債務の責任を免除(免責)するかどうかの判断を下します。
管財手続では、破産管財人の事務処理費用や報酬等に充てるため、予納金として少なくとも50万円程度を用意する必要があります。
少額管財手続
管財手続では予納金が必要ですが、債務が支払不能となって自己破産を申立てようとする債務者にとって、最低50万円を準備することは簡単なことではありません。
そこで、東京地裁や大阪地裁など一部の裁判所では、通常の管財手続のほかに手続きを簡略化し、予納金を低く抑えた少額管財手続という運用を行っています。
少額管財の具体的な運用は裁判所によって異なりますが、一般的には予納金の最低額は20万円程度で、弁護士が申立代理人として関与していることが要件です。予納金が安い=管財人の報酬も安くなるということなので、破産管財人の負担は軽減されます。すなわち、弁護士が債務者の代理人として必要な調査、資料の収集等をすることになっているのです。
同時廃止手続
破産法上は管財手続が原則とされています。しかし、債務者の財産が僅かしかなく、総債務額も高額ではない、といった調査の必要性が乏しい場合、管財人の選任を必要とすることは、配当を受けられない債権者にとっては意味がなく、債務者にとっては大きな負担となり債務者の経済的な再生を妨げるおそれがあります。
そこで破産法は、このような場合には、原則として、破産手続の開始と同時に破産手続を廃止する決定をすると定めており、この手続を同時廃止手続といいます。
自己破産のメリット

- 一部の例外を除いて債務の支払義務がなくなる
- 一定額以下の現金など最低限の財産は手元に残すことができる
自己破産にはどんなメリットがあるのですか?
自己破産の最大のメリットは、税金等の一部の例外を除いて債務の支払義務がなくなるということです。また、自己破産をすると財産を全て失うと誤解されている方が多いですが、実際には一定額以下の現金など、最低限の生活費用は手元に残すことができます。
借金の支払義務がほぼなくなる
裁判所は、破産管財人による清算または同時廃止の手続をするとともに、残債務について法律上の責任を免除するかどうかを判断します。その手続を免責の手続といいます。
裁判所が免責を許可する決定をした場合、税金など免責の対象とならないものを除き、借金の支払義務がなくなります。借金の支払義務から解放され、経済的な再生を図ることができるということが、自己破産の最大のメリットです。
最低限の生活費用は残せる
自己破産をすると、破産管財人が債務者の財産を管理・処分しますが、債務者の全ての財産が破産管財人による処分の対象となると、債務者は日常生活を送ることができなくなってしまいます。
そのため、生活に必要な家財道具や、最低限の財産として「自由財産」は保有することが認められています。自由財産の代表的な例は、99万円以下の現金、破産手続開始後に取得した新得財産などです。
また、例外として認められる「自由財産の拡張」の対象となるのは、一定額以下の預貯金、一定額以下の評価額の保険契約や自動車などです。
債権者からの強制執行・取り立てがなくなる
債務の支払いが滞ると、債権者から取り立てを受け、給与の差押などの強制執行の手続がなされる場合があります。しかし、破産手続をして免責されると、支払義務がなくなるので、債権者から取り立てや強制執行を受けることはなくなります。
また、破産手続をする前に給与の差押などの強制執行を受けていた場合、管財手続では破産手続開始決定によって強制執行手続は効力を失います。同時廃止手続では、強制執行は、同時廃止決定によって中止され、免責許可決定の確定によって効力を失うとされています。
なお、抵当権などの担保権の行使・強制執行は、破産手続の開始の有無を問わず、これを中止したり無効にすることはできません。
自己破産のデメリット

- 新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなる
- 自己破産したことを知られるおそれがある
自己破産をすることに何かデメリットがありますか?
信用情報機関に事故情報が登録されるため、新たにキャッシングやローンなどの借入をすることや、クレジットカードを利用することができなくなります。また自己破産をしたことが家族や勤務先、その他の第三者に知られるおそれがあることもデメリットといえます。
キャッシング・ローンなど新たな借入ができなくなる
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます(「ブラックリストに載る」と言われる状態になります)。
そのため、自己破産をした後は一定期間、新たにキャッシングやローンなどの借入はできません。
官報に住所や氏名などの情報が掲載される
自己破産をすると、官報に破産者の氏名、住所が公告されます。
官報は政府が発行する新聞のようなものであり、以前は一般の方が官報を目にすることはほとんどなかったのですが、近年はインターネットで官報が閲覧できるため、自己破産したことを第三者に知られることがないとは言い切れません。
一部免責されない債務がある
一部の債権は、自己破産をしても免責されません。そのような債権を非免責債権といいます。非免責債権には次のようなものがあります。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意または重大な過失により加えた「人の生命または身体を害する不法行為」に基づく損害賠償請求権
・婚姻費用、養育費等
・雇用関係に基づいて生じた労働者の請求権等
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
クレジットカードの利用ができなくなる
自己破産をした後、一定期間は新たにクレジットカードを作ることができなくなります。
なお、自己破産を申立てる時点で残債務のないクレジットカードについては裁判所に申告する必要がないので、たとえばカード一度も使用していないクレジットカードについては、自己破産申立て後もしばらくは使用することができる可能性があります。
もっとも、クレジットカード会社は、カードの更新時など定期的に契約者の信用情報を確認するので、いずれは契約者が自己破産をしたことを把握し、カードを停止してしまいます。
一部の職業・資格が制限される
自己破産をすると、一部の職業に就くことが制限されます。
職業制限の代表的な例としては、貸金業者、生命保険募集人、質屋、警備業などです。また、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士等のいわゆる士業も対象とされています。
ただし、自己破産をすると永久にこれらの職業に就けないわけではなく、免責許可決定が確定する等の一定の要件を満たした場合、職業の制限が解除されます。これを復権といいます。
家族や職場に自己破産の事実が発覚する可能性がある
自己破産をしても、裁判所等から家族や職場に通知をするわけではないので、家族や職場に知られない場合もあります。
しかし、家族が保証人になっていたり、会社からの借入があったりする場合には、自己破産が家族や職場にも影響するため、隠し通すことはできません。
また、そのような事情がなかったとしても、管財手続の場合は債務者宛の郵便物が破産管財人に転送されるので、債務者宛の郵便物が届かないことに疑問を持った同居の家族に問い詰められ、自己破産をしたことが発覚する場合もあります。
自己破産手続が向いている方・向いてない方

- 自己破産には借金の支払義務がなくなるという他の整理手続にはないメリットがある!
- デメリットも大きいが、生活ができなくなることはないように配慮されている。
- 自分に合った借金整理を選ぶため、弁護士に相談してみよう!
債務整理手続がある中で自己破産手続が向いているのはどのような方なのでしょうか。
自己破産手続が向いている方・向いていない方はいくつかパターンがあるので確認しましょう。
自己破産手続を利用するのが向いている・向いていないのは、どのような方なのでしょうか。
自己破産手続が向いている方
まず、自己破産手続を利用するのが向いているのは以下のような方です。それぞれ説明します。
・収入がない・少ない
・任意整理では支払いきれない・支払えなくなるおそれがある
・任意整理で頑張れば支払えなくもないが早く経済的に立ち直りたい
一つ目は、収入がないような場合には、そもそも任意整理・個人再生の毎月の支払ができません。
そのため、自己破産をするのが基本となります。
また、債務額がそれほど多くなくても、収入が少ないような場合には、長期間返済のために厳しい生活を送るのは適切ではないともいえますので、自己破産手続のほうが向いているといえるでしょう。
なお、一時的な失職で体調面に問題がなく、再就職すればしっかり支払っていけるような場合には、実際に就職が決まってから、どの債務整理手続を利用するのが適切か検討することもあります。
二つ目は、任意整理で支払いきれないような場合には、任意整理を利用することができません。
任意整理をする場合、基本は元金を36回分割(3年)、例外的に60回分割(5年)まで延ばすことが限度です。
つまり、300万円の借金がある場合には、毎月約5万円~約8万4千円の支払ができなければならず、それを3~5年間支払い続けられるだけの余裕が必要です。
3~5年の間には、賃貸に住んでいる方の中には家賃の更新がある方もいるかもしれませんし、冠婚葬祭で急な出費に見舞われることもあります。
1回支払いが遅れただけであれば、次回までに遅れを取り戻せば良いですが、2回以上支払いが滞ると、債権者は一括請求をすることができるようになり、返済計画が頓挫してしまいます。
任意整理で支払いきれないような場合、または支払いきれないおそれがある場合には、弁護士は基本的に自己破産を薦めます。
三つ目は、計算の上では任意整理で頑張れば支払えるという場合でも、3年~5年も借金返済を続けるのは苦しいという方もいらっしゃいます。
早く経済的に立ち直りたいのであれば、借金と返済能力のバランス次第では、任意整理ができる場合でも、自己破産手続を利用できるケースもあるので、弁護士と相談をしてみましょう。
自己破産手続が向いていない方
一方、次のような方は自己破産手続には不向きです。
・住宅ローンの借り入れをしていて住宅を失いたくない
・自己破産すると資格を失う仕事についている
・連帯保証人に絶対に迷惑をかけられない
一つ目は、住宅ローンの借り入れをしていて住宅を失いたくないという場合です。自己破産手続においては、住宅ローンを含む全ての債権者を対象に手続を行います。
住宅ローン債権者は、債務者の自宅に抵当権という担保を持っている状態ですので、自己破産手続に入ると抵当権を行使して住宅を競売にかけられます。これによって自宅から退去する必要が生じます。
このような場合、個人再生の手続を取ることで住宅ローンだけ手続対象から除くことができ、従来どおり支払うことによって競売を免れることができます。
住宅ローンで借り入れをしていて住宅を失いたくない場合には、自己破産は向いておらず、個人再生を利用することを検討します。
二つ目は、自己破産すると資格を失う仕事についている場合です。自己破産手続の申立てをすると、破産法に規定されている「破産者」という状態になります。
この状態になると、一定の資格や登録を必要とする仕事についている方は、一時的に資格を失うことになります(欠格事由)。該当する例として多いのが、警備員・宅建士・保険募集人などで、いずれもお金を預かる可能性がある仕事です。
このような仕事についている方の場合には、個人再生の利用を考えます。
なお、医師・看護師・薬剤師といった生命・身体への影響を考えて資格制にしているものについてはそのまま仕事を続けることができます。
三つ目は、連帯保証人に絶対に迷惑をかけられないという場合です。
奨学金や事業資金の借り入れに代表されるような、連帯保証人がついている債務については、主債務者が自己破産をすると連帯保証人に請求がいくことになります。
家族等の連帯保証人には絶対に迷惑をかけられないような場合には、連帯保証人がいる債権を除いて任意整理を行うことを検討します。
ただ、任意整理で支払えないような場合には、連帯保証人に事情を話して自己破産をする他ありません。この場合、迷惑をかけたからといって自己破産の準備中や手続中に連帯保証人にだけ返済することは、偏頗弁済として禁止されますので絶対にしないようにしましょう。
自己破産できる条件とは?

- 債務者が支払不能にあることが破産手続開始の条件
- 免責不許可事由がないことが免責許可決定の条件
自己破産をするには何か条件がありますか?
自己破産は破産手続で債務者の財産を清算し、免責手続で残債務を支払う責任を免除してもらうために行うものです。破産手続を開始するには、債務者が支払不能であることが要件とされています。また、免責許可決定をするには、免責不許可事由がないことが要件とされています。
自己破産が認められるには、まず破産手続を開始するための要件を満たすことが必要です。
破産手続を開始するための要件は、債務者が支払不能にあることです。ここでいう支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。
また、裁判所が免責許可決定をする要件は、破産法が定める免責不許可事由のいずれにも該当しないことです。
・債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠匿等すること
・特定の債権者に対する債務について、その債権者に特別な利益を与える目的または他の債権者を害する目的で弁済等をすること
・浪費または賭博その他射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと
・虚偽の債権者名簿を提出したこと
・破産手続において裁判所が行う調査において説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと
また、非免責債権は免責許可決定を得ても免責されないことから、債務の全てが租税公課などの明らかな非免責債権である場合、自己破産を申立てる意味がありません。債務者が非免責債権に該当しない債務を負担していることも、自己破産ができる条件ということができます。
まとめ
自己破産特有のメリット・デメリットはそれぞれ沢山あります。
どの手続が自分に合っているのか、法律の専門家である弁護士と相談してみましょう!

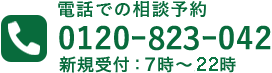
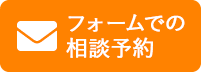


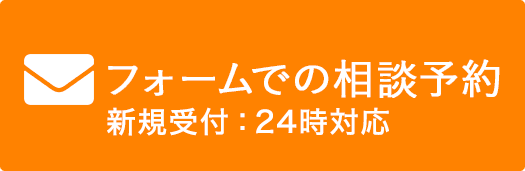
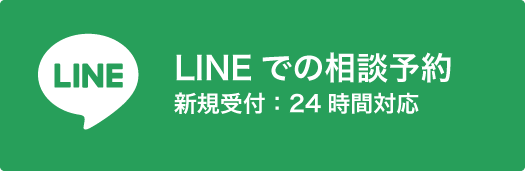
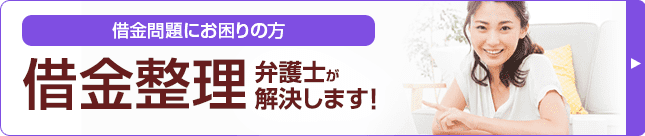
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください