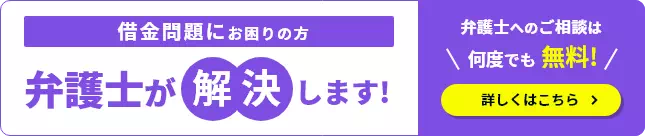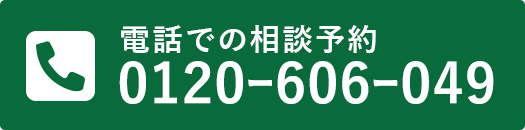- 自己破産が認められるためには条件がある
- ギャンブルや浪費が原因でも、裁判所の裁量免責が認められることもある
- 自己破産が認められなくても、借金問題を解決する方法は他にある
【Cross Talk 】自己破産が認められる4つの条件とは?
自己破産を考えているのですが、誰でもできるものなのでしょうか?
自己破産の手続を進めるにはいくつかの条件があります。
そうなんですね。自己破産の条件について詳しく教えてください。
借金問題で悩んでいる方の中には、自己破産を検討している方も多いでしょう。しかし、自己破産は誰でも認められるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、条件を満たしていても、借金の経緯や債務の種類によっては認められない場合もあります。そこで本記事では、自己破産が認められる4つの条件と、認められない場合の具体的な状況、そして代替手段について詳しく解説します。
借金の悩みから解放されるための第一歩として、まずは自己破産の正しい知識を身につけましょう。
自己破産が認められるための4つの条件

- 支払不能の状態になければ自己破産ができない
- ギャンブルや過度な浪費によって認められない場合がある
自己破産は誰でも認められるのでしょうか。それとも、何か条件がありますか?
自己破産にはいくつかの条件があるので、誰でも認められるわけではありません。
自己破産の条件について、詳しく教えてください。
支払不能の状態である
自己破産をするには、債務者が「支払不能」の状態に陥っている必要があります。この「支払不能」について、破産法では以下のように定められています。
引用元:破産法 | e-Gov法令検索
支払不能に当たるかどうかを判断するにあたっては、債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出を考慮するほか、借入や弁済猶予を得ることができるか否かに関係するため、債務者の方の信用も勘案されます。
免責不許可事由がない
免責不許可事由は、債権者にとって著しく不公平な結果になることを防ぐために設けられた規定です。
代表的な免責不許可事由としては、浪費や賭博射幸行為などがあります。また、債権者を害する目的での財産隠匿や不利益な処分、虚偽の債権者名簿の提出や裁判所への説明拒絶なども、免責不許可自由に該当します。
もっとも、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、破産手続き開始に至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責が許可される場合もあります(破産法252条2項)。
この裁判所の裁量による免責を裁量免責ということがあります。裁量免責の認否に一律の基準はありませんが、免責不許可事由の軽重、破産手続きへの協力姿勢、経済的更生の可能性などが総合的に考慮されます。例えば、軽微な浪費やギャンブルで反省が認められる場合は許可される傾向にある一方、財産隠匿や手続き妨害など、重大な事由がある場合には比較的免責許可の決定がされにくいでしょう。
関連記事:自己破産で免責不許可事由があったけど、免責された場合
非免責債権に該当しない
債権の性質によっては自己破産手続における免責許可決定に適さない性質のものがあり、これを非免責債権といいます。非免責債権は、自己破産をしても免責の対象とはなりません(破産法253条但書き)。
非債免責債権には、以下のようなものがあります。
なお、非免責債権があるからといって、自己破産や個人再生ができないわけではありません。非債免責債権がある場合、自己破産しても非免責債権は免責・減額の対象外になり、それ以外の借金のみが免責されることになります。
費用を支払える
破産手続きを開始するには、裁判所に対して予納金等の費用を納付することが必要です。裁判所に納付する費用を用意できない場合、破産手続が開始できません。
予納金は、裁判所の手続に要する費用として使用され、手続き終了後に余剰が生じても、申立人には返還されずに債権者への配当に充てられます。
納付する金額は破産手続の種類によって異なり、手続が簡易な同時廃止の場合、一般的に2万円程度の納付が必要になります。これに対し、破産管財人による財産調査が必要な管財事件の場合、20万円を超える費用が発生する場合もあります。
破産を検討する際は、これらの手続費用を賄える資力があるうちに、早期の決断を行うことが重要です。
自己破産ができない状況について

- 借金の額が少額だと自己破産が認められにくくなる
- 債権の種類や借金の経緯などにより、自己破産できない場合がある
実際に自己破産ができない場合もあるのでしょうか。
はい。条件を満たしていない場合、自己破産できない場合もあります。
それでは、どのような場合に自己破産ができないのか、詳しく教えてください。
借金の額が少額である
債務総額が少額である場合、支払不能状態とは認定されないため自己破産の申立てが認められない可能性があります。
また、自己破産の手続費用の総額が50万円以上必要となることが多く、破産手続にかかる費用を払えるのであれば債務を弁済できるということになるため、経済的合理性の観点からも50万円を下回る債務額での破産申立ては適切ではないともいえます。
最終判断は個々の状況を総合的に検討して行われるため、金額の多寡のみで決めるのではなく、資産や収入状況など総合的に考えて破産の要否を検討すると良いでしょう。
債務が税金の滞納や保険料の滞納しかない
破産は、債務について免責決定を受けることによって、再び経済活動をやり直すことを主な目的として申し立てることが多いですが、公租公課は非免責債権として扱われる「租税等の請求権」(破産法253条1項1号)に分類されるため、これらの債務のみの場合は実質的に破産の効果が期待できません。
所得税・住民税などの各種税目、国民健康保険料、国民年金保険料などは、破産法253条により非免責債権とされており、破産手続を経ても弁済義務が残ります。したがって、これらの債務のみがある状態で破産申立てを行っても実益がありません。
公租公課の滞納については、破産以外の解決手段が用意されています。例えば、税務署や自治体窓口で分納計画の策定が可能であり、国民健康保険料については減免制度の適用も検討できます。
まずはこれらの制度活用を優先し、支払条件の見直しや軽減措置の申請を行うと良いでしょう。
浪費やギャンブルでの借金が大半である
投機行為や過度な消費が債務の主な原因となっている場合、免責不許可事由に抵触して免責許可決定を受けられない場合があります。
破産法252条1項4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由として定めています。
該当する行為としては、パチンコ・競馬・競輪などの公営ギャンブル、外国為替証拠金取引や株式投資等の投機的取引などが挙げられます。また、過度な買い物や娯楽費の支出なども「浪費」として免責不許可事由とみなされる可能性があります。
関連記事:ギャンブルの借金って破産できる?借金の種類で自己破産に影響あるの?
過去7年間に自己破産したことがある
破産法252条1項10号により、免責許可の申立ての前7年以内に免責許可の決定が確定したことが免責不許可事由として規定されているため、前回の免責から7年を経過していない場合は原則的に免責が認められません。
手続費用が払えない
破産手続きに必要な費用を準備できない場合、申立て自体が受理されないため、自己破産手続きを開始できません。
費用の額は破産手続の類型により大きく異なり、同時廃止事件では比較的少額ですが、管財事件では20万円程度が標準的であり、事案の複雑さによってはさらに高額となる場合があります。
なお、管財事件における予納金は申立て時の一括納付が求められ、分割による納付は原則として認められないので、自己破産を検討している場合には最低限予納金を支払う資金は確保しておくことが重要です。
自己破産ができない場合の対処法

- 自己破産以外の債務整理ができる場合がある
自己破産ができない場合、どうすれば良いでしょう。
自己破産の他にも、借金問題を解決する方法はいくつかあります。
では、自己破産ができない場合の対処法について教えてください。
任意整理をする
任意整理は、債権者との直接交渉により主として将来利息の免除を求め、元本を3~5年で分割して返済する手続きです。基本的には裁判所の関与がない私的整理であるため、当事者間の合意に基づいて行われます。
任意整理では、対象となる債権を選択できる点が他の債務整理との大きな違いです。例えば、保証人付き債務や住宅ローンを債務整理の対象から除外することで、第三者や重要な財産への影響を回避しながら債務の軽減を図ることができます。
一方、元本の大幅な圧縮は期待できないため、返済資力がなければ借金の解決手段にはなりません。そのため、将来利息の免除程度では完済が困難な場合、より強力な債務整理手続きを検討する必要があるでしょう。
関連記事:任意整理とは?~任意整理の手続やメリット・デメリットを解説!~
個人再生をする
個人再生は、裁判所の認可を得た再生計画に基づき、債務を大幅に圧縮する法的手続きです。債務総額を一定の割合まで減額し、圧縮後の債務を原則3年間で弁済します。債務者の方が保有している資産にもよりますが、例えば、債務額が500万円以上1500万円以下の場合、その5分の1まで債務が減額されるのが原則となります。任意整理と同じで債務の完全な免除ではなく、減額された債務の履行が前提となります。
個人再生の大きなメリットは、住宅資金特別条項の活用により、居住用不動産を維持しながら債務整理ができる点です。ただし、継続的な収入の見込みが必要であり、圧縮後の債務を確実に履行できる資力が求められます。
関連記事:個人再生ってどのくらいかかるの?個人再生の期間と費用を解説
まとめ
自己破産が認められるには、支払不能状態であること、免責不許可事由がないこと、負っている債務が非免責債権に該当しないこと、予納金等の手続費用を支払えることの4つの条件を満たす必要があります。
また、借金額が少額、ギャンブルや浪費が原因、過去7年以内の破産歴がある、予納金が支払えないといった場合、自己破産の申立てができないか、もしくは免責許可決定がされない場合があります。
ただし、ギャンブルや浪費行為などの免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められることがあります。また、自己破産ができないとしても、任意整理や個人再生といった他の手段で借金問題を解決できることがあります。
まずは自分の状況を正確に把握し、どの手続きが最も適しているかを慎重に検討することが大切です。迷った際は弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な方法を選択しましょう。

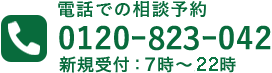
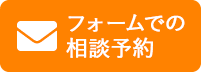


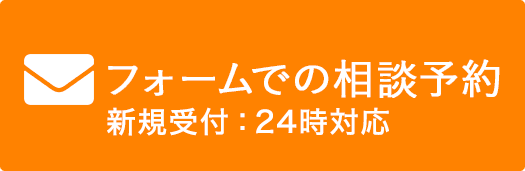
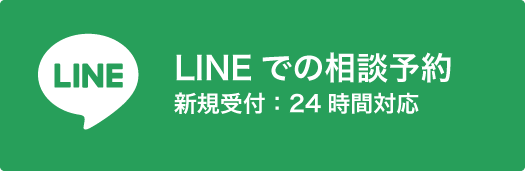
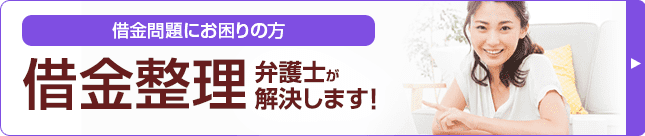
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください