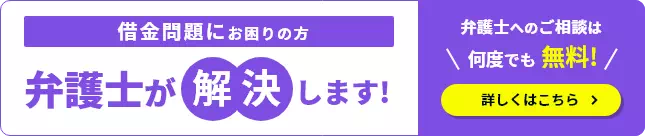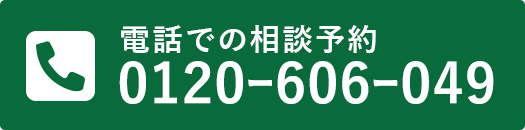- 自己破産をする金額は決まっていない
- 自己破産は「支払不能」である場合に利用可能
- 自己破産自体にかかる金額
【Cross Talk】自己破産をすることができる借金額はいくらからですか?
借金が200万円を超えていて、返済がかなり厳しく、自己破産を考えています。ところで自己破産はいくら借金があれば手続きができるのでしょうか。
自己破産手続きは、借金がいくらあれば利用できる…と決められているわけではなく、「支払不能」である場合に利用できるとされています。これは借金の額と支払能力のバランスから決まります。
そうなのですね!私の場合はどうでしょうか?
自己破産手続きを利用するにあたって借金がいくらからいくらまでという明確な金額が定められているわけではありません。自己破産手続きを利用することができるのは「支払不能」である必要があるとされています。自己破産にかかる費用と併せて確認をしてみましょう。
借金の金額によって自己破産の可否が決められるわけではない

- 借金の金額がいくらであれば自己破産ができる…と決められているわけではない
- 自己破産をすることができるのは「支払不能」といえる場合
自己破産をするための借金の金額が明確に決められているわけではないのですね?
はい、一見借金が多額でも収入がそれに応じて多いような場合には返済できない状態にあるとはいえません。
自己破産をすることができる借金の金額に決まりはあるのでしょうか。
自己破産をするための条件として具体的な借金の額が決まっているわけではない
まず、自己破産をするために必要な借金の額が決まっているわけではありません。
つまり、借金が〇〇万円以上の方は自己破産手続きを利用できる、借金が〇〇万円以下の方は自己破産手続きを利用することができない、と明確な基準が存在するわけではないのです。
このような勘違いするのは、同じ裁判所を通じた債務整理手続きである小規模個人再生が、借金の額が5,000万円を超えている場合には利用することができないとされていることに原因があると考えられます(民事再生法221条1項、239条1項)。
自己破産が認められる条件とは?
自己破産手続きにより債務が免責されるための要件について確認しましょう。
支払不能であること
自己破産手続きが開始されるためには、申し立てをした際に支払不能である必要があります(破産法15条1項)。
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
「支払不能」とはどのような状態を指すかについて、同じく破産法2条11項で次にように定められています。
難しい定義ですが、一時的に返済ができない状態であるだけでは足りず、債務の全部または大部分について当面返済ができない状態にある必要があります。
支払不能かどうかを判断するためには、債務の総額だけでなく、預貯金等の資産や毎月の収支状況などを具体的に検討する必要があります。
自分が支払不能の状態にあるかどうかを確認するためにも、弁護士に相談するようにしてください。
免責不許可事由がないこと
債務の免責を受けるためには、破産手続開始の申立てに加えて免責許可の申立てを行い、破産法が定める「免責不許可事由」がないことが必要です(破産法252条1項)。
免責を受けるのにふさわしくない様々な事情が252条1項に列挙されており、例としては、
なお、免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責(破産法252条2項)を受けることで、免責される可能性はあるので、諦めずに弁護士に依頼して破産手続きを行いましょう。
非免責債権に当たらないこと
免責される債権は非免責債権以外の債権に限られます。
破産法253条1項各号で、自己破産手続によっても免責されない債権について規定されています。
いくつか代表的なものを挙げると、
といったものが挙げられます。
銀行や消費者金融・信販会社などの貸金業者からの借金については、非免責債権ではなく、免責の対象となります。
自己破産が認められない条件とは?
そもそも破産手続きが開始されない場合、免責許可がなされない場合を見てみましょう。
支払不能状態ではないと判断される場合
支払不能ではない場合には、破産手続開始の原因がないので、そもそも自己破産手続きを利用できません。
代表的な例としては、
以上のような例が挙げられます。
免責不許可事由に該当する場合
上述するように、自己破産手続きが開始したとしても、免責不許可事由が存在し、裁量免責も受けられない場合には免責されません。
自己破産の可否をどのように判断すればよいのか
実務上自己破産を利用できるかどうかは、弁護士に依頼して判断していることがほとんどです。
債務整理の方法として、自己破産以外に任意整理というものがありますが、これは債権者と直接交渉して残債務を36回(3年)~60回(5年)に分割して毎月支払う手続きになります。
例えば300万円の借金がある場合には、36回払いだと月8万4千円、60回払いだと月5万円の支払いが必要となります。
毎月の収支状況にかんがみて、この金額の支払いができない場合には任意整理を行うことができないので、自己破産を利用するのが基本です。
ただ、住宅ローンを支払っている場合や、破産による職業制限を受けるような場合には、個人再生を検討することになります。
自己破産にかかる費用

- 自己破産手続き自体にかかる費用
- 自己破産手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用
金額という言葉に関連してもう一つ気になるのが、自己破産手続きにかかる費用なのですが…。
自己破産手続き自体にかかる費用と、弁護士に依頼するときにかかる費用があるので確認しておきましょう。
自己破産手続きは裁判所を通じた手続きであるため諸費用が発生します。また、弁護士に依頼する場合には弁護士費用が発生します。
それぞれの金額を確認しておきましょう。
自己破産手続き自体にかかる費用
自己破産手続き自体には次のようなお金がかかります(個人1件の場合を想定しています。)。
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 1,500円 |
| 予納郵券(切手) | 裁判所による(東京地方裁判所の場合には原則っとして4,950円) |
| 予納金 | 同時廃止事件の場合1万1859円 管財事件の場合 最低20万円及び1万8543円 |
弁護士費用の金額
自己破産を含む債務整理については弁護士に依頼をして行うのが通常です。
というのも、弁護士に依頼をすると、債権者に取り立てを止めさせることが可能なので、落ち着いて自己破産手続きを行うことができるからです。
弁護士費用は法律事務所によって異なるのですが、1件20万円~50万円程度かかります。
そのような金額を一括で支払うのは難しいという方が大半なので、債務整理を取り扱う法律事務所では費用の分割払いに対応しているところが多いです。
破産手続きを申し立てる方針を採った場合、借金の返済をしてはいけないので、その分を弁護士費用の分割支払いに充てることが可能となり、手持ちの現金が少ない場合にも無理なく依頼をすることができます。
自己破産をしたいなら弁護士に相談を

- 自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット
- 同時廃止で手続きが終われば自分で申立てをするよりも安くなる
自己破産をする場合には必ず弁護士に依頼する必要がありますか?
法律的には依頼する必要はないのですが、弁護士に依頼をしていただければ正しく・スムーズに手続きを進められることはもちろん、同時廃止・少額管財などの簡易な手続きを利用するためには弁護士に依頼することが欠かせない場合があります。
自己破産をしたい場合には弁護士に依頼した方がスムーズに進められます。
その理由としては、
- 自己破産が相当かどうかアドバイスをもらえる
- 弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てを止めることができる
- 自己破産を依頼すれば法的サポートを受けることができる
- 弁護士に依頼すれば簡易な手続きで終わらせることができる場合がある
という4つの理由からです。
自己破産が相当かどうかアドバイスをもらえる
まず、相談することで本当に自己破産が相当なのかどうかアドバイスがもらえます。
上述したように、自己破産手続きは支払不能の状態に至っていなければ、申立てができません。
支払不能状態に至っているのか、他の手段のほうが相当なのか、個人の収支状況や借入内容を確認しなければ判断できないことのほうが多いです。
借金の相談が無料というところも多いので、どの手続きが良いのか迷っているのであれば、まずは相談してみるべきです。
弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てを止めさせることができる
自分で自己破産手続きをすることも法律上は可能です。
しかし、弁護士に自己破産手続きを依頼すると、それ以降返済をしてはいけませんし、債権者からの取り立てを止めさせることができます。
返済を止めなければ債務額がいつまでも確定しませんし、返済の苦労がともないます。
また、弁護士に依頼しないで返済をやめると、当然のように電話・通知での取り立てが始まります。
弁護士に依頼をすれば、貸企業法21条1項9号に定められているように、正当な理由がない限り取り立てができなくなります。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
自己破産手続きは書面を作成したり、記載内容を裏付けるための証拠を収集して提出する必要があったりと、やることが多く時間がかかります。
弁護士に依頼すれば落ち着いて自己破産手続きを行うことが可能です。
自己破産を依頼すれば法的サポートを受けることができる
弁護士に依頼すれば、自己破産の申立てにあたっての法的サポートを受けることができます。
申立書の作成、必要な証拠資料の収集、裁判所・管財人とのやりとりや、裁判所・管財人の事務所への同行などを行ってくれます。
同じ債務整理をしている司法書士は、裁判所への書面の提出業務にとどまり、裁判所・管財人の事務所への同行を行えないので注意しましょう。
弁護士に依頼すれば簡易な手続きで終わらせられる
弁護士に依頼すれば簡易な手続きで終わらせることができる可能性があります。
破産手続きは、破産法の理念からすると、通常、管財(特定管財)事件で行われることが想定されています。
しかし、同時廃止や少額管財など、管財人・裁判所の調査などの手続きを簡易にするような運用がなされており、これらは申立代理人である弁護士が適切な申立てをすることが前提となっているものです。
そのため、弁護士が申立てに関与していない本人申立ての場合には、通常管財とすることになっており、同時廃止としないこととする裁判所も少なくありません。
弁護士に依頼して、簡易な手続きで終わらせられるほうが、管財人に支払う費用を節約できます。
なお、司法書士は上述したように自己破産手続きでは書類作成のみに権限が限られるので、本人申立てと同様に扱われます。
自己破産が相当な案件である可能性がある段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
まとめ
このページでは、自己破産に関する借金額について、支払不能という要件や自己破産にかかる費用などと一緒にお伝えしました。
自己破産に関する借金額は一律ではなく、個人が置かれている状況に応じて「支払不能」かどうかが判断されます。
自己破産をすることが適切かどうかも含めて、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

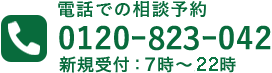
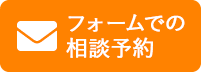


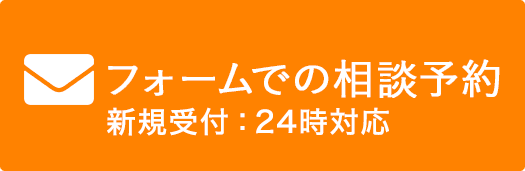
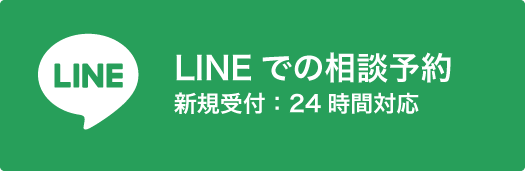
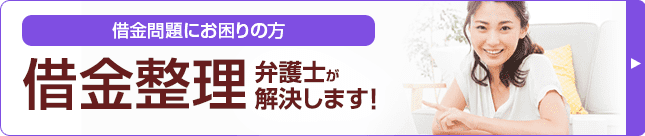
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください