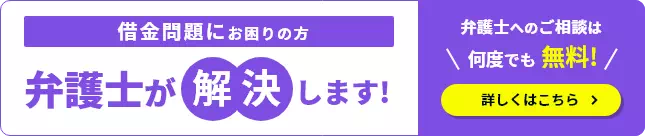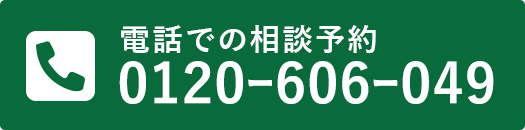- 法人破産には予納金と弁護士費用が主な費用として必要
- 予納金は負債規模や事案の難易に応じて20万円〜1000万円以上かかる
- 費用が支払えない場合は資産処分や分割払いなどの対処法がある
【Cross Talk 】法人破産の申立に必要な費用を解説!
会社の経営が行き詰まり、法人破産を検討していますが、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
法人破産には主に予納金と弁護士費用がかかります。予納金は負債規模や事案の難易によって異なりますが、1,000万円以上になることもあります。
既に資金がほとんどない状態なのですが、そんな高額な費用は支払えないかもしれません。
費用が支払えない場合の対処法もあるので、状況に応じた方法を一緒に検討しましょう。
法人破産を申立てるには、裁判所への予納金や弁護士費用などが必要です。しかし、既に資金繰りに行き詰まっている会社にとって、これらの費用を捻出することは容易ではありません。
そこで、本記事では、法人破産にかかる具体的な費用の内訳と金額の目安、そして費用が支払えない場合の実践的な対処法について解説します。適切な準備と知識があれば、財政的に厳しい状況でも法人破産の手続きを適切に進めることが可能です。
予納金とは破産手続に必要な費用に充てるお金

- 予納金は破産法で定められた裁判所へ支払う費用
- 予納金を納めないと破産手続開始決定がなされない
予納金とは具体的にどのようなお金なのですか?
予納金とは破産手続きの費用として、申立時に裁判所に納める費用です。破産法で義務付けられており、主に破産管財人の報酬などに使われます。
いつ、どのように支払うのでしょうか?詳しく教えてください。
予納金とは、破産や個人再生をする際に裁判所へ支払う費用のことであり、破産法によって裁判所への支払いが義務付けられています。
第二十二条破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
予納金は、主に破産管財人の報酬に充てられるほか、破産を進める際の様々な手続きに使われ、手続き後に余った分は債権者に分配されます。
破産申立てから2週間~1か月後に、裁判所から予納金の額に関する通知が届くので、予納金はその際に支払います。支払期限は定められていませんが、予納金を納めないと破産手続開始決定が出されないため、破産によって免責を受けるためには予納金の支払いが必須です。
法人破産にかかる主な費用

- 予納金は負債額や事案の難易に応じて20万円~1,300万円程度必要
- 弁護士費用は中小企業で50~150万円程度が一般的
法人破産にかかる費用には、具体的にどのようなものがありますか?
主な費用は予納金と弁護士費用です。他にも申立印紙代や官報公告費用などの諸費用がかかります。
具体的にはどのくらいの金額になるのでしょうか?それぞれの費用について詳しく教えてください。
予納金
予納金の金額は各地域の裁判所によって異なりますが、おおよそ以下のような金額とされています。
| 負債額1億円未満 | 200万円 |
| 負債額1億円~10億円未満 | 250万円 |
| 負債額10億円~30億円未満 | 300万円 |
| 負債額30億円~50億円未満 | 350万円 |
| 負債額50億円~100億円未満 | 500万円 |
| 負債額100億円~250億円未満 | 900万円 |
| 負債額250億円~500億円未満 | 1000万円 |
| 負債額500億円~1000億円未満 | 1,200万円 |
| 負債額1000億円以上 | 1,300万円 |
予納金の金額は、債権者の数や破産手続きにかかる日数などに応じて金額が変動します。少額管財であれば20万円程度で済む場合が多いのですが、複雑で時間がかかるほど予納金も高額になり、1,000万円を超えることもあります。
弁護士費用
弁護士費用は中小企業の場合で50~150万円程度が一般的です。ただし、会社の財産、債権者の数などによって変動するため、一概にはいえません。
以前は日弁連が報酬規程を定めており、その報酬規程に従って弁護士費用が定められていましたが、日弁連の報酬規程が撤廃されて以降は各弁護士が自由に報酬を定めています。そのため、報酬規定が撤廃されて以降も(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をそのままを用いている弁護士事務所はありますが、独自の報酬を設定している弁護士事務所も数多くあります。
弁護士費用の金額を明確にしておくためには、依頼前に無料相談を利用するなどして、見積もりを取っておくようにしましょう。
その他の印紙代など
予納金と弁護士費用のほかに、法人破産には以下のような費用が掛かります。
| 申立印紙代 | 1,000円 |
| 官報公告予納金 | 10,000~15,000円 |
| 予納郵券 | 5,000~10,000円 |
| 債権者宛封筒 | ~1,000円 |
破産の内容によって多少金額は異なりますが、数万円以内に収まる場合がほとんどです。そのため、予納金や弁護士費用と比較すれば、これらの雑費はそこまで大きな金額にはなりません。
予納金の費用を抑えることができる場合

- 少額管財を選択すれば予納金を20万円程度に抑えられる
- 少額管財は弁護士が代理人となることが条件
予納金が高額で支払うのが難しいのですが、費用は抑える方法はありますか?
少額管財という制度を利用すれば、予納金を大幅に抑えることができます。
少額管財とはどのような制度なのですか?詳しく教えてください。
予納金を抑えるポイントは、少額管財を選択することです。少額管財であれば予納金を20万円程度に抑えられるので、高額の出費を抑えることができます。
ただし、少額管財が利用するには、弁護士が代理人となって破産申立てをすることが条件となります。これは、弁護士が代理人となることで事前に十分な調査がなされ、スムーズに手続きが行えることが期待できるからです。
法人破産の費用が支払えない場合の対処法

- 会社の財産処分や未回収の売掛金回収で費用を捻出できる
- 弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多い
会社にほとんど資金がない場合、破産費用をどのように工面すれば良いですか?
いくつかの資金調達方法があり、社内の資産活用から外部支援まで選択肢を検討できます。
では、それぞれの方法について具体的に教えてください。
1)会社の財産を処分する
予納金を支払う余裕がない場合、会社の保有財産を適切に処分して費用に充てるという方法があります。オフィス家具、事務機器、在庫品、車両など、売却可能な資産があれば、それらを現金化することで費用を捻出できる可能性があります。
ただし、破産手続き開始前は会社財産の処分に制約があるため、適正価格での売却を心がけることが重要です。破産法では、破産者が債権者を害するような財産の処分を行った場合、処分行為自体が破産管財人によって否認されることが定められています。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2)未回収の売掛金を回収する
会社に未回収の売掛金がある場合、それらを積極的に回収して破産費用に充てることも有効な手段です。取引先に対して状況を丁寧に説明し、可能な限り早期の入金を依頼しましょう。
3)第三者が代わりに支払う
法人の財産の中から費用を支払う余裕がない場合、家族や知人などの第三者から援助を受けるという方法もあります。
4)弁護士費用を分割払いする
法人破産の場合、依頼者の経済状況が厳しいことが多いため、多くの弁護士事務所が柔軟な支払い条件を提示しています。そのため、弁護士費用については分割払いに応じている事務所が多くあるので、予納金の支払いを最優先にして残りの財産の中から弁護士費用を分割で支払うという方法もあります。
もし、相談中の弁護士が分割払いに対応していない場合、複数の事務所に相談して比較検討すると良いでしょう。
また、弁護士が受任通知を債権者に送付すれば一時的に債権者からの取り立てが止まるので、従来の返済資金を破産費用に回すことも可能です。
まとめ
法人破産には予納金、弁護士費用、その他の諸費用などが必要です。予納金は負債規模や債権者数、事案の難易によって異なり、小規模な会社であれば20万円程度から、大規模な会社では1,000万円を超える場合もあります。
これらの費用を支払うのが難しい場合でも、会社の財産処分、未回収の売掛金回収、第三者からの援助、弁護士費用の分割払いなど、いくつかの対処法があります。また、少額管財の制度を利用できれば、予納金を大幅に抑えることも可能です。
法人破産の手続きを検討する際は、早い段階で弁護士に相談し、費用面も含めた適切なアドバイスを受けることをおすすめします。適切な専門家のサポートを受けることで、会社の状況に適した方法で破産手続きを進めることができるでしょう。

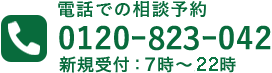
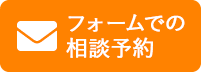


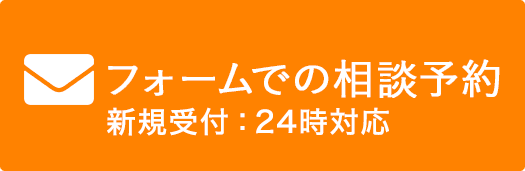
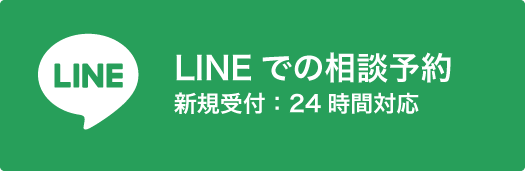
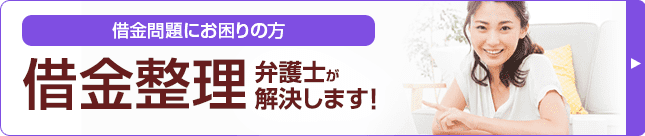
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください