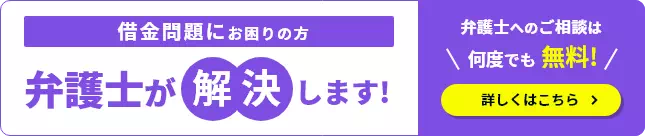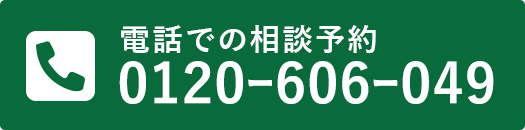- 放置すると差押や取立てで状況が悪化する
- 法人破産をすると債務がゼロになり、従業員・取引先への被害も最小限に抑えられる
- 破産・清算・再生など、状況に応じた複数の選択肢がある
【Cross Talk 】法人の破産手続きをせずに放置するリスクとは?
会社の経営が厳しいのですが、このまま放置してしまうとどうなるのでしょうか?
放置することで差押や連帯保証人への取立てなど、より深刻な問題に発展する可能性があります。
具体的にはどのようなリスクがあるのか、また法人破産以外にも選択肢があるのか、詳しく教えてください。
経営難に直面し、法人破産という選択肢が頭をよぎりながらも、実際に踏み切ることの重大さに躊躇する経営者は少なくありません。しかし、法人破産を放置することで生じる影響は、適切に手続きを行った場合と比べて格段に深刻になる可能性があります。
本記事では、放置することの具体的なリスクと、適切に対処することのメリットについて詳しく解説します。
法人の破産手続きをせずに放置するとどうなるか

- 放置しても債務は消滅せず、債権者からの督促や取立てが継続する
- 債権者破産により、経営者の意思とは無関係に破産手続きが進行する場合がある
破産手続きをせず、このまま放置するとどうなってしまうのでしょうか?
債権者からの督促は続きますし、場合によっては債権者側から破産申立てをされることもあります。
具体的な影響について、詳しく教えてください。
経営状況が悪化して事業継続が困難になり、法人破産をしなくてはならない状況にあるにもかかわらず、これをせずに放置し続けると、債権者側からの請求や取立てによって経営難になる可能性が高まります。また、債権者破産が申立てられ、経営者の意思とは無関係に破産手続きが進行する場合もあります。
経営難に陥った際、「破産手続きに費用がかかる」「手続きが煩雑で心理的負担が大きい」といった理由で法人破産を放置してしまうことがありますが、破産手続きを行わずに放置しても問題の根本的な解決にはなりません。そのため、法人破産を行わない限り債権者からの督促や取り立ては継続します。
つまり、法人破産の放置は一時的な問題の先送りに過ぎず、最終的にはより深刻な事態を招く危険性があるのです。
関連記事:
法人破産のメリット・デメリットを解説
法人破産をせずに放置するデメリット

- 財産を差押られ、連帯保証人へも取立てがいく
- 長期間の精神的プレッシャーと社会的信用失墜で将来の事業展開にも影響
具体的に放置することでどのような被害が発生するのでしょうか?
主に4つの深刻なデメリットがあります。財産の差押、連帯保証人への取立て、精神的負担の継続、そして社会的信用の失墜です。
連帯保証人にも迷惑をかけてしまうのですね。それぞれのデメリットについて詳しく教えてください。
財産を差押られる
法人破産の手続きをしないまま放置すると、債権者によって会社や代表者の財産が差押られる可能性があります。
債権者が裁判を起こして勝訴すると、債務者は金銭の支払いを命じられますが、それでも支払いがなされない場合は不動産、預金口座、売掛金、機械設備などの財産が差押の対象となります。そして、差押られた財産は換価処分され、債権者への返済に充てられます。
差押が実行されると事業の継続に必要な資産も失うことになるだけでなく、従業員の給与すら払えなくなってしまうこともありえます。
関連記事:
法人(会社)破産に必要な費用を完全解説!
連帯保証人が取り立てられる
法人破産を放置すると、連帯保証人への取立てが開始される可能性が高まります。金融機関からの借入金については代表者個人が連帯保証している場合が多く、会社が返済できない場合は代表者に対しても取立てが及びます。
精神的なプレッシャーがかかる
法人破産を放置すると、長期間にわたって精神的なプレッシャーを受け続けます。債務の時効は最大で10年間なので、その間は債権者からの取立てや督促が続きます。
継続的な取立てによる心理的なプレッシャーは非常に大きく、精神的にも肉体的にも深刻なストレスが蓄積されるでしょう。
適切な時期に破産手続きをおこなえば、こうした長期間の苦痛から解放されます。
社会的信用を失う
法人破産を放置すると、会社および代表者個人の社会的信用に深刻な影響を与えるおそれがあります。
取引先や金融機関は支払い遅延の情報を把握すると、リスク回避のために新規取引や融資に慎重になります。また、こうした経営状況の悪化は噂として広まりやすく、「責任ある対応を取らない会社」というイメージが定着してしまう可能性もあります。
そうなれば、これまで築いてきた実績や信頼関係が揺らぎ、顧客が取引継続不可と判断する可能性があります。
代表者が法人破産後に新たな事業を始めた際も、このような過去の信用問題が足かせとなることがあるので、先の事業展開にも大きな影響を与えるリスクがあるのです。
法人破産をするメリット

- 会社の債務が消滅し、代表者個人も連帯保証債務から免れる
- 従業員・取引先への被害を最小限に抑え、新たな事業スタートの機会を得られる
法人破産をすることで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
最大のメリットは借金がゼロになることです。また、適切なタイミングで手続きを行えば従業員や取引先への被害も最小限に抑えられます。
借金がゼロになる
法人破産を行うことで、会社全ての債務が法的に消滅し、借金がゼロになります。
個人の自己破産では裁判所の免責決定が必要ですが、法人破産では会社自体が消滅するため債務も自動的になくなります。これにより、債権者からの督促や取立ても完全に停止し、長期間続いていた精神的な負担から解放されます。
また、代表者が会社の債務を連帯保証している場合、会社と同時に個人の自己破産をすれば連帯保証債務も免責されます。金融機関からの借入金の多くは代表者の連帯保証が付いているため、代表者個人も債務から解法されるために自己破産が必要です。
従業員・取引先の被害を最小限に抑えられる
適切な時期に法人破産を行うことで、従業員や取引先への被害を最小限に抑えられます。
まず、破産手続きを早期に決断すれば、換価処分の対象となる財産の目減りが抑制され、結果的により多くの配当を債権者に提供できる可能性があります。
また、従業員の未払給料や退職金は「財団債権」や「優先的破産債権」として他の債権よりも優先的に扱われるうえに、国の未払賃金立替払制度の活用によって建て替えも受けられるので、会社が破産しても救済される手段があります。
※参考:
破産法149条1項、同98条1項│破産法 – e-Gov 法令検索、
未払賃金立替払制度の概要と実績│厚生労働省
新たに事業をスタートできる
法人破産によって債務から解放されることで、代表者は新たな事業をスタートする機会を得られます。
法人破産後に別会社を立ち上げることは法律上問題なく、破産をすれば新事業で得た売上や利益を借金返済に回す必要もありません。社会的信用の回復には時間を要するため、金融機関からの事業資金の借入はしばらくの間行うことはできません。段階的に事業を拡大していけば、、法人破産を放置し続けた場合と比べれば有利な状態からスタートできるでしょう。
法人破産の種類

- 破産手続と特別清算は会社を消滅させる清算型の手続き
- 民事再生と会社更生は事業を継続しながら再建を図る再建型の手続き
法人破産以外にも選択肢があると聞きましたが、どのような種類があるのでしょうか?
大きく分けて清算型と再建型があります。会社を解散する場合は破産手続や特別清算、事業を継続したい場合は民事再生や会社更生という選択肢があります。
それぞれの手続きの特徴や違いについて教えてください。
破産手続
破産手続は、破産法に基づいて行われる一般的な法人破産の手段です。全ての債務が清算されると同時に会社の法人格が消滅する「清算型」の手続きであり、会社は再建されることなく消滅します。
破産手続きでは、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を調査・換価処分し、債権者へ公平に分配します。破産手続きは経営者にとって大きな手続きである反面、借金問題の解決方法としては確実性の高い手続きであるといえるでしょう。
特別清算
特別清算は、破産と同様に裁判所を利用する清算手続きですが、破産ほど厳格ではないため比較的簡易に会社の清算を行うことができます。ただし、特別清算は株式会社のみが利用できる手続であり、特別清算を行うには株主総会での特別決議のほか、債権額の3分の2以上の同意が必要です。
そのため、債権者の協力が得られやすい状況でのみ利用可能な手続きであるといえます。また、特別清算は破産管財人ではなく株主総会で選任された清算人が清算を行うため、会社側で手続きを主導できる点が破産手続きとの違いです。
関連記事:
法人(会社)の特別清算って何?倒産や破産との違いを解説
民事再生
民事再生は、経営が悪化した企業が事業を継続しながら再建を図る法的手続きです。破産とは異なり、会社を存続させたまま経営の立て直しを目指す「再建型」の手続きに分類されます。
民事再生の申立て後も事業活動は継続され、現在の経営陣が主体となって再建計画を策定・実行します。
裁判所が選任した監督委員の監督は受け、経営の主導権は会社側にあるものの、民事再生を行っても再建の見通しが立たない場合、結果的に破産手続きに移行することもあります。
関連記事:
法人(会社)の民事再生とは?~メリット・デメリットを解説~
会社更生
会社更生は株式会社の抜本的な再建を図る法的手続きであり、民事再生と同じく「再建型」に分類されますが、より強力な企業再生を目指す制度です。株式会社のみが利用でき、手続きの規模や費用から事実上大企業向けの制度と言えるでしょう。
会社更生の特徴は、手続き開始によって現経営陣が全員退任し、裁判所が選任した更生管財人に経営権と財産の管理処分権の全てを移転することです。民事再生では困難な抜本的な事業再編が可能な反面、手続きの複雑さと費用の高さがデメリットといえるでしょう。
関連記事:
法人(会社)が借金から解放される?民事再生と会社更生の違いを解説
まとめ
経営難に陥った企業を放置することは、根本解決を遠ざけるだけでなく状況をより悪化させる危険性があります。督促の継続、資産の強制執行、保証人への影響、長期にわたる心理的負担など、放置によるダメージは計り知れません。
これに対し、法的手続きを適切に活用すれば、債務の整理と関係者保護を両立できます。完全清算を目指す破産・特別清算から事業継続を前提とした民事再生・会社更生まで、状況に応じた選択肢が用意されています。
法人破産のような複雑な手続きについては、弁護士に相談することで最適な選択肢を見極められ、手続きの負担も軽減されます。放置による被害拡大を防ぐために、弁護士と相談しながら適切な解決策を図ると良いでしょう。

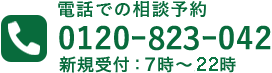
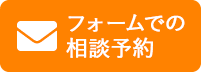


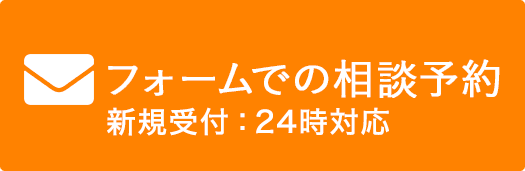
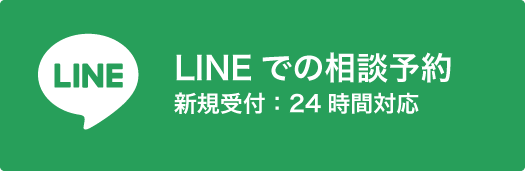
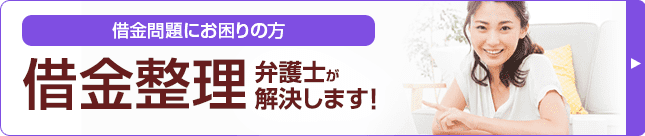
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください