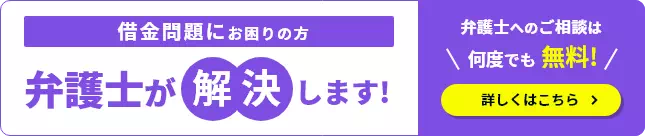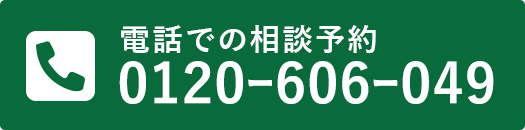- 法人破産とは
- 法人破産のメリット・デメリット
- 法人破産の流れ
【Cross Talk】会社が倒産をするときの流れを知りたい
会社の代表者です。会社の経営が完全に行き詰まってしまっています。会社の破産の流れを教えていただけますでしょうか。
大まかな流れとしては、破産の申立てを行う、破産手続き、を経て会社の財産を精算して債権者に配当します。代表者様個人が連帯債務を負っているような場合には、個人の自己破産手続きも一緒に行います。
そうなんですね。詳しく教えていただけますか?
会社の経営がうまくいかなくなった場合に行う倒産処理の手続きの一つが法人破産です。倒産処理方法として破産を利用する場合にもメリット・デメリットがあります。
他の倒産処理の概要や破産手続きの流れと一緒に確認しましょう。
法人破産とは

- 法人破産とは
- 法人破産のメリット・デメリット
- 他の倒産処理手続き
法人破産ってどんな手続きですか?
法人の倒産処理手続きの中でも会社をたたんでしまうもので手続きが厳格であるという特徴を持っています。
法人破産とはどのような手続きでしょうか。
法人破産とは
法人破産とは、借金の返済などの債務の支払いができなくなった法人について、破産手続きで会社を精算することをいいます。
債務の返済ができなくなった場合、破産法に基づいて債務の精算をすることができます。
「自己破産」という言葉がよく利用されますが、これは個人が破産手続きを利用する場合をいい、これとの対比で法人破産と呼ばれています。
法人が債務の返済をできなくなった場合の倒産処理手続きの一つで、会社を精算することから精算型倒産処理手続と呼ばれることがあります。
他の法人の倒産処理手続き
他の法人の倒産処理手続きにはどのようなものがあるかを確認しましょう。
特別精算
法人破産と同じく会社を精算する倒産処理手続きに、特別清算があります。
特別清算は、会社法に基づいて会社の精算を行う倒産処理手続きです。
法人破産と同様に会社の精算を行うための手続きですが、法人破産と比べると手続きが簡易になっているもので、株式会社だけが利用可能です。
民事再生
民事再生は、民事再生法に基づく再建型の倒産処理手続きです。
法人破産は会社を精算する手続きですが、民事再生は会社債務を調整して会社を再建する手続きである点で法人破産とは異なります。
会社更生
会社更生は、会社更生法に基づく再建型の倒産処理手続きです。
会社更生も民事再生と同様に、会社債務を調整して会社を再建する手続きであり、会社を精算する法人破産とは異なります。
会社更生も民事再生と同様に会社を再建する手続きですが、利用できるのは株式会社のみで、大規模な株式会社が利用するための再建型手続きであるという特徴があります。
私的整理
私的整理とは、債権者と債務者の合意に基づいて行う倒産処理手続きです。
法人破産・特別清算・民事再生・会社更生ともに、裁判所に申立てをして行う倒産処理手続きですが、私的整理は債権者と債務者の合意に基づいて行うことを基本とします。
私的整理は法人を精算する精算型と、法人を再建する再建型の両方の倒産処理手続きですが、多くは会社を再建するために用いられます。
昨今では、債権者の公平・手続きの透明性の見地から、「私的整理ガイドライン」というものが策定されており、これに従って行われることがほとんどです。
法人破産のメリット・デメリット
倒産処理方法として法人破産を利用することのメリット・デメリットには次のようなものがあります。
法人破産のメリット
法人破産のメリットには次のようなものがあります。
法人破産の手続きをとると、会社をたたむことになり、併せて代表者個人が会社と関連して債務を負っている場合には免責されることになるので、資金繰りの悩みや督促から解放されることになります。
また、精算型の私的整理や特別清算と比べると透明性の高い公平手続きで、会社の精算を行うことができます。
債権者側としては、訴訟などの手続きによらずに債権について貸倒れ償却をすることができるのがメリットでしょう。
法人破産のデメリット
一方で法人破産には次のようなデメリットもあります。
まず、会社破産は会社を精算するものなので、会社を精算する必要があり、会社を維持できなくなるというデメリットがあります。
そのため、会社財産や従業員、会社がもっているノウハウが散逸してしまうことに繋がります。
また代表者は免責されるも、取引先・債権者などからは経済的な信用を失うことになります。
法人破産のメリット・デメリットについては、「法人破産のメリット・デメリットを解説」でも解説しているので併せて確認してみてください。
代表者はどうなるのか?
法人破産すると代表者はどうなるのでしょうか。
法人破産はあくまで法人についての手続きで、代表者については効力を及ぼしません。
しかし、会社が倒産するような場合では、会社の代表者が会社の債務について連帯保証をしている場合が非常に多いです。
また、代表者自身の名義で会社のための費用捻出に借り入れをしていることもあります。
そのため、法人破産をする際には、会社の代表者個人の自己破産をする状況であることがほとんどです。
そこで、法人破産の手続きと一緒に代表者個人の自己破産手続きを併せて行うことになります。
法人破産の流れ

- 法人破産の流れ
法人破産はどのような流れで行われるのでしょうか。
法人破産の流れについて確認しましょう。
法人破産は次のような流れで進みます。
1.弁護士に相談する
法人破産は、弁護士に依頼して行うことがほとんどです。
法律上は弁護士に依頼しなければならないとはされていませんが、手続きが非常に複雑であることに加え、少額管財という簡易でかかる費用が少なくなる手続きを利用するためには、弁護士に依頼して手続きを行う必要があります。
そのため弁護士に依頼するのですが、弁護士に依頼するためにはまず弁護士に法律相談を行います。
弁護士の事務所に連絡をして、法律相談を行う日程を決めて相談を行います。
2.破産申立ての準備をする
弁護士に依頼をした後は、破産申立ての準備を行います。
破産申立てをするには、破産申立書という書類を作成するほか、破産申立書に記載される事項を裏付ける添付資料の提出が必要となります。
そのため、まず書類に記載すべき事項についての調査や、裏付け資料の収集を行います。
その他状況に応じて、債権者・取引先・金融機関との調整、従業員への対応なども行います。
場合によっては裁判所と事前に打ち合わせをすることもあります。
3.取締役会・理事会の決議
破産申立て取締役会・理事会の自己破産をするための会社の決議を行います。
法人破産の申立てをするような場合には、会社の種類に応じた決議が必要となります。
会社がどのような機関を設置しているかに応じて、必要となる決議も異なるので注意しましょう。
4.破産申立て
法人破産の準備ができると裁判所に破産申立てを行います。
破産申立ては、破産申立書や破産法で提出が指示されている債権者一覧表・財産目録・貸借対照表などを提出することになります。
また、破産申立書等に記載していることを裏付ける書類の提出も必要であるのは上述した通りです。
このときに、申立て手数料・官報公告費用・引継予納金の支払いも行い、裁判所が使用する郵便切手(予納郵券)の納付も行います。
提出された書面に基づいて破産手続きを開始する要件を充たしているかの調査を行います。
5.債務者審尋
破産手続きを開始する要件を充たしているかの調査にあたって、裁判所が必要と判断した場合には、債務者に対する聞き取り調査を行う債務者審尋が開かれることがあります。
裁判所に出頭をして、裁判官からの質問に答える形で対応を行います。
なお、東京地方裁判所では、申立時に代理人となる裁判所と裁判官で協議を行う即日面接というものが行われます。
6.破産手続き開始決定・破産管財人が選任される
破産手続きの開始に問題がなければ、裁判所が破産手続き開始決定を下します。
このときに、破産手続きをリードする役割になる破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所に登録されているその地域の弁護士が選任されることになります。
この時点で会社財産の管理処分権は破産管財人に移ることになり、会社の代表者による処分が禁止されます。
7.管財人面接
管財人面接が行われます。
選任された破産管財人は、申立て資料などから自己破産について調査を行い、必ず管財人と面接を行うことになります。
管財人免責に先立って不明点があるには確認する旨の問い合わせが代理人の弁護士に行われ、状況に応じて資料の提出を行うことになります。
上述したように破産管財人は弁護士が選任されますので、管財人面接は弁護士が所属している事務所で行われることになります。
8.債権者集会の開催
管財人面接が終わると債権者集会が行われます。
担当裁判官・申立人・破産管財人が集まり、破産管財人から事件についての報告が行われます。
小規模な法人破産であれば、第一回債権者集会で終了することが多いですが、大規模な法人破産の場合には、会社財産の換価や債権者との調整に時間がかかることもあるため、第二回以降も続くことになります。
9.債権者への配当
会社財産を破産管財人が換価し、得られた金銭を債権者に配当します。
配当できる金銭がない場合には、配当を行わずに破産手続きを終了することになります。
10.破産手続きの終結
配当が終わると法人破産の手続きは終了し、法人については法人格が消滅します。
代表者個人は、破産法の免責の規定に従って免責されることになります。
まとめ
このページでは、法人破産の大まかな流れを中心にお伝えしました。
裁判所への申立てを行う法人破産は、ほとんどの場合で弁護士に依頼して行われることになります。
まずはご相談いただき、確実に破産手続きを行うようにしましょう。

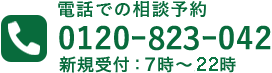
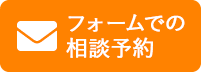


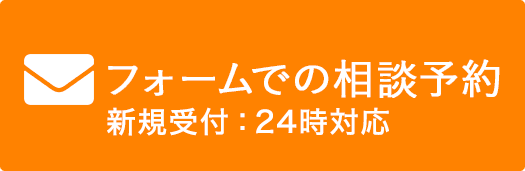
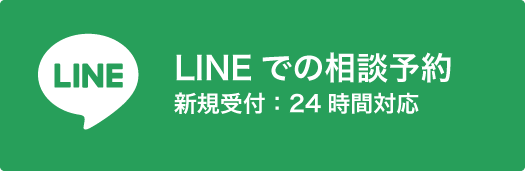
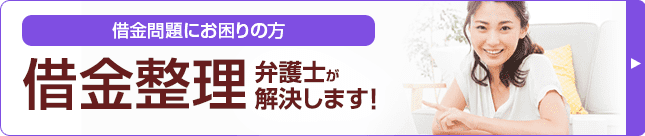
 「友だち追加」からご相談ください
「友だち追加」からご相談ください