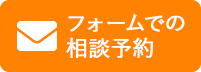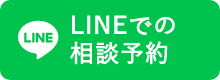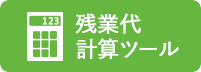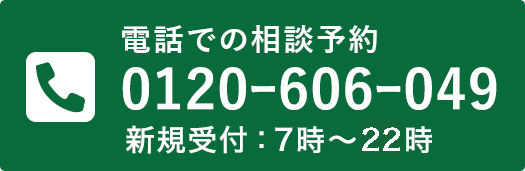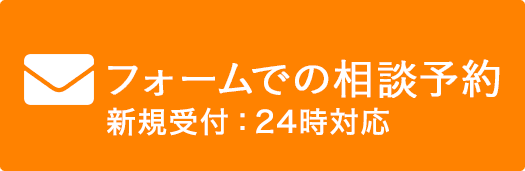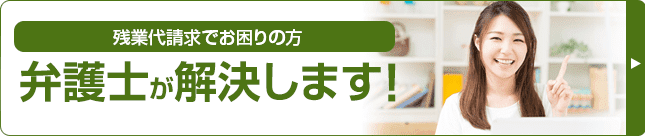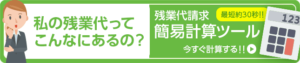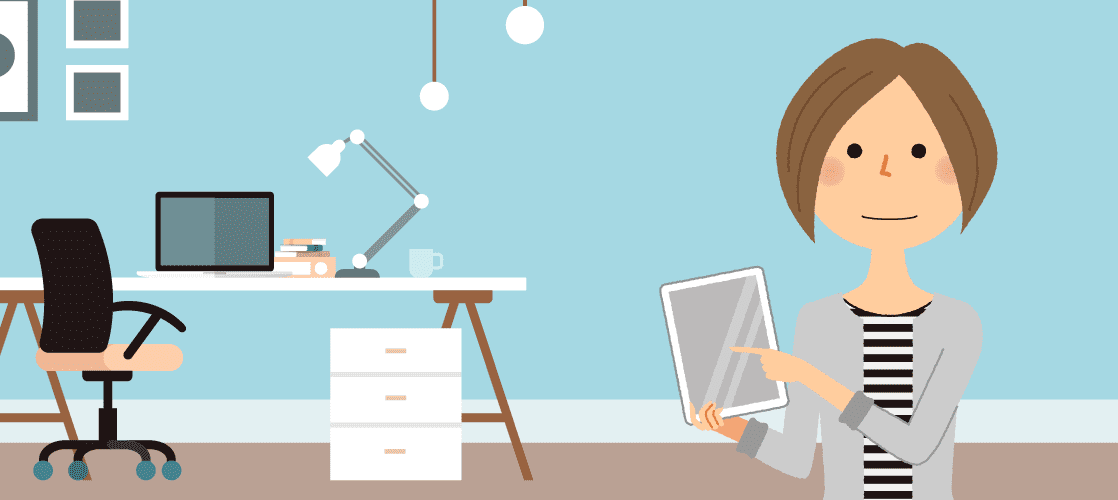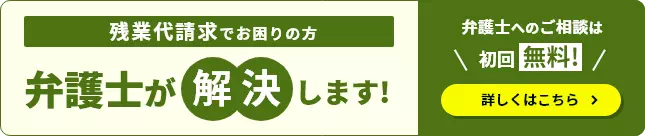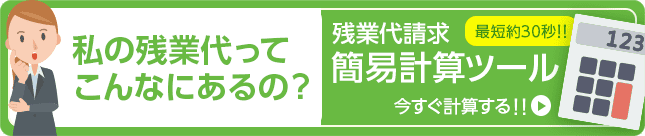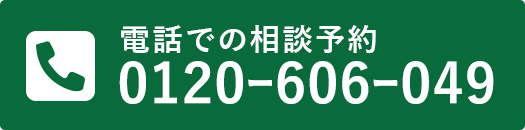- フレックスタイム制は出退勤時間を労働者が決めることができる制度
- 総所定労働時間は週平均40時間を超えない範囲で定める
- フレックスタイム制を導入するには就業規則や労使協定で定めることが必要
- 総所定労働時間を超えれば通常の賃金を、法定労働時間の上限を超えれば割増賃金を請求できる
【Cross Talk】フレックスタイム制は計算が複雑?
うちの会社はフレックスタイム制を導入しています。繁忙期は長時間働かなければいけないので、できれば残業代を請求したいのですが、請求できますか?できるならどうやって残業代を計算したらいいですか?
フレックスタイム制の場合、1週または1日ごとに見るのではなく、あらかじめ定められた一定期間(通常は1ヶ月)における総所定労働時間を超える労働をしたときに、残業代を請求することができます。
請求できるんですね!詳しく教えてください!
情報通信業をはじめとして、労働者が出退勤時間を決めることができるフレックスタイム制を採用している企業があります。
フレックスタイム制を採用する企業では、労働者の判断で労働日の労働時間を長くしたり短くしたりすることができます。
そのため、そもそも残業代を請求できるのか、請求できるとしてもどのように計算するのかと言った疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。
そこで今回は、フレックスタイム制の制度の概要や残業代の計算方法等について詳しく解説いたします。
フレックスタイム制とは?

- フレックスタイム制では自分で出退勤時間を決めることができる
- 労働しなければならないコアタイムが決められていることが多い
- フレックスタイム制でも残業はある
フレックスタイム制とはどのような制度ですか?
わかりやすくいえば、労働者が出退勤時間を自分で決めることができる制度です。ただし、完全に自由というわけではなく、必ず働かなければいけない時間帯を決めることもできます。
フレックスタイム制の概要
フレックスタイム制は、1ヶ月などの単位期間の労働時間を定め、その範囲内で労働者が日々の出勤時間(始業時刻)と退勤時間(終業時刻)を決めることができる制度をいいます(労基法32条の3)。
一般的には、その時間帯であればいつ出勤、退勤しても良いフレキシブルタイムと、その時間帯は必ず労働しなければならないコアタイムを組み合わせることが多いようです。
例えば、午前7~10時、午後3時~午後6時をフレキシブルタイム、午前10時~午後3時までをコアタイムと定めた場合、労働者は午前10時から午後3時までは必ず働かなければなりませんが、始業時刻は午前7時から午前10時の間で、終業時刻は午後3時から午後6時の間で、労働者が自由に決めることができます。
フレックスタイム制の「残業」
フレックスタイム制において「残業」などの時間外労働はどのように計算されるのでしょうか。
通常は、1日の労働時間が決まっていて、その労働時間を超過した部分が残業(早く出勤した場合は早出)となります。
しかし、フレックスタイム制の場合には出退勤の時間を自分で自由に決められるので、この考え方では計算できないことになります。
上述したように、フレックスタイム制の場合には1ヶ月などの一定に単位を設けて労働時間を計算することになります。
この期間のことを精算期間と呼びます。
フレックスタイム制の場合には、この精算期間ごとに残業などの超過勤務を計算します。
例えば、精算期間を1ヶ月として、総労働時間が160時間、実労働時間が180時間であるような場合には20時間の超過勤務があるので、この部分について残業代を請求することが可能です。
フレックスタイム制の「休日労働」
フレックスタイムはあくまで出退勤の時間についての自由を認める制度にすぎません。
そのため休日に出勤させた場合には当然ですが休日労働となります。
仮に、実労働時間が160時間で、総労働時間が170時間である場合には、割増賃金の支払い義務はないように見えても、実労働の中に休日労働が含まれている場合には、割増賃金を支払う義務があります。
フレックスタイム制の労働時間の管理

- 総所定労働時間は週平均40時間を超えない範囲内でなければならない
- 労働時間が不足した場合は繰り越しできるが超過した場合は繰り越しできない
出退勤時間は自由に決められるとしても、トータルの労働時間はどうやって決まるのですか?
週平均40時間を超えない範囲で、1カ月以内の単位期間内(平成31年4月1日から清算期間を1カ月以上3カ月以内に設定することができる)の総所定労働時間を定めることになっています。実際の労働時間が総所定労働時間を超える場合または総所定労働時間に満たない場合は、次の単位期間に繰り越すことできるかという問題があります。
総所定労働時間についての制限
フレックスタイム制では、1ヶ月以内の単位期間(清算期間)における総所定労働時間を定めることになっています。(平成31年4月1日から清算期間を1カ月以上3カ月以内に設定することができるようになりました。)
ただし、フレックスタイム制はあくまで始業時刻と終業時刻の決定を労働者に委ねたものであるので、総所定労働時間には、清算期間内の週平均労働時間が40時間を超えない範囲内で決めなければならないという制限があります。
したがって、総所定労働時間は、
清算期間の日数÷7日×40時間
の範囲内で定めなければなりません。
清算期間が28日なら160.0時間、29日なら165.7時間、30日なら171.4時間、31日で177.1時間以内ということになります。
労働時間に超過または不足が生じた場合
[総所定労働時間についての制限]になるとは限らず、総所定労働時間を超過したり、不足したりすることがありえます。そのような場合、本来はその都度清算すべきですが、過不足分を次の清算期間に繰り越すことができれば、事務処理が簡易になります。このような処理が認められるでしょうか?
まず、実際の労働時間が所定労働時間を超える場合に、超過した部分を次の清算期間に繰り越すこと、つまり、超過した時間を次の清算期間の総労働時間の一部に充て、超過した時間に対する賃金を次の清算期間の賃金支払日に支払うことは、賃金全額払いの原則(労基法24条)に違反し、許されません。
他方、実際の労働時間が総所定労働時間に足りない場合、不足した部分を次の清算期間に繰り越すこと、つまり、賃金カットせずに総所定労働時間に対応する賃金を支払い、次の清算期間において総所定労働時間に前期の不足した時間を加算して労働させることは、法定労働時間の範囲を超えない限り、前期の過払いを次の清算期間で清算するだけですから、労基法24条違反にはならないとされています(昭和63・1・1基発1号)。
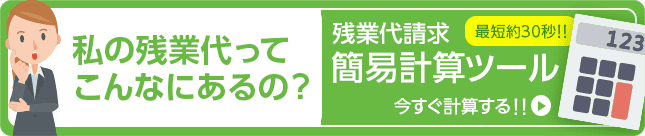
フレックスタイム制導入の要件

- 就業規則と労使協定で所定の事項を定める必要がある
- 18歳未満の者には導入できない
どのような要件を満たせばフレックス制を導入できるのですか?
就業規則で始業・終業時刻を欠く労働者の決定に委ねることを定め、労使協定で1ヶ月以内の単位期間や単位期間の総労働時間などを定める必要があります。
フレックスタイム制の要件
フレックスタイム制を導入するには、まず、就業規則またはこれに準ずるもので、始業時刻と終業時刻を各労働者の決定に委ねることを定めなければなりません。
それに加えて、労使協定で、次の事項を定める必要があります。変形労働時間制と異なり、必ず労使協定が必要になります。
- フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
- 1ヶ月以内の単位期間(清算期間)(平成31年4月1日から清算期間を1カ月以上3カ月以内に設定可能)
- 清算期間における総労働時間
- 清算期間が1カ月を超える場合の労働時間上限の設定(週平均50時間以内)
- 標準となる1日の労働時間の長さ(年休手当の計算の基礎とするため)
- コアタイムを定める場合にはその開始時刻と終了時刻
- フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその開始時刻と終了時刻
- 清算期間が一カ月を超える場合には労働基準監督署に労使協定を届出
ただし、フレキシブルタイムが極端に短い場合や、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合などは、始業時刻と終業時刻を労働者の決定に委ねたとはいえないでしょう(昭和63・1・1基発1号)。
なお、フレックスタイム制は、あくまで始業時刻と終業時刻を労働者の決定に委ねるというものであり、休憩時間まで労働者の決定に委ねられたわけではありません。
そのため、フレックスタイム制を導入した場合であっても、労働基準法通り(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間)の休憩を与える必要があります。
フレックスタイム制の適用制限
年少者を保護するため、満18歳未満の者には、フレックスタイム制を導入することはできません(労基法60条)。
なお、変形労働時間制については、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています(労基法66条1項)。
フレックスタイム制でも残業代請求ができる

- 総所定労働時間を超えれば通常賃金を請求できる
- 法定労働時間を超えれば割増賃金を請求できる
フレックスタイム制でも残業代を請求することができますか?
清算期間における実労働時間が総所定労働時間を超える場合には、超過時間についての通常賃金の請求が可能です。法定労働時間を超過する場合には、割増賃金を請求することができます。
フレックスタイム制の効果
一般的な固定労働時間制の場合、残業代を請求できるかについては、実労働時間が1日の所定労働時間や、1日または1週の法定労働時間を超えるかを検討します。
しかし、フレックスタイム制は労働者に出退勤時間の決定をゆだねるものですから、週平均40時間の範囲内であれば、清算期間内に労働者の判断でたまたま1週あるいは1日の法定労働時間を超える週または日があったとしても、時間外労働にはなりません。
そのため、フレックスタイム制では、清算期間における実労働時間が清算期間の総所定労働時間や法定労働時間を超えるかを検討することになります。
なお、1ヶ月以内の期間において繁閑の差が大きい業務の場合、フレックスタイム制を導入し、労働者が閑散期には労働時間を短くし、繁忙期には労働時間を長くすることで、実労働時間を総所定労働時間の範囲内におさめるということも可能になります。
これが、フレックスタイム制のメリットの一つとして挙げた残業代の削減が期待できるということです(通常の残業代計算方法と比較したほうが理解しやすいので、「私の残業代はいくら?残業代計算方法【図解で分かり易く解説】」も参考にしてみてください。)。
残業代の計算方法
清算期間における実労働時間が法定労働時間を超える場合、超過部分は法外残業に当たり、25%以上の割増賃金を請求することができます(割増率について詳しく知りたい方は「【図解】残業代の計算に必要な時間単価の「割増率」とは?」をご覧ください。) 。
また、実労働時間が総所定労働時間を超過した部分のうち、法外残業に当たらない部分が法内残業となり、通常の賃金を請求することができます。
例えば、1ヶ月(31日)の総所定労働時間が172時間と定められていたが、実際には180時間働いたという場合、法定労働時間177.1時間を超える2.9時間分は法外残業として割増賃金を、総所定労働時間を超え法定労働時間までの5.1時間分は法内残業として通常の賃金を、それぞれ請求することが可能です。
フレックスタイム制の残業代請求の対処法

- 在職中であれば労基署に相談をする
- 退職後であれば弁護士に依頼して残業代請求をしやすい
- 残業代請求の注意点として時効に注意するとの証拠をきちんと集めること
フレックスタイムはとっていますが残業代が支払われない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
在職中にできることと、退職後にできることについて確認しましょう。
在職中は労働基準監督署に申告を行う
残業代は、会社の福利厚生などではなく、労働基準法上の賃金として、必ず支払わなければならないものです(労働基準法24条)。
そのため、残業代の支払いがない場合には、労働基準法に違反している状態で、行政指導の対象になったり、刑事罰の対象となるものです(労働基準法120条)。
会社が労働基準法に違反している場合、労働者は労働基準監督署に申告をすることができます(労働基準法104条)。
労働基準監督署への申告によって、会社に対する行政指導を通じて、適切な残業代の支払いに繋がることが期待されます。
退職後に弁護士に依頼して残業代請求をおこう
在職中だと請求しづらい残業代請求ですが、退職後であれば比較的請求しやすくなります。
残業代請求は、自分で請求・訴訟をすることも可能です。
しかし、残業代の請求を労働者個人が行うと、感情的な対立に終始してしまい、金額・解決までの期間が長くかかるなど不利益を被ることも少なくありません。
弁護士に依頼をすれば、弁護士費用はかかるも、会社と面と向かって交渉する必要はなく、訴訟・労働審判などの手続きもスムーズに行なってもらえますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
残業代請求をする場合の注意点
残業代請求については次の2点に注意をしましょう。
一つは、残業代請求については、毎月の給与の支払日から3年で時効にかかることです(労働基準法105条)。
退職してから3年分はさかのぼって請求することができますが、毎月時効が完成してしまいます。
いったん内容証明で残業代の請求を行なって、6ヶ月以内に交渉を終えるか、訴訟を定期することによって時効の完成をとめることができるので(時効の完成猶予・更新:民法147条1項1号・民法150条)、早めにまずは内容証明を送ることに着手すべきです。
また、残業代請求にあたって、最終的に支払い義務を確定するためには裁判を起こして勝訴する必要があります。
裁判に勝訴するためには、原告となる労働者側で証拠を集めなければなりません。
どのような証拠を集めれば良いか・集められそうかについては、その方がどのような労務管理のもとで働いているかを検討する必要があります。
退職したあとでは証拠がうまくあつまらず、その結果交渉も不利になることも想定しえます。
退職前の証拠の収集段階から弁護士に相談をするようにしましょう。
まとめ
このコラムでは、フレックスタイム制の残業代請求について解説しました。
総所定労働時間は労使協定に記載されているはずですし、法定労働時間は[フレックスタイム制の労働時間の管理]で記載したとおりですので、フレックスタイム制で働いている方は、ご本人の労働時間が法内残業や法外残業にあたらないかを確認してみてください。
法内残業や法外残業については「「残業」とは?残業の種類と定義について」を参考にしてみてください。