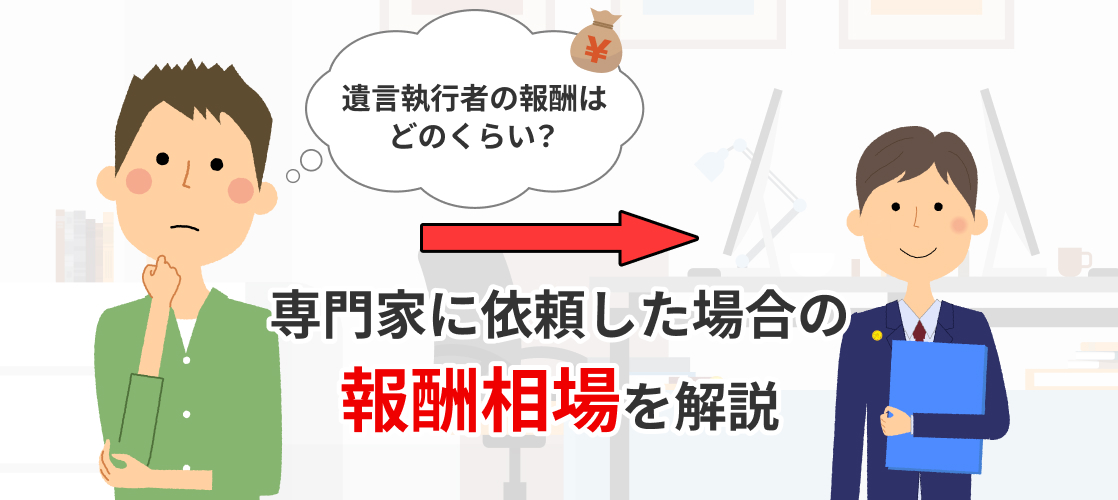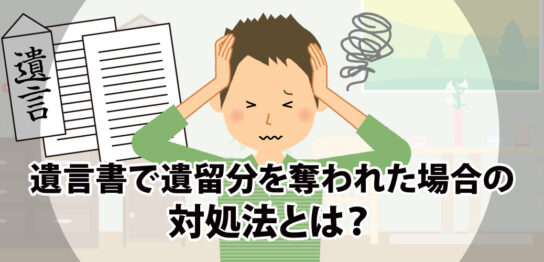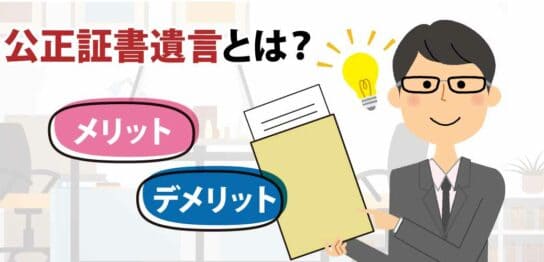- 遺言執行者の役割・選任方法とは?
- 遺言執行者の報酬相場は?
- 弁護士を遺言執行者に選任するメリットとは?
【Cross Talk】遺言執行者に支払う報酬はどのくらいでしょうか?
遺言執行者への報酬の相場はどのくらいなのでしょうか?
遺言執行者に専門家を依頼する場合、依頼する職種や財産総額に応じて報酬が決定することになります。
遺言執行者の報酬相場について、詳しく教えてください。
亡くなった方の生前の意思をスムーズに実現するために、遺言執行者を選任しておくことがあります。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う方のことです。それでは、専門家を遺言執行者に指定した場合、その報酬の相場はどのくらいなのでしょうか。ここでは、遺言執行者の役割や選任方法、専門家ごとの報酬の相場、弁護士を遺言執行者として選任した場合のメリットなどについて、弁護士が解説していきます。
遺言執行者とは?

- 遺言執行者とは?
- 遺言執行者の役割や選任方法とは?
遺言執行者とはどのような人のことなのでしょうか?
ここでは、遺言執行者の役割や選任方法について解説していきます。
遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う方のことです。 遺言者が死亡した後、財産の名義変更や預貯金の解約、分配などの手続きが円滑に進むようにする重要な役割を担います。
遺言執行者は、「遺言書に記された内容を実現するため、必要な行為を行う権利と義務を持つ者」(民法1012条1項)とされています。たとえば、以下のような手続きが必要となります。
・不動産の名義変更:遺贈内容に基づき、法務局で不動産の所有権移転登記を行う
・預貯金の解約・払戻し:遺言に基づき、銀行で解約手続きを行い、財産を分配する
これらの手続きには相続人全員の協力が求められる場合もありますが、遺言執行者がいればスムーズに進めることが可能です。
また、以下のような手続きは、遺言執行者がいなければ実行できません。
| 推定相続人の廃除 | 被相続人に対する虐待や重大な侮辱などを理由に、特定の相続人を相続人から外す手続き(民法892条、893条) |
| 推定相続人の廃除の取消し | 被相続人が生前に廃除した相続人を復帰させる手続き(民法894条) |
| 認知の実現 | 遺言で記された婚外子の認知を行う手続き(民法779条、781条2項) |
これらの内容が遺言書に記されていても、遺言執行者がいない場合は家庭裁判所に執行者の選任を依頼する必要があります。
遺言執行者の指名・選任方法
遺言執行者を選任するためには、次の2つの方法があります。
遺言書で指定する方法:
遺言執行者を選任する最も基本的な方法は、遺言書の中で指定することです。遺言書に「遺言者は遺言執行者として〇〇を指定する。」などを加えることで、遺言執行者を明確に指定できます。
一方的に指定した場合、専門家が引き受けない可能性があるためです。また、候補者に遺言書が存在することと、自分が執行者に指定されていることを伝えておくと、相続が発生した際にスムーズに手続きを進められる場合があります。
家庭裁判所で選任してもらう方法:
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された執行者が辞退・就任不能となった場合は、家庭裁判所に申立てを行い選任してもらう必要があります。
選任を申立てる際には、遺言執行者候補者を挙げることができます。家庭裁判所が特に問題なしと判断した場合、その候補者が遺言執行者として選任されます。
そして、家庭裁判所への申立てには、遺言書や候補者の身分証明書などの書類が必要です。選任された遺言執行者が正式に職務を引き受けた後、遺言の内容に基づく執行が進められます。
遺言執行者を適切に選任することで、遺言内容の実現がスムーズに進み、相続手続きが効率的に行えるようになります。状況に応じた方法を選び、計画的に準備することが重要です。
関連記事:遺言執行者は必要?メリット・デメリットと選任すべき主な5つのケースを紹介
遺言執行者の報酬の相場

- 遺言執行者の報酬の相場は?
- 弁護士、司法書士、税理士、信託銀行の報酬相場を解説
遺言執行者に支払う報酬の相場はどれくらいなのでしょうか?
遺言執行者に専門家を依頼する場合、依頼する職種や財産総額によって報酬が異なることになります。以下では、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行のそれぞれの報酬相場と特徴を解説します。
弁護士に依頼した場合
遺言執行者に専門家を依頼する場合、依頼する職種や財産総額によって報酬が異なります。
まず、弁護士に遺言執行を依頼する場合、遺産総額の0.5~2%が相場です。旧日本弁護士連合会報酬基準を参考にしている事務所もあり、基本料金に加えて遺産総額に応じた報酬が発生します。
旧報酬規程に則って計算すると、遺言執行者の報酬は以下のように計算することができます。
・遺産総額300万円以下:一律30万円
・遺産総額300~3000万円以下:遺産総額の2%+24万円
・遺産総額3,000~3億円以下の場合:遺産総額の1%+54万円
・遺産総額が3億円を超える場合:遺産総額の0.5%+204万円
遺言執行者を弁護士に依頼するメリットとしては、他の相続人が遺言書に納得していない場合でも、遺言執行者が、遺言執行者の権限で、他の相続人の協力を得ずにスムーズに相続手続きができる点にあります。
ただし、報酬体系については法律事務所によって異なる可能性があり、事務手数料や交通費が含まれない場合もあるため、詳細は事前にしっかりと確認したうえで依頼するようにしてください。
司法書士に依頼した場合
遺言執行者は、司法書士に依頼することができます。ただし、旧弁護士会報酬基準のようなものはないため、、各司法書士事務所によって報酬体系が大きく異なる傾向があります。
司法書士の報酬相場は、基本料金25~30万円に加え、遺産総額に応じて0.5~2%が加算される場合が多いです。
事務所ごとに報酬額や取り扱い業務が異なる可能性があるため、事前に見積もりを取得し、含まれるサービス内容を確認するようにしてください。
税理士に依頼した場合
遺言執行者を税理士に依頼する場合、基本料金20~30万円に加えて、遺産総額の0.5~2%を報酬として設定している事務所が一般的です。過去には税理士の報酬に関して最高限度額を定めた規定がありましたが、現在は規定が廃止され報酬設定が自由化されています。
税理士に遺言執行者を依頼する場合には、相続税の申告や納税に関する専門知識を活かしたアドバイスを受けられ、税務署との対応を代行してもらえるため手間が省けるというメリットがあります。ただし、報酬に追加費用が発生する場合も少なくないため、見積もり時に明細を確認するようにしてください。
信託銀行に依頼した場合
信託銀行は、最低報酬額100万円程度の「遺言信託サービス」を提供しています。サービスの内容は各信託銀行で異なりますが、遺言の作成、保管、執行を包括したプランが一般的です。
信託銀行に依頼した場合の報酬の参考相場としては、以下の通りです。
・遺言作成時:30~50万円程度
・相続発生時:財産総額に応じた報酬(例:財産総額1億円の場合、0.5~2%)
信託銀行の遺言信託サービスを利用した場合、弁護士や税理士など他の専門家に比べて報酬が高額になる可能性があります。また、相続トラブルへの対応力は限定的で、法的な争いには弁護士が別途必要になる可能性もあります。
遺言執行者を選任するメリット

- 遺言執行者を弁護士に依頼することのメリットとは?
それでは、遺言の執行については弁護士に依頼するのが一番いいのでしょうか?
ここでは、弁護士を遺言執行者に選任することのメリットについて解説していきます。
遺言執行者に弁護士を選ぶことには、以下のようなメリットがあります。
まず、相続人の間の対立を回避して手続きをスムーズに進めることが期待できます。遺言の内容が複雑であったり、相続財産が多岐にわたったりする場合、遺言執行者には大きな責任と負担が生じます。
このような場合であっても弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続手続きに関する法律知識や実務経験を活かして、スムーズに業務を遂行できる可能性があります。例えば、相続方法が細かく指定されている場合や第三者への遺贈が含まれる場合でも、確実に手続きを進めることが可能です。
まとめ
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人物です。遺言執行者については相続人の1人を指定することもできますが、専門家に任せるのが安心です。弁護士や税理士、司法書士などの専門家に依頼した場合には、遺産の中から報酬を支払わなければなりません。遺言執行者に専門家を依頼する場合、依頼する職種や財産総額によって報酬が異なりますので、あらかじめしっかりと確認しておくことが重要です。
専門家に遺言執行を依頼したいと検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所には、遺言執行を含む相続問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ご希望に沿ったサービスをご提供いたします。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介