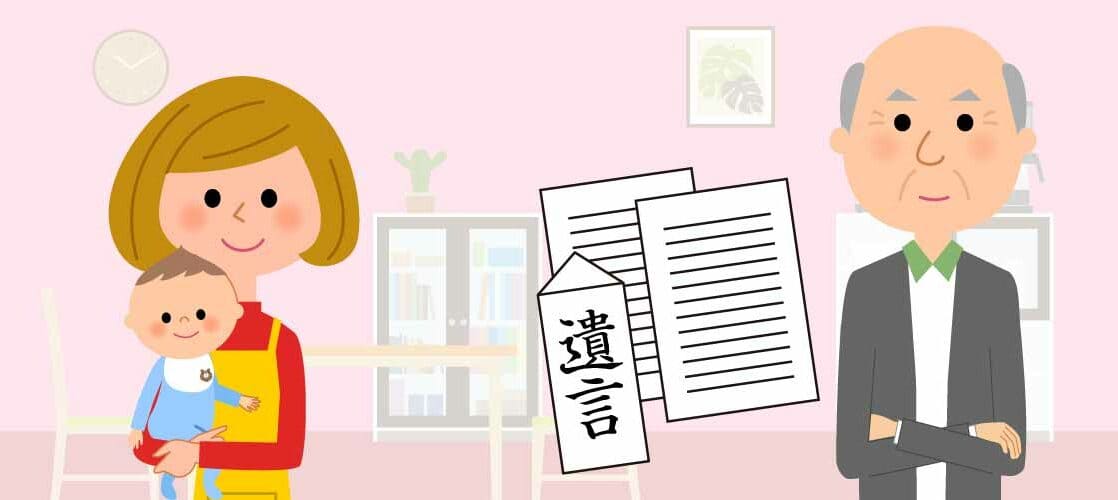はじめに
そのため、どれだけ長く一緒に暮らしていたとしても、遺言書がない限り、内縁の妻は遺産を受け取ることができないのです。
そこで本記事では、内縁関係にある妻に確実に財産を残すためになぜ遺言書が必要なのか、どのように遺言を作成すればよいのかについて、わかりやすく解説します。
内縁の妻に相続させるために遺言書を作成する以外にできることも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
【前提】内縁の妻には相続権がない
内縁の妻が遺産を相続するためには、そもそも「内縁」という状態や内縁の妻の相続権について理解しておかなければなりません。
以下では、内縁の妻に関する基本的な知識をおさえておきましょう。
そもそも内縁とは?内縁が認められるためには
内縁とは、対外的な関係においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻届を提出しておらず、 法律上は夫婦と認められない関係のことをいいます。
事実上は夫婦関係にある状態という意味で「事実婚」という場合もあります。
内縁関係と認められるためには、当事者の合意によって事実上の夫婦としての生活関係が存在することが必要です。
また、日本ではたとえ内縁関係であっても扶助義務・婚姻費用の分担などの婚姻に関する規定()について類推適用をすることで、内縁関係の当事者の保護をしています。
内縁の妻は配偶者ではないので相続権はない
婚姻状態にない内縁関係であっても、なるべく婚姻関係に関する規定の類推適用をすることで内縁当事者は保護されています。
しかし、相続において、「配偶者は常に相続人とする」と規定している民法890条の規定は類推適用されません。つまり、内縁の妻には相続権がないということです。
これまでは内縁状態でも夫婦と同じように扱ってもらえた場合でも、相続手続きにおいては実質的な配偶者として遺産を相続することはできないので注意しましょう。
寄与分は法定相続人に認められるもので内縁の妻には認められない
内縁の妻が事実婚状態の夫の遺産を相続したいとき、「寄与分を主張すれば実質的に遺産を相続できるのでは?」と考えるかもしれません。
寄与分とは、被相続人の遺産の増加や維持をした法定相続人がいる場合に、相続において有利に扱う制度です。
しかし、寄与分が認められるのは法定相続人のみであって、内縁の妻には認められません。
また、寄与分と似たものに「特別寄与料」がありますが、こちらも被相続人の親族のみに認められているため、内縁の妻が主張することはできない点に注意しましょう。
内縁の妻が遺産を相続できる2つのケース
ここまでで、内縁の妻には相続権がなく、寄与分などの主張も難しいことを解説しました。
しかし、内縁の妻が遺産を相続することは不可能ではありません。
具体的には、以下のような方法で遺産を相続することが可能です。
- 特別縁故者になる
- 遺言や遺贈によって相続する
以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。
また、内縁の妻との間にできた子どもの相続権や、内縁の妻に認められるそのほかの権利についてもみていきましょう。
内縁の妻が遺産を受け取ることができるのは特別縁故者になった場合だけ
内縁の妻は法定相続人として遺産を相続することはできませんが、特別縁故者として遺産の配当を受けられる場合があります。
特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めたりと、特別な関係があった場合に、家庭裁判所に請求をして遺産を与えてもらう制度です。
被相続人に法定相続人がいない場合には、利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、相続財産管理人の主導のもと、相続人不存在の場合の手続きを行うことになります。
そして、この手続きによって相続人の不存在が確定した場合に、特別縁故者へ遺産の配分が行われます。
内縁の妻は、家計を同一にしていたり、被相続人の療養看護をしていると認められていたりする場合が多いので、特別縁故者として遺産を受け取れる可能性が高いでしょう。
しかし、そもそも法定相続人が一人でもいれば、特別縁故者として遺産を受け取ることはできません。
また、仮に特別縁故者として遺産を受け取れる場合でも、実際に遺産を手にできるのは、被相続人が亡くなってから相当期間が経過したあとになるので、スムーズに遺産を受け継がせることができません。
遺言や遺贈であれば内縁の妻にも財産を残すことができる
内縁の妻が遺産を相続するには、特別縁故者の制度を利用する選択肢がありますが、被相続人に法定相続人がいる場合、特別縁故者として遺産を受け取ることはできません。
また、遺産の受け取りまでに時間を要する点でも注意が必要です。
そこで、内縁の妻が遺産をできるだけ確実かつ、スムーズに相続するには、遺言書を活用するのが望ましいでしょう。
遺言書で内縁の妻に遺産を与える遺贈をすれば、内縁の妻でも遺産を受け取ることができます。
内縁の妻に子どもがいる場合は、子どもは法定相続人になる
被相続人と内縁の妻との間に子どもがいる場合、被相続人がその子どもを認知していれば、子どもは法定相続人となります。
通常、内縁の妻との間に子どもができた場合、母親は分娩の事実で子どもと法律上の親子関係が認められますが、父親と子の間には親子関係が認められません。
そのため、父と子の法律上の親子関係が認められるためには、父親が子を認知する必要があります。
そして、法律上子どもである場合には、当然に相続において法定相続人となります。
内縁の妻でも認められる権利
相続の際、被相続人の内縁の妻は法定相続人にはなりません。
しかし、以下のような権利は内縁の妻でも認められています。
- 遺族年金の受給
- 賃借権
それぞれについて、以下で詳しくみていきましょう。
遺族年金の受給
内縁の妻には、遺族年金の受給権が認められています。
遺族年金とは、厚生年金に加入している方が亡くなった場合に、その遺族に支払われる年金のことです。
厚生年金法58条では、遺族に対して遺族年金の支払いをするとしています。
次に、厚生年金法59条では遺族年金を受給できる遺族の範囲として、「被保険者であつた者の配偶者」と規定しており、厚生年金法3条2項では、厚生年金法では内縁の妻を配偶者として取り扱う旨が規定されています。
そのため、内縁の妻も遺族年金を受け取ることができるとされているのです。
賃借権
内縁の夫婦が住居を賃借していた場合で、賃借人となっている人が死亡した場合、内縁関係にある同居者は賃借人の権利義務を承継することはできます。
そのため、内縁関係の夫婦の夫が亡くなった場合でも、内縁の妻は現在の住居にそのまま住み続けることが可能です。
ただし、賃貸人が死亡したことを知った日から1ヵ月以内に、賃貸人の権利義務を承継しない意思表示をした場合には、賃借権を承継しません。
内縁の妻に財産を残す場合の遺言書の作成方法
内縁の妻に財産を残す場合は、遺言書の作成が有効ですが、具体的にどんな内容の遺言書を作成すべきかで悩む方は多いでしょう。
そこでここからは、内縁の妻に財産を残す場合の遺言書の作成方法について解説します。
なお、ここでは自筆証書遺言を作成することを前提としています。
内縁の妻のみに財産を残す場合
まず、内縁の妻のみに財産を残す場合に、自筆証書遺言を作成する場合は遺言書に次のように記載します。
ポイントは、「内縁の妻〇〇」と名前や住所までしっかりと記載することです。
「内縁の妻に相続する」といったあいまいな表現にすると、誰が内縁の妻にあたるのかがわからなくなるおそれがあるので注意しましょう。
内縁の妻と他の法定相続人に財産を残す場合
次に、子どもや兄弟姉妹がいるなどで他にも法定相続人がいる場合の記載例を確認しましょう。
ここでは預貯金を内縁の妻に、残った財産を子どもに相続させることを念頭に記載します。
第○条 子東京一郎(昭和○○年○○月○○日生、住所 東京都新宿区東新宿…)に、その他一切の財産を相続させる。
遺言で内縁の妻に遺贈をする場合の注意点
内縁の妻には、遺言を残すことで遺産を相続することができますが、内縁の妻に遺贈をする内容の遺言書を作成する場合は、いくつか注意すべきポイントも存在します。
- 法定相続人がいる場合には遺留分に注意する
- 遺言が無効にならないように注意する
- 内縁の妻と遺族との交渉が発生する
- 相続税の2割加算が適用される
- 配偶者控除が利用できない
- 障害者控除が利用できない
- 小規模宅地等の特例が利用できない
以下では、それぞれの注意点について詳しくみていきましょう。
法定相続人がいる場合には遺留分に注意する
まず、内縁の妻以外に法定相続人がいる場合には遺留分に注意しましょう。
遺留分とは、相続の際に法定相続人が最低限の財産を相続できる権利のことをいいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続分の1/2(直系尊属のみが法定相続人である場合には1/3)が遺留分として認められており、この分を相続できない場合は、遺贈を受けた内縁の妻が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、相続する財産の範囲を遺留分の侵害しないように調整したり、遺留分侵害額請求を受けてもきちんと支払いができるようにしたりといった対策をしておくべきでしょう。
遺留分については、以下の記事でも詳しく説明していますので参考にしてください。
【関連記事】 遺留分とは
遺言が無効にならないように注意する
次に、遺言書の内容が無効にならないように注意しましょう。
特に、自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言については、内容を誤ると遺言が無効であると判断される可能性があります。
遺言の効力を確実なものにしたい場合は、公証人によって作成される公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。
内縁の妻と遺族との交渉が発生する
内縁の妻に相続させたいとき、単に遺言書を作成するだけだと、あとあと法定相続人との交渉が必要となる可能性があるため注意しましょう。
例えば、法定相続人に対して遺産の引き渡しについて交渉したり、不動産がある場合には登記義務者として不動産登記に協力してもらったりする必要がありますが、法定相続人がこれに応じないと裁判を起こさなければならない場合もあります。
そのため、交渉などのトラブルを防ぎ、確実に内縁の妻に相続させたい場合は、遺言書を作成するほか、遺言執行人をつけておくことも検討しましょう。
相続税の2割加算が適用される
内縁の妻が相続する遺産について、相続税の課税対象となる場合は相続税の2割加算が適用される点にも注意が必要です。
遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要となり、遺贈を受けた方もその義務があります。
そして、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の方が相続する場合、その方の相続税額は2割加算されることになっています。
内縁の妻はそもそも血族でも配偶者でもなく、配偶者として扱ってもらうこともできないため、相続税の2割加算の対象となるのです。
配偶者控除が利用できない
内縁関係の夫婦の相続では、相続税の配偶者控除が利用できないことも注意が必要です。
相続税の配偶者控除とは、配偶者に認められている相続税の税制優遇措置で、遺産が1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額どちらか多い額までは相続税がかからないとするものです。
当然この制度は配偶者にだけ認められる控除なので、内縁の妻には認められません。
障害者控除が利用できない
内縁関係の夫婦の相続では、相続税の障害者控除も利用できません。
相続税の障害者控除とは、障害者に認められている相続税の税制優遇措置で、その障害者が満85歳になるまでの年数✕10万円(特別障害者に該当する場合には20万円)を税額から控除するものです。
しかし、障害者控除を利用するためには法定相続人である必要があり、内縁の妻はこれにあたりません。
小規模宅地等の特例が利用できない
内縁関係の夫婦の相続では、小規模宅地等の特例も利用できません。
小規模宅地等の特例とは、事業の用または居住の用に供されていた宅地等を相続する場合に、その土地の価額を最大80%減額する制度です。
しかし、この制度を利用するには配偶者・親族であることが要件であるため、内縁の妻はこれにあたりません。
遺言のほかに内縁の妻に財産を残す方法
内縁の妻に財産を残したい場合、遺言書を作成するほかにもいくつかの方法があります。
- 生前贈与をする
- 生命保険の受取人にする
- 婚姻する
- 養子縁組をする
以下では、それぞれの方法について詳しくみていきましょう。
生前贈与をする
被相続人がまだ生きていている場合、生前贈与をすることによって内縁の妻に財産を残すことができます。
ただし、生前贈与を行う場合は贈与税に注意する必要があるほか、法定相続人が居る場合には遺留分侵害額請求の対象にならないように慎重に行わなければなりません。
必要に応じて弁護士や税理士に相談しながら、手続きを進めましょう。
生命保険の受取人にする
契約している生命保険の受取人に内縁の妻を設定することでも、実質的に内縁の妻に財産を残すことができます。
内縁の夫の資産で保険料の支払いを行い、夫が亡くなったあとは内縁の妻が保険金を受け取ることになるので、実質的には財産を残すことができるでしょう。
なお、生命保険金の支払いは生命保険契約の履行によるものであり、相続ではありません。
しかし、生命保険は相続の実質をもっているため、受け取った保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象となり得る点に注意が必要です。
そのため、保険金を含む遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告・納税が必要となります。
婚姻する
内縁の妻に確実に相続をしたいなら、内縁ではなく正式に婚姻届を提出することも検討しましょう。
正式に配偶者となれば、法定相続人として遺産を受け取ることができます。
ただし、子どもがいる場合には法定相続分についてトラブルになることもあるので、よく話し合うことをおすすめします。
養子縁組をする
同性パートナーである場合など、婚姻ができない事情がある場合は、養子縁組をすることも検討しましょう。
内縁の妻と養子縁組をすれば法律上の子どもとして相続人となることができ、財産を残すことが可能です。
ただし、婚姻の場合と同じように、他の法定相続人がいる場合にトラブルになることがあるので、よく話し合いながら行いましょう。
まとめ
本記事では、内縁の妻が遺産を取得するための方法についてお伝えしました。
内縁の妻には法定相続人になる権利がないため、何も対策しなければ、特別縁故者に該当する場合にしか遺産を手に入れることができません。
「内縁の妻に相続させたい」という希望がある場合は、遺言書を作成するほか、婚姻を結ぶ、養子縁組をする、生前贈与をするなど対策をしておきましょう。
ただし、これらの手続きには注意点があるうえ、法的な知識も必要になるので、不安なことがあれば弁護士に相談してください。

- 死亡後の手続きは何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続人の範囲や遺産がどのくらいあるのかわからない
- 手続きの時間が取れないため専門家に任せたい
- 喪失感で精神的に手続をする余裕がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28相続全般寄与分の相場はいくら?タイプ別の計算方法を解説
- 2025.11.26遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を行う場合の不動産の評価はどのように行うのか
- 2025.10.29相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2025.10.22遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?