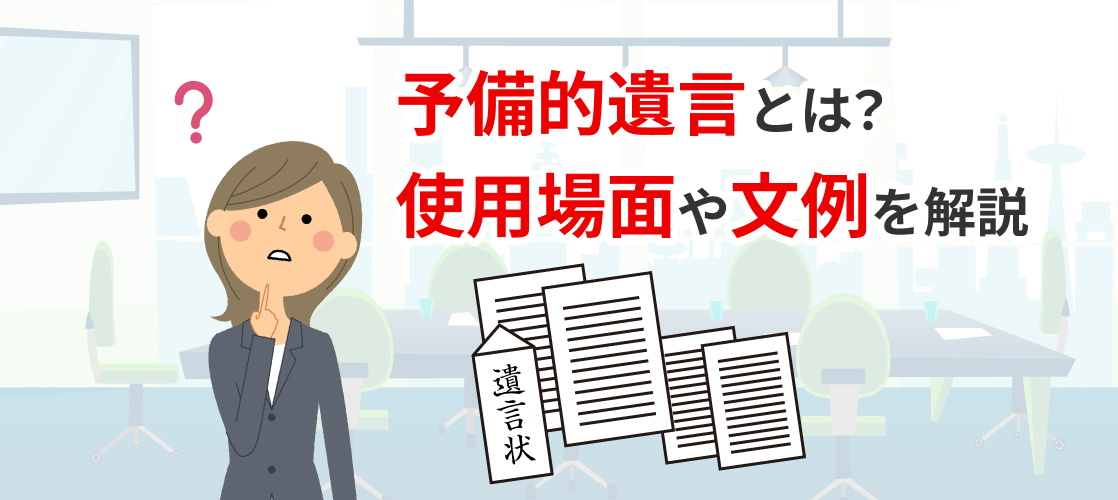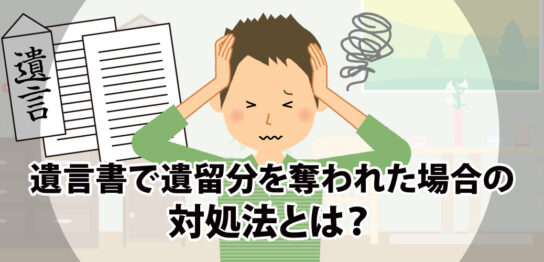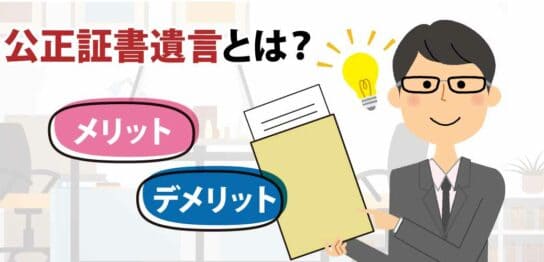- 予備的遺言とは、遺産を譲りたい相手が先に死亡した場合に備える遺言の方法
- 予備的遺言をすることで、遺産をめぐるトラブルを防止しやすくなる
- 予備的遺言をする場合は弁護士に相談するのがおすすめ
【Cross Talk】予備的遺言ってどんな遺言のこと?
予備的遺言をしておいたほうがいいと言われたのですが、予備的遺言とはどのような遺言書ですか?
予備的遺言とは、遺産を譲るはずの相手が、遺言者よりも先に亡くなった場合に備えて、予備の遺言書を作成しておくことです。
ある一定の場合に備えて、文字通りに予備的な遺言書を作成することなんですね。予備的遺言を使う場合や文例についても教えてください!
予備的遺言とは、ある一定の場合に備えてあらかじめ予備の遺言をしてくことです。
予備的遺言をすることで、相続人らによる遺産をめぐるトラブルを防止しやすくなるのがメリットです。
そこで今回は、予備的遺言の概要や文例などを解説します。
予備的遺言とは

- 予備的遺言とは、遺産を譲りたい相手が先に死亡した場合に備える遺言の方法
- 予備的遺言をすることで、遺産をめぐるトラブルを防止しやすくなる
予備的遺言とはどのような遺言書ですか?
遺言者よりも先に相手が亡くなった場合に備えて、予備的な遺言書を作成しておく方法です。相手が亡くなった場合に遺産をどうするかを指定しておくことで、遺産をめぐる相続人間のトラブルを防止しやすくなります。
予備的遺言を使う場合
予備的遺言とは、相続人など遺産を譲りたい相手が遺言者よりも先に死亡した場合に備えて、その場合の予備的な遺言書を作成しておくことです。
遺言者が亡くなって相続が開始した場合、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。
遺言書によって遺産を譲る相手を指定しておけば、遺言者が亡くなって相続が開始した場合、原則としてその相手に遺産を譲ることができます。
しかし、遺言者よりも先に、遺言書によって指定した相手が先に亡くなってしまうと、その相手に遺産を譲ることはできません。
また、相手が亡くなって、その相手に対する遺言書の効果が無効になってしまうことで、その遺産についての指定も無効になってしまいます。
相手に土地を譲る旨の遺言書を作成していた場合、相手が亡くなって指定が無効になることで、その土地を誰に譲るかについて何も指定していないのと同じ状態になってしまうのです。
遺産を誰に譲るかの指定がない場合、相続人全員で遺産分割協議をして、誰がその遺産を相続するかを決めて遺産分割協議書に署名と押印をしますが、遺産をめぐって相続人の間で争いになる可能性があります。
例えば、被相続人が「自分が亡くなったら、妻に土地Aを相続させる」という遺言書を作成したとします。
もし妻よりも先に被相続人が亡くなって相続が開始した場合、遺言書の内容に従って相続が行われれば、妻に土地Aを相続させることができます。
ところが、遺言者よりも先に妻が亡くなってしまうと、妻に土地Aを相続させることはできません。
それだけでなく、土地Aを誰に相続させるかの指定も無効になってしまうので、土地Aを誰が相続するかを指定していないのと同じ状態になってしまいます。
その結果、誰が土地Aを相続するかについて、相続人の間で争いになるリスクが生じます。
遺言書によって指定した相手よりも先に、遺言者が亡くなってしまうことによる弊害を防止するための方法が、予備的遺言です。
予備的遺言によって、遺言者よりも先に相手が亡くなってしまった場合にどうするかを指定しておけば、相続人の間での争いなどのトラブルを防止しやすくなります。
例えば、「自分が亡くなったら、妻に土地Aを相続させる。ただし、自分よりも先に、あるいは同時に妻Aが亡くなった場合は、長男に土地を相続させる」と記載するなどです。
上記のように予備的遺言をしておけば、妻が亡くなって土地Aを相続できなくなった場合でも、誰が土地Aを相続するかを決めることができるので、遺産をめぐる争いを防止しやすくなります。
予備的遺言をする場合の記載方法
予備的遺言をする場合の基本的な記載方法は、以下の通りです。
第〜条:妻(氏名と生年月日も記載)に遺産Aを相続させる。
第〜条:遺言者が死亡する前、または同時に妻(氏名と生年月日も記載)が死亡した場合は、長男(氏名と生年月日も記載)に遺産Aを相続させる。
預貯金を相続させる場合の基本的な記載方法は、以下の通りです。
第〜条:妻(氏名と生年月日も記載)に下記の預貯金と利息金を相続させる。
・金融機関の名称・支店名・口座の種類・口座番号
第〜条:遺言者が死亡する前、または同時に妻(氏名と生年月日も記載)が死亡した場合は、長男(氏名と生年月日も記載)に前条記載の預貯金と利息金を相続させる。
不動産を相続させる場合の基本的な記載方法は、以下の通りです。
第〜条:妻(氏名と生年月日も記載)に下記の不動産を相続させる。
・土地の所在・地番・地目・地積など
・建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など
第〜条:遺言者が死亡する前、または同時に妻(氏名と生年月日も記載)が死亡した場合は、長男(氏名と生年月日も記載)に前条記載の財産を相続させる。
予備的遺言が争われた最高裁判例から注意点を確認

- 予備的遺言について判示した最高裁判例がある
- 予備的遺言をする場合は弁護士に相談するのがおすすめ
予備的遺言について判示した最高裁判例はありますか?
単に相手に相続させる旨の遺言書を作成した場合、相手が先に亡くなってしまうと、特段の事情がない限りは遺言書の効力が認められないとする判例があります。予備的遺言の重要性を示す判例といえるでしょう。
最高裁判所平成23年2月22日判決の内容
予備的遺言について判示した最高裁判例として、平成23年2月22日の判決があります。
同判例は、「相続させる」旨の文言の遺言の効力について、以下のように判示しました。
・遺言によって遺産を相続させるとした推定相続人が、遺言者が死亡する以前に死亡した場合は、その推定相続人の代襲者など、その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと解するのが相当である。
つまり、単にある相手に遺産を相続させるという旨の遺言書を作成しただけの場合、その相手が先に亡くなってしまうと、その他の者に遺産を相続させる意思があると見えるような特別な事情がない限りは遺言書の効力が生じないと判示したのです。
上記の判例によって、相手が先に亡くなってしまった場合に備えて、予備的遺言をしておくことの重要性が示されました。
予備的遺言のような複雑な遺言書を作成する場合には弁護士に相談するのがおすすめ
予備的遺言をする場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
予備的遺言のような複雑な遺言書を作成する場合、遺言書の文章も技巧的になるので、誤った内容を記載してしまう可能性が高くなります。
もし誤った文言を記載してしまうと、予備的遺言としての効力が認められなかったり、想定した内容とは異なる効果が発生してしまったりなどのリスクがあります。
相続問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、適切な文言をアドバイスしてくれるので、法的に誤りのない予備的遺言を作成することができます。
まとめ
予備的遺言とは、遺言を譲るはずの相手が先に亡くなった場合に備えて、予備的な遺言書を作成しておくことです。
予備的遺言をすれば、相手が先に亡くなった場合でも遺産を誰に譲るかを指定できるので、遺産をめぐる相続人のトラブルを防止しやすくなります。
予備的遺言は内容が複雑になりがちなので、弁護士に相談したうえで作成することをおすすめします。
<参照>
2予備的遺言が争われた最高裁判例から注意点を確認
1)最高裁判所平成23年2月22日判決の内容
https://miyagawa-legal.com/invalid-will/

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 亡くなられた方の生きた軌跡である財産を引き継ぐ相続は様々なトラブルの種になり得ます。「私の家は大丈夫。」と思っていた矢先、小さなほころびから大きなモツレになることもあります。そのような重要な場面においてご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向け尽力致します。
最新の投稿
- 2025.09.05相続放棄・限定承認遺贈の放棄はできるの?期限はあるの?相続放棄との違いは?
- 2025.09.04相続放棄・限定承認遺言書があった場合の相続放棄について確認しよう
- 2025.08.25相続全般独身の方の法定相続人は誰になる?相続割合や独身の方ができる相続対策
- 2025.08.25遺言書作成・執行遺言書を作成する際に関係してくる公証人ってどんな人?