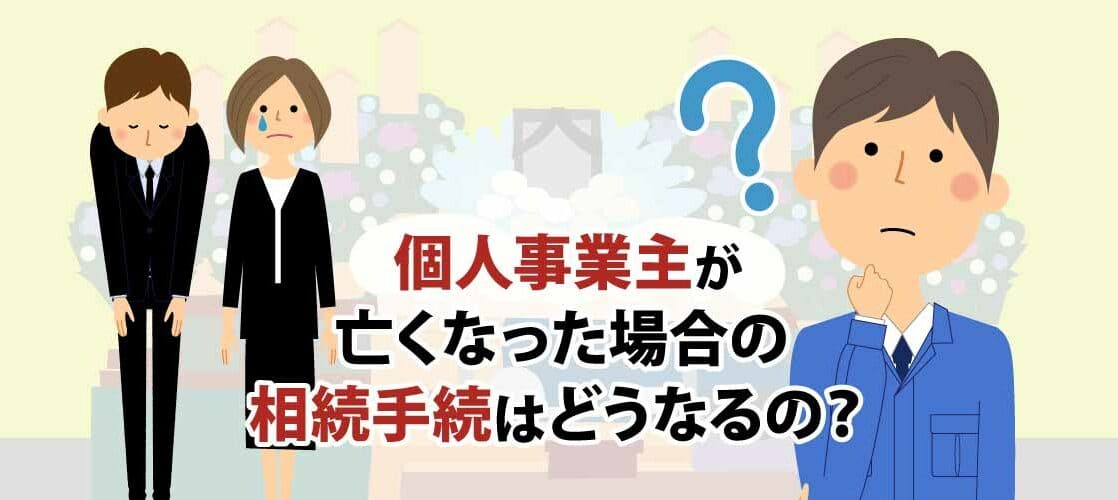個人事業を営んでいた故人には事業用の資産や借金、税務手続きなどがあり、対応しなければならない問題が多く存在します。
特に「準確定申告」は期限が決まっており、期限に遅れてしまうと遅延税や罰金を支払うリスクがあります。
本記事では、個人事業主が亡くなった場合に相続人が行うべき手続きや事業の引継ぎ、相続放棄などについて、わかりやすく解説します。

- 個人事業主が亡くなったときに発生する手続きと注意点を確認する
個人事業主が亡くなった際の手続き
はじめに、個人事業主が亡くなった際に、やるべき手続きは以下です。
- 死亡届
- 廃業届
- 事業廃止届
- 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届け出
- 所得税関係の書類提出
- 消費税関係の書類提出
- 準確定申告
準確定申告は納税者が亡くなったときに相続人が行う確定申告のことで、通常の確定申告とは期限が異なるため、注意が必要です。
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
死亡届
死亡届は、個人事業主であるかどうかに関わらず、人が亡くなった際に提出する書類です。 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合には3カ月以内)に、市区町村役場へ提出しなければなりません。② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
引用元:戸籍法 | e-Gov 法令検索
また、死亡届を出す際に死亡診断書(もしくは死体検案書)を添付しなければなりませんが、死亡を確認した医師から渡されます。
廃業届
個人事業主が死亡した場合には、廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を相続人が提出します。引用元:所得税法 | e-Gov 法令検索
事業廃止届
被相続人が課税事業者だった場合は、消費税を納めている税務署に事業廃止届を提出する必要があります。引用元:消費税法 | e-Gov 法令検索
給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届け出
従業員を雇って給与支払いをしている場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届け出」の提出が必要です。第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用元:所得税法 | e-Gov 法令検索
所得税関係の書類提出
個人事業主で亡くなった方が、確定申告において青色申告をしていた場合には「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。 この書類の提出期限は翌年の3月15日ですが、ほかの提出書類と一緒に早めに提出しておきましょう。消費税関係の書類提出
亡くなった方が消費税の納税義務者だった場合は、「個人事業者の死亡届出書」を提出してください。この書類の提出は、個人事業主の死亡後に速やかに行うことが国税庁ホームページに記載されています。
準確定申告
準確定申告とは、個人事業主が亡くなったときに行う確定申告のことです。 納税者は亡くなっていますので、相続人が行う必要があります。
確定申告というと、2月16日から3月15日までに申告を行うイメージがあると思いますが、準確定申告は亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得について申告を行うことになっています。
引用元:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
相続人が個人事業を引き継ぐ際の手続き
相続人が被相続人の個人事業を引き継ぎたいという場合もあるでしょう。 事業を引き継ぐ際の手続きや提出書類について説明します。
- 廃業届出書などの書類提出をしなければならないのは変わりない
- 相続人は個人事業主として開業するための書類の提出が必要
- 相続人は屋号を引き継げる
廃業届出書などの書類提出をしなければならないのは変わりない
亡くなった方の個人事業を引き継ぐ場合でも、「個人事業主が亡くなった場合の手続き」を行うことは変わりません。税務署への届出・準確定申告については、あくまでも亡くなった方に関する手続きとして必要だと考えておきましょう。
相続人は個人事業主として開業するための書類の提出が必要
事業を引き継ぐ方(相続人)が個人事業主として開業届を出していない場合、その方が個人事業主として開業届を提出する必要があります。相続人は屋号を引き継げる
たとえば、飲食店を引き継いだ場合に店名(屋号)を変えてしまうと、これまでお店に通ってくれていたお客さんが離れてしまう可能性があります。そのため、同じ店名(屋号)を引き続き使いたい……ということもあるでしょう。
被相続人の廃業届を出したからといって、その屋号は使ってはならないということはありません。
相続人が開業届を出す際に、被相続人が使っていた屋号で登録することで、引き続き利用することが可能です。
個人事業主が死亡した場合の相続税軽減の制度
個人事業主が死亡した場合に相続税を軽減する制度がいくつかあります。
- 小規模宅地等の特例
- 個人版事業承継税制
小規模宅地等の特例
不動産を相続した際に、土地の評価額を減額できる小規模宅等の特例があります。被相続人が事業を行っていた土地の場合や、被相続人と生計を一にしていた(共通の資金で生活をしていること)親族が事業を行っていた土地の場合には、「特定事業用宅地等」に該当するため、最大80%の減額をすることができます。
被相続人が不動産賃貸事業のために貸付をしていた土地である場合や、被相続人と生計を一にしていた親族が不動産賃貸事業のために貸付をしていた土地である場合には、「貸付事業用宅地等」に該当するため、最大50%の減額をすることができます。
個人版事業承継税制
青色申告事業者について、相続などによって取得した特例受贈事業用資産または特例事業用資産(以下、これらを「特例事業用資産等」とします)に係る相続税や贈与税の納税を猶予し、後継者がさらに次世代の後継者にその特例事業用資産等を承継した場合などに、猶予されていた相続税・贈与税が免除される制度 です。 小規模宅地等の特例が利用できなくなりますが、そのあと何代にもわたって事業を続けていることが想定できる場合には、利用によって相続税が免除されることになるので、節税の観点からはメリットが大きい制度であるといえるでしょう。 いずれも、非常に複雑な制度なので、個人事業を引き継ぐ場合には、弁護士・税理士に相談することをおすすめします。個人事業主が亡くなった場合の相続財産
株式会社などの法人の場合、法人に帰属している財産については個人が相続することはありません。
しかし、個人事業主についてはこのような制度ではないので、相続においてはプラスの資産も相続しますし、借金や買掛金のようなマイナスの財産である債務も相続することになります。
個人事業主が死亡した場合の相続放棄
個人事業主の相続をした場合には借金や債務も引き継ぐことになります。事業の規模によっては、個人が銀行や消費者金融でする借金よりも多額の事業用の借金や買掛金が残ってしまっている……ということもあるでしょう。
そのような場合、相続放棄や限定承認という手続きを利用すれば借金を相続しなくても済みます。
しかし、借金や買掛金の調査がとても難しいです。
ここでは、個人事業主が死亡した場合の相続放棄について解説します。
個人事業主を相続した場合も相続放棄は可能
相続放棄は被相続人の職業によって差はなく、個人事業主を相続した場合も相続放棄は可能です。 被相続人が個人事業主であった場合には、事業の規模によっては莫大な借金・債務を抱えていることがあります。 また、特定の相続人に事業用資産を集めたい場合に、相続放棄を利用することも考えられます。個人事業主の場合に債務の調査に注意
通常、消費者金融・貸金業者などから借り入れをしている場合には、信用情報を確認すれば借金があるか確認することができます。しかし、個人事業主の場合には、信用情報でわかるのは貸金業者からの借金だけで、親族やほかの経営者など個人的に借金をしているものや、事業の買掛金・未払金、ほかの債務の連帯保証債務については信用情報から確認することはできません。
そのため、信用情報の確認とともに帳簿類を調査したり、生前に付き合いのあった経営者仲間や取引先などに債務や連帯保証債務がないか確認したりする必要があります。個人事業主の場合も相続放棄の期間は3カ月なので、調査に時間がかかる場合には期間の伸長の手続きを早めに行いましょう。
引用元:相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所
さいごに|個人事業主の相続手続きは専門家に相談
個人事業主が亡くなった場合には、税務署や市区町村役場などでさまざまな手続きが必要で、期限など注意が必要です。 また、個人事業をしているという点から借金をしている可能性があり、相続放棄なども考えなければなりません。 相続に詳しい弁護士や税理士になるべく早めに相談をして、手続きを進めるようにしましょう。


- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2023.08.11相続全般自殺で損害が生じた場合は相続人が損害賠償義務を負う?自殺の際の相続手続きについても解説
- 2023.08.11相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2023.07.18相続全般被相続人が外国人だったら違いはあるの?相続人が外国人だったら?
- 2023.06.09相続全般相続人となる直系尊属とはどのような人か