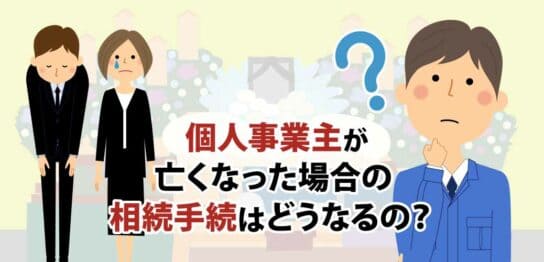はじめに
親の不動産を相続したものの、兄弟姉妹で共有するべきか悩んでいませんか。
実家などの不動産の相続は、多くの家庭で避けられないテーマです。
特に相続人が複数いる場合、「共有」という形で不動産を引き継ぐことがありますが、その選択にはメリットもデメリットも存在します。
節税や手続きのしやすさがある一方、後々トラブルの火種になることも。
本記事では、不動産を共有状態にするメリット・デメリットを整理し、判断の助けになる情報をわかりやすく解説します。
相続した不動産を共有状態にするとは?
不動産の相続が開始されると、その不動産は相続人全員が共有している状態になります。
共有には持分があり、この段階での持分は法定相続分に従う形となります。
たとえば、被相続人である親が亡くなって3人の子が相続人となる場合、遺産となる不動産の持分は1/3ずつ共有している状態です。
不動産の所有者が亡くなった場合に、登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きを相続登記といいますが、相続人全員の共有になった段階では、必ずしも相続登記をする必要はありません。
共有状態になっている不動産を誰が相続するか確定するために遺産分割協議をしますが、遺産分割協議の結果として不動産を複数の相続人で共有する場合もあります。
また、遺産分割協議の結果、1人が現金を相続し、ほかの2人が共有する場合などもあります。
遺産分割方法は他に3種類ある
共有以外の主な遺産分割方法として、以下の3種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
現物分割
現物分割は、相続される財産を処分することなく、それぞれの相続人が遺産をそのまま相続する方法です。
たとえば、長男と次男に土地と現金の遺産が残されていた場合に、長男が土地を相続し、次男が現金を相続するケースです。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が遺産をそのまま相続し、ほかの相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば、親の不動産を長男が単独で相続し、次男に代償金として不動産の価値に見合う金銭を支払うのが代償分割です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して金銭にしたあと、その金銭を各相続人で分配する方法です。
相続財産として土地が残されたが誰も相続したくない場合や土地より現金として受け取りたい場合に有効です。
相続した不動産を共有状態にするメリット
相続した不動産を共有状態にするメリットは、以下の2つです。
- 遺産分割協議を完了させやすい
- 節税になる可能性がある
それぞれ詳しく説明します。
遺産分割協議を完了させやすい
相続した不動産をどうするか意見がまとまらない場合、遺産分割協議がいつまで経っても完了せず、トラブルに発展するおそれがあります。
また、相続税の申告は原則として相続開始から10カ月以内に行う必要があるため、相続の手続きが進まないと相続税の申告に弊害が生じる可能性もあります。
未分割のまま相続税の申告を行うことも可能ですが、修正申告が必要になるといった手間もあるため、不動産を共有にすることで遺産分割協議を完了させ、相続の手続きを進めやすくすることができます。
節税になる可能性がある
相続した不動産を共有すると、節税になる可能性があります。
一般にマイホーム特例と呼ばれる特別控除の制度で、マイホーム(居住用の財産)を売却した場合に得られる譲渡所得について、最高で3,000万円まで譲渡所得税が控除されます。
所定の要件を満たした場合、不動産を共有している各相続人がそれぞれ特例を利用できるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
相続した不動産を共有状態にするデメリット
相続した不動産を共有する場合に、デメリットもあります。

- 1.相続登記の手続きの手間が増える
- 2.売却に共有者全員の同意が必要となる
- 3.見知らぬ人と共有状態になるリスクがある
- 4.権利関係が複雑化するリスクがある
それぞれのデメリットについて解説します。
相続登記の手続きの手間が増える
相続開始時に相続人全員の共有で相続登記をして、その後の遺産分割協議によって誰が不動産を所有するか(共有するか)が決まった場合、それに従って再度登記する必要があるため、手間や費用がかかります。
売却に共有者全員の同意が必要となる
共有している不動産は保存、管理、変更の3種類の行為があります。
保存は共有物の清掃や修繕などが当てはまり、各共有者が独自の判断で行うことができます。
管理は共有物の賃貸借契約の締結や解除などで、持分の過半数の同意が必要です。
変更は共有物全体の売却や取り壊しを行うことを指し、変更をするには共有者全員の同意が必要となります。
なお、各共有者は自己の持分に関する権利(持分権)については、ほかの共有者の同意を得ず他者に売却することができます。
見知らぬ人と共有状態になるリスクがある
共有者が不動産の持分権を他者に売却した場合、持分権を取得した人が新しい共有者になります。
ほかの共有者にとっては、見ず知らずの者と共有状態になることで、トラブルの原因になる可能性もあるでしょう。
権利関係が複雑化するリスクがある
共有状態が長期間継続すると、ほかの共有者が複数の者に持分権を売却したり、共有者が亡くなって複数の相続人が持分権を相続したりするなど、権利関係が複雑になるおそれがあります。
共有者が増えると、管理や変更のための話し合いが困難になるなどの問題が生じやすくなります。
単独使用時の賃料支払い義務
共有者の1人が権限なく共有不動産を単独で使用している場合、ほかの共有者は占有者に対して賃料相当額を請求できるという判例(最判平12・4・7裁判集民198号1頁)があります。
共有不動産を単独で使用できる権限とは、ほかの共有者と使用貸借契約を締結している場合などです。
この点、使用貸借契約は、相当期間が経過したあとに解約の申し入れをすれば、原則として契約を終了させることができます。
契約が終了したあとに単独で使用を継続する場合、賃料相当額の支払が必要になります。
さいごに
相続が開始して不動産を共有した場合、揉めることなく遺産分割協議を完了させやすい、節税できる可能性があるなどのメリットがあります。
一方で、共有した不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になる、持分権の売却によって他人が共有者になる可能性があるなどのデメリットもあります。
遺産分割協議をスムーズに進めるための選択肢としてはありですが、共有状態が長く続くとさまざまなトラブルに発展するおそおれがありますので、注意しましょう。
参考記事:
親から相続した土地の売却にかかる税金一覧!特例と節税対策をプロが解説
法定相続分とは?計算方法や遺留分との違いをわかりやすく解説|ワケガイ
実家リノベーションは建て替えよりお得?事例や費用相場、注意点を解説|フルリノ

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.09.22相続全般相続した不動産は共有にすべき?メリット・デメリットと注意点を解説
- 2025.09.19相続税申告・対策弔慰金は相続税ではどのように評価するか解説
- 2025.09.05相続手続き代行遺産分割協議後に新たな財産が発覚!この場合どうすればいいの?
- 2025.08.15相続税申告・対策相続した不動産の固定資産税は誰が支払う?税金の計算方法についても解説!