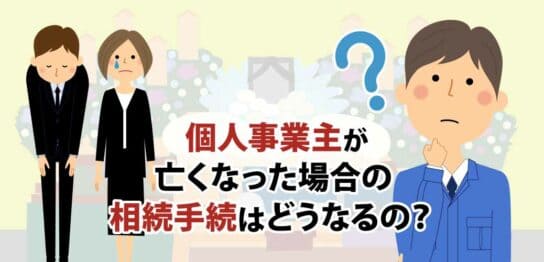はじめに
特に被相続人(いとこ)に配偶者や子ども、親兄弟がいない場合、家族構成が複雑なことから、相続関係もわかりにくくなりがちです。
相続人がいないケースでは、財産は最終的に国庫に帰属することになりますが、生前に関わりの深かった親族や内縁関係者などが財産を受け取れる可能性があります。
本記事では、いとこの相続に関する基本知識や、相続財産を受け取るための具体的な方法について、法律の観点からわかりやすく解説します。
いとこの相続人になりうるのは誰か
いとこの相続人は誰になるのでしょうか。
まずは、法律で定められている相続人について詳しく解説しましょう。
・子ども
・直系尊属
・兄弟姉妹
配偶者
配偶者は常に相続人になるとされています。
ただし、離婚した場合には配偶者として相続をすることはできません。
また、事実婚に過ぎない内縁の妻・夫は、配偶者として相続人となることができないので注意が必要です。
子ども
子どもは相続人となります。
子どもであれば嫡出子・非嫡出子は問いません。
離婚した相手との間に子どもがいる場合、その子どもも相続人となります。
子どもの代襲相続人として孫などの直系卑属がいる場合も子どもとして相続をすることになります。
普通養子縁組・特別養子縁組を問わず養子も、子どもとして相続をすることができます。
直系尊属
子どもがいない場合には、次の順位の相続人として、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、自分から直通する血族関係にある(直系)、親等が上の人のことをいい、具体的には親・祖父母・曽祖父母などが挙げられます。
普通養子縁組・特別養子縁組問わず、養親も相続をすることができます。
兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続をします。
兄弟姉妹については再代襲が認められていないので、甥と姪が代襲相続をすることができるのみで、その子どもは相続できないので注意しましょう。
いとこに相続権はない
叔父と叔母の子どもであるいとこは、法律上のどの規定にも当てはまりません。
そのため、いとこである場合には、たとえ親族であったとしても、相続をすることができません。
相続人がいない状態でいとこが亡くなると相続財産はどうなるか
相続人がいない状態でいとこが亡くなると、相続財産はどうなるのでしょうか。
生活の面倒をみていた場合、遺産を受け取ることができるのでしょうか。
相続人がいない場合の手続きと、いとこが財産を手にすることができる制度について解説しましょう。
相続人が不存在の場合
相続人がいない状態でいとこが亡くなった場合については、民法951条以下の相続人の不存在という章の規定が適用され、以下のように手続きが進みます。
② 期間を定めて公告するなどして相続人の捜索を行う
③ 亡くなった方に対する債権者などへの弁済などの精算を行う
④ 最終的に相続財産は国庫に帰属する
これにより最終的には、国庫に収められることになります。
特別縁故者による請求
ただし、相続財産に対して特別縁故者がいる場合には、家庭裁判所の許可を得て、相続財産の精算の際に財産を分け与えることができます。
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
亡くなったいとこと内縁関係にあった場合や、いとこの生活の面倒を見ていたような場合には、特別縁故者として財産を分けてもらうように請求することが可能です。
特別の寄与の制度は相続人がいる場合の制度
2019年7月1日から相続人に対して特別寄与料を請求できる制度が施行されました。
これにより、いとこは4親等の血族となり、生活の面倒を見るなど療養看護をしていた場合に特別寄与料の請求が可能です。
ただし、これは相続人がいる場合の規定で、相続人がいない場合にはあくまで特別縁故者として請求をすることができるにとどまります。
相続権のないいとこに財産を継がせるための方法
特別縁故者にあたらない場合には、いとこの遺産を引き継ぐことができません。
また仮に特別縁故者にあたる場合でも、いとこの遺産を引き継ぐためにはとても時間がかかります。
相続権のないいとこの財産を継ぐためには、どのような方法があるのかみていきましょう。
・養子縁組
・遺言書の作成
・死因贈与
・生前贈与
婚姻
婚姻をすることで配偶者となれば相続人となるので、いとこの財産を相続することができます。
民法734条は近親婚を禁止していますが、直系血族と3親等内の傍系血族の婚姻を禁じるものですので、4親等内の傍系血族であるいとこ同士は婚姻をすることが可能です。
婚姻をした場合には相続をすることができますが、生前は同居義務や扶助義務等も発生しますので注意が必要です。
養子縁組
養子縁組をすることで親子関係が発生すれば、養子・養親として相続人となり、相続することが可能となります。
婚姻と同様に法律上の親子関係が発生するので、扶養義務などが発生する点に注意が必要です。
遺言書の作成
遺言書を作成することで、相続人でない人に遺産を譲り渡すことが可能です。
遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言を問いませんが、無効となってしまうリスクを避けるために、公正証書遺言にすることや、自筆証書遺言・秘密証書遺言を作成する場合でも専門家に不備がないか確認してもらうとよいでしょう。
死因贈与
遺言書のほかにも、死亡を条件とする贈与をする、死因贈与を行うことで遺産を譲り渡すことが可能です。
贈与契約の一種なので、法律上は口頭でも成立しますが、手続きを行うにあたって証明することができません。
きちんと死因贈与契約書を作成するようにしましょう。
生前贈与
亡くなる前に生前贈与を行うのもひとつの手です。
この場合においても、トラブルにならないように贈与契約書を作成しておくようにしましょう。
また、110万円以上の生前贈与を行うと、贈与税の申告・納税が必要となる点についても注意が必要です。
さいごに
いとこが相続人として相続することはなく、特別縁故者に該当しない場合には遺産は国庫に収められてしまいます。
特別縁故者と認定されたとしても、遺産を受け取れるのは相続人の不存在の手続きが終わったあとなりますので、可能であれば遺言などの対策をしておくようにしましょう。
どのような対策が適切かについては、一度弁護士に相談することをおすすめします。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介