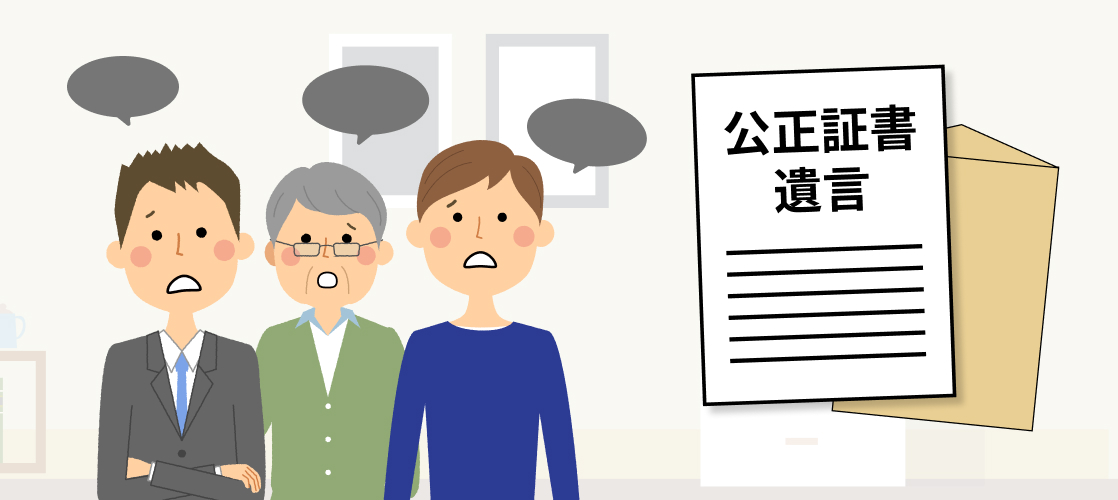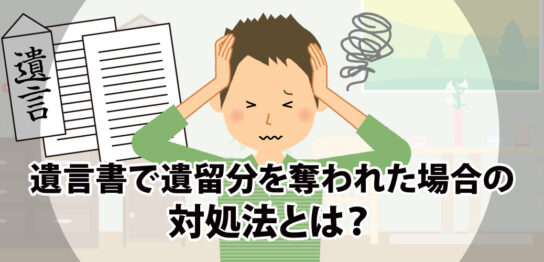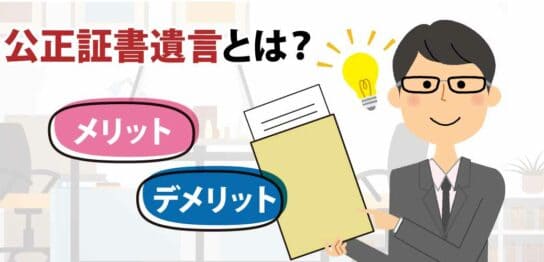- 公正証書遺言とは?
- 公正証書遺言があっても相続でもめる場合とは?
- 公正証書遺言のある相続でもめないためのポイントとは?
【Cross Talk】公正証書遺言があっても相続でもめてしまうのは、どのような場合ですか?
公正証書での遺言書の作成を検討しています。公正証書遺言があっても相続でもめるのはどのような場合でしょうか?
形式的な効力や実質的な内容に問題があると、相続人の間でもめる原因になります。
公正証書遺言でもめる場合について、詳しく教えてください。
ご自身が亡くなった後に、家族がスムーズに相続手続きができるよう、遺言書の作成を検討している方も多いと思います。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
このうち、公正証書遺言は、形式の不備による無効のリスクが低く、紛失や捏造のリスクがありません。
それでは、公正証書遺言とはどのようなもので、公正証書遺言があっても相続人がもめてしまうのはどのような場合なのでしょうか?
この記事では、このような疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。
公正証書遺言とは?

- 公正証書遺言とは?
- 公正証書遺言を作成しておくメリットとは?
そもそも、公正証書遺言とはどのようなものなのでしょうか?
ここでは、公正証書遺言の意義やメリットについて解説していきます。
公正証書遺言について
公正証書遺言とは、遺言者がその内容を公証人に伝え、公証人が法律に従って作成する公文書の遺言書です。
公証人は、法務大臣によって任命された法律の専門家であり、全国の公証役場でその職務を行います。公証人は、遺言者の意思を正確に聞き取り、遺言書として適切な法的表現を用いて作成する義務を負っています。そして、公正証書遺言は、遺言者本人が公証人と面談し、遺言の内容を口頭で伝えることで作成が進められます。
完成した遺言書は、遺言者と証人2名が内容を確認し、署名・押印することで効力を生じます。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない、非常に信頼性の高い遺言方式といえるでしょう。
公正証書で遺言を残しておくメリット
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
公正証書遺言は形式的な不備によって無効になるリスクが低い
公証人が法律の専門家として作成するため、自筆証書遺言のように形式不備で無効になるリスクを大幅に減らすことができます。また、作成時に遺言者の本人確認や意思能力の確認が厳格に行われるため、「偽造」や「脅迫による作成」といった主張がされにくく、相続争いを予防する効果が期待できます。
紛失、変造、破棄・隠匿のリスクがない
原本は公証役場に保管されるため、遺言者が自分で保管する必要がなくなり、紛失や変造、破棄などのリスクがありません。遺言者は、正本や謄本といった写しを受け取ることができ、相続手続きにはこれらを使用します。万が一、正本や謄本を紛失した場合でも、公証役場に申請することで再交付してもらうことが可能です。
寝たきりの状態でも作成できる
自筆証書遺言は遺言者本人が全文を自筆する必要があるため、身体的な理由でそれが困難な場合には作成できません。しかし、公正証書遺言であれば、遺言者が公証人に口頭で内容を伝えれば作成してもらえるため、どのような状況の方でも遺言を残すことができます。
公証人に出張してもらうことも可能であり、自宅や病院、介護施設などで作成することもできます。
公正証書遺言でもめる場合とは

- 公正証書遺言でもめる場合とは?
- 遺言の効力や相続の内容でもめる可能性がある
公正証書遺言があっても相続人がもめてしまうのはどのような場合なのでしょうか?
遺言の効力や相続の内容をめぐって争いになる可能性があります。
遺言の効力が問題になっている
公正証書遺言は原則として有効性が高いものの、その効力が争われることがあります。主となるのは、遺言能力の疑いがある場合です。遺言書作成時に遺言者が認知症などで遺言内容を理解する能力(遺言能力)を欠いていたと判断されれば、遺言は無効となります。医師の診断や遺言作成時の状況などが争点となることが多いです。
また、公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要ですが、証人に欠格事由があった場合も無効となる可能性があります。未成年者、推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の親族などは証人になれません。
さらに、公正証書遺言の作成手続きにおける口授要件が満たされていなかった疑いがある場合も、無効となる可能性があります。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えることが原則であり、単に公証人が作成した案文を承認しただけでは口授と認められない場合があります。
相続人の遺留分を侵害している
公正証書遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重するものではありますが、一定の相続人(配偶者、子ども、直系尊属)には法律で保障された最低限の遺産の取り分である遺留分が存在します。
公正証書遺言の内容がこの遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人から、遺産を多く取得した相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」が行われる可能性があり、これが相続争いの火種となることがあります。
遺留分を侵害する遺言自体は有効ですが、金銭的な支払い義務が生じるため、紛争に発展しやすいといえます。
遺言書に一部の遺産について記載がない
遺言書に一部の遺産について記載がない場合、その遺産の分け方を巡って相続人間で協議が必要となり、意見が対立すると紛争が生じることがあります。
公正証書遺言でもめないポイント

- 公正証書遺言でもめないためのポイントとは?
- 相続に詳しい弁護士に相談する
公正証書でもめないようにするためには、どうすればいいのでしょうか?
ここでは、公正証書でもめないためのポイントについて解説していきます。
相続に詳しい弁護士に相談する
公正証書遺言の作成にあたっては、相続問題に精通した弁護士に相談することがもっとも有効な手段の一つです。
弁護士は、相続人間のトラブルに繋がりやすい遺言の内容を熟知しているため、個々の家族構成や財産状況に合わせて、将来的な紛争を予防するための適切なアドバイスを受けられます。遺言書の原案作成や公証人との打ち合わせといった煩雑な手続きを代行してもらうことも可能です。
公証人は遺言の形式的な適法性は確認しますが、内容面での紛争予防に関するアドバイスは行わないため、弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。
遺留分を侵害しない遺言にする
相続争いの大きな原因となるのが遺留分の侵害です。
公正証書遺言を作成する際には、各相続人の遺留分を事前に正確に把握し、できる限り遺留分を侵害しない内容にすることが重要です。もし、特定の相続人に多くの財産を相続させたいなどの理由で遺留分を侵害する可能性がある場合は、その理由を遺言書の付言事項に記載し、他の相続人に理解を求めることも有効な場合があります。
ただし、付言事項には法的拘束力はないため、遺留分侵害額請求を完全に防ぐことはできません。遺留分に配慮した遺言書を作成するためには、弁護士などの専門家の助言を得ることをおすすめします。
遺言執行者を指定しておく
遺言者の死後、遺言の内容をスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定しておくことが有効です。
遺言執行者とは、遺産目録の作成、相続財産の管理、名義変更手続きなど、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を持つ人物です。
中立的な第三者である弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することで、遺産分割手続きの透明性と円滑性を高め、相続人間の紛争を予防する効果が期待できます。遺産や相続人の状況によっては、専門知識を持つ弁護士を遺言執行者に選任することが賢明な判断といえるでしょう。
公正証書遺言でもめた場合の対処法

- 公正証書遺言でもめた場合の対処法とは?
- 家庭裁判所の調停や訴訟を活用する
公正証書遺言があってももめた場合にはどうすればいいのでしょうか?
ここでは、公正証書遺言で相続争いになった場合の対処法を解説していきます。
相続人の間で話し合う
どのような争点がある場合でも、まずは相続人間で冷静に話し合い、解決の糸口を探ることが重要です。 感情的な対立がある場合は、第三者である弁護士に交渉の代理を依頼することも有効な手段となります。 当事者間の直接的な話し合いが難しい場合でも、弁護士が間に入ることで、法的な観点からの合理的な解決を目指せる可能性があります。
遺言無効確認調停・訴訟を活用する
公正証書遺言の有効性に争いがある場合(例えば遺言者の遺言能力の有無、作成手続きの不備など)には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てることを検討してください。
調停は、裁判所の調停委員が間に入り、当事者間の合意による解決を目指す手続きです。
調停が不成立に終わった場合や、早期に法的判断を求める必要がある場合には、遺言無効確認訴訟を提起し、裁判所に遺言の有効性について判断を仰ぐことになります。遺言が無効と確定した場合、その後の遺産分割は相続人全員の協議によって行われます。
遺留分侵害額請求調停・訴訟または遺産分割調停・審判を活用する
遺言の有効性には争いがないものの、遺言に記載がない遺産の分け方について相続人間の意見が対立し、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、調停委員の仲介のもと、具体的な遺産の分け方について合意を目指します。
調停が成立しない場合には、遺産分割審判へと移行し、最終的には裁判所が遺産の分割方法を決定することになります。これは、遺言の内容を前提としつつ、公平な遺産分割を実現するための手続きです。
また、遺言が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
まとめ
公正証書遺言は、形式不備による無効のリスクは低いものの、遺言者の遺言能力、証人の欠格、作成手続きの瑕疵などにより無効となる場合や、遺留分を侵害している場合、遺言に一部の遺産について記載がない場合には、争いに発展する可能性があります。
もめてしまった場合の対処法としては、まずは相続人間での話し合いを試み、合意に至らない場合は遺言無効確認調停・訴訟、または遺留分侵害額請求調停・訴訟や遺産分割調停・審判といった法的手段を検討する必要があります。
当事務所では、公正証書遺言の有効性の検討から、遺留分侵害額請求、遺産分割に関する交渉・調停・訴訟まで、幅広くサポートしております。公正証書遺言を巡るトラブルでお困りの場合には、ぜひ、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続全般相続分の譲渡とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、税金や方法について解説
- 2025.10.27遺産分割協議遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか記載の注意点や文例などについて解説
- 2025.10.20相続全般任意後見人ができること・できないこと|なれる人の条件について
- 2025.09.25成年後見成年被後見人は遺言を作成できるのか