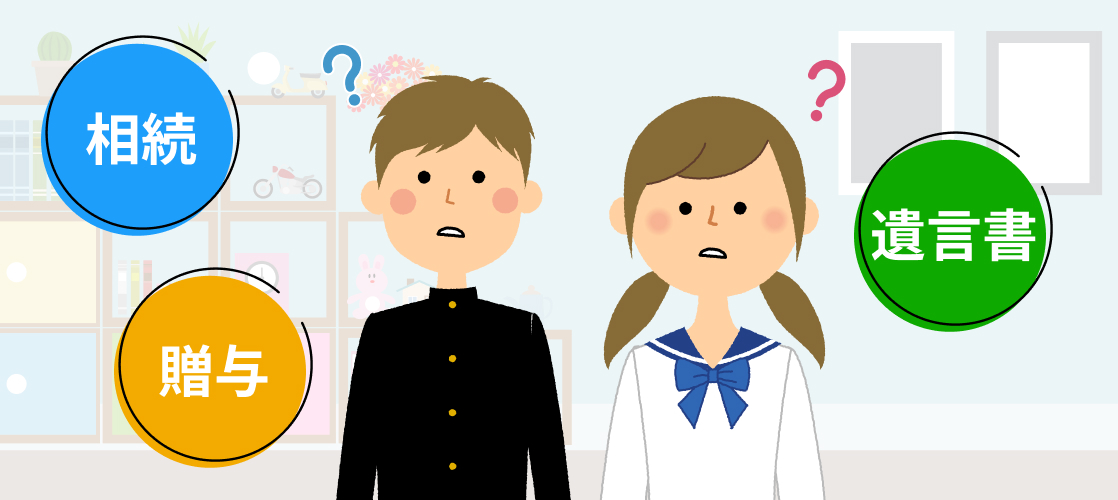- 民法の改正によって成人年齢が18歳に引き下げられた
- 18歳以上で遺言の証人になったり、相続放棄をしたりすることができるようになった
- 成人年齢の引き下げによって相続・遺言書・贈与への影響が生じた
【Cross Talk】成人年齢の引き下げによって、相続や遺言書にどんな影響が生じた?
成人年齢の引き下げによって、相続・遺言書・贈与などにどんな影響がありましたか?
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、相続や遺言書に関する手続きの多くが18歳からできるようになりました。
成人年齢の引き下げは、相続の分野にも影響があったんですね。影響について詳しく教えてください!
民法の改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 成人年齢の引き下げによって、相続や遺言書など、相続分野の手続きにおいても影響がみられます。 そこで今回は、成人年齢の引き下げによって相続・遺言書・贈与にどのような影響があるかを解説いたします。
成人年齢の引き下げについて

- 民法の改正によって成人年齢が18歳に引き下げられた
- 18歳以上で遺言書の証人になったり相続放棄をしたりできるようになった
成人年齢の引き下げについて教えてください。
民法の改正によって、成人になる年齢が18歳に引き下げられました。引き下げによって、18歳以上で遺言書の証人になったり、相続放棄したりできるようになりました。
成人年齢を18歳に引き下げる民法の改正
成人年齢を引き下げる民法の改正(2022年4月1日施行)によって、成人年齢(成年年齢)が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者が法律行為をする場合、原則として法定代理人(親権者)の同意を得なければならず、同意を得ずにした法律行為は原則として取り消すことができます。
従来は20歳以上が成人として単独で法律行為ができたところ、成人年齢の引き下げによって、18歳以上であれば成人として単独で法律行為ができるようになりました。
未成年者がいる場合の相続
成人年齢の引き下げによって、18歳以上であれば単独で遺産分割協議に参加できるようになりました。
遺産分割協議とは、相続人全員が協議をして遺産をどのように分割するかを話し合う手続きです。
遺言書によって遺産の分割方法が指定されていない場合は、相続人全員が遺産分割協議に同意しなければ、原則として遺産を分割することができません。
未成年者は単独で遺産分割協議に参加することができないので、親権者が代理人として参加しなければなりません。
親権者も相続人である場合は、未成年者と親権者の利益が相反するため、家庭裁判所に申立てて特別代理人を選任する必要があります。
成人年齢が20歳であった頃は、18歳は未成年者なので、遺産分割協議に単独で参加することができませんでした。
成人年齢が引き下げられたことで、遺産分割協議の時点で18歳以上であれば、協議に単独で参加することができるようになりました。
未成年者の遺言書について
民法の規定により、15歳以上であれば未成年者でも単独で遺言書を作成することができます(民法第961条)。
民法の改正によって成人年齢が18歳に引き下げられましたが、遺言書の場合はそもそも15歳以上であれば、改正前でも単独で遺言書を作成することが可能でした。
遺言書を作成できる年齢が18歳ではなく15歳以上とされている理由は、遺言書の効果は本人が亡くなった後に生じるので、未成年者を保護する必要性が通常よりも低いと考えられるからです。
未成年者が法律行為をするには通常は親権者の同意が必要ですが、遺言書の場合は15歳以上であれば、未成年者でも単独で遺言書を作成することができます。
また、契約などの法律行為は、未成年者本人の代理として親権者が行うことができますが、遺言書の場合は親権者が代理することができません。
未成年者の生前贈与について
成人年齢の引き下げによって、18歳以上であれば単独で生前贈与の受贈者になることができます。
生前贈与とは、贈与者が生きている間に、自分の財産を受贈者に譲る行為です。
例えば、孫が大学に進学したお祝いとして、自分が生きている間に祖父が孫に金銭を与えるケースです。
未成年者を受贈者として生前贈与をする場合は、親権者の同意が必要です。
従来は成人年齢が20歳以上だったので、18歳の受贈者に生前贈与をするには、親権者の同意が必要でした。
成人年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳以上であれば親権者の同意によらずに単独で受贈者になることができます。
遺言書の証人になること
成人年齢が引き下げられたことで、18歳以上から遺言書の証人になれるようになりました。
遺言書の証人とは、公正証書遺言における証人のことです。
公正証書遺言を作成するには公証役場で手続きをする必要がありますが、公正証書遺言を作成する要件の一つとして、2人の証人が要求されます。
公正証書遺言の証人になれるのは、遺言者と利害関係がなく(相続人になると思われる方やその配偶者など)、かつ未成年者でない者です。
かつては成人年齢が20歳だったので、18歳は未成年者であり、証人にはなれませんでした。
しかし、成人年齢が18歳に引き下げられたので、18歳以上であれば公正証書遺言の証人になれるようになりました。
相続放棄
成人年齢の引き下げによって、18歳以上であれば単独で相続放棄ができるようになりました。
相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産を相続したくない場合に手続きをすることで、被相続人の遺産を相続しなくてすむ制度です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして法的に扱われます。
相続放棄によって借金などの不利益となる財産を相続せずにすみますが、預貯金などの利益となる財産も相続できなくなります。
単独で相続放棄ができる年齢は従来までは20歳以上でしたが、成人年齢の引き下げによって、18歳以上から相続放棄ができるようになりました。
成人年齢の引き下げによる相続・遺言書・贈与への影響とは?

- 成人年齢の引き下げによって未成年者控除の期間が短縮された
- 贈与税の各種特例が適用される年齢が18歳からになった
成人年齢の引き下げによって、相続・遺言書・贈与などにどのような影響がありますか?
未成年者控除の計算に用いる期間が短縮された、贈与税の各種特例の年齢が18歳以上からになった、などの影響がありますね。
相続への影響
成人年齢の引き下げによって、18歳から単独で遺産分割協議に参加したり、相続放棄をしたりすることができるようになりました。
また、相続税には未成年者控除の制度がありますが、成人年齢の引き下げによって、以下のように期間が2年分短縮されています。
・引き下げ後の未成年者控除:(18歳 − 相続時の年齢) × 10万円
例えば、16歳で相続人になった場合、従来の控除額は40万円でしたが、成人年齢引き下げ後の控除額は20万円です。
遺言書への影響
未成年者であっても、15歳以上であれば単独で遺言書を作成することができます。
成人年齢の引き下げによって18歳以上から成人となりますが、引き下げ以前から15歳以上であれば単独で遺言ができたので、18歳であれば引き下げにかかわらず単独で遺言書作成が可能です。
贈与への影響
成人年齢の引き下げによって、18歳以上であれば単独で贈与の受贈者になることができます。
贈与を受けた受贈者は贈与税の対象になりますが、贈与税には暦年課税制度の特例税率や、相続時精算課税制度などの特例があります。
成人年齢の引き下げによって、贈与税に関するこれらの特例が、18歳以上から利用できるようになりました。
まとめ
民法の改正によって、成人になる年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
相続の分野においては、遺産分割協議書に単独で参加したり、公正証書遺言の証人になったりすることなどが、18歳からできるようになりました。
また、贈与においても18歳から単独で受贈者になることができます。
相続における成人年齢の引き下げの影響について詳しく知りたい場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
<参照>
1成人年齢の引き下げについて
2)未成年者がいる場合の相続
https://www.e-souzok.com/report/archives/566
18歳未満が未成年者に!成年年齢の引き下げと相続への影響
4)未成年者の生前贈与について
https://aichi-souzoku.com/case/case-2049/
https://www.setuzei.biz/archives/2292
2成人年齢の引き下げによる相続・遺言・贈与への影響とは?
成年年齢が18歳に引き下げ!相続税・贈与税への影響とは

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28遺産分割協議兄弟姉妹の遺産分割で発生しやすいトラブル!争いを避けて円満に解決するポイント
- 2026.01.19遺言書作成・執行遺言は録音やビデオメッセージでも有効?書けない場合の対応方法について解説
- 2025.11.26遺言書作成・執行遺言執行者は必要?メリット・デメリットや選任した方が良い場合について
- 2025.07.28遺産分割協議数次相続が発生する場合の遺産分割協議書について