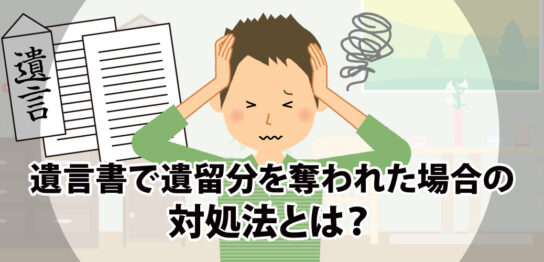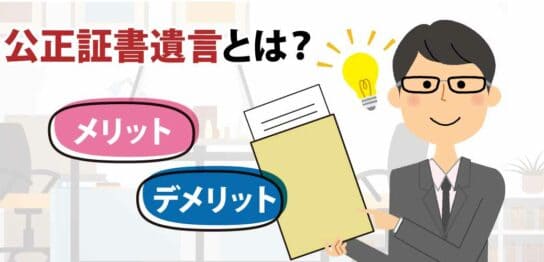- 偽造・変造された自筆証書遺言は無効である
- 遺言の偽造・変造を防止するには、公正証書遺言がおすすめ
- 遺言の無効を裁判で争う場合は、遺言無効確認訴訟を提起する
【Cross Talk 】遺言の偽造・変造にはどう対処すればいいの?
遺言書を書こうと思うのですが、偽造・変造されないか心配です。
自筆証書遺言は自分で遺言書を作成できますが、偽造・変造されやすいのがデメリットです。偽造・変造を予防するにはいくつかの方法があるほか、ご本人が亡くなった後も遺言書の偽造・変造について裁判で争うこともできます。
遺言の偽造・変造への対策法や、裁判で争う方法などがあるのですね。それぞれ詳しく教えてください!
せっかく遺言書を作成したのに、遺言の内容が気に入らなかった相続人などによって、遺言書が偽造・変造されないか心配になるかもしれません。 自分で遺言書を作成する自筆証書遺言の場合、遺言書の偽造・変造が行われやすいというデメリットがあります。 しかし、自筆証書遺言の保管制度を利用したり、裁判で遺言の無効を争ったりなど、遺言の偽造・変造に対抗する方法はいくつかあります。 そこで、遺言の偽造・変造への対策法や、裁判で争う方法などを解説いたします。
遺言が偽造・変造される場合

- 偽造・変造された自筆証書遺言は無効である
- 裁判所が遺言書を検認しても、それによって偽造・変造が有効になるわけではない
父親の押印のある遺言書が見つかったのですが、どうも怪しいのです。遺言が偽造・変造されることはありますか?
本人の印鑑を利用して偽の遺言書を偽造したり、本人が作成した遺言書の文章を勝手に変造したりなどが考えられます。
遺言が偽造される場合
遺言の偽造とは、遺言書を作成する権限のない方が、遺言書を作成することです。 遺言の偽造の例としては、同居人が印鑑などを利用して、本人が作成した遺言書であるかのように偽った遺言書を作成することも考えられます。例えば、父親と同居している子どもが、父親の印鑑を使って父親が書いたかのように偽って遺言書を作成することがあります。 遺言の偽造は、主に自筆証書遺言において問題となることが多いです。
自筆証書遺言とは、遺言者(遺言をする)本人が自書して遺言書を作成する方式です。 自筆証書遺言においては、本人が全文・氏名・日付などを自書したうえで、本人が押印をしなければなりません(民法第968条)。 本人以外が本人の印鑑を使用したり、本人を偽って文章を作成したりした場合は、自筆証書遺言の要件を満たさないので、遺言の効力が認められないのです。遺言が変造される場合
遺言の変造とは、権限のない方が正しい遺言に変更を加えることで、偽りの遺言にしてしまうことです。例えば、父親と長男が同居している場合で考えてみましょう。 父親が作成した遺言書を長男が偶然発見したところ、内容が気に入らなかったことから、長男が遺言書の内容を勝手に書き換えてしまうなどです。 父親が作成した遺言書に変更を加える権限があるのは、遺言者である父親自身です。権限のある父親自身が、遺言書に変更を加えることは問題ありません。
しかし、長男は父親の遺言書を変更する権限がないので、長男が遺言書に勝手に変更を加えた場合は、遺言書の変造になり得ます。検認されたとしても有効となるものではない
裁判所によって検認されたとしても、偽造・変造された遺言が有効になるわけではありません。検認とは、家庭裁判所が自筆証書遺言について公的に確認するための手続きです。 自筆証書遺言を発見した方は、遺言者が亡くなったことを知った後に遅滞なく、家庭裁判所に対して検認を申立てなければならないと規定されています(民法第1004条第1項)。 家庭裁判所による検認は、相続人に対して遺言が存在することと、遺言の内容について知らせるために行われます。
また、検認の時点において遺言書がどのような状態であったかを確定することで、遺言書の偽造・変造を防止する役割もあります。 ただし、検認は遺言書の状態を明確にするために行われるものなので、検認が行われたとしても、それによって偽造・変造された遺言書が有効になるわけではありません。遺言書を偽造・変造した場合のペナルティ

- 遺言書の偽造・変造は相続欠格事由に該当する可能性がある
- 有印私文書偽造の罪に当たり刑罰が科される可能性がある
遺言書を偽造・変造した場合に何かペナルティはありますか。
遺言書を偽造・変造すると、相続人の資格を失う相続欠格事由に該当し、相続できなくなる可能性があります。また、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪が成立し、刑罰が科される可能性もあります。
相続欠陥事由に該当する可能性がある
相続欠格とは、法律の定める一定の事由がある場合に当然に相続人の資格を失わせる制度です。
一定の事由には、たとえば被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させるなど、相続についての重大な非行が5つ列挙されています。相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿することは欠格事由の一つとして定められています。
そのため、遺言書を偽造・変造すると、相続欠格事由に該当し、相続人としての資格を失う可能性があるのです。ただし、相続人の資格を失うのは重大な非行をした相続人に限られ、その相続人に子どもがいる場合には代襲相続できます。
有印私文書偽造罪が成立する可能性がある
行使の目的で遺言書を偽造、変造した場合、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪が成立し、3月以上5年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
また、偽造・変造した遺言書を、相続人に示すなどの方法により真正な文書として使用した場合、偽造有印私文書行使罪、変造有印私文書行使罪が成立し、同じく3月以上5年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
遺言の偽造・変造が疑われる場合の対応方法

- 公正証書遺言であれば、遺言の偽造・変造を防止できる
- 遺言の偽造・変造を裁判で争うには、遺言無効確認訴訟を提起する
遺言を作成しようと思うのですが、偽造されないかが心配です。効果的な予防方法はありますか?
遺言の偽造・変造を防止するには、公正証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言の場合は、保管制度を利用する方法もありますよ。
公正証書遺言は偽造・変造できない
遺言の偽造・変造を効果的に防ぐには、公正証書遺言を作成する方法があります。公正証書遺言とは、民法が定める遺言を作成するための方式の一つで、公証役場という公的機関において、公証人という特別な専門家である公務員の立ち会いのもとで作成されます。 公正証書を作成するには公証役場での手続きが必要で、作成には費用がかかりますが、専門家によって作成されるだけでなく、原本が公証役場で保管されるので、偽造・変造のリスクが低いのがメリットです。
公正証書は原本以外に正本や謄本がありますが、正本や謄本を遺言者名義の印鑑などで訂正したとしても、原本としての効力が認められるわけではないので、偽造・変造の防止に役立ちます。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合も同様
自筆証書遺言の偽造・変造を防止する方法として、「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。 自筆証書遺言は従来、遺言者の自宅などで保管されることが多く、遺言書の紛失や、遺言書が偽造・変造されたりなどのトラブルが少なくありませんでした。
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局によって本人確認が行われるほか、自筆証書遺言者の原本が法務局に保管されているので、遺言書の偽造・変造を防止しやすいのがメリットです。 また、制度を利用すると裁判所による検認が不要になります。自筆証書遺言・秘密証書遺言の偽造・変造が疑われる場合には遺言無効確認
自筆証書遺言や秘密証書遺言において、偽造・変造が疑われる場合は、遺言無効確認訴訟を提起する方法があります。遺言無効確認訴訟とは、偽造や変造などによって遺言の有効性に疑いがある場合に裁判を起こし、遺言が無効になるかどうかを裁判所に判断してもらう訴訟のことです。 ただし、遺言の有効性を争う場合は、原則として、まずは調停を申立てることが必要になります。
調停とは、中立的な立場である調停委員を交えて、裁判所における話し合いでの解決を目指す手続きです。 調停が成立しなかった場合、遺言無効確認訴訟を提起して、遺言の有効性を裁判所に判断してもらいます。 裁判の結果、遺言が無効であるとの判決が確定すれば、無効とされた部分については、遺産分割協議(相続人が話し合い、遺産をどのように分割するかを決める手続き)をやり直さなければなりません。 遺言無効確認訴訟においては、筆跡鑑定などの専門性の高い主張・立証が重要になってくるので、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。遺言書の偽造された場合の対処法

- 偽造が疑われる場合でも遺言書の検認は必要
- 遺言書が偽造されたことを明らかにする証拠を集める
遺言書を偽造・変造された場合、どのように対処すればいいですか。
まず、偽造・変造を立証するための証拠を収集する必要があります。遺言が偽造・変造されたもので無効であると争うには、遺言無効確認調停、遺言無効確認訴訟という裁判所の手続があるので、早めに弁護士に相談するといいでしょう。
偽造を立証する証拠を集める
遺言書が偽造・変造されたものであることを立証するための証拠を集める必要があります。 偽造・変造されたことを立証する方法としては、次のようなものが考えられます。
- 筆跡鑑定で遺言者本人が書いたものかどうかを明らかにする
- 遺言者の診断書、診療録などで遺言者の意思能力(判断能力)や身体的機能(自分で文字を書くことができる状態であったか)を明らかにする
- 日記等によって遺言者の日頃の言動と遺言書の内容が乖離していることを明らかにする
弁護士に相談する
遺言書を偽造・変造すると、民事上、刑事上のペナルティがあるので、偽造・変造をした方が素直に偽造・変造をしたことを認めるとは限りません。
偽造・変造をした方が事実を認めない場合に、偽造・変造を理由に遺言書が無効であるとして争う手段としては、裁判所の遺言無効確認調停、遺言無効確認訴訟という手続があります。
これらの手続を適切に進めるには専門的な知識が必要になるので、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめ致します。
まとめ
自筆証書遺言は自分で遺言書を作成できるのがメリットですが、偽造・変造されやすいデメリットもあります。 遺言書の偽造・変造を防止するには、公正証書遺言の作成や、自筆証書遺言書保管制度を利用したりなどの対策が重要です。 遺言書を偽造・変造されないように作りたい場合や遺言書が偽造・変造された疑いがある場合は、相続の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめ致します。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 葬式の準備、役所の手続き、親族の話し合い…等々、慌ただしい中で法律的なことを色々考えて動くことは大変なご苦労があると思われます。そのご苦労を少しでも肩代わりできるようお手伝いさせていただきます。
最新の投稿
- 2026.01.28遺言書作成・執行遺言書で遺留分を奪われた場合の対処法とは?
- 2026.01.28遺産分割協議遺産分割協議の期限はいつまで?遅れるリスクも解説
- 2025.12.21死後事務委任死亡届提出後の銀行口座はどうなる?NG行為とその理由について解説
- 2025.06.13遺留分侵害請求遺留分が認められる代襲相続人とは?範囲や遺留分割合を解説