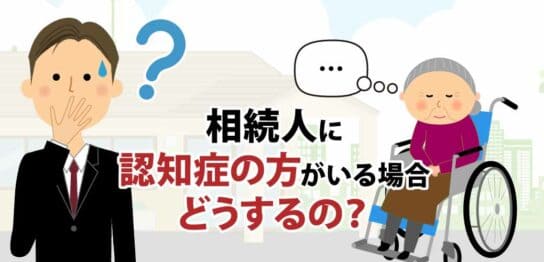- 任意後見制度のメリット
- 任意後見制度のデメリット
- 任意後見制度のデメリットを回避する方法
【Cross Talk 】任意後見制度にはどのようなメリット・デメリットがありますか?
任意後見の利用を考えているのですが、本当に任意後見をすべきかどうか、費用もかかるものなので悩んでいます。
確かに任意後見の利用には費用がかかるなどデメリットもありますね。メリットとデメリットどのようなものがあるかを把握して考えてみませんか?
はい、よろしくお願いします。
任意後見制度を利用するにあたってもメリット・デメリットがあります。自分で任意後見人を選任できること以外のメリットや、費用がかかること以外のデメリットも知って、任意後見制度を利用すべきかどうか考えてみましょう。
任意後見制度とは?

- 任意後見は本人の判断能力が低下する前に契約であらかじめ後見人を決めておくもの
- 任意後見には将来型、移行型、即効型の3つの利用形態がある
そもそも任意後見制度とはどのようなものなのですか?
任意後見制度とは、本人の判断能力が低下する前に、本人が選んだ人との間で契約を結び、その方が将来後見人となることや後見人に与える代理権の範囲等を決めておくというものです。任意後見契約には、将来型、移行型、即効型の3つの利用形態があり、本人の状況等に応じて選択することができます。
任意後見制度・法定後見制度の違い
後見には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
法定後見は、本人の判断能力が低下した後に親族等の申立てにより家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。後見人は家庭裁判所によって選任されますし、後見人の代理権等の範囲は法律で定められています。
これに対して任意後見契約は、本人の判断能力が低下する前に、本人が選んだ人との間で契約を結び、その方が将来的に後見人になることや後見人の代理権の範囲等をあらかじめ決めておくという制度です。
本人が後見人となる人を選び、後見人の権限の範囲を決めることができるという点が、法定後見制度との最大の違いであると言えます。
任意後見制度の利用形態
任意後見制度には、将来型・将来型・即効型の3つの利用形態があります。
将来型は、任意後見契約だけを締結する利用形態です。将来的に任意後見契約の効力が発生するまでの間は、後見人となる予定の方との間に何らの委任関係もないので、その間は本人が財産管理等をすることになります。
移行型は、任意後見契約を締結するとともに、身上監護・財産管理に関する委任契約を締結する利用形態です。任意後見契約の効力が発生するまでの間は、委任契約の受任者として委任された事務を行い、任意後見契約の効力発生後は後見人として委任された事務を行うので、「移行型」と言われているのです。これによって、任意後見契約の効力発生前でも本人の財産管理等の負担を軽減し、本人の判断能力が低下した場合は速やかに任意後見監督人の申立てをすることができます。
即効型は、任意後見契約を締結した後に直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる利用形態です。本人の判断能力が低下し始めて支援の必要が生じたが、任意後見契約を締結するのに必要な能力はまだあるというような場合に利用されます。
任意後見制度のメリット

- 任意後見制度のメリット
- 一番大きなメリットは誰に後見をしてもらうか自分で決めることができる点
任意後見制度のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
一番大きなメリットはやはり、後見人を自分で選ぶことができる点です。
任意後見制度のメリット・デメリットを確認しましょう。
後見を受ける本人の意思で後見人を選ぶことができる
任意後見制度を利用する最大のメリットは、後見人を本人が選べる点です。 何もしないで判断能力を失った場合には、通常は配偶者や親族などの申立てによる法定後見を利用することになり、後見人は事実上申立人をする人や資産が多い場合には裁判所が選ぶことになります。 本人にも法律上申立は可能ですが、判断能力を失っている段階でこのような申立ては難しいので、誰を後見人にするか選ぶことは事実上不可能です。 任意後見制度は、後見人や後見事務の内容について判断能力があるうちに決めておくことが可能で、このことが任意後見制度の最大のメリットといえます。後見人が適切な職務をするかを家庭裁判所によって選任される任意後見監督人によって監督することができる
任意後見制度には任意後見監督人が必須です。 任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場にあり、任意後見人が不適切な事務を行わないように監督してくれます。信頼できる任意後見人に依頼をし、任意後見監督人がそれを監督するということが可能になるという点もメリットの一つです。
関連記事:任意後見人を選任する場合の費用について解説任意後見人は後見事務を行うのに報酬を得ることができる。
任意後見人として後見事務を行う際には、任意後見人は本人の遺産から報酬を得ることが可能です。 また、法定後見人の報酬は、後見人が家庭裁判所に報酬付与の申立をしないと報酬が発生しない上、その額についても家庭裁判所が決定します。これに対し、任意後見人の報酬は、本人との協議に基づき定めることができる点もメリットの一つです。任意後見制度のデメリット

- 任意後見制度のデメリット
- 任意後見制度のデメリットを避ける方法
任意後見制度にはどんなデメリットがあるのでしょうか。
費用がかかることのほかにもデメリットはあります。それを避ける方法と一緒に確認しましょう。
任意後見制度にもデメリットがあるので、どのようなデメリットがあるか、それを避ける方法も確認しましょう。
任意後見契約だけでは死後の事務までは委任できない
任意後見契約によって、本人の財産管理や療養介護に関する契約について代理権が与えられます。 しかし、任意後見契約では死後に何かをしてほしいなどの死後事務の委任をすることができません。 もっとも、このデメリットは別途死後事務委任をすることで回避が可能です。任意後見人には取消権がない
任意後見人には取消権がないのもデメリットです。 法定後見が利用される場合には、本人は日常生活を営む以外の法律行為を単独で行うことができず、もしそのような法律行為がされた場合には、成年後見人が取り消すことが可能です(民法9条)。 問題になったような事例ですと、判断能力が不十分な方が自宅で一人のときに、保険の契約やリフォームの契約をさせられることがありますが、法定後見の場合にはこれらは取り消すことができます。 任意後見では後見人に与えられる権限は代理権のみで、取消権までは与えられていないのがデメリットです。 独居しているなどで、本人が単独で法律行為を行う可能性がある場合には、単独で大きな契約をすることができないような配慮が別途必要でしょう。財産管理委任契約に比べると諸々の手続きに時間と手間がかかる
財産を管理させたいだけならば、財産管理に関する委任契約を結んでおけばよく、このような契約をするに比して、公正証書を作成する・裁判所に申立てをするという手続きが必須な任意成年後見制度は、時間・手間(専門家に依頼をする場合には費用)がかかるものであるといえます。 これらのデメリットに見合うメリットを得られる見込みがあれば、任意後見を利用することに価値があるといえるでしょう。任意後見契約を解除されるリスクがある
任意後見監督人が選任される前は、本人または任意後見受任者はいつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除できます。そのため、本人は任意後見受任者に将来のことを任せたいとの意思が変わらない場合でも、任意後見受任者から任意後見契約を解除されるリスクがあるのです。
任意後見監督人に対する報酬が発生する
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。本人の親族等ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任されるのが一般的です。それらの専門職は、業務の一環として任意後見監督人になるため、報酬を支払わなければなりません。
任意後見契約に記載されていないことはできない
任意後見契約は、本人の意思を尊重して、本人が任意後見受任者を選び、その方に任せる代理権等の範囲をあらかじめ決めることができる制度です。そのため、任意後見人の代理権等の範囲は任意後見契約に記載されたものに限られるとされており、任意後見契約に記載されていないことは基本的に何もできません。ですから、任意後見契約を締結する際に、任意後見人にどのような権限をあたるかを慎重に検討する必要があるのです。
まとめ
このページでは、任意後見を利用するメリット・デメリットについてお伝えしました。 自分が任意後見を利用すべきかどうか迷われる場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.27相続手続き代行遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?注意点は?
- 2025.10.22成年後見任意後見制度のメリット・デメリットについて解説
- 2025.09.19遺産分割協議母や兄弟が遺産を独り占めする場合の典型的な手口と法的な対処法
- 2025.08.25相続全般会社経営者(社長)が亡くなった場合の相続手続きはどうなる?