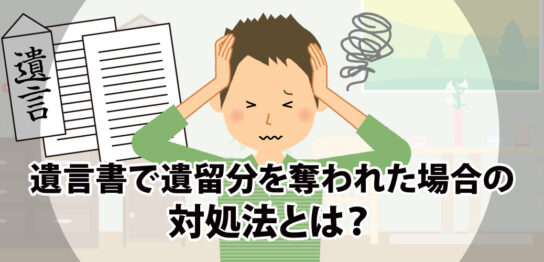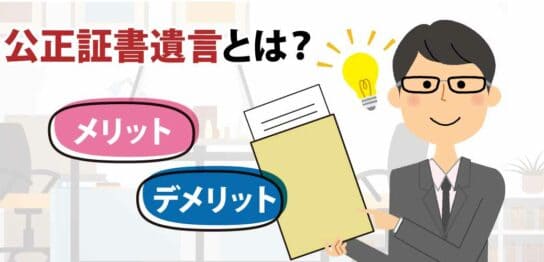- 遺言書の有無の確認の仕方
- 遺言検索システムの利用の仕方
【Cross Talk】父は遺言をしていた?遺言書の有無をどうやって確認すれば良い?
先日父が亡くなりました。葬儀で父の友人から「父の遺言に証人として立ち会ったので遺言書がある」ということを教えてもらいました。そこで形見分けもかねて父の遺品を探したのですが、自宅にはそれらしきものが出てこなくて…。どうやって探せば良いでしょうか。
公正証書という形で残した遺言であれば遺言検索システムというものが公証役場にあるので、それを使って確認することもできます。
そのようなものがあるんですね!詳しく教えてください。
遺言者が急に亡くなったような場合には、遺言をしていたとしても相続人がこれを見つけられないことがあります。
公正証書遺言を作成する場合、遺言書は公証人が遺言者の嘱託を受けて作成し、日本公証人連合会が情報をデータベースで管理しています。遺言書が見つからないときには、まず公証役場で遺言検索システムを利用してみましょう。
遺言書があるかどうかを調べるためには?

- 遺言検索システムとは?
- 公正証書遺言以外の遺言書の探し方
遺言書の有無を調べるシステムがあるんですね。
公正証書遺言については日本公証人連合会がデータベースで管理しており、遺言検索システムで調べることができます。公証役場に申込みをすれば遺言書の有無が確認できます。それ以外の遺言書については残念ながら自力で調べるしかありません。
「遺言をしたらしいがなかなか遺言書が見つからない」という場合、遺言の有無を調べるためにはどうすれば良いのでしょうか。
遺言検索システム
公証人は、昭和64年1月1日以降に公正証書遺言をしたものについては、遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・遺言書を作成した公証人名を日本公証人連合会に報告して、日本公証人連合会でデータベース化しています。そのため、遺言書の有無をこのデータベースを利用して探すことが可能となっています。 もし遺言書が保管されていた場合には、保管されている公証役場に請求をして遺言書の謄本を発行してもらえるため、この遺言書を利用して相続手続きをすすめることができます。自筆証書遺言書保管制度を利用している場合
自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で自筆証書遺言書の有無を確認することができます。自筆証書遺言書保管制度とは、一定の方式に基づいて行った自筆証書遺言書を法務局で保管するものです。
自筆証書遺言書保管制度についての事務を取り扱っている法務局であれば、自筆証書遺言書があれば閲覧し、画像化された遺言書を取得することができます。
なお、閲覧をするとほかの相続人に対して通知がされることになり、自筆証書遺言書が存在することがほかの相続人にも分かる仕組みになっています。
詳しくは、「【令和2年7月10日スタート】自筆証書遺言書保管制度ってどんな制度?」で解説していますのでご確認ください。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の遺言書は自力で探すほかない
公正証書遺言以外の自筆証書遺言・秘密証書遺言でされたものについては、2020年5月1日の段階で上記のような検索システムはありません。そのため、自力で探すほかないと言えます。。 自宅の金庫、通帳などを保管してある場所、日記やアルバムなどを保管してある場所などを探しても遺言がない場合には、本人が貸金庫に入れて保管している可能性もあります。貸金庫の利用料金は、口座のある銀行からの口座振替で行われますので、遺言者の通帳の利用明細を見て、貸金庫を利用しているような形跡がないか確認しましょう。
公正証書遺言以外が見つかったときには検認の手続きを忘れない
遺言書を探し、見つかった場合には、その内容にしたがって手続きをすすめます。 ただし、見つかった遺言書が、公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言書ではなかった場合には、「検認」という手続きが必要となります。検認をしないで勝手に開封したり、遺言の内容にしたがった手続きをした場合は、5万円以下の過料に処される可能性もある(民法1005条)ので注意が必要です。
基本は遺言書の検認がなければ、遺言書を使って不動産の名義変更や銀行預金の解約なども行えません。
遺言の検認には約1ヶ月半~2ヶ月程度の期間がかかるので、早めに行うようにしましょう。
遺言検索システムを利用するためには?

- 遺言検索システムの利用方法
遺言検索システムの利用方法を教えてください。
公証役場に必要な書類を持っていくことになります。近くの公証役場で大丈夫です。
遺言検索システムの利用方法を見てみましょう。
請求は公証役場で行う
遺言検索システムの利用請求は公証役場で行います。特に遺言者が公正証書遺言を作った公証役場に限られるというわけではないので、近くの公証役場に請求をします。請求にあたっては後述する必要書類を持参して行います。なお、検索をすることができるのは、遺言者が死亡した後であって、遺言者が生存中は本人以外一切回答をもらうことはできません。
請求をすることができる人
請求をすることができるのは相続人や利害関係人になります。 相続人は民法で規定された相続人のことを指します。利害関係人とは、遺言があることに利害関係を有する者のことをいい、相続人以外で財産を譲り渡される受遺者・遺言執行者・相続財産管理人がこれにあたります。請求をするための書類
検索をする際に必要な書類は、次の3つです。 まず、遺言者の死亡の記載がある資料として、遺言者が死亡したことが記載されている戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。データ化されている場合には戸籍全部事項証明書という名前になっています。次に、請求している人が請求権者であることを示す書面が必要になります。相続人の場合には戸籍謄本を集めることによって相続人であることを示すことができます。利害関係人については必要な書類が複雑になるので公証役場に問い合わせて決めます。 最後に、請求者本人を確認するための資料として、A:運転免許証かマイナンバーカードと認印B:交付から3カ月以内の印鑑登録証明書と実印、ABのどちらかを持参します。
なお、戸籍謄本については、他の相続手続きにおいても頻繁に使用することから、法定相続情報証明制度を利用して、認証文付きの法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍に代えて提出することが可能です。 戸籍については「相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!」法定相続情報一覧図については「相続手続で使える法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)とは?」こちらで詳しく解説しておりますので参照してください。
まとめ
このページでは遺言書の有無について調べる方法・遺言検索システムについてお伝えしてきました。
本人が急に亡くなってしまったような場合に、遺言書があるかどうかわからない、遺言書があってもどこにあるのかわからないということはよくあります。
貸金庫を調べることや、公証役場での遺言検索システムを利用するなど効率的に調べてみましょう。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 亡くなられた方の生きた軌跡である財産を引き継ぐ相続は様々なトラブルの種になり得ます。「私の家は大丈夫。」と思っていた矢先、小さなほころびから大きなモツレになることもあります。そのような重要な場面においてご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向け尽力致します。
最新の投稿
- 2025.09.05相続放棄・限定承認遺贈の放棄はできるの?期限はあるの?相続放棄との違いは?
- 2025.09.04相続放棄・限定承認遺言書があった場合の相続放棄について確認しよう
- 2025.08.25相続全般独身の方の法定相続人は誰になる?相続割合や独身の方ができる相続対策
- 2025.08.25遺言書作成・執行遺言書を作成する際に関係してくる公証人ってどんな人?