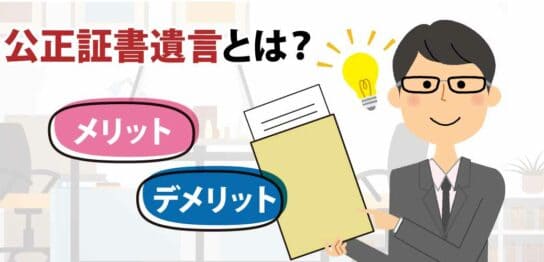- 公証人とは
- 公証人になる人はどのような人か
- 遺言において公証人がどのように関わるのか
【Cross Talk 】公証人ってそもそもどういう人なのでしょうか。
私は亡くなった後のことを考えて遺言書をつくっておこうと思っています。質問なのですが、公正証書遺言を作成する際、公証人という人が作成に関与すると思うのですが、この公証人とはどのような人なのでしょうか。
公証人とは、公証事務という国の公務を行う人です。遺言書においては公正証書遺言を作成したり、秘密証書遺言に関わります。
詳しく教えてください。
公正証書を作成する際、「公証人」という職務をもった人がかかわっていることがわかります。この公証人とはどのような人なのでしょうか。
このページでは公証人とは何か、どのような職務の人なのか、誰がなるのか、遺言書作成でどのように関与するのかについてお伝えいたします。
公証人とは

- 公証事務を担当するのが公証人
- 元裁判官など法律・手続きのエキスパートがなる
公証人ってどのようなことをする人なのですか?
公証事務という国の公務を行います。法律・手続きに関わるものなので、元裁判官や元検察官、元弁護士などの法律と手続きのエキスパートがなります。
公証人について詳しく見てみましょう。
公証人とは
公証人とはどのような職務の人なのでしょうか。公証人は、公証人法(明治41年法律第53号)に規定されている公務員で、公証人法1条により下記のような事務を行う権限を持っています。
- 法律行為や私人間の権利についての公正証書を作成する
- 私署証書に認証を与える
- 会社法30条1項などの規定により定款に認証を与える
- 電磁的記録に認証を与える
公証人になるのは元裁判官や元弁護士
公証人になることができる人については、公証人法12条以下に規定があります。弁護士・裁判官・検事の資格をもっている人は試験をしなくても公証人になることができるとしており、現実には元裁判官が公証人となるケースが多いです。
また、公証人法13条の2において、いわゆる特任公証人を公募して行っており、現実には長年法務に携わったものとして、裁判所・検察事務官・簡易裁判所判事・副検事・司法書士・法人の法務を長期間(簡易裁判所判事と副検事は5年、その他は15年以上)つとめた人は試験を受験することで公証人になることができます。
このように、法律実務に関するスペシャリストが公証人になることができます。
公証役場とは
公証役場とは、公証人が職務を行うための場所で、全国に約300カ所設置されています。公務に関するものなので、市区町村の役場にあるように思えますが、公証役場は独立した場所にあります。
公正証書の作成はこの公証役場で行うのですが、公証人が文書作成の委託者の自宅などに出向いて手続きを行うことも可能となっています。
公証人と証人との違いは
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際に、公証人のほかに「証人」という人が必要となります。遺言書作成における「証人」とは、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際に、立会いが必要となる人です。
証人は公証人のように資格があるわけではなく、証人欠格として証人になれない人(民法974条)以外は誰でも証人になることができます。
公証人と遺言との関係

- 公正証書遺言における公証人の役割
- 秘密証書遺言における公証人の役割
- 公証人に関する証人欠格事由
公証人は遺言書の手続きではどうかかわってくるのでしょうか。
公正証書遺言と秘密証書遺言で関わってきます。
公証人は遺言書作成でどのように関わるのかを確認しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言においては、公正証書として遺言書を作成するので、遺言書の作成過程から、遺言書原本の保管まで公証人・公証役場が深くかかわってきます。まず条文の規定としては、民法969条で、
- 証人2人以上の立会いのもと
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(直接話して伝えること)
- 公証人が口授の内容を筆記
- 遺言者と証人に読み聞かせる
- 筆記の内容が正確であれば、署名捺印を行う
実務上は、
- 事前に遺言者(およびその代理人)と交渉人との間で、どのような遺言をするかの打ち合わせを行う
- 日時を指定して公証役場に遺言者・公証人・証人2名が集まり、公証人と遺言者が遺言内容について質疑応答を行い、問題がなければ本人・証人2名が署名・捺印を行い、最後に公証人が署名・捺印を行う。
- 原本は公証役場で保管し、遺言者には正本と謄本が手渡される
公正証書遺言はその名のとおり遺言書を公正証書で作成するものなので、作成者は公証人ということになります。
なお、本人の健康状態が悪い、足が不自由であるといった場合には公証人に出張してもらうことも可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言を作成する際にも、公証人が関わることになります。秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしつつ、公証人に遺言書の存在のみを証明しもらう遺言書のことです。 実務上、秘密証書遺言は、遺言書をすべて自分で作成したうえで、公証役場で、
- 遺言者が作った遺言書に署名・捺印
- 遺言書に捺印した印鑑で、遺言書を封印(封紙につつんで出せないようにする)
- 公証人と証人2人の前に封書になった遺言書を提出して、自己の遺言書であること・氏名・住所を告げる
- 公証人が遺言書を提出した日時と遺言者が告げた氏名と住所を封紙に記載し、遺言者本人と証人2名も封紙に氏名を記載し印鑑を押す
この場合でも、公証役場に行けないような場合には、公証人に出向いてきてもらうことが可能です。
任意後見契約でも公証人が関係する
なお、遺言書の他に高齢者の法律問題で公証人が関係あるものとして、任意後見制度を利用するためにする任意後見契約があります。任意後見制度を利用するためには、任意後見契約を結ぶ必要があるのですが、任意後見契約を証するための任意後見契約書を公正証書で作成しなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。
そこで、公証人に依頼をする必要があります。
公正証書遺言をする

- 公正証書遺言をするメリット・デメリット
- 公正証書遺言作成の手続きと必要な書類
公正証書遺言を作成するにはどのようにするのですか?
公正証書遺言作成の手続きなどについて確認しましょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言を作成するデメリットとしては、公証人に支払う手数料や、弁護士に支払う費用がかかることです。その一方で、公正証書遺言を作成すると、死後に遺言書の検認が不要になり、その後の相続の手続きがスムーズに進むことが多いです。また、公証人が作成する遺言書なので作成された遺言書への信頼性が高くなり、遺言書の無効を主張される可能性が極めて低くなるなどのメリットがあります。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は、次のような流れで作成します。- 必要書類の収集
- 遺言書案の作成
- 公証人との事前の打ち合わせ
- 公証役場に出頭して公正証書遺言を作成する
また、遺言書案を作成して公証人に送付して、公証人と遺言書の内容について事前に打ち合わせを行います。
遺言書の内容が固まると、公証役場に証人2名と一緒に赴いて公正証書遺言を行います。
公正証書遺言をするのに必要な書類
公正証書遺言をするのに必要な書類としては、- 遺言者の身分証明書
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 財産に関する書類
- 不動産:不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 預貯金の残高が分かる書類(通帳の写し)
- 株式に関する書類(取引状況報告書の写しなど)
秘密証書遺言をする

- 秘密証書遺言をするメリット・デメリット
- 秘密証書遺言の手続き
もう一つの秘密証書遺言はどのように行いますか?
秘密証書遺言の行い方を確認しましょう。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言は、公正証書遺言ほどではないですが費用がかかることと、遺言書の内容を公証人が確認するわけではないので形式に不備を生じると無効となる可能性がある、遺言書の検認が必要というデメリットがあります。一方で、証人にも内容を知られずに秘密にしておくことができる、パソコン・ワープロで作成が可能などのメリットがあります。
秘密証書遺言の作成手続き
秘密証書遺言は、次のようなステップで行います。- 遺言書の内容を作成する
- 遺言書に署名し印鑑を押す
- 遺言書に押した印鑑を綴じ目に押して封印を行う
- 証人2名以上と公証人に対して封書を提出して、公証人が日付・遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者・証人が署名を行って印鑑を押す。
秘密証書遺言の作成に必要な書類
秘密証書遺言の作成をするときには、公証人は内容について確認するわけではないので、本人および証人の身分証明書のみが必要です。まとめ
このページでは公証人とはどのような人なのか、などについてお伝えしてきました。
公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場で手続きを行う遺言書では、必ず関与することになります。
疑問がある場合には早めに弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
- 第二東京弁護士会
- 亡くなられた方の生きた軌跡である財産を引き継ぐ相続は様々なトラブルの種になり得ます。「私の家は大丈夫。」と思っていた矢先、小さなほころびから大きなモツレになることもあります。そのような重要な場面においてご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向け尽力致します。
最新の投稿
- 2025.09.05相続放棄・限定承認遺贈の放棄はできるの?期限はあるの?相続放棄との違いは?
- 2025.09.04相続放棄・限定承認遺言書があった場合の相続放棄について確認しよう
- 2025.08.25相続全般独身の方の法定相続人は誰になる?相続割合や独身の方ができる相続対策
- 2025.08.25遺言書作成・執行遺言書を作成する際に関係してくる公証人ってどんな人?