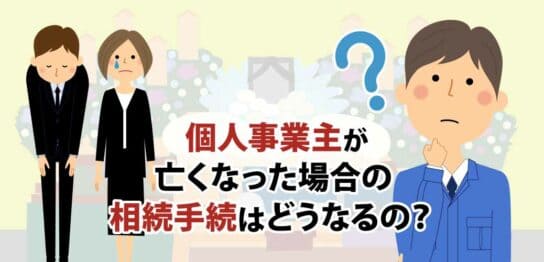「死んだらこの家はお前にやるよ」
「財産は全部任せるからな」
被相続人の生前に、このような言葉をかけられた経験がある方もいるのではないでしょうか。
しかし、こうした“口約束”は、法的には相続の根拠とはならず、遺産分割をめぐるトラブルの火種になることも少なくありません。
相続は、感情や信頼関係が絡むデリケートな問題だからこそ、明確な証拠や手続きが不可欠です。
本記事では、相続において口約束が問題になるケースや、トラブルを防ぐ方法を詳しく解説します。

- 口約束も法的には有効
- 法的に有効であっても証拠がないと
- トラブルを避けるためにきちんとした書面を作成することが重要
相続対策として生前贈与の口約束をされていた場合はどうなる?
相続対策として親から口約束で生前贈与を受けることになっていたものの、贈与を受ける前に親が亡くなってしまった場合、この生前贈与はどうなるのでしょうか。 以下では、生前贈与における口約束の効力や、トラブルを防ぐ方法について解説します。
口約束での生前贈与は法的にどのように扱われる?
民法では、贈与について次のように定めています。つまり、贈与は当事者の合意が成立することで効力を生じるのであり、書面の作成など特別な要式は必要ありません。 したがって、口約束であっても生前贈与は効力を生じることになります。 ただし、ここで注意が必要なのは、「当事者の合意が成立したことが認められれば」効力が発生するということです。
そして、相続の際に他の相続人が口約束での生前贈与を認めない旨を主張してきた場合は、贈与の効力の発生を主張する者、つまり受贈者が、当事者間で合意が成立したことを証明しなければなりません。
しかし、口約束での生前贈与を証明することは難しいのが通常です。
贈与者が亡くなっている場合、贈与者に事情を確認することができないため、受贈者が「約束した」という以外に証拠がなく、証明は非常に困難でしょう。
そうなると、口約束で生前贈与をしていたことが事実だとしても、生前贈与の効力が認められない可能性があります。
また、契約書がない贈与については、以下のように民法で履行前の解除が認められています。
つまり、いったん口約束で生前贈与をしたとしても、贈与者は履行前であればいつでも贈与を解除することができるのです。
また、贈与者が履行前に死亡した場合、相続人は贈与者の地位をそのまま引き継ぐことになるので、履行前であれば相続人は生前贈与を解除することができます。
口約束での生前贈与による相続トラブルを防ぐ方法
「口約束で生前贈与を受けることが決まっていたのに、相続の際に他の相続人に認めてもらえない」という事態を回避するためには、生前贈与の際に贈与契約書を作成するのが一番です。
贈与契約書は、贈与の合意があったことの有力な証拠になるため後々になって生前贈与の効力が認められないという事態を避けられるでしょう。
ただし、贈与契約書を作成したとしても、他の相続人から「贈与者本人が作成した契約書ではない」などと主張される可能性はゼロではありません。
そこで、贈与契約書には実印を押印し、印鑑証明書を添付するようにしましょう。これにより、贈与契約書の証拠としての価値をより高めることができます。
後々トラブルになるリスクを考えれば、費用をかけてでも公正証書で贈与契約書を作成するということも考えられるでしょう。
また、贈与契約書を作成することには、贈与の証拠になること以外にもう一つのメリットがあります。贈与契約書を作成すれば、その贈与は「書面による贈与」となります。
民法550条の反対解釈から、書面による贈与は、履行前であっても各当事者が一方的に解除をすることはできないため、生前贈与が認められやすくなるでしょう。
「遺産をあげる」という口約束は遺言になる?
生前贈与とは別で「遺産をあげる」など、相続に関する口約束をしている場合も考えられます。
この場合の口約束は法的にどのように扱われるのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
遺言書として有効か?
相続に関する口約束については、それだけで遺言として扱われる可能性は低いといえます。 なぜなら、遺言は要式行為といって法律に規定されている形式で作成される必要があるためです。一般的な用語として、生前の言葉のことを「遺言」と表現することがありますが、民法の定める形式での遺言でない場合は、遺産に関する権利を取得する効果は発生しません。 当事者で口約束をしただけで、遺言として成立する可能性があるとすると、船舶遭難者の遺言のみで、その要件は非常に限定されています。 この方式の遺言以外はいずれも遺言書を作成する必要があるので、通常の口約束が遺言として成立する可能性は極めて低いでしょう。
死因贈与契約として有効か?
次に、「遺産をあげる」という口約束が、死後に財産を贈与する死因贈与契約にあたるかどうかも検討してみましょう。 しかし、死因贈与の場合も生前贈与と同じく、契約の存在・内容を証明できない点や、当事者が契約を解除できるという点で、同様のトラブルが発生するおそれがあるでしょう。「遺産をあげる」という口約束を実現するための方法
「遺産をあげる」という口約束を実現するためには、以下3つの方法が有効です。・遺言書を作成する
・急いで生前贈与をしてしまう
・死因贈与契約書を作成しておく
特に、相続人以外の人の場合、遺産に関する口約束を証明できないと特別寄与料の請求・特別縁故者になること以外に方法がないので、必ず何らかの対策を行っておくのが望ましいでしょう。
【ケース別】口約束を実現するための方法
以下のような場合では口約束を実現するにはどうすればよいのでしょうか。・時間がないような場合
・耳が聞こえない・口がきけない・文字が書けないような場合
それぞれのケースにおける対処法について、詳しく解説します。
時間がないような場合
遺言を遺したい人が危篤状態にあるなど、時間がないような場合には、民法976条に規定されている、死亡危急時遺言という方式を利用することが可能です。死亡危急時遺言とは、死亡の危急に迫っている人が行う遺言で、証人3人の立会いにより行われます。
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
引用元:民法|e-GOV法令検索
死亡危急時遺言を作成する際は、以下の要件を満たさなければなりません。
・証人3人が立会う
・遺言者が証人の1人に口授をする
・口授を受けた証人がこれを筆記して遺言者と証人に読み聞かせる、もしくは閲覧させる
・筆記が正確であることを承認して署名・押印する
・遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受ける
また、死亡危急時遺言については、家庭裁判所は遺言者が真意から作成したものであるという心証を得られなければ確認することができません。
なお、遺言者が死亡の危急にあるような場合であっても、公証人が病院まで出張することで公正証書遺言を作成できるケースもあるので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
耳が聞こえない・口がきけない・文字が書けないような場合
耳が聞こえない場合でも、公証人や証人に口授ができ、作成者が遺言書を閲覧したうえで記名・押印ができれば、公正証書遺言・死亡危急時遺言の作成は可能です。 また、自書できれば自筆証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。 死因贈与契約も同様に、意思疎通ができれば問題なく行うことが可能です。口がきけない場合には、公正証書遺言や死亡危急時遺言の「口授」ができないことになりますが、手話などの通訳を用いるほか、自書によって対応することができます。
文字が書けない場合には自筆証書遺言における「自書」ができないことになりますが、自書ができなくても公正証書遺言などを利用することは可能です。
遺産分割協議で口約束をした
生前贈与や遺言のほか、遺産分割協議での口約束についても相続の際に問題になりやすい傾向があります。
ここでは、遺産分割において口約束が問題になるケースや、トラブルを防ぐための対象法を解説します。
遺産分割において口約束の効力が問題になるケース
遺産分割において口約束が問題になるケースとしては、例えば父が亡くなった場合、長男が母の面倒を見ることを約束して、長女が遺産を少なめに相続するという状況が考えられます。
このような場合で、長男が口約束を破って母の面倒を見ようとしないとき、「母の面倒を見る」という口約束はどうなるのかが問題となるのです。
遺産分割協議書には条件についても記載することが大切
遺産分割においても生前贈与の場合と同様に、口約束だけでは相手方から「そんな約束はしていない」と言われてしまい、証拠が不十分ために約束をした事実が認められない可能性があります。
そのような事態を避けるには、書面を作成しておくことが重要です。
遺産分割協議が成立した場合は、相続人全員が署名のうえで実印を押印し、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
そこで、この遺産分割協議書に「母の面倒を見る」などの条件を記載するとよいでしょう。
これにより、遺産分割の条件を証拠として残すことができます。
なお、遺産分割の条件を遺産分割協議書に記載したにもかかわらず、その条件が満たされない場合、他の相続人は義務の履行を求めるよりも遺産分割をやり直したいと考えるかもしれません。
上記のケースでいえば、約束を守らない長男には母を任せられない、自分が母の面倒を見る代わりに長男が少なめに相続することにしたい、と長女が考えたとしても無理はないでしょう。
しかし、最高裁では、遺産分割協議のやり直しについて「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」との判断を示しています(最判平成元・2・9民集43巻2号1頁)。
その理由について、最高裁は「遺産分割はその性質上、協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。」と説明しています。
さいごに|相続では口約束は避け、書面を作成しよう
本記事では、相続についての口約束によるトラブルとそれを避けるための対処法を解説しました。
相続において、口約束が原因のトラブルを避けるには、適切な書面の作成が不可欠です。
しかし、どのように書面を作成すべきかわからないという方も多いでしょう。
書面を作成しても、内容が不十分であっために結局トラブルになってしまったのでは意味がありません。
そのような事態を避けるには、事前に相続について詳しい弁護士へ相談し、書面の作成についてアドバイスしてもらうのがおすすめです。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺産分割協議相続財産?遺産分割財産?この2つの違いについて解説!
- 2025.09.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2024.05.23相続全般相続法が改正された!いつから?今までと何が変わった?
- 2024.05.23相続全般相続人代表者指定届とは?その効力は?書き方も併せて解説