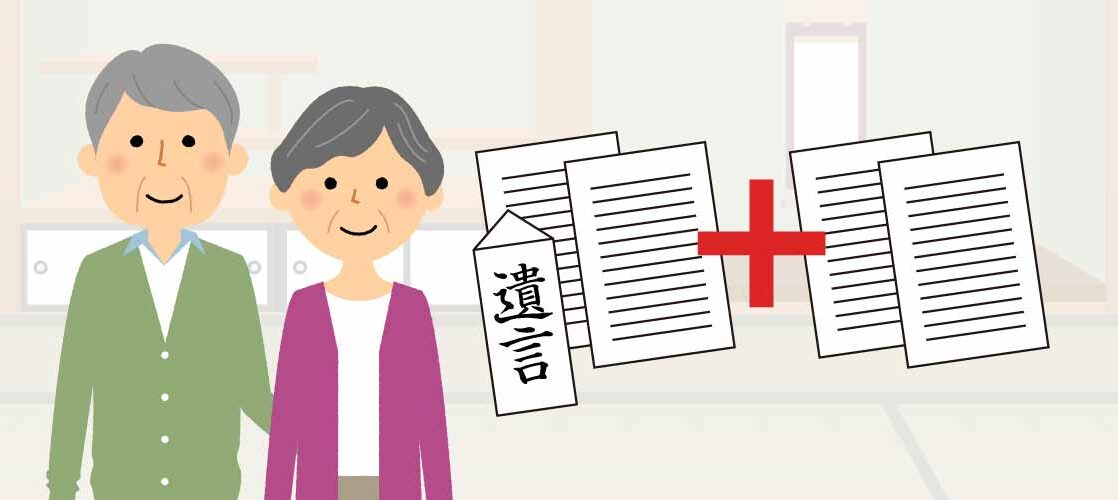- 遺言書と一緒にメッセージを残す方法として、付言事項やエンディングノートがある
- 相続の内容によっては相続人がもめないようにメッセージを残しておくべき
- メッセージを残すべき場合として、やむを得ず遺留分を侵害する場合などがある
【Cross Talk 】遺言書と一緒にメッセージを残したい場合は、どんな方法があるの?
遺言書を作成したのですが、なぜこのような遺言内容にしたのかをメッセージとして残したいと思います。相続人などにメッセージを残すには、どのような方法がありますか?
相続人などにメッセージを残す方法としては、遺言書の付言事項やエンディングノートなどがあります。
メッセージを残す方法がいくつかあるんですね。それぞれの方法について教えてください!
相続人などに普段言えなかったことを伝えたり、なぜこのような遺言書を作成したかなどを説明したりするには、遺言書と一緒にメッセージを残す方法が有効です。 相続人などにメッセージを残す方法としては、付言事項やエンディングノートなどがあります。 そこで今回は、遺言書と一緒に相続人にメッセージを残す方法について解説いたします。
遺言書と一緒にメッセージを残す方法

- 遺言書と一緒にメッセージを残す方法として、付言事項やエンディングノートがある
- 付言事項は遺言書のうち法的な効力がない部分であり、エンディングノートは死後に備えて記載するノートである
遺産について遺言書を作成するだけでなく、相続人たちにメッセージを残したいのですが、どのような方法がありますか?
遺言書と一緒にメッセージを残す方法として、遺言書の付言事項やエンディングノートを活用する方法があります。
遺言書の付言事項に記載する
遺言書と一緒にメッセージを残す方法として、遺言書の付言事項に記載する方法があります。 遺言書の付言事項とは、遺言書に記載された事項のうち、法的な効力のないもののことです。 遺言書に記載される事項には、法的な効力のある法定遺言事項(相続分の指定や相続人の排除など)と、法的な効力のない付言事項があります。付言事項は法的な効力はありませんが、相続人や遺族にあてたメッセージや、遺言書を作成した経緯などを記載することができます。
遺言書とは別にエンディングノートを用意する
相続人にメッセージを残す方法として、エンディングノートに記載する方法があります。 エンディングノートとは、自分の死後に備えて伝えたいことを記載するためのノートです。 遺族や友人に普段言えなかったことをメッセージとして記載したり、自分の死後にどのような葬儀をしてほしいかを指定したりなどの用途で使用されます。 遺言書の付言事項と同じように、エンディングノートには法的な拘束力はありませんが、どのようなことを記載するかは自由です。 付言事項とエンディングノートの違いは、付言事項は自分の死後について記載することが多いのに対し、エンディングノートは介護の方法など生前の事項についても記載することが多い点にあります。付言事項・エンディングノートによく記載される事項
付言事項やエンディングノートによく記載される事項として、以下のものがあります。- 相続人や遺族への感謝の気持ち
- 相続人や遺族に普段言えなかったことを伝える
- 自分の死後にどのように生活してほしいか(兄弟みんなで仲良くするなど)
- 遺言書を作成した経緯(なぜそのような遺言内容にしたのか)
- 財産以外の指定事項(葬儀の方法や臓器提供など)
遺言書とともにメッセージを残したほうがいい場合

- 相続の内容によっては、相続人がもめないようにメッセージを残しておくべき
- やむを得ず遺留分を侵害する場合や、相続財産以外のものを取得する場合などがある
遺言書を作成したのですが、不満を感じる相続人がいないか心配です。なにか対策はありますか?
不満を感じる相続人がでてくる可能性がある場合は、相続の理由について、付言事項やエンディングノートなどでメッセージとして説明するのがおすすめです。
相続するものに不満がある相続人がいる可能性がある
相続するものに不満がある相続人がいる可能性がある場合は、付言事項やエンディングノートなどを用いて、メッセージを残す方法がおすすめです。 相続の内容によっては、遺言書を作成するだけでは、相続人の間でもめてトラブルになりやすい場合があります。 なぜそのような相続をさせるかについて、付言事項やエンディングノートにメッセージを残して説明しておけば、相続人が納得しやすくなることが期待できます。 相続内容に不満がでる可能性が高い遺言書を作成する場合は、付言事項やエンディングノートを使ってメッセージを残しておくとよいでしょう。例えば、相続人として長男と長女の2人がいる場合に、長男のほうに多く相続させる場合などです(遺産の総額が1,000万円の場合に、長男が600万円、長女が400万円とするなど)。
相続の理由についてきちんと説明しておかなかった場合、自分の相続分が不当に少ないと感じた長女が長男に文句を言って、相続トラブルになってしまう可能性があります。 付言事項やエンディングノートを活用して、なぜそのような相続をさせるかをきちんと説明しておけば、相続分の少ない相続人が納得して、相続がスムーズに進む可能性が高くなることが期待できます。 例えば、「長男は生前に自分の面倒をよく見てくれたし、実家の家業を継がなければならないので、今までの感謝とこれからの苦労を考えて、長男の相続分を多くしました」とメッセージをしておくなどです。やむをえず遺留分を侵害する遺言書を作成する場合
遺留分を侵害するような遺言書を作成する場合も、付言事項やエンディングノートでメッセージを残しておいたほうが良いでしょう。遺留分とは、一定の法定相続人に法律で権利が認められている、遺産の最低限の取り分のことです。 遺留分を侵害された相続人は、侵害された分に相当する金額を相手に請求することができます。
例えば、遺産の総額が1,000万円であり、長男と長女の2人が相続人の場合で考えてみましょう。 上記の場合においては、長男と長女はそれぞれ250万円の遺留分の権利があります。もし「長男に遺産の全てを相続させる」という遺言書を作成して、長男が1,000万円全てを相続した場合、長女は自分の遺留である250万円を侵害されています。 この場合、長女は長男に対して、自身の遺留分が侵害されたとして、自分の遺留分である250万円分の金銭を支払うように請求できるのです。
やむをえず遺留分を侵害するような遺言書を作成する場合は、きちんとメッセージを残しておかないと、遺留分請求をめぐってトラブルになる可能性が高いです。 そこで、「長男は家業を継いでもらうので、そのために私の遺産をすべて長男に相続させることにしました。どうか理解してあげてください」などとメッセージを残すことで、遺留分を侵害された長女も納得でき、遺留分侵害額の請求をせずに終わりやすくなる可能性があります。相続財産以外のものを取得する相続人がいる場合
生命保険金など、相続財産以外のものを取得する相続人がいる場合は、メッセージを残しておくとよいでしょう。 例えば、生命保険金は契約内容によっては、相続の対象である相続財産ではなく、受取人の固有の財産に該当する場合があります。 相続財産以外を取得する相続人がいる場合、なぜ預貯金や不動産などの相続財産を相続できないのだろうかと、相続人が不満に感じてトラブルになる可能性があるので注意しましょう。 付言事項やエンディングノートを活用して、なぜ相続財産以外のものを取得させるのかを説明しておけば、相続トラブルの防止につながりやすくなります。まとめ
遺言書と一緒に相続人などにメッセージを残す方法としては、付言事項やエンディングノートがあります。 付言事項やエンディングノートには法的な拘束力はありませんが、伝えたいことや依頼したいことなど、基本的に自由に記載することができます。 遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成する場合など、いくつかの相続の場合においては、メッセージによってきちんと説明しておくことが重要です。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.02.13相続全般不動産(土地)の生前贈与とは?手続きや発生する費用、メリット・デメリット
- 2025.09.22相続全般相続した不動産は共有にすべき?メリット・デメリットと注意点を解説
- 2025.09.19相続税申告・対策弔慰金は相続税ではどのように評価するか解説
- 2025.09.05相続手続き代行遺産分割協議後に新たな財産が発覚!この場合どうすればいいの?