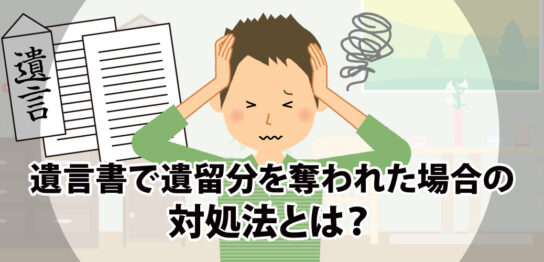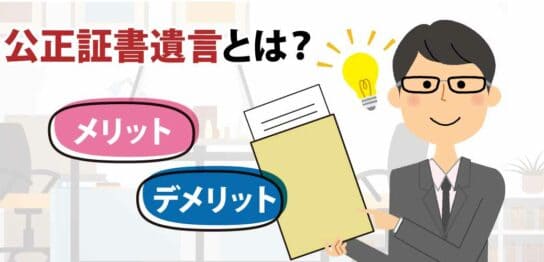はじめに
どちらも大切な財産をスムーズに引き継ぐための方法ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、状況によってどちらを選ぶべきかが変わります。
そこで本記事では、遺言と生前贈与の違いや活用場面、選ぶ際の注意点についてわかりやすく解説し、自分に合った相続対策のヒントをお届けします。
遺言とは?種類ごとのメリット・デメリットについて
遺言とは、広い言葉の意味では「自分の死後のためのメッセージ」を指しますが、法律上は「人の財産についての最終意思表示のこと」をいいます。
遺言書がない場合、相続は民法の規定に従って行われることになります。
しかし、相続人が複数いる場合には、誰が何を相続するかを話し合う「遺産分割協議」が必要となり、意見の対立からトラブルに発展することも少なくありません。
こうした相続争いを未然に防ぐためには、あらかじめ遺言書で自身の財産の分け方を明確にしておくことが、生前の有効な相続対策となります。
例えば、「実家の不動産をめぐって兄弟間で争いが起こりそうだ」と予想される場合、遺言で「家は兄に相続させ、弟には預金を相続させる」と記しておくことで、トラブルを回避し、家族関係の悪化を防ぐ効果が期待できます。
遺言の種類
遺言には3つの種類があり、それぞれでメリット・デメリットが異なります。
それぞれの違いについて、以下でチェックしておきましょう。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・全文を自費して作成するため、気軽かつ誰にも知られずに作成できる | ・様式を間違えると無効になりやすい |
| 公正証書遺言 | ・公証役場で公証人が作成をするため、無効になることがめったにない ・遺言の検認が不要 |
・作成に費用がかかる |
| 秘密証書遺言 | ・遺言の内容を誰にも知られずに作成できる | ・証人が2人必要 ・作成に費用がかかる ・遺言が発見されないリスクがある |
それぞれ詳細は「3種類の遺言について」でも紹介しているので、あわせて参考にしてください。
生前贈与とは?メリット・デメリットや具体的なやり方について
生前贈与とは、相続が発生する前にあらかじめ財産を贈与することをいいます。
法律的には「贈与契約」にあたるもので、相続に関連する用語としては「死因贈与死亡時に効力が生じる贈与契約)」と区別する意味で「生前」と表現されています。
相続によって財産を引き継げるのは相続人に限られるため、孫に進学資金を直接渡したい、長男の妻に感謝の気持ちを込めて財産を渡したいといった希望は、相続では原則として叶えられません。
もちろん、遺言によって遺贈することも可能ですが、その効果は死亡後にしか発生しません。
その点、生前贈与であれば生きているうちに確実に財産を移転できるというメリットがあります。
また、生前贈与は相続税対策としても有効です。
相続税は、亡くなった時点での財産が基礎控除額を超える場合に課税されますが、資産が多いほど税負担も大きくなります。
そこで、あらかじめ生前贈与で資産を移しておくことで、相続時の課税対象を減らすことができ、結果として相続税の軽減が期待できるのです。
ただし、生前贈与には注意点もあります。
仮に亡くなる直前に全財産を贈与した場合、確かに相続財産はゼロになりますが、税逃れを防ぐために「贈与税」が課される仕組みになっており、単純に相続税を回避することはできません。
つまり、生前贈与を相続対策に活用するには、計画的かつ、贈与税と相続税のバランスを見極めながら行うことが重要です。
税務上のトラブルを避けるためにも、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
生前贈与のやり方
生前贈与は、基本的に「贈与契約」として行われます。
法律上は、「あげます」や「もらいます」という双方の意思が合致すれば、それだけで贈与契約は成立します。
しかし、口約束だけで贈与を済ませてしまうと、あとになって「本当に贈与されたのか?」と税務署などから疑問をもたれる可能性があります。
実際に税務調査が入った際、証拠がないと正当な贈与として認められず、贈与税が発生したり、相続財産として扱われてしまったりするおそれもあるでしょう。
そのため、生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことが非常に重要です。
契約書には、贈与する財産の内容や金額、日付、双方の署名・押印などを記載し、必要に応じて公証役場で確定日付をとっておくと、より信頼性が高まります。
遺言か生前贈与はどちらを利用するのがよい?
ここまで、遺言と生前贈与について、それぞれのメリット・デメリットなどを解説しました。
では、実際に相続対策をするとなった場合、生前贈与と遺言はどちらを利用するのがよいのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
どちらがよいかというものではなく遺産の性質によって組み合わせて利用する
結論からお伝えすると、遺言と生前贈与は「どちらが優れているか」を選ぶものではなく、それぞれの特徴を活かして上手に組み合わせて活用するのがおすすめです。
遺産の内容や構成(不動産・現金・株式など)、相続人の状況、そして被相続人や相続人の希望によって、最適な相続対策は大きく異なります。
例えば、不動産のように分けにくい資産がある場合は遺言で明確に分配先を指定し、現金などは生前贈与で早めに渡しておくなど、目的に応じて手法を使い分けることで、相続トラブルや税負担を最小限に抑えられるでしょう。
専門家に相談しながら行うのがよい
資産内容が複雑だったり、相続税がかかったりするような場合は、遺言や生前贈与について専門家に相談しながら進めるのが安心です。
例えば、生前贈与は贈与税の課税対象となるため、贈与のタイミングや金額、贈与先によっては思わぬ税負担が生じることがあります。
さらに、生前贈与を行った結果、相続時に本来受けられるはずだった相続税の特例が使えなくなってしまうおそれもあるため、注意が必要です。
よくある例としては、配偶者に対する居住用不動産の生前贈与です。
この場合、一見すると税負担が軽くなるように思えますが、実は相続時に使える「小規模宅地等の特例(最大80%評価減)」が使えなくなってしまうことで、かえって相続税が高くなるといった逆効果も起こり得ます。
そのため、遺言を作成する場合も、生前贈与を検討する場合も、相続に詳しい弁護士や税理士と相談しながら計画的に進めることが大切です。
正確な法的知識と税務知識をもとに、自身の状況に合った最善の対策を見つけましょう。
まとめ
本記事では、遺言と生前贈与の基本的な特徴をおさらいしながら、それぞれのメリット・注意点について解説してきました。
結論としては、「遺言と生前贈与のどちらがよい」という単純な話ではなく、相続の目的や状況に応じて、うまく組み合わせて活用することが大事です。
ただし、適切に活用するためには法律や税金に関する専門知識が欠かせません。
誤った判断を避けるためにも、相続の経験が豊富な弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、将来のトラブルを防ぎ、納得のいく相続対策が実現できるでしょう。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺言書作成・執行遺言書を見つけた場合にどうやって開ければいい?うっかり開けてしまった場合の対象法など
- 2025.10.29相続全般相続した土地(不動産)を売却したい場合の手続について解説!
- 2025.09.22相続手続き代行遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能?
- 2025.09.19遺留分侵害請求遺留分侵害額請求権を行使する際には内容証明を利用する