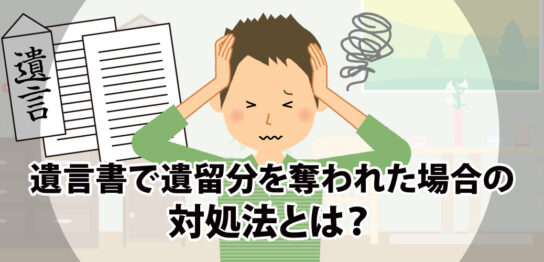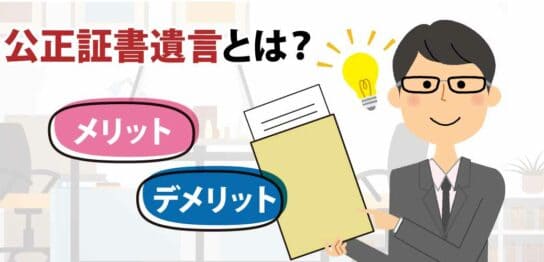- 自筆証書遺言とはどういうものか
- 自筆証書遺言にはどんなメリット・デメリットがあるか
- 自筆証書遺言の書き方
【Cross Talk】自筆証書遺言とはどんなものか
遺言として自筆証書遺言の作成を考えています。自筆証書遺言について詳しく教えてください。
自筆証書遺言は、記載内容を誰にも知られずに作成できるというメリットはあります。その一方で、法律に定められた方式を間違ってしまうと遺言が無効になることもあるため、注意が必要です。そのほかにも留意点がありますので、自筆証書遺言について詳しくみていきましょう。
遺言は、法律に定められた方法によって行われなければなりません。 その方法の一つとして自筆証書遺言があります。特に手続きを必要とするわけではないため手軽に作成できるのですが、その分法律の規定に沿わない形で作成してしまって、無効となってしまうことも多いのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは?

- 遺言とはどのようなものか
- 自筆証書遺言とはどのようなものか
そもそも遺言や自筆証書遺言とは、どのようなものなのでしょうか。
遺言は被相続人の意思表示をするものです。民法の規定に沿った遺言をすることで、相続財産を誰に分けるか、相続分をどうするか、といった事を決められます。自筆証書遺言は、その遺言を残す方法のひとつです。
まず、遺言とは何か、自筆証書遺言とはどのようなものかを確認しましょう。
遺言とは?
遺言とは、一般的に自身の死後に残すメッセージのことを指し、遺産処分や相続に関する意思表示を行うものです。 相続というと、相続人が民法で決められた割合に従って行うのが基本ですが、遺言することによって被相続人が自由に遺産配分や割合を決めることができます。 遺言は民法に従った形で行ってはじめて効力を有するものになります。自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、民法が定めている遺言の方式の一つで、基本的には全文を直接自書して記載する方法で行うものです。 従来は全文を自書しなければならなかったのですが、法令が改正され、財産目録についてのみ、自書に限らずパソコンで作成したものも有効とされました(2019年1月13日施行)。 さらに2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービス(自筆証書遺言書保管制度)が開始しました。自筆証書遺言書に記載することは?

- 自筆証書遺言書に記載すること
自筆証書遺言書に記載する内容としてはどのようなものがありますか?
自筆証書遺言書に記載する内容について確認しましょう。
まず、遺言とは何か、自筆証書遺言とはどのようなものかを確認しましょう。
遺贈
遺贈をする場合には遺贈について記載します。
遺言書によって自分の財産を譲り渡す行為のことを遺贈といい、遺言書中に記載することで、効力が生じます。
相続人以外にも財産を譲り渡したい場合には、遺贈によって行うことになります。
遺贈の記載については特定の財産の遺贈である特定遺贈と、遺産に対する割合を示して行う包括遺贈がありますので、考えている方法に応じて記載をします。
なお、全部の財産についての遺贈を記載しておかないと、遺言書に記載されなかった財産については相続人が遺産分割をする必要があるので注意しましょう。
記載をする場合には、誰に何を遺贈するかを明確に記載し、「○○にあとを託す」といった曖昧な記載は無効となる可能性があります。
相続分の指定
相続分の指定をする場合には、相続分の指定について記載します。
遺言がなければ法定相続分で遺産分割することになるのですが、希望する分割割合がある場合にはその旨を指定します。
分割割合を直接定める方法のほかに、相続分の指定を第三者に委託することも可能です(民法902条)。
遺産分割の指定・遺産分割の禁止
どの財産をどの相続人に相続させるかを指定したい場合には、遺産分割の指定を行います。
また、遺産分割を禁止する旨の記載をした場合、最大5年間遺産分割を禁止することを規定することができます。
未成年者がいる場合に成年になってから遺産分割をしてほしい、冷却期間を置きたいなどの希望がある場合に記載されることがあります。
推定相続人の廃除
被相続人に対して虐待した・重大な侮辱を加えたなど、推定相続人にその他の著しい非行があったときには、推定相続人の廃除の請求をすることができます。
推定相続人の廃除は、遺言で記載して行うことが可能です。
推定相続人の廃除は家庭裁判所に請求して行いますが、遺言で行う場合には遺言執行者が家庭裁判所に請求を行います(民法893条)。
なお、推定相続人の廃除は非常にハードルが高いため、どうしても確実に行いたいのであれば、生前に家庭裁判所に申立てをして行うことをおすすめします。
特別受益の持ち戻しの免除
民法903条1項の規定に従って、生前贈与・遺贈などの特別受益がある相続人について、特別受益を相続財産に加算して遺産の計算を行うのが特別受益の持ち戻しです。
そして、同3項で被相続人が特別受益の持ち戻しを行わない意思表示をすれば、特別受益の持ち戻しは免除されることが規定されています。
この意思表示をする手段として、遺言が用いられるので、特別受益の持ち戻しの免除をしたい場合には、遺言書に記載します。
保険金受取人の変更
保険金受取人の変更をしたい場合には、遺言書に記載します。
生命保険金の受け取る権利を有する受取人は、遺言によって変更することができる旨が規定されています(保険法44条1項)。
亡くなった後に保険金受取人の変更をしたい場合には、遺言書に記載します。
なお、遺言による保険金受取人の変更は、保険会社に通知をしなければ、遺言で保険金受取人が変更されていることを保険会社に主張できないとされています(保険法44条2項)。
つまり、従来の保険金受取人が保険金を受け取る前に、変更後の保険金受取人が遺言書を示す必要があるのです。そのため、遺言書に保険金の受取人変更の記載があった場合、すぐ保険会社に連絡したほうが良いでしょう。
遺言執行者の指定
遺言執行者の指定をする場合には、遺言書に記載し、遺言の内容を実現する方が遺言執行者です。
遺言執行者を指定、および指定を第三者に委託する場合には、遺言で行う旨が規定されています(民法1006条)。
祭祀承継者の指定
祭祀承継者を指定する場合には、遺言書に記載します。
民法897条は、祭祀承継者について、被相続人が指定できる旨を規定しており、指定をする場合に遺言書に記載をします。
祭祀とは、神や先祖を祀ることをいい、祭祀承継者は墓や仏壇などの祭祀財産を承継することになります。
絶対に相続人を指定しなければならないというわけではありません。
信託の指定
遺産を信託財産とする場合に、受託者の指定は遺言で行います。
財産を預けて運用してもらう契約のことを信託契約といい、遺産を預けて管理・運用してもらって相続人に受益をさせる方法があります。
遺言で遺産を信託財産とする場合、受託者の指定も遺言で行います。
認知
遺言で子の認知をする場合、遺言書に記載します。
子の認知とは、法律上婚姻関係のない状態で生まれた子について、自分の子であると認める行為をいいます。
法律上の婚姻関係にない子との間に親子関係を発生させるためには認知が必要で、その認知について民法781条2項は、遺言で行える旨が規定されています。
未成年後見人の指定
未成年後見人の指定を行う場合、遺言書に記載します。
未成年後見人とは、親権者がいないなどの場合に、未成年者の法定代理人として未成年者の財産管理や身上監護を行う人のことをいいます。
親権者が亡くなってしまった場合や、親権を喪失するなどした場合に、親権者に代わって未成年後見人が選任され、未成年者の財産管理や身上監護を行います。
最後に親権者になる方は、未成年後見人となる方を遺言で指定できるとされており(民法839条1項)、この指定を行うために遺言書に記載します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット

- 自筆証書遺言のメリット
- 自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言を残すことにはどんなメリット、デメリットがありますか?
手続きが不要なため一人で気軽に作成できるというメリットがある一方、民法の定める規定に沿っていない場合には無効になってしまうというデメリットがあります。
自筆証書遺言にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言にはどのようなメリットがあるのでしょうか。 まず、自筆証書遺言は、他の方式のように公証人を利用するようなものではありません。そのため、気軽に作成できることがメリットのひとつです。また、一度書いた遺言の内容を変更したい場合にも、変更手続きなどが不要なため、容易に訂正することができます。 ほかにも、他の方式が要求するような公証役場での手続きや証人を必要としないため、遺言したことやその内容を秘密にすることができます。 公証役場を利用しないので、その分の費用を抑えられるというのもメリットとして挙げられるでしょう。自筆証書遺言のデメリット
一方で自筆証遺言には次のようなデメリットもあります。 まず、誰にも知られずに自由に作成することができるので、民法に規定された要件に沿っていない場合には、遺言が無効になるということが挙げられます。 また、内容以前に遺言の存在自体、自分の死後に見つけてもらえないおそれもあります。 さらに、自筆証書遺言は、死後に遺言書が見つかった時点で遺言書の検認という手続きを経る必要があります。 検認には時間がかかるので、検認が不要な公正証書遺言に比べて手続きがスムーズにいかないというデメリットもあります。自筆証書遺言の書き方

- 自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言はどのように書くのですか?
基本的な自筆証書遺言の書き方について確認しましょう。
自筆証書遺言はどのように書くのでしょうか。法律で必要とされている事項についてお伝えします。
日付を必ず入れる
自筆証書遺言には、記載した日付を必ず入れます。 この日付は正確なものにするべきで、かなり昔の事ですが「◯月吉日」としたものが無効とされたことがあります。その他「◯才の誕生日に」など、一見わかるようなものでも、後に争いの種とならないように、きちんと日付を記載するようにしましょう。署名
自筆証書遺言には署名をする必要があります。当然ですが本人の名前を記載します。 芸能や執筆の仕事をしているなどで、本名以外の名前を持っている場合でも、かならず戸籍上の本名を記載します。 どうしても芸名などを記載したいという場合には「本名(芸名)」あるいは「芸名こと本名」と本名と芸名の違いがわかる記載をするのが良いでしょう。 芸名でも本人であると特定されれば効力が認められる判例がありますが、争いの種になりかねないので注意が必要です。押印
書面に押印をします。どの印鑑を使うべきかについて規定はされていないので、極端な話三文判でもよいのですが、固有の印影でないため被相続人以外が押印したのではないか?という争いの種になる可能性もあります。なので、できれば実印を利用するのがよいでしょう。割印
ページとページのつなぎ目、両方のページにまたがって押印することを割印といいます。 特に法律上定められているものではありませんが、これがあることによってそれぞれのページが連続して作られているという事がわかりますので、偽造されたものではない、という事を証明できます。財産目録
先ほど、パソコンで作って良いものとして財産目録があるという事をお伝えしました。 対象になるような資産が多い場合には、財産目録を作成した上で、その財産目録にあるものは誰に渡しますという記載が必要となります。 なお、財産目録を自書しない場合、目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名と押印が必要です。相続に関する指定する
相続財産を誰に受け継がせるか決まっている場合には、対象になる財産と相続人を指定します。預金口座と不動産の例について見てみましょう。預金口座の時には次のように記載します。
不動産の場合には次のように記載します。
この不動産の情報については、不動産登記事項証明書に記載されている内容を正確に記載します。
祭祀に関する事項
祭祀とは家にかかわる財産で、「系譜・祭具・墳墓」の事をいいます。 たとえば、一家代々の墓があるような場合、通常の財産のように承継するようなものではない、というのは一般的な感覚です。そのため、これらの財産は、いわゆる後継ぎといわれるような人を決めて、一人に承継させるのが一般的です。次のように書くのが一般的でしょう。
付言
遺言書には基本的に遺産や法律関係に関することを記載します。 しかし、遺言するにあたって、どうしてこのような分配になったか、どのような想いがあるか、という事も記載しておきたいという場合もあります。そのような場合には、付言(あるいは付言事項)として、記載をすることがあります。自筆証書遺言書のひな型
以上を踏まえて、自筆証書遺言書のひな形を確認してください。遺言書
1.妻 新宿一子 に次の財産を相続させる 東京銀行新宿支店の遺言者名義の普通預金(口座番号1234567)の全て
2.長男 新宿一郎 に次の財産を相続させる
土地 所在:東京都新宿区西新宿1丁目 地番:1番1 地目:宅地 地積:300平方メートル
建物 所在:東京都新宿区西新宿1丁目 家屋番号:11番123 種類:居宅 構造:木造かわらぶき平屋
床面積:1階150平方メートル
3.現金・本遺言に記載のない一切の財産については、次男新宿 二郎 に相続させる。
4.遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、 前記 長男 甲野一郎を指定する。
5.遺言者は祭祀を主宰すべき者として、長男 新宿一郎を指定する。
付言事項
私はとても幸せな人生でした。素晴らしい妻と子に恵まれたことを感謝します。
私が亡くなった後も、家族で助け合って暮らしていくことを希望します。
不動産については同居している長男一郎に相続させることにして、妻一子の面倒を見てもらうことになったので、次男二郎が相続できる分は少なくなりますが、理解してくれると助かります。
妻一子のことをよろしくお願いします。
令和◯年◯月◯日
住所 東京都新宿区西新宿1丁目
遺言者 新宿太郎 印
自筆証書遺言書作成の際の注意点

- 自筆証書遺言書作成の際の注意点
- 訂正方法・共同遺言が禁止されていること・封筒の作成方法について
自筆証書遺言書作成の際の注意点はありますか?
自筆をするので書き間違えた場合の訂正方法に注意が必要です。ほかにも共同遺言が禁止されていることや、封筒を作成する方法についても併せて確認しましょう。
自筆証書遺言書作成の際の注意点としては次のものがあります。
訂正方法
自筆証書遺言書を作成する場合、財産目録以外の全文を自書する必要があり、どうしても書き間違える可能性があります。
長文にわたる場合に、1から書き直すのは手間であるため、修正をすることが考えられますが、その際には指定の変造を防ぐ意味で、所定の方法が民法968条3項に規定されており、その方法に従ったものでなければ効力が発生しません。
その方法は、加除その他の変更について、遺言書の中で場所を指定して、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押すという方法で行われます。
遺言書の訂正の方法は、「遺言の訂正をしたい場合にはどうすればよいか」で解説していますので、参考にしてください。
共同遺言の禁止
共同遺言とは、一つの遺言書で複数の人間が遺言をすることいい、民法975条では共同遺言をすることはできないことが規定されています。
よく挙げられるのは、夫婦で一つの遺言書を作成することですが、権利関係が錯綜するため、これが禁止されています。
自筆証書遺言は従来に比べるとカジュアルに行われる傾向にはありますが、法的効果を生じさせるための厳格なものなので、法律に従い別々に作成しましょう。
封筒を作成する場合
自筆証書遺言書は封をすることまでは民法・その他の法律では要求されていません。
そのため、封筒を作成する場合に、どのような封筒を用意しても法的には問題ありません。
しかし、亡くなった後に相続人に遺言書であると認識されず遺品整理で破棄されてしまったり、あるいは見つかったときに破棄・改ざんされるおそれがあったりすることがあるため、封筒を作成する場合には工夫が必要です。
遺言書であることを認識できるように、遺言書が入っていることを封筒に記載しておくことが望ましいですが、改ざんされないように封をする(封筒を糊などで閉じて、綴じ目に印鑑を押す)ことがおすすめです。
また、封筒に名前や日付を記載しておき、家庭裁判所で検認をするまでは開封しないように記載しておくと良いでしょう。
自筆証書遺言が無効になる場合

- 自筆証書遺言が無効になる場合
- 自筆をしていない・日付の記載・様式に沿った訂正がされていない・記載事項が正確でない場合
自筆証書遺言はどのような場合に無効となりますか?
無効となる場合を確認しましょう。
自筆証書遺言が無効となる場合として次のものが挙げられます。
自筆をしていない
自筆証書遺言書を自筆していない場合に無効となります。
自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆することが要件となっており、パソコンで作成した場合や、例えば誰かに代筆をしてもったような場合、自筆とはいえず無効となります。
手が不自由などで自筆ができない場合には、公正証書遺言・秘密証書遺言によって行います。
日付の記載など様式に沿っていない
日付の記載など、自筆証書遺言書の様式に沿っていない場合には、自筆証書遺言が無効になります。
日付の記載・署名・押印など遺言書に必ず記載すべき事項について漏れていると、遺言自体が無効となってしまいます。
様式に沿った訂正がされていない
様式に沿った訂正されていない場合、その訂正が無効となります。
上述したように、遺言書の訂正には法律に従った様式があり、その通りに行う必要があります。
その様式に違反して行った訂正については、訂正が無効となります。
例えば遺言書の日付の記載が不適切である場合に、訂正して適切な記載をしたけども、遺言書の様式に沿った訂正ではない場合、訂正が無効となる結果、遺言書の日付の記載が不適切なまま残り、遺言自体が無効になることもあります。
その他の訂正については、訂正のみが無効とされます。
記載事項が正確でない
記載事項が正確でない場合には無効となるおそれがあります。
例えば、不動産の遺贈について、不動産登記簿と異なる内容が遺言書に記載されている場合、遺贈が無効とされます。
記載事項が正確でない場合でも、最高裁は「意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探究し,できるかぎり適法有効なものとして解釈すべきを本旨とし,遺言についてもこれと異なる解釈をとるべき理由は認められない」としていますが(最判昭和30年5月10日)、記載が無効となる可能性がある点に注意が必要です。
自筆証書遺言を弁護士に依頼する場合の費用

- 自筆証書遺言の作成のサポートを受ける場合の弁護士費用について
自筆証書遺言を書くにあたって相談や作成の指導をしてもらう場合、いくらくらいかかりますか?
事務所にもよりますが100,000~200,000円を基本として、財産の内容などによって増えると考えてください。
自筆証書遺言は上記のように、ミスをしてしまうと無効となる危険性があります。そのため、専門家である弁護士に相談をしながら作成する事も検討したいものです。その場合、弁護士に相談・依頼をするための費用がかかってくるのですが、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。 まず、一例として弁護士に法律相談をする際には30分5,000円程度の費用がかかります。相談後、遺言書の作成を依頼する場合は100,000~200,000円を最低額として、財産の内容・相続人の数によって費用が増えます。
自筆証書遺言書の保管

- 自筆証書遺言書の保管をどのように行うか
- 専門家に保管を依頼することもできる
自筆証書遺言書の保管についてはどのようにおこなうべきでしょうか。
破棄・隠匿や改ざんされないようにする、遺言書をみつけてもらえないことがないようにする、という注意が必要です。専門家に保管を依頼することもできるので検討してみましょう。
作成した自筆証書遺言書はどのように保管すべきでしょうか。
自筆証書遺言書の保管については、同居している方に見つかってしまい破棄・隠匿や改ざんされないようにすべきという観点と、亡くなった後に遺言書を見つけてもらえないようにすべきという観点から考える必要があります。
自宅で通帳や不動産の権利証などの重要書類と一緒に保管しているような場合、亡くなった後に整理の過程で見つけてもらえることが期待できますが、同居している方がこれを見つけ、自分に不利である結果破棄・隠匿してしまったり、改ざんしてしまったりする危険があります。
一方で、誰にもみつからないように隠しておけば、破棄・隠匿や改ざんのおそれはなくても、亡くなった後も見つけてもらえず、遺言がないものとして相続が進んでしまう懸念があります。
貸金庫の契約をしている場合には、貸金庫に預けておくことで、生前に誰かに見つかる可能性は低く、また死後に整理をするために確認してもらえるでしょう。
遺言書の作成を弁護士に相談して行う場合には、弁護士が預かってくれることがあるので確認してみましょう。
また、弁護士に遺言執行者となることを依頼している場合には、遺言の執行に必要であり無料で弁護士が預かってくれます。
公正証書遺言の方が良い場合

- 公正証書遺言の方が良い場合
- 自筆ができない・判断能力が衰えている・相続争いとなるのを絶対に防ぎたいなど
公正証書遺言にしておいた方が良い場合としてはどのようなものがありますか?
自筆ができない場合は自筆証書遺言ができないので公正証書遺言によることになります。また非常に高齢であったり初期の認知症であったりする場合で、本人の判断能力が疑われる場合や、相続争いになる可能性がある場合などには、信頼性の高い公正証書遺言が良いでしょう。
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にしたほうが良い場合は以下の通りです。
自筆ができない場合
まず、全く自筆ができない場合には、自筆証書遺言の要件である自筆がそもそも行えません。
また病気や怪我の影響で、字を書くのが難しい状況になっている場合に、頑張って自筆したとしても、他の相続人から本人の筆跡ではないことを理由に争いになる可能性があります。
公正証書遺言は作成を公証人が行うので、自筆ができなくても作成ができるので、自筆ができない場合には公正証書遺言にしたほうが良いでしょう。
本人の判断能力が衰えている場合
本人が高齢であったり、初期の認知症にかかっていたりして判断能力が衰えているような場合には、公正証書遺言にした方が良いでしょう。
遺言をするには、遺言をしたらどうなるかを判断するための遺言能力が必要であり、これを欠くと遺言は無効となります。
高齢や認知症であるというだけで遺言能力が全くなくなるわけではないですが、そのような状態で自筆証書遺言がある場合、無理やり書かせた・本人が書いたものではないという主張をされるおそれがあります。
公正証書遺言の場合でも、遺言能力自体は必要ですが、公正証書遺言書作成の過程で準公務員である公証人が要件を満たしているか事実上のチェックを行い、判断能力がないような場合には遺言書作成ができません。
そのため、公正証書遺言によるべきでしょう。
相続争いとなるのを絶対に防ぎたい場合
相続争いとなるのを絶対に防ぎたい場合には、公正証書遺言によるのが良いでしょう。
相続人の仲が悪いような場合はもちろん、相続できる割合が偏っているなど、争いになりそうな場合があります。
この場合、自筆証書遺言書について偽造・変造を主張することが考えられます。
公正証書遺言は上述したように準公務員である公証人が作成するので、信頼性が高く、遺言書の無効を主張されづらいという特徴を持っています。
そのため、公正証書遺言によるべきでしょう。
まとめ
このページでは、自筆証書遺言についてお伝えしてきました。手軽に作成できるものである一方、現実に要件を満たさないで無効となりやすいのが自筆証書遺言です。 法令改正が相次いでいることもあるので、自分に合っているかどうかの相談も含めて弁護士に相談しながら作成するのが望ましいといえます。

- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺産分割協議相続財産?遺産分割財産?この2つの違いについて解説!
- 2025.09.22相続放棄・限定承認遺留分放棄とは?相続放棄との違いやメリット、撤回の可否を解説!
- 2024.05.23相続全般相続法が改正された!いつから?今までと何が変わった?
- 2024.05.23相続全般相続人代表者指定届とは?その効力は?書き方も併せて解説