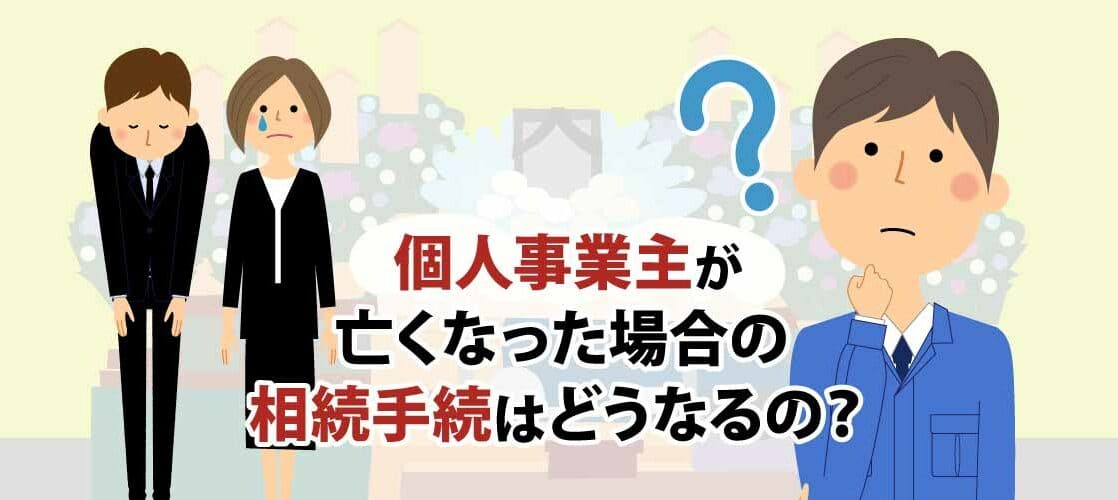- 個人事業主が亡くなったときに発生する手続きと注意点を確認する
【Cross Talk】個人事業主が亡くなった!そのときに何をやらなければならないのか
父が亡くなりまして、母と私で相続をすることになりました。父は個人事業主だったのですが、個人事業主に関して何か相続で気を付けておくことはありますか?
個人事業に関する書類提出と準確定申告です。そのほか、商売をするのに大きな借金をしているような場合には相続放棄の期間にも気を付けてください。/p>
個人事業主が亡くなった場合には注意すべきポイントがたくさんあります。 個人事業主は通常、税務署に個人事業主の開業届を行っている関係で、廃業に関する手続きが必要です。
またサラリーマンと違って個人事業主は確定申告をする必要があるのですが、個人事業主が亡くなった場合には、死亡を知ったときから4ヶ月以内に確定申告(準確定申告)をする必要があります。
手続き的な注意点だけではなく、商売をしていることから多額の借金をしていることもありますので、相続放棄については気を付けておく必要があります。
個人事業主が亡くなった際の手続き

- 個人事業主が亡くなったときの税務署関連の手続きを知る
- 準確定申告の必要があることを知る
まず、個人事業主が亡くなった場合にしなければならない手続きにはどのようなものがあるのでしょうか
個人事業主は通常、税務署に個人事業主の開業届を提出していますので、税務署に関する手続きをまとめて知っておきましょう。 また、準確定申告は期限のある手続きでもあるので必ず確認しておきましょう。/p>
個人事業主が亡くなった場合に法定されている手続きについて知りましょう。
死亡届
個人事業主であるかどうかに関わらず、人が亡くなった場合に役所に提出するのが死亡届です死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合には3ヶ月以内)に提出しなければなりません(戸籍法86条1項)。
医師が発行する死亡診断書(もしくは死体検案書)を添付して提出することになっているのですが(戸籍法86条2項)、死亡診断書(死体検案書)と一緒になった死亡届が遺族に渡されるのが一般的です。
なお、火葬をするのに火葬許可証が必要なのですが、この火葬許可証は死亡届を提出した際にもらうのが通常の流れで、葬儀社がこの作業を代行してくれることが多いです。
個人事業者の死亡届出書
消費税法上の課税事業者である場合には、個人事業主の死亡後速やかに、消費税を納めていた税務署に「個人事業者の死亡届出書」を提出します(消費税法57条1項4号)。
廃業届
一般に廃業届と呼んでいますが、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、廃業のところにチェックをして提出します(所得税法229条)。
廃業届は、個人事業主が死亡した日から1ヶ月以内に、開業届を出している税務署に届け出なければなりません。
事業廃止届
消費税法上の課税事業者である場合には、個人事業主の死亡後速やかに、消費税を納めていた税務署に対して事業廃止届を提出しなければなりません(消費税法57条1項4号等)。
給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届け出
従業員を雇って給与支払いをしている場合には、一カ月以内に、給与支払事務所の所在地の税務署に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届け出」を提出します(所得税法230条)。
こちらも、一つの届出書に開設・移転・廃止のチェック欄があるので、廃止のところにチェックをして届出を行います。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
所得税関係の届出に関するものについて見てみましょう。
個人事業主は、事業を開始する際に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しているのですが、亡くなった方が確定申告において青色申告をしていた場合には、所得税を納めていた税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です(所得税法151条)。
この提出期限は、翌年の3月15日が期限になります。
準確定申告
個人事業主が亡くなったときに気を付けなければいけないのは、準確定申告です。
個人事業主は所得税・消費税の申告をするのですが、個人事業主が亡くなった場合には、相続人がその年の確定申告を行う必要があります(所得税法124条、消費税法45条2項・3項)。
個人事業主が亡くなったときに気を付けなければいけないのは、準確定申告です。 個人事業主は所得税・消費税の申告をするのですが、個人事業主が亡くなった場合には、相続人がその年の確定申告を行う必要があります(所得税法124条、消費税法45条2項・3項)。
個人事業主が亡くなった場合の相続財産

- 個人事業主の相続人が何を相続するか確認する
取引先の会社の社長より、会社の債務・借金については、代表者が連帯保証人になっていなければ、代表者の相続人に影響しないと聞きました。
個人事業主も同様ですか?
いいえ、個人事業主は会社ではないので、個人事業主の相続人は、個人事業の債務・借金も相続することになります。
個人事業主の相続においては何を相続するのでしょうか。 現金・預金・自家用車・自宅など個人の生活にかかわる財産を相続することは問題ないのですが、商売用の資産はどのように考えるべきでしょうか。
株式会社などの法人の場合には、法人に帰属している財産については、個人である代表者自身の財産ではなく、代表者の相続人が相続することはありません。法人と個人は、法律上、別人格として扱われます。
しかし、個人事業主については、個人事業の主体と、個人事業主自身は、同一視される個人です。
したがって、相続人は個人事業主に帰属している商売用の資産についても相続します。
なお、相続財産としてはプラスの資産も借金や買掛金のようなマイナスの財産である債務も、いずれも含まれます。
亡くなった個人事業主の債務が多い場合

- 借金が多いときには相続放棄や限定承認を利用する
父の商売は残念なのですがあまり上手くいっておらず、借金や債務がかなりあるのですが、これは私たち相続人で払わなければならないでしょうか。
相続放棄や限定承認という、全ての借金を引き継がないようにする手続きを利用しましょう。
上述した通り、個人事業主の相続をした場合には借金や債務を引き継ぐこともあります。事業の規模によっては、個人が銀行や消費者金融でする借金よりも多額の事業用の借金や買掛金が残ってしまっている…ということもありえます。
このような場合に、相続放棄(プラス財産もマイナス財産も全て引き継がない)や限定承認(プラス財産の範囲内でマイナス財産を負担する)といった手続きを利用すれば、借金を相続しなくても済みます。
相続人が個人事業を受け継ぐ方法

- 相続人が個人事業を受け継ぐ場合の手続き
場合によっては母の存命中は母が引き継ぐことも考えているのですが、この場合には手続きは必要ですか?
上記の手続きのほかに、母親名義で個人事業の開業届を出すことは忘れないでください。
相続人が個人事業を継ぐ場合の手続きについて確認しましょう。
廃業届出書などの書類提出をしなければならないのは変わりない
まず、相続人の誰かが個人事業を継ぐときでも、1で述べた手続きについては同様に行わなければなりません。あくまで税務署への届出・準確定申告については被相続人に関する手続きとして必要になるものだと考えておきましょう。
相続人は個人事業主として開業するための書類の提出が必要
事業を継ぐ方が個人事業主として開業届を出していない場合には、その方が個人事業主として開業届をあらためて提出する必要があります。
個人事業主として開業するための書類は、青色申告承認申請、青色専従者給与に関する届出、給与支払い事務所等の解説届、消費税の開業届等、上記の他にも沢山提出すべき書類がありますが、このコラムでは割愛します。
相続人が屋号を引き継ぐ方法
たとえば飲食店のように、従来通りの屋号を引き継ぐ…ということもあります。 被相続人の廃業届を出したからといって、その屋号は使ってはならないというわけではありません。 個人事業主の開業届を出す際に、被相続人が使っていた屋号で登録することで、屋号を引き続き利用することが可能になります。
事業を引き継ぐ際に発生する主な税金の種類

- 相続開始後に事業を引き継ぐ場合は相続税が発生する
- 生前に事業を引き継ぐ場合は贈与税が発生する
個人事業を引き継ぐ場合、何か税金が発生するのでしょうか?
事業を引き継ぐタイミングによって、発生する税金が異なります。具体的には、個人事業主が亡くなった後に事業を引き継ぐ場合は相続税が、個人事業主の生前に事業を引き継ぐ場合には贈与税が発生する可能性があります。
相続税
個人事業主が亡くなった場合、事業用の財産も含め、た被相続人の一切の財産が相続の対象になります。
したがって、被相続人の相続開始後、被相続人の個人事業を引き継ぐために事業用の財産を相続した場合、相続税が発生する可能性があります。なお、ここでいう財産には、事業に利用している土地や建物といった不動産、車両などの動産のほか、販売目的で仕入れたもののまだ販売されていない商品(棚卸資産)なども含まれます。
事業用の財産が多く、それ以外の財産が少ない(特に現預金が少ない)場合、納税資金を捻出するために事業用の財産を処分せざるを得ないことがあり、事業の円滑な承継が妨げられる可能性があります。
そのため、後ほど解説する各種の相続税軽減の制度の利用を検討するといいでしょう。
贈与税
個人事業主が亡くなった後、相続によって事業を承継する場合、どうしても相続の手続に時間がかかってしまいますので、被相続人の死亡後に直ちに事業を再開することができず、取引先等に迷惑をかけてしまうおそれもあります。
そのような事態を避けるには、個人事業主の生前に事業用の財産を贈与して事業を承継させる、という方法も選択肢の一つです。
ただし、生前贈与をすると、贈与税が発生する可能性があることを理解しておきましょう。贈与税は、相続税と比較して、控除額が少なく、税率も高いことから、通常は同じ財産を相続によって取得する場合よりも生前贈与によって取得した場合の方が、税額が高くなりやすい傾向にあります。
そのため、後述の個人版事業承継税制を利用する等の節税対策を講じる必要があります。
個人事業主が死亡した場合の相続税軽減の制度

- 個人事業主が死亡した場合の相続税軽減の制度
個人事業主が死亡した場合に相続税を軽減する制度があるのですか?
いくつかありますので確認しましょう。
個人事業主が死亡した場合に利用できる相続税軽減のための制度を知っておきましょう。
小規模宅地等の特例
不動産を相続した際に、土地の評価額を減額できる小規模宅等の特例(租税特別措置法第69条の4等)があります。被相続人が事業を行っていた土地の場合や、被相続人と生計を一にしていた(共通の資金で生活をしていること)親族が事業を行っていた土地の場合には、「特定事業用宅地等」に該当するため、最大80%の減額をすることができます。
被相続人が不動産賃貸事業のために貸付をしていた土地である場合や、被相続人と生計を一にしていた親族が不動産賃貸事業のために貸付をしていた土地である場合には、「貸付事業用宅地等」に該当するため、最大50%の減額をすることができます。
個人版事業承継税制
青色申告事業者について、相続などによって取得した「特定事業用資産」に係る相続税や贈与税の納税を猶予し、後継者がさらに次世代の後継者にその特例事業用資産等を承継した場合などに、猶予されていた相続税・贈与税が免除される制度です(措置法第70条の6の10等)。 です。 小規模宅地等の特例が利用できなくなりますが、そのあと何代にもわたって事業を続けていることが想定できる場合には、利用によって相続税が免除されることになるので、節税の観点からはメリットが大きい制度であるといえるでしょう。 いずれも、非常に複雑な制度なので、個人事業を引き継ぐ場合には、弁護士・税理士に相談することは不可欠であるといえるでしょう。個人事業主が亡くなった場合の相続財産
株式会社などの法人の場合、法人に帰属している財産については個人が相続することはありません。
しかし、個人事業主についてはこのような制度ではないので、相続においてはプラスの資産も相続しますし、借金や買掛金のようなマイナスの財産である債務も相続することになります。
個人事業主が死亡した場合の相続放棄

- 個人事業主が死亡した場合の相続放棄
- 借金・負債の調査の方法
個人事業主の相続をした場合に相続放棄をすることはできるのでしょうか?
もちろんできます。ですが、借金や買掛金の調査が難しいので、コツを知っておいてください。
個人事業主を相続した場合も相続放棄は可能
相続放棄は被相続人の職業によって差はなく、個人事業主を相続した場合も相続放棄は可能です。 被相続人が個人事業主であった場合には、事業の規模によっては莫大な借金・債務を抱えていることがあります。 また、特定の相続人に事業用資産を集めたい場合に、相続放棄を利用することも考えられます。個人事業主の場合に債務の調査に注意
個人事業主の場合には、債務の調査に注意をしましょう。 一般的に消費者金融・貸金業者などから借り入れをしている場合には、相続人が信用情報を確認すれば、借金の存在は確認できることが多いです。
しかし、個人事業主の場合には、信用情報で分かるのは貸金業者からの借金だけで、親族や他の経営者から個人的に借金をしているものや、事業の買掛金・未払金、他の債務の連帯保証債務については信用情報からは判明しません。
そのため、信用情報の確認とともに、会社の帳簿類を調査したり、生前に付き合いのあった経営者仲間や取引先などに、債務や連帯保証債務がないか確認したりする必要があります。
個人事業主の場合にも、相続放棄の期間は3ヶ月なので、早めに手続きに着手し、調査に時間がかかる場合には、3ヶ月の期間の伸長の手続きを早めに行いましょう。
まとめ
このページでは、個人事業主が亡くなった場合の手続きについてお伝えしてきました。
個人事業主が亡くなった場合には、税務署への準確定申告といった手続きがあるので注意が必要です。
また、商売をしているという特性から、多めに借金をしているということもあり得ますので、相続放棄などの利用も考えなければなりません。
相続に詳しい弁護士や税理士に相談をして早めに手続きを進めるように心がけましょう。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28相続全般寄与分の相場はいくら?タイプ別の計算方法を解説
- 2025.11.26遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を行う場合の不動産の評価はどのように行うのか
- 2025.10.29相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2025.10.22遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?