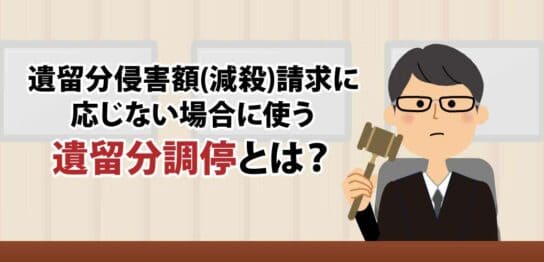はじめに
・自分の取り分があまりに少ない
・まったく相続できなかった
親の遺言書を見て、遺産の取り分の少なさに戸惑っている方もいるかもしれません。
法定相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が保障されています。
そして、遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額を請求することができます。
ただ、弁護士へ依頼する前に、まずは自身で遺留分侵害額請求の意思を伝えたいと考える方もいるでしょう。
本記事では、法的な請求の第一歩として有効な「内容証明郵便」の作成方法や注意点を、わかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求権で内容証明郵便を利用する理由
遺留分を侵害された場合の金銭の請求は内容証明郵便を利用するのが一般的です。
その理由について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、相続人に対して最低限の相続分を保障する制度のことです。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。
直系尊属(被相続人からみて血のつながった上の世代)のみが相続人となる場合は1/3、それ以外の場合は1/2が遺留分となります。
この割合は、相続人全体のために留保される遺産の割合で、相続人が複数いる場合は、この遺留分の割合に各相続人の法定相続分をかけた割合が、各相続人の遺留分となります。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
例えば、親が亡くなって、1,000万円の遺産を子ども2人が相続する場合、子ども2人の遺留分はそれぞれ1/2×1/2の1/4(250万円)ということになります。
遺留分侵害額請求とは
生前贈与や遺贈によって、遺留分に相当する遺産を相続することができなくなることを、遺留分の侵害といいます。
そして、遺留分を侵害された相続人は、生前贈与や遺贈を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
時効にかからないためには内容証明を送ること
遺留分侵害額請求権の行使方法については、特に民法に定めはありません。
そのため、口頭で行使することも可能です。
しかし、遺留分侵害額請求を行使しても相手方が支払いに応じるとは限りません。
口頭で権利行使すると記録が残らないため、時効はまだ先だと思ってのんびりと対応していると、相手方から「1年経過したから時効だ」と言われるおそれがあります。
そのような事態を防ぐために、遺留分侵害額請求権は、内容証明郵便を利用して行使するようにしましょう。
内容証明を作成しよう
内容証明郵便とは、郵便局が文書の謄本(写し)保を存することによって、誰が誰に対し、いつ、どのような文書を送ったかを証明する制度です。
通常の郵便では、郵便物の内容は差出人と受取人にしかわかりません。
そのため、通常の郵便で遺留分侵害額請求権を行使しても、相手方から「そんなことは書いてなかった」と言われるおそれがあります。
内容証明郵便を利用して郵便局に写しを保存してもらい、文書の内容を証明してもらうことで、このような相手方の主張を防ぐことができるのです。
内容証明の作成方法と出し方
内容証明の出し方には、以下2つがあります。
①手書きかパソコンで作成した文書を郵便局の窓口に持ち込む方法
②インターネットを利用した電子内容証明による方法
以下では①の作成方法について説明します。
まず、相手に差し出す文書を作成しましょう。
用紙は特に制限がありませんが、字数・行数の指定があることに注意が必要です。
手書きの場合には、市販の内容証明用紙を用いるのが無難でしょう。
差し出す文書が完成したら、その謄本を2通作成します。
1通は郵便局で保存するためのもの、1通は差出人が手元で保存しておくためのものです。
あとは差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意して、郵便局の窓口に向かいましょう。
なお、内容証明を取り扱っていない郵便局もあるので、事前にインターネットや電話などで確認しておくといいでしょう。
内容証明にかかる費用
内容証明にかかる費用は、基本料金に加えて一般書留の加算料金435円、内容証明の加算料金(1枚目440円、2枚目以降260円増)です。
また、内容証明郵便を利用する場合、あわせて配達証明(郵便物を配達した事実を証明するもの)を利用するのが一般的で、これを利用する場合は加算料金320円が必要になります。
遺留分侵害額請求権を行使する文書は、通常は1~2枚の分量になります。
したがって、定形郵便を利用(ごく普通の封筒で送る)するとすれば、内容証明及び配達証明にかかる費用は、 以下の計算となります。
1枚:基本料金84円+一般書留加算435円+内容証明加算440円+配達証明加算320円=1279円
2枚:上記計算式に260円加算して1539円
内容証明に何を記載する?
金銭の支払いを請求する場合、請求する金額を特定するのが一般的です。
しかし、遺留分侵害額請求の場合は遺留分権利者が遺産の全容を把握できていないことも多く、1年という短期間で消滅時効にかかるため、請求金額などの詳細な記載をすることは求められていません。
そのため、受取人に対する生前贈与や遺言書によって差出人の遺留分が侵害されているので、遺留分侵害額請求をすることを明らかにすれば、それで十分と考えられています。
遺留分侵害額請求権を行使する内容証明郵便の文例
遺留分侵害額請求権を行使する内容証明郵便の文例は、次のようなものです。
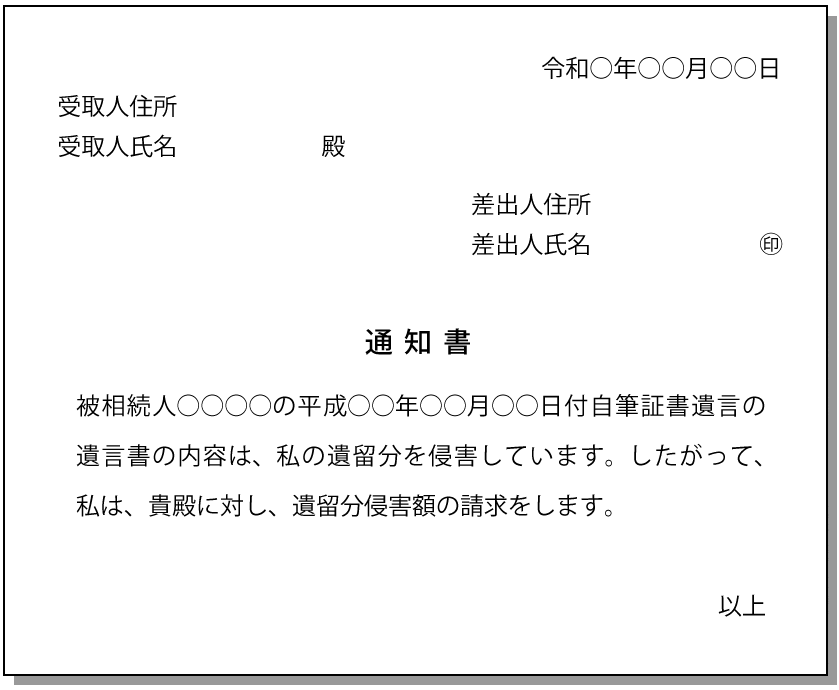
さいごに
遺留分侵害額請求には時効があるため、迅速な対応が必要です。
特に、時効のリスクを避けるには、証拠として残る内容証明郵便の利用が有効です。
本記事で解説したポイントを参考に、適切な手続きを行い、自身の権利をしっかり守りましょう。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺言書作成・執行遺言書を見つけた場合にどうやって開ければいい?うっかり開けてしまった場合の対象法など
- 2025.10.29相続全般相続した土地(不動産)を売却したい場合の手続について解説!
- 2025.09.22相続手続き代行遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺産分割協議は可能?
- 2025.09.19遺留分侵害請求遺留分侵害額請求権を行使する際には内容証明を利用する