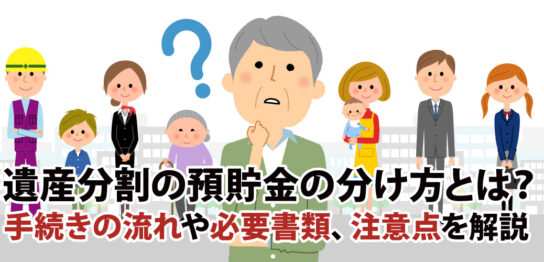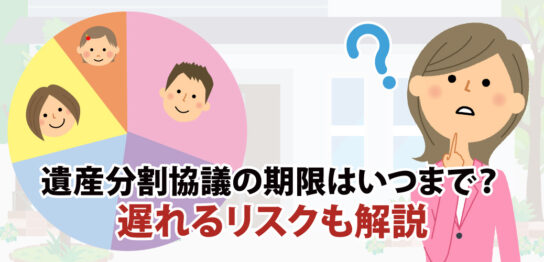- 数次相続とは、相続の手続きが終わらないうちに次の相続が発生すること
- 数次相続の場合、遺産分割協議書の書き方に注意が必要
- 数次相続であることがはっきりと分かるように遺産分割協議書に書く
【Cross Talk】数次相続が発生する場合、遺産分割協議書はどう書く?
数次相続が発生した場合、遺産分割協議書はどのように書けばいいですか?
相続手続きが終わらない間に、複数の相続が発生する数次相続においては、遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。ポイントとしては、数次相続であることがはっきり分かるように記載しましょう。
数次相続の場合は、遺産分割協議書の書き方に注意が必要なんですね。具体的な書き方についても教えてください!
ある方が亡くなって、遺産分割協議などの相続手続きが終わらないうちに、次の相続が発生することを数次相続といいます。
遺産分割協議で取り決めをした内容について記載した書類を、遺産分割協議書といいますが、数次相続においては、遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
そこで今回は、数次相続が発生した場合の遺産分割協議書の書き方について解説いたします。
数次相続とは?

- 数次相続とは、相続の手続きが終わらないうちに次の相続が発生すること
- 数次相続の場合、遺産分割協議書の書き方に注意が必要
数次相続とはどのような相続ですか?
数次相続とは、ある方が亡くなって相続が発生し、その手続きが終わらないうちに、次の相続が発生することです。数次相続の場合、遺産分割協議書の書き方に注意しましょう。
数次相続とは
数次相続とは、ある方が亡くなって相続が発生し、その相続の手続き(主に遺産分割協議)が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生することです。
数次相続のうち、最初の相続を一次相続といい、次の相続を二次相続といいます。
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の遺産をどのように分割するかを、相続人(遺産を相続する方)全員で話し合って決める手続きです。 誰がどの遺産を相続するかで揉めるなどして、遺産分割協議が成立しない間に、相続人の1人が亡くなってしまい、数次相続が発生する場合があります。 数次相続の典型例としては、以下の2点があります。
・父母のどちらかが亡くなり、次に子どもが亡くなる場合
数次相続が発生する場合の遺産分割協議書作成時の注意点
遺産分割協議書に厳密な書式はありませんが、数次相続の遺産分割協議書を作成する場合は、数次相続であることがはっきりと分かるように書くことが大切です。
数次相続であることを明確にするには、以下の2点がポイントになります。
・2番目に亡くなった被相続人は、「相続人兼被相続人」と記載する
数次相続において2番目に亡くなった被相続人は、一次相続においては相続人ですが、二次相続においては被相続人です。
例えば、夫・妻・長男・長女の家族において夫が亡くなった場合(一次相続)、妻は一次相続においては夫の遺産を相続する相続人です。
しかし、遺産分割協議が成立しないうちに妻が亡くなった場合(二次相続)、妻は遺産を遺して亡くなった被相続人になります。
上記の場合の妻のように、相続人と被相続人を兼ねる場合は、「相続人兼被相続人」と記載すると、数次相続であることが分かりやすくなるのです。
・2つの相続をする相続人は、「相続人兼〜(2番目に亡くなった方)の相続人」と記載する
数次相続においては、一次相続における相続人であると同時に、二次相続においても相続人となる場合があります。
例えば、夫・妻(名前をBとします)・長男・長女の家族においてまず夫が亡くなった場合(一次相続)、一次相続の相続人は妻と長男と長女の3人です。
次に、遺産分割協議が成立しないうちに妻(B)が亡くなった場合(二次相続)、二次相続の相続人は長男と長女です。
上記の場合において、長男と長女は一次相続の相続人であると同時に、二次相続の相続人でもあります。 その場合、長男と長女については遺産分割協議書において、「相続人兼Bの相続人」と記載すると、数次相続であることが分かりやすくなります。
中間省略登記ができるかどうかを検討して登録免許税を節約
数次相続が発生した場合、登録免許税を節約するために、中間省略登記ができるかを検討することが重要です。
中間省略登記とは、複数の権利移転があった場合に権利移転毎に逐一登記するのではなく、最初の名義人から最終的な名義人に直接登記をすることです。
中間省略登記が認められると、省略された登記分につき、登録免許税などの費用を節約できます。
中間省略登記は原則として禁止ですが、以下の場合は、例外的に中間省略登記が認められます。
・中間の相続人が複数いるものの、遺産分割協議や相続放棄などによって単独相続となった場合
数次相続が発生したときの遺産分割協議書の作成例

- 数次相続の遺産分割協議書は分けて作成することが可能
- 一次相続の遺産分割協議書の記載方法に注意すべき
数次相続が発生したのですが、遺産分割協議書を一次相続と二次相続に分けて作成することはできますか?
数次相続において、遺産分割協議書をそのように分けて作成することは可能です。作成のポイントは、一次相続の記載において、「相続人兼被相続人」や「相続人兼〜の相続人」と書くなど、数次相続であることを分かりやすく記載することです。
一次相続のときの遺産分割協議書
以下の事案をモデルとして、遺産分割協議書の作成のポイントを見ていきましょう。
・一次相続の遺産分割協議が成立しないうちに、妻Bが亡くなり、長男C・長女Dが相続人となった(二次相続)
本事案の一次相続における遺産分割協議書の作成のポイントは、以下のようになります。
・「被相続人A」と記載
Aの生年月日・死亡日・本籍地・最後の住所地を記載
・「相続人兼被相続人B」と記載
Bの生年月日・死亡日・本籍地・最後の住所地を記載
・「被相続人A(以下、「被相続人」という)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下、「甲」という)、および被相続人の長女D(以下、「乙」という)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに遺産分割協議が成立した。」と記載
・「甲は以下の遺産を取得する」と記載
甲が相続する遺産の詳細を記載(不動産・動産・車両・預貯金など)
・「乙は以下の遺産を取得する」と記載
乙が相続する遺産の詳細を記載
・「以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。」と記載
・遺産分割協議書を作成した日付を記載
・「相続人兼Bの相続人甲(長男C)」と記載
Cの生年月日・住所・署名押印を記載
・「相続人兼Bの相続人乙(長女D)」と記載
Dの生年月日・住所・署名押印を記載
二次相続のときの遺産分割協議書
本事案の二次相続における遺産分割協議書の作成のポイントは、以下のようになります。
・「被相続人B」と記載
Bの生年月日・死亡日・本籍地・最後の住所地を記載
・「被相続人B(以下、「被相続人」という)の遺産相続につき、被相続人の長男C(以下、「甲」という)、および被相続人の長女D(以下、「乙」という)の相続人全員で遺産分割協議を行い、本日、下記のとおりに遺産分割協議が成立した。」と記載
・「甲は以下の遺産を取得する」と記載
甲が相続する遺産の詳細を記載(不動産・動産・車両・預貯金など)
・「乙は以下の遺産を取得する」と記載
乙が相続する遺産の詳細を記載
・「以上のとおり、甲および乙の相続人全員での遺産分割協議が成立したことを証明するために、本協議書を2通作成し、甲および乙の相続人全員が署名押印したうえで、各1通ずつ所持する。」と記載
・遺産分割協議書を作成した日付を記載
・「相続人甲(長男C)」と記載
Cの生年月日・住所・署名押印を記載
・「相続人乙(長女D)」と記載
Dの生年月日・住所・署名押印を記載
まとめ
ある方が亡くなって、遺産分割協議などの手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生することを数次相続といいます。
数次相続について遺産分割協議書を作成する場合、数次相続であることがはっきりと分かるように記載することが重要です。
ただし、数次相続について遺産分割協議書を作成する場合、一般に記載の仕方が難しくなるので、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
<参照>
1数次相続とは?
1)数次相続とは
https://www.i-sozoku.com/navi/guide_suujisouzoku-isanbunkatukyougisho/
2)数次相続が発生する場合の遺産分割協議書作成時の注意点
3)中間省略登記ができるかどうかを検討して登録免許税を節約
https://souzoku.asahi.com/article/14336384
2数次相続が発生したときの遺産分割協議書の作成例
https://isansouzoku-guide.jp/suujisouzoku-isanbunkatukyougisho
参考記事:
遺産相続で揉める人と揉めない人の差とは?揉めないための対策も紹介!

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28遺産分割協議兄弟姉妹の遺産分割で発生しやすいトラブル!争いを避けて円満に解決するポイント
- 2026.01.19遺言書作成・執行遺言は録音やビデオメッセージでも有効?書けない場合の対応方法について解説
- 2025.11.26遺言書作成・執行遺言執行者は必要?メリット・デメリットや選任した方が良い場合について
- 2025.07.28遺産分割協議数次相続が発生する場合の遺産分割協議書について