はじめに
身内を亡くし、勤務先などから弔慰金を受け取った際、「このお金に税金はかかるのだろうか」と疑問に思う遺族の方もいるかもしれません。
相続税や所得税の扱いが曖昧な場合、税務署へ相談する前に制度の概要を把握しておきましょう。
本記事では、弔慰金の基本的な考え方や香典・退職金との違い、非課税となる範囲、課税対象となるケース、申告時の注意点などについて、わかりやすく解説します。
弔慰金とは
弔慰金とは、従業員(被相続人)が亡くなったときに、勤務していた会社が遺族に対して支給するお金のことです。
会社の規定や被相続人の役職などによって金額は異なります。
「花輪代」「葬祭料」「見舞金」「功労金」として支給されることもあります。
香典との違い
亡くなった方の通夜や葬儀において霊前に備えるために渡される金銭を香典といいます。
弔慰金は国や企業が故人の遺族に渡すもので、香典は参列者が喪主に渡すものという違いがあります。
死亡退職金との違い
死亡退職金とは、労働者が死亡したときに、亡くなった方の勤務先などから遺族に支払われる退職金です。
弔慰金は亡くなった方の死を悼み・遺族を慰めるために渡されるものですが、死亡退職金は亡くなった従業員が本来受けるべきであった退職金のかわりになるものです。
儀礼的な意味がある弔慰金は非課税の財産とされる一方で、退職金は相続税の課税財産となるという違いもあります。
弔慰金として支給される金額の決め方
弔慰金は会社などが独自に決めるものなので、金額についてのルールはありません。
弔慰金の金額は、会社が自由に決めます。
一般的には、以下の傾向があります。
- 勤続年数が長いほうが多くなる
- 役職が上であると多くなる
- 業務外の理由で亡くなった場合よりも業務中に亡くなった場合のほうが多くなる
原則として弔慰金は相続財産に含まれない
国税庁のホームページには、弔慰金で「社会通念上相当と認められるもの」については税金の対象とならないと記載されています。
しかし、一般的にみて退職手当金等に該当するといえる場合には、相続税の対象となります。
以下の金額を超える場合は、退職手当金等に該当すると判断され、相続税の対象となります。
・業務上死亡の場合:普通給与額の3年分相当額
・業務上の死亡でない場合:普通給与額の半年分相当額
会社以外からの弔慰金は非課税
個人からの弔慰金、香典、花輪代も基本的には非課税となります。
相続税の評価基準を示す「相続税法基本通達」では、「社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるもの」に関しては税金を課さないとされています。
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
引用元:第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁
もっとも、個人間の関係を考慮し、社会通念上弔慰金としては明らかに高額であり、贈与税を回避するために贈られたとみなされる場合には贈与税が課される可能性があります。
また、戦没者遺族を対象とした特別弔慰金・災害で亡くなった人の遺族に渡す弔慰金、国会議員が死亡したときに遺族に支給するもの、国外犯罪被害弔慰金など国や自治体が独自で行うものもありますが、これらも非課税とされています。
過去に勤務していた会社から弔慰金を貰った場合
被相続人が何度か転職をしていた場合、以前に勤めていた会社から弔慰金が支給されることがあります。
この場合、以前の会社から遺族に対して支払われる弔慰金については、遺族一時所得として処理されます。
そのため、相続税の対象にはなりませんが、一時所得の特別控除額である50万円の金額になる場合には遺族が確定申告を行う必要があります。
弔慰金が課税の対象になるケース
弔慰金が相続税の課税対象となる場合もあります。
詳しく解説します。
弔慰金が課税の対象になる場合
「相続税法基本通達3-20」では、弔慰金は以下のように規定されています。
(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額
引用元:〔退職手当金関係〕|国税庁
3-18、3-19には退職金等に関して記されていますので、一定額を超える部分は退職手当金として取り扱い相続税の課税対象となることになります。
(退職手当金等の取扱い)
3-18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正)
(退職手当金等の判定)
3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。
引用元:〔退職手当金関係〕|国税庁
弔慰金が課税の対象になる場合の計算方法
「相続税法基本通達3-20」の「次に掲げる金額」とは、業務上の死亡であるときは普通給与(直近の俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額で賞与は除く)の3年分に相当する額、業務外の死亡である際には普通給与の半年分に相当する額を指します。
これらの額を超えた部分は死亡退職金とみなされ、相続税が課されます。
死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」部分が非課税となりますので、課税対象価額からこの非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。
例として、死亡退職金1,500万円、弔慰金1,000万円、業務外の死亡で法定相続人が2人、普通給与が40万円の場合で計算してみましょう。
弔慰金の相続税非課税枠×40万円×6カ月×240万円となりますので、相続税の課税対象額は1,000万円(弔慰金の金額)-240万円で760万円です。
760万円を死亡退職金として取り扱うことになります。
死亡退職金の非課税枠は500万円×2(法定相続人の数)で1,000万円です。
死亡退職金1,500万円と760万円を足した2,260万円から非課税枠1,000万円を差し引き、残り1,260万円が課税対象額となります。
弔慰金が課税の対象になる場合の相続税申告書の記載方法
弔慰金が課税の対象になる場合には、相続税申告書の第10表(退職手当金など)に記載します。
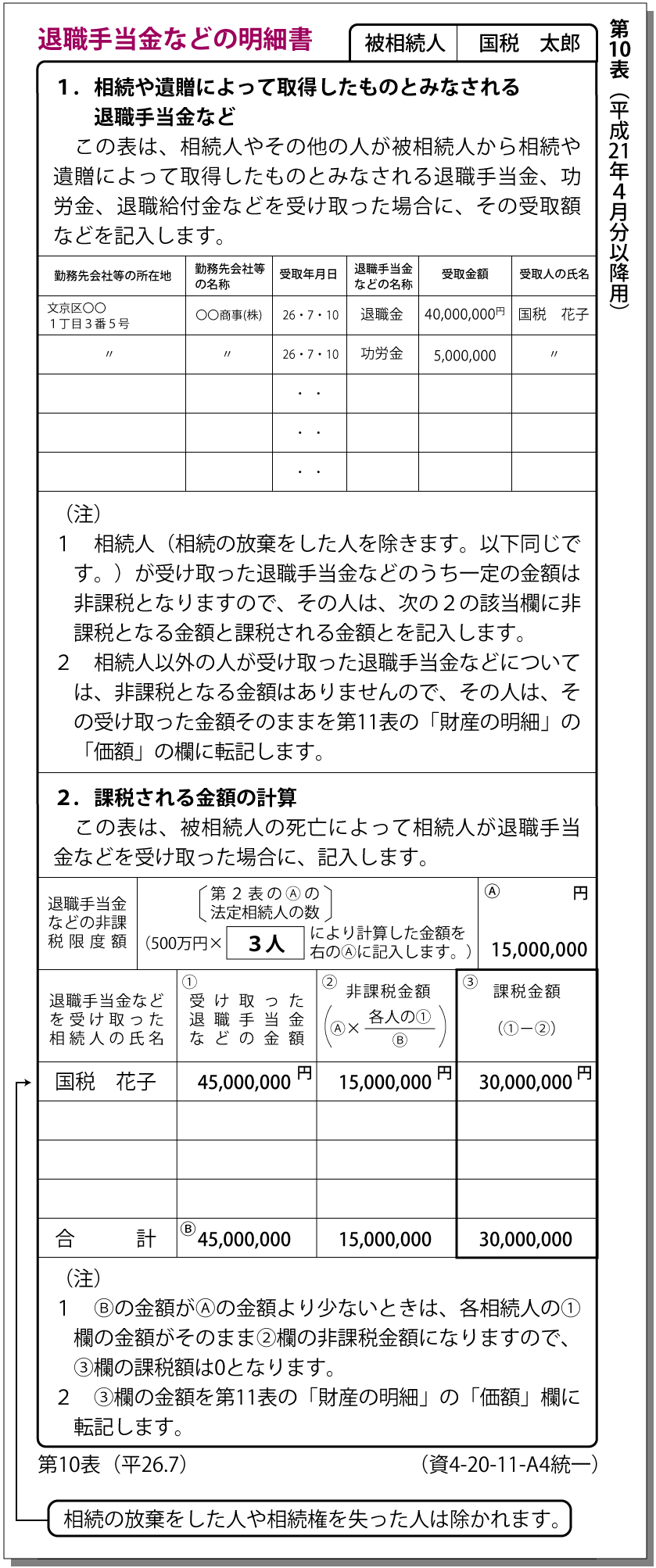 参照:国税庁 相続税の申告書の記載例 17頁
参照:国税庁 相続税の申告書の記載例 17頁
上段に退職金・弔慰金(功労金)の受取金額を記載し、下段に受取金額の合計、非課税金額、課税金額を記載します。
ほかの申告書と合わせて相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内に申告・納付を行ってください。
さいごに
弔慰金は原則として非課税ですが、金額や支給元によっては相続税や所得税の課税対象となることがあります。
香典や死亡退職金との違いを正しく理解し、非課税となる範囲や課税対象となるケースを把握しておくことが大事です。
不安がある場合は専門家に相談し、適切な申告・手続きを行いましょう。

- 相続税対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続税について相談できる相手がいない
- 税務署に調査されないように申告をしたい
- 税務署から通知が届いて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.09.22相続全般相続した不動産は共有にすべき?メリット・デメリットと注意点を解説
- 2025.09.19相続税申告・対策弔慰金は相続税ではどのように評価するか解説
- 2025.09.05相続手続き代行遺産分割協議後に新たな財産が発覚!この場合どうすればいいの?
- 2025.08.15相続税申告・対策相続した不動産の固定資産税は誰が支払う?税金の計算方法についても解説!


































