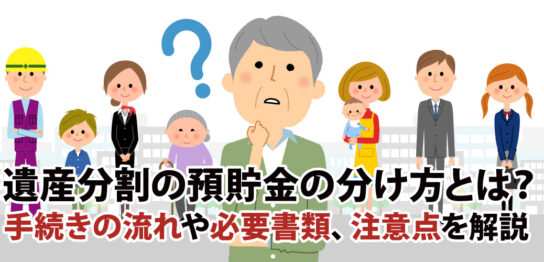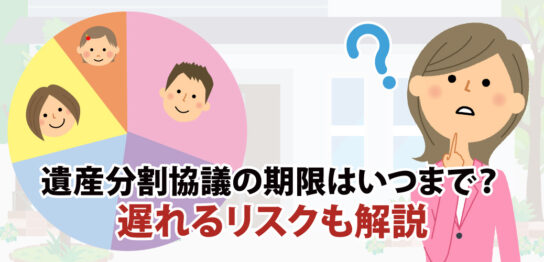- 遺産分割協議書の概要
- 遺産分割協議書の文例
- どこに提出するのか
【Cross Talk】遺産分割協議書はどうやって作るの?
先日母が亡くなり、父と私と弟で相続をすることになりました。
銀行の預金口座について銀行から「遺産分割協議書」を作ってください、と言われました。
どのようなものか、作り方などを教えていただいてもいいですか?
遺産分割協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
作成方法に決まりはありませんが、だいたいの文例はあるのでお伝えいたします。
遺産分割協議書はその名の通り「遺産分割協議」の内容を書面にするものです。
文章はひな型を利用してパソコンのワープロソフトで作成して構いません。
このページでは遺産分割協議書の概要と文例についてお伝えいたします。
遺産分割協議書とは?

- 遺産分割協議書とは遺産分割協議の内容を作成した書面
- 遺産分割協議書は相続手続きを進めるために必要な書類
遺産分割協議書とはどのようなものかを聞かせてもらえますか?
文字通り「遺産分割協議」の内容を書面にしたものです。
相続に関する様々な手続きを進めていくのに使います。
遺産分割協議書は文字通り「遺産分割協議」を書面にしたものです。
相続において相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人が共有しているという状態になります(民法第898条)。
これらの相続財産について、例えば土地・建物などの不動産や、銀行預金などの財産について、誰が取得することになるのかを話し合わなければ、名義を書き換えたり、銀行預金を引き出したりすることができません。
この話し合いのことを遺産分割協議といい、遺産分割協議書はこの協議の内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書の存在によって、どのような協議がされたのかが分かるようになり、相続手続きを行うことができるようになります。
遺産分割協議書を作成する義務はあるのか?
遺産分割協議書を作成する義務を定める法律の条文はありません。
その後の不動産の所有権の移転、銀行預金を引き出すのに不可欠です。
そのため、事実上遺産分割協議書を作成する必要があるといえるでしょう。
遺産分割協議書作成までに行うことは何か
遺産分割協議書の作成までに行うべきこととしては、
- 遺産の確認
- 債務の確認
- 相続人の確定
があります。
まず、どのような遺産があるかを確認します。
遺産分割協議の前提としてどの遺産を誰に分けるかを確定する必要があります。
遺産を全て把握していないと、誰にどの程度分けるか協議ができません。
また、一旦協議をしても、後に金額が大きい・こだわりがあるような遺産が出てきたときに、争いになることがあります。
あわせて、債務の確認も行いましょう。
債務もマイナスの相続財産として相続することになり、多額の借金をしているような場合には相続放棄を検討しなければなりません。
そのため、細かいものでも遺産はしっかり確認しておくべきです。
公正証書として作成する場合もある
遺産分割協議書の作成にあたって、公正証書として作成する場合があります。
公正証書とは、委託を受けて公証人が作成する文書のことで、遺産分割協議書を公正証書で作成することによって裁判を行わずに強制執行ができるという効果があります。
そのため、遺産分割後にもトラブルになりそうな場合や、対価の支払いが必要となる代償分割をする場合などには、スムーズに手続きを終わらせるために、公正証書として作成することがあります。
遺産分割協議書作成のタイミング

- 遺産分割協議書案は協議の詰めの段階から案を作成しはじめる
- 遺産分割協議書は遺産分割協議が終わったらすぐに完成させる
遺産分割協議書はいつ作成すれば良いでしょうか?
遺産分割の協議をしている最中から少しずつ文章を作りはじめるのが、良いといえるでしょう。
遺産分割協議書案として遺産分割協議の詰めの段階で作り始める
遺産分割協議書は、遺産分割協議段階から「案」として作り始めるようにしましょう。文書にせずに協議をして合意したものの、実際の遺産分割協議書を見て合意を渋るということもあります。
少なくとも大枠が決まった段階で一度文書にして、文書を作成しながら詰めるのが良いでしょう。
遺産分割協議書自体は遺産分割協議が終わったらすぐに完成させる
遺産分割協議書案をもとに遺産分割協議がまとまったならば、遺産分割協議書はすぐに完成させましょう。いったん遺産分割協議が終わったにもかかわらず、遺産分割協議書を完成させていないと、しばらく経った後にやはり協議をやりなおしたい、という当事者が出てくる可能性があり、遺産分割協議がなかなか終わらないということがあるためです。
遺産分割協議書作成時の注意点

- 特に遺産の内容と相続人については明確に規定をしておく
遺産分割協議書を作成する場合にはどのような注意が必要でしょうか。
3点注意しておくと良いことをお伝えいたします。
どの相続人が何の遺産を相続するかを明らかにする
どの相続人が何の遺産を相続するかをきちんと明らかにしましょう。遺産を全て誰かが取得することになったとしても、個別の資産について明記をして相続人を特定するほうが無難です。
また、長男・長女・次男…などとだけ記載するのではなく、きちんと氏名まで記載します。
遺産分割協議書中には、相続人全員の氏名・住所・生年月日・続柄も記載しておくと、当事者の特定で争いになることはありません。
遺産分割協議後に新たな遺産が出てきた場合についても協議しておく
遺産分割協議をした後に新たな遺産が出てくることがあります。新たな遺産が見つかった場合も記載しておきましょう。
パターンとしては
- 特定の相続人に相続させる
- 新しく見つかった部分について遺産分割協議をする
- 新たに見つかった遺産があまりにも多い場合には協議をやり直す
遺産分割協議書は相続人の数だけ用意する
作成した遺産分割協議書は1通ではなく相続人の数だけ用意をしましょう。用意した遺産分割協議書には押印した印鑑で割印をするのを忘れないようにしましょう。
日付は明確に記載する
日付の記載を明確に行いましょう。遺言書と異なり、遺産分割協議書には日付の記載を明確に行わなければならない決まりはありません。 しかし、遺産分割協議がいつ調ったのか問題になることがあります。 例えば、共有持分を売却した場合に、遺産分割協議中に売却したのか、遺産分割協議後に売却したのかによって、問題が変わるため、日付が問題になることがあります。 そのため、遺産分割協議書には日付を明確に記載しましょう。
手書き・パソコンどちらが良いのか
遺産分割協議書は手書きにすべきなのでしょうか、それともパソコンで作成して良いのでしょうか。 この点については、自筆証書遺言は民法で自筆によって記載しなければならないと規定されているのですが、遺産分割協議書は自筆を要件としていません。 共同相続人の数だけ同じ遺産分割協議書を作成する必要がありますし、後述する契印・割印によって偽造・変造は防げるので、パソコンで作成することも可能です。印鑑には実印を利用する
遺産分割協議書の作成をする場合には、記名捺印をするのですが、この捺印には実印を使用します。 大事な書類であるという観点はもちろんですが、相続手続きで遺産分割協議に参加してきちんと納得して印鑑を押したかどうかということを確認するために、遺産分割協議書にあわせて印鑑証明書の提出が要求されます。 実印ではない印鑑で押印して、印鑑証明書を添付したときには、印鑑が相違するので遺産分割協議がきちんと行われたのかが確認できず、相続手続きができなくなります。 もし実印がない場合には、実印を作成して市区町村役場で印鑑登録を行いましょう。契印・割印の意味と方法
上述もしましたが、遺産分割協議書は、長いと数ページにもなり、共同相続人の数だけ同じものを作ります。偽造や変造を防ぐために、契印・割印をします。 契印とは、遺産分割協議書が複数のページになる場合に、2つのページにまたがって印鑑を押すことをいいます。 契印により、もし2つのページが破れるなどで別々になったとしても、印鑑がきちんと重なればもともとは遺産分割協議書として連続したものであるという判断が可能になります。 割印とは、複数の遺産分割協議書がある場合に、2つの文書にまたがって印鑑を押すことをいいます。 これによって、複数の遺産分割協議書は同じ内容で作成されたものであるという判断が可能になります。対象となる財産は正確に記載する
遺産分割協議の対象となる財産は正確に記載しましょう。 遺産分割協議の対象となる財産の記載が曖昧だと、当事者で遺産分割協議書の記載を巡って争いになる可能性があります。 預金の場合は銀行口座の口座番号まで記載する、不動産の場合には不動産登記事項証明書に記載されている地番まで記載するなど、財産を正確に区別できるように記載しましょう。遺産分割協議書は相続人全員がそれぞれ1通ずつ保有する
遺産分割協議書は相続人全員がそれぞれ1通ずつ保有します。 遺産分割協議後に相続手続きをする際に、それぞれ相続人が遺産分割協議書を使用します。 そのため、同じ書面を相続人の数だけ作成して、それぞれ1通ずつ保有します。 上述したように、遺産分割協議書が複数できるので、それぞれに割印を必ず押すことになります。後から財産が出てきた場合の処遇について記載する
遺産分割協議前に徹底的に財産を調べるのですが、それでも後から財産が出てくることがあります。 その場合の処遇についても記載するようにしましょう。 実際の記載例は後述します。遺産分割協議書の文例

- 遺産分割協議書の文例
遺産分割協議書はどのように作れば良いですか?
あとで署名捺印をすれば本文はワープロなどで作ってもかまいません。
文例を見てみましょう。
特に直筆でないとダメ、◯◯の指定する方式でないとダメ…という事はありませんので、ワープロで必要に応じて作成します。
一般的な遺産分割協議書の文例
一般的な遺産分割協議書の文例を見てみましょう。最後の住所 東京都港区1-2-3
最後の本籍 東京都港区1-2-3上記被相続人の相続財産について、相続人 鈴木花子、鈴木一男 の2名は次のとおり分割する(ことに合意した)。※3
1. 相続人 鈴木一男は、次の不動産を取得する。※4
土地 所在 東京都港区1丁目
地番 2番3号
地目 宅地
地積 150.00㎡建物
所在 東京都港区1丁目
家屋番号 2番3号
構造 木造平屋建て
床面積 60㎡
2. 相続人 鈴木花子は下記財産を取得する。※5
港区銀行 港支店の被相続人名義の預金
普通預金 口座番号 1234567 のすべて
(後日判明した財産)
3. 本協議に記載なき相続財産は相続人全員によって、その財産について再度協議を行うこととする。
上記の協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を2通作成し、各自1通保有する。
令和2年2月1日
住所 東京都港区1-2-3
相続人 鈴木花子 印
住所 東京都港区1-2-3
相続人 鈴木一男 印
表題※1
表題の部分については「遺産分割協議書」と記載します。被相続人の表記※2
被相続人の表記をします。最後の住所 東京都港区1-2-3
最後の本籍 東京都港区1-2-3
遺産分割協議書の柱書※3
遺産分割協議書の柱書になる部分には、相続人の氏名と、遺産分割をすることを表記します。不動産に関する遺産分割協議書上の書き方※4
不動産がある場合には不動産登記簿の表題部にある事項を記載します。土地については所在・地番・地目・地積を、建物については所在・家屋番号・構造・床面積を記載します。
土地
所在 東京都港区1丁目
地番 2番3号
地目 宅地
地積 150.00㎡
建物
所在 東京都港区1丁目
家屋番号 2番3号
構造 木造平屋建て
床面積 60㎡
現預金に関する遺産分割協議書上の書き方※5
現金については少額であれば記載しないことのほうが多いですが、念のため記載する場合には現金と記載して、具体的な金額は分割しない限り記載する必要はありません。また預金については銀行名・支店名・普通当座の別・口座番号を記載し、具体的な預金額の記載は分割しない限り記載する必要はありません。
普通預金 口座番号 1234567 のすべて
有価証券(株式)などに関する遺産分割協議書上の書き方
株式などの有価証券を保有している場合には、保有している有価証券を識別できるように記載します。投資のために上場会社の株式を購入する場合には、証券会社を通じて購入するので、その証券会社の会社名と支店・口座番号を記載します。
A株式会社 株式100株
B株式会社 株式1,500株
配偶者居住権に関する遺産分割協議書上の書き方
配偶者居住権を設定する場合には、対象となる建物について、不動産登記簿の表題部に記載されている所在地・家屋番号・構造・床面積を記載します。建物
所在 東京都港区1丁目
家屋番号 2番3号
構造 木造平屋建て
床面積 60㎡
現物分割の場合の文例
例えば、その物自体を相続人で分ける現物分割をするような場合には、次のように記載します。代償分割の場合の文例
例えば、不動産を特定の相続人に対してのみ相続させて、ただそれでは相続分から考えると不釣り合いであるような場合に、不動産を相続する方から不利益を受けている方にバランスをとるために金銭を交付する方法を代償分割といいます。このような場合には次のような記載の仕方をします。
換価分割の場合の文例
不動産など分割にそぐわず、代償分割もできないような場合には、換価分割といってお金に換えて分割します。換価分割の対象は不動産である場合が多いので、売却にかかる不動産仲介手数料・登記費用などを差し引いた額を分けることになります。
このような場合には次のように記載をします。
遺産分割協議書の提出先

- 遺産分割協議書はどこに提出するか
作成した遺産分割協議書はどこかに持っていくのですか?
遺産分割協議書自体をどこかに提出する義務があるというわけではありません。必要な手続きに応じて写しを作って提出します。
まず、遺産分割協議書だけを作成してどこかに提出しなければならないものではありません。
あくまで、相続税申告・不動産登記などの手続きにおいて、内容を証明するために提出することになります。
不動産があり相続登記をする場合には、登記申請書とともに法務局に提出をします。
相続税申告をする場合には税務署に申告をする際の添付書類となります。
銀行口座の解約をする場合には銀行に提出します。
この時、作成した遺産分割協議書の原本を提出する必要があるのですが、当然に銀行口座の解約・相続登記・相続税の申告など複数の手続きで利用をします。
そのため、提出をする際にはコピーを作成した上でコピーと一緒に提出をして、原本の内容を確認したうえで原本を返してもらう原本還付という方法があることを知っておいてください。
まとめ
このページでは遺産分割協議書とはどのようなものかと、書き方の一部の文例についてお伝えしてきました。 また、遺産の内容については、よくある資産とされる不動産・銀行預金を中心にお伝えしました。 相続によってどのような資産があるかは異なりますし、どのような分け方をするかというのもそれぞれです。 どのような記載が良いか迷うような場合には、弁護士に相談するようにして、確実に手続きを進めましょう。
参考記事:亡くなった人の確定申告は必要?準確定申告とは?|葬儀の口コミ

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続全般相続分の譲渡とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、税金や方法について解説
- 2025.10.27遺産分割協議遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか記載の注意点や文例などについて解説
- 2025.10.20相続全般任意後見人ができること・できないこと|なれる人の条件について
- 2025.09.25成年後見成年被後見人は遺言を作成できるのか