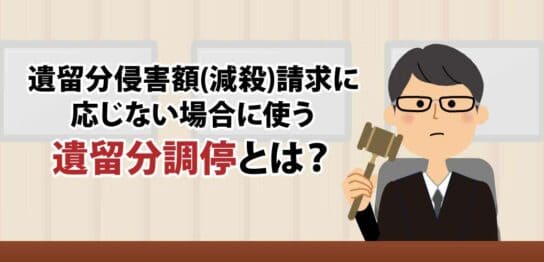- 代襲相続とは、孫や甥・姪に遺産を相続する権利が生じる制度。
- 代襲相続は、被相続人が死亡した時に相続人が死亡していた場合などに発生する。
- 出生の時期によっては養子の子どもには代襲相続が生じないこともあるので要注意
【Cross Talk】死亡した子どもの代わりに孫が相続になる「代襲相続」ってどんな制度?
私は今年で70歳になりますので、そろそろ自分の相続について考えなければいけないと思っています。私と妻の間には息子と娘がいましたが、息子は10年前に妻と2人の子どもを残して病気で他界してしまいました。娘は健在です。このような場合、私が死亡したときの相続関係はどうなるのでしょうか。
その場合、奥様とお嬢様に加えて、亡くなられたご子息のお子様(ご相談者様のお孫様)が相続人となります。お孫様が相続人となるのは、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という法律上の制度があるからです。
代襲相続とは、初めて聞いた言葉です。どのような制度なのか教えていただけますでしょうか。
本来相続人となるべき方が被相続人より先(もしくは同時)に死亡した場合に、その子どもなどが代わりに相続人となるのが代襲相続です。例えば被相続人の子どもが被相続人より先に死亡していた場合、孫が代わりに遺産を相続することができます。
代襲相続とは?

- 代襲相続とは、被相続人が死亡する前(もしくは同時)に被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っていたときに発生する相続のことをいう。
- 代襲相続の対象となるのは相続人の子または兄弟姉妹に限られる。
代襲相続はなぜ認められているのでしょうか。
親、子ども、孫の3世代を想像してみてください。
親、子ども、孫の順番で死亡した場合、親の遺産はまず子どもに引き継がれ、ゆくゆくは孫に引き継がれることになります。
ところが子どもが親より先に死亡してしまった場合、代襲相続の制度がなければ、孫の世代は親の遺産を引き継ぐことができなくなります。これでは公平性に欠けてしまいます。そこで、孫の世代、あるいはさらにその下の世代が相続財産を取得できるように認められているのが代襲相続の制度です。
なるほど、理解できました。では代襲相続がどのような制度なのか、もう少し詳しく教えてください。
代襲相続の意味
代襲相続とは、被相続人が死亡する前(もしくは同時)に被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っていたときに発生する相続をいいます。通常であれば、Aが死亡したとき、Aの子どもであるBがAの遺産を相続することができます。
ところが、本来相続するはずだったBがAより先に死亡している場合があります。
このようなとき、Bの子どもであるCがBの代わりにAの遺産を相続することができます。これが代襲相続の制度です。 この場合、本来相続人となるはずだったBを「被代襲者」、代わりに相続人になったCを「代襲者」または「代襲相続人」と呼びます。
代襲相続できる者の範囲
死亡した子どもの直系卑属の場合
被相続人の子どもが相続開始以前に亡くなっていたときは、被相続人の孫が代襲して相続人になります。
被相続人の養子が相続開始以前に亡くなっていたときは、養子縁組と養子の子どもが生まれる時期の先後によって、養子の子どもが代襲相続人になるかどうか判断されます(後述4参照)。
死亡した兄弟姉妹の子の場合
被相続人に直系卑属(子や孫)も直系尊属(父母や祖父母)もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の相続開始以前に被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていたときは、兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲して相続人になります。
代襲相続人である孫や甥姪も亡くなっている場合
被相続人の相続開始以前に被相続人の子どもも孫も亡くなっていたときは、孫の子ども(ひ孫)が相続人になります。これを再代襲相続といいます。被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫、玄孫など)は、被相続人から何世代離れていても代襲相続人になることができます。
これに対し、代襲相続人にあたる兄弟姉妹の子ども(甥姪)が被相続人の相続開始以前に亡くなっていたときは、甥姪に子どもや孫がいたとしても、甥姪の子どもや孫は代襲相続人にはなりません。
代襲相続することについて手続は不要である
孫や甥・姪が代襲相続するときには、裁判所への申立てなどの特別な手続をする必要はなく、通常の相続の手続にのっとって遺産分割が行われます。代襲相続人と連絡が取れない場合の対処法
代襲相続が発生するような場合、代襲相続人と既に疎遠となっており、連絡先がわからなくなっていることがあります。
このような場合には、戸籍の取り寄せとあわせて、戸籍の附票を取り寄せると、現在の住所が判明します。
現在の住所に手紙などで代襲相続人となった旨を通知して、連絡を取ることを試みましょう。
なお、弁護士など専門家に手続きを依頼すれば戸籍や住民票の取得なども行ってくれます。戸籍が複雑で取得するものが多い場合は、時間もかかりますので、弁護士への依頼も検討すると良いでしょう。
代襲相続と相続税の基礎控除額
代襲相続が発生する場合に、相続税の基礎控除額について確認しておきましょう。
相続税の基礎控除を超える遺産がある場合には、相続税申告をする必要があります。
相続税の基礎控除額は、
3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)
で計算します。
代襲相続が発生する際に代襲相続人が複数居る場合には、法定相続人の数も増えることになります。
例えば、父・母・子ども2人の家庭で、父が無くなった場合の相続人は、母・子ども2名の3名で相続することになり、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円✕3)=4,800万円」となります。
しかし、子どものうち一人が既に死亡しており、その子どもが3人(父からすれば孫)いる場合には、相続人は5人となるため、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円✕5)=6,000万円」となります。
代襲相続人は2割加算されない
同じく相続税との関係で、代襲相続が発生した場合で、その子どもは被相続人からすると孫であることになります。
配偶者や一等親の血族(子ども・父母)以外の方が相続や遺贈で財産を取得した場合、財産を取得した方が支払う相続税額は、法律の規定で算出した税額に2割加算されます。
そのため、相続人たる子どもの孫に遺贈をするような場合、孫が支払う相続税額は2割加算することになります、 しかし、孫が代襲相続で相続人となった場合には、上記の2割加算は行われません。
代襲相続によって相続人の二重資格が生じることがある
代襲相続によって相続人の二重資格が生じることがあることを知っておきましょう。
例えば、相続税対策などのために、孫を養子にすることがありますが、孫を養子にした後に、養子にした孫の親(つまり被相続人からすれば子ども)が亡くなった場合には、養子としての地位と代襲相続人としての地位で相続をすることになります。
この場合、養子として・代襲相続人として両方の資格で相続をすることになります。
代襲相続が開始する原因

- 代襲相続が開始する原因となるのは、相続人死亡、相続欠格、相続廃除の3つ
- 相続放棄は代襲相続の原因とはならない。
私の知人は親が借金を残して亡くなったので、相続放棄したと聞きました。このような場合にも代襲相続が発生し、その子どもが相続する権利を得るのでしょうか。
代襲相続が開始する原因となるのは、相続人死亡、相続欠格、相続廃除の3つです。相続放棄は含まれません。
相続人死亡はわかりますが、相続欠格、相続廃除は聞いたことがありません。簡単に教えていただけますでしょうか。
相続人死亡の場合
代襲相続が開始する原因の典型が、相続人が死亡した場合です。
既に説明した通り、被相続人が死亡した時点で相続人となるべき方が既に死亡しており、その方に子どもがいるような場合に代襲相続が発生します。
同じ交通事故で親と子どもが亡くなった場合など、被相続人と被代襲者が同時に死亡した場合にも代襲相続が生じます。
相続欠格の場合
1つ目の条件は、相続欠格の場合です
相続欠格とは、相続人が被相続人を故意に殺そうとしたとき、遺言書の作成を妨害したときなど法律が定める事由(民法891条)があるときに、相続人としての資格を剥奪する制度です。なお、相続欠格の場合、特に手続きを必要とせず、当然に相続権を失います。
相続廃除の場合
2つ目の条件は、相続排除の場合です。
相続排除とは、特定の相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、または著しい非行を行っていた場合に、被相続人の意思により、その方を相続人から除く制度です(民法892条)。
相続欠格の場合と異なり、廃除が認められるためには被相続人が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄の場合は代襲相続されない
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄することをいいます。相続をすると遺産だけでなく負債も引きつがなければなりませんので、遺産より負債の方が多い場合などに相続放棄が利用されます。
代襲相続が発生する原因は、死亡、欠格、廃除の3つで(民法887条2項)、相続放棄は代襲相続の原因に含まれていませんから、相続放棄の場合には代襲相続は発生しません。
相続放棄が代襲相続の発生原因にならない理由としては、相続放棄をする際は自分の子どもなども含めて財産を取得しない意思で放棄していると思われること、遺産の分散を防ぐ目的で放棄した場合に、代襲相続が発生してしまうと子どもや孫も手続きせねばならなくなり、手続きが非常に面倒になることなどが挙げられています。
代襲相続による相続をした方の相続分について具体例を交えて解説

- 代襲相続人は、被代襲者が相続するはずだった相続分を相続する。
- 一人の被代襲者に対して代襲相続人が複数いる場合には、均等に配分される。
先ほど申し上げました通り、他界した私の息子には妻と2人の子どもがいます。このような場合にはどのように遺産が配分されるのでしょうか。
まず、亡くなったご子息の奥様には相続権はありません。ご子息の2人のお子様(相談者様のお孫様)は、ご子息が相続するはずだった遺産が均等に配分されます。
もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
孫が代襲相続する場合
代襲相続が発生した場合の具体的な相続分は状況によって異なります。 ここでは、被相続人Aに妻Bと2人の子どもCとDがいたが、Aが死亡したときにDは既に死亡しており、DにはE、Fという2人の子どもがいた場合を考えてみましょう。
配偶者は常に相続人となり、被相続人が残した遺産の1/2を相続します。本来であればAの子どもであるCとDが残りを半分ずつ(1/4ずつ)を相続するはずでした。 ところがDは既に死亡しているため、EとFに代襲相続が生じます。
EとFはDが本来相続するはずだった遺産を半分ずつ相続します。
したがって、この場合の相続分は、配偶者のBが1/2、子どものCが1/4、孫のEとFがそれぞれ1/8(Dが相続するはずだった1/4をさらに半分ずつ)となります。
兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続する場合
甥や姪が代襲相続するためには、前提として、甥や姪の親、すなわち兄弟姉妹が相続人である必要があります。上の例のように被相続人に直系卑属(子どもや孫)や直系尊属(両親や祖父母)がいる場合には直系卑属、直系尊属の順に優先されますので、今回は相続人に配偶者・子ども・両親がいない場合を検討します。
被相続人Aは、配偶者や子どもはおらず、Aの両親も既に他界していたとします。
Aには2人の兄BとCがいましたが、いずれもAが死亡したときには既に他界していたことにします。
Bには子どもが1人(D)、Cには2人(EとF)いたとします。
もしAの死亡時にBとCが存命であれば、BとCはAの遺産をそれぞれ1/2ずつ相続することができました。ところが既に死亡していたため、BとCの子ども(Aの甥・姪)であるD、E、Fに代襲相続が発生します。
DはBが相続するはずだった遺産の1/2の全部を相続することができ、EとFはCが相続するはずだった遺産の1/2を半分ずつ相続します。したがって、相続分はDが1/2、EとFがそれぞれ1/4となります。
養子の代襲相続については注意点がある

- 養子も代襲相続の対象となる。
- 養子の子どもが代襲相続人になるかは出生時期によって変わる。
代襲相続の対象となるのは相続人の子どもまたは兄弟姉妹ということでしたが、養子縁組した場合の養子は子どもに含まれるのでしょうか?被相続人に養子がいた場合には、その養子も被代襲者になることができます。ト
被相続人の養子も子どもと同様に被代襲者になることができます。しかし養子の子どもについては出生時期によって代襲相続権が生じる場合と生じない場合があるので注意が必要です。
出生時期によって変わってくるのですか?それはどういうことでしょうか。
養子縁組後に養子の子どもが出生した場合
養子縁組は、法律上の親子関係を成立させる制度です。養子縁組をした後は、養子は基本的に実子と同じように扱われます。
代襲相続人になるためには、代襲者が被相続人の「直系卑属」である必要があります。
直系卑属の代表は、血の繋がりのある親族で、自分より下の世代、すなわち子どもや孫ですが、血縁関係がなくても養子は直系卑属に含まれます。
養子の子どもが養子縁組後に出生した場合は、直系卑属となりますので、代襲相続人となります。
養子縁組前に養子の子どもが出生している場合
では、養子の子どもは常に代襲相続人になるかというと、そうではありません。
養子の子どもが養子縁組前に出生している場合、すなわち養子の連れ子である場合は、直系卑属とはなりませんので、代襲相続は発生しません。
代襲相続と遺留分

- 遺留分とは、法律上の相続人が被相続人の遺産のうち一定の割合を相続する権利。
- 代襲者が孫の場合は遺留分が認められるが、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)の場合は認められない。
よくドラマなどで、妻や子どもではなく愛人に遺産を相続させる、なんていう話がありますね。もちろん私はそのようなことはしませんが、そのような内容の遺言書があったら相続関係はどうなるのでしょうか?
遺留分という制度がありますので、そのような場合でも法律上の相続人は一定の遺産を相続することができます。代襲相続が生じた場合、代襲者の立場によって遺留分が生じるかどうかが変わります。
「遺留分」とは、初めて聞いた言葉です。詳しく教えてください。
遺留分とは?
遺留分とは、相続において遺産に対して最低限保障されている権利のことをいいます。
どのような遺言書を作成するかは自由とされているので、「愛人に全財産を相続させる」といった内容も可能といえば可能です。
しかし、それでは相続人が生活できなくなるような事態に発展しかねません。
そのため、遺産の一定割合の取得をできるように、遺留分という権利が定められています。
そして、遺留分に相当する遺産の受け取りができない場合には、遺贈を受けた方などに対して、遺留分侵害額請求をすることが可能となっています。
遺留分制度についての詳細は、「遺留分の割合と計算方法・請求方法について解説」で詳しく解説していますので、気になる方はご参照ください。
代襲者が孫の場合
代襲者が孫の場合、被代襲者である子どもは遺留分権利者ですので、代襲者である孫も遺留分を行使することができます。
代襲者が兄弟姉妹の子ども(甥・姪)の場合
一方で代襲者が甥や姪の場合は、被代襲者である兄弟姉妹に遺留分を行使する権利がありませんので、代襲者である甥や姪も遺留分を行使することができません。
代襲相続特有のトラブルに発展する可能性

- 被相続人に近い相続人が代襲相続人に財産を渡したくないと考えてトラブルになる
- 代襲相続人が寄与分や特別受益を知らずに法定相続分を主張してトラブルになる
通常の相続と違った代襲相続に特有のトラブルはありますか?
代襲相続の場合、代襲相続人と他の相続人が疎遠であることが珍しくありません。そのため、被相続人と近い関係にあった他の相続人が、財産隠しをしたり、代襲相続人に不利な遺産分割協議書を作成しようとすることがあります。また、代襲相続人が被代襲者の特別受益や他の相続人の寄与分を把握していないことで、トラブルに発展することもあります。
通常の相続と代襲相続人がいる場合の相続を比較すると、後者には代襲相続人が被相続人や他の相続人と疎遠であることが多い特徴があります。そのため、次のような問題が生じる可能性があります。
まず、被相続人と近い関係にあった代襲相続人以外の相続人がいる場合、その相続人が、疎遠であった代襲相続人には財産を渡したくないと考えることが珍しくありません。
そのような場合、代襲相続人に財産を渡したくない相続人が、預貯金を引き出して現金化して隠匿するなどの財産隠しを行うことや、代襲相続人に対して相続財産について十分な説明をしないまま、その相続人に有利な遺産分割協議書に署名押印するよう要求してくることがあります。
しかしながら、相続人は単独で(全員共同でなくても)名寄帳や預貯金の入出金明細等、被相続人の不動産や預貯金等の財産に関する資料を取り寄せることができます。そのため、代襲相続人が被相続人の財産を調査することによって、他の相続人による財産隠しが発覚したり、被相続人に多額の財産があることが判明したりして、トラブルに発展することがあるのです。
被相続人が遺言を残していない場合、相続開始時の被相続人の財産を法定相続分で分割するのが原則です。しかし相続人の一部が被相続人の生前に相続の先渡しとして贈与を受けていたり、被相続人に経済的援助をしていたりした場合、単純に相続開始時の被相続人の財産を法定相続分で分割したのでは、相続人間に不公平が生じてしまいます。そのような不公平を是正するため、民法は寄与分、特別受益という制度を設けています。
しかしながら、被相続人等と疎遠である代襲相続人は、被相続人と被代襲者、他の相続人との間に、寄与分や特別受益にあたる特別な事情があることを把握していない場合があります。そのため、代襲相続人が、相続開始時の被相続人の財産を法定相続分で分割することを強く主張し、特別受益や寄与分を主張する他の相続人との間でトラブルに発展する可能性があるのです。
まとめ
このページでは、相続が開始した際に、既に相続人が死亡している場合に生じる、代襲相続について解説しました。 代襲相続が生じる場合の相続関係は一見複雑ですが、基本的な考え方を理解すれば難しいものではありません。 ご本人が関与する相続で代襲相続が発生する場合には、この記事を参考にしていただければ幸いです。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28相続全般寄与分の相場はいくら?タイプ別の計算方法を解説
- 2025.11.26遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を行う場合の不動産の評価はどのように行うのか
- 2025.10.29相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2025.10.22遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?