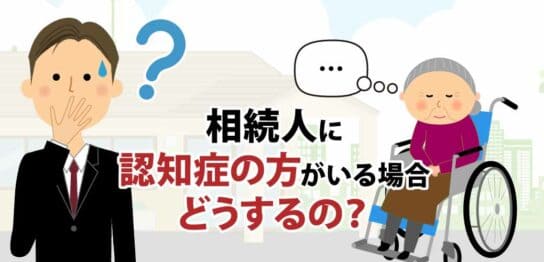はじめに
被相続人である父親が亡くなったあと、父親の面倒をみていた母親や長男が当然のように遺産を取り仕切り、自分の取り分が無視されていると感じていませんか?
「面倒をみてきたのは私だから」などと言われると、強く反論しづらいのが現実です。
しかし、相続は感情論でなく、法律に基づいて平等に行うべきものです。
本記事では、遺産を母や長男が独り占めしようとしている場合に起こり得る手口と、それに対する具体的な対処法をわかりやすく解説します。
相続において遺産を独り占めにする場合とその方法
被相続人(父)が亡くなった場合、配偶者である母や子どもたちには相続権があります。
しかし、母や長男が「被相続人の面倒を見てきたのは私だけなのだから、私だけが相続すべきだ」と主張して、遺産を独り占めしようとする場合があります。
遺産を独り占めしようとする方法を紹介します。
遺産分割協議で相続放棄を迫る
相続放棄をした相続人は遺産を相続できなくなるので、自分以外の相続人全員が相続放棄をした場合は、遺産を独り占めすることができます。
そこで、遺産を独り占めするために遺産分割協議において、ほかの相続人に相続放棄を迫ってくる場合があります。
遺産分割協議に参加させず実印と印鑑証明を送るように迫る
遺産分割協議をしたあとの相続手続においては、一般的に預貯金の払い戻しや相続登記など、さまざまな場面で実印や印鑑証明書を要求されることがあります。
遺産を独り占めするために、ほかの相続人を遺産分割協議には参加させずに、実印や印鑑証明書などの必要物だけを送るように迫る場合があるので注意が必要です。
被相続人に遺言書を書かせて遺産を独り占めにする
法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。
例えば、「長男に全ての遺産を相続させる」という内容の遺言書がある場合、原則として長男が全ての遺産を相続することになります。
こういった遺言書のルールを悪用し、被相続人をそそのかせて、自身にとって有利な遺言書を書かせる場合があります。
遺産を独り占めにしようとしている場合の対応策
遺産の独り占めに対しては、状況によってさまざまな対応策が考えられます。
それぞれの状況別に対応策を説明します。
被相続人の銀行口座を凍結する
被相続人のキャッシュカードを持っていて暗証番号を知っている相続人がいる場合、銀行口座から被相続人のお金を引き出されてしまう可能性があります。
被相続人が亡くなった場合は、早めに銀行口座を凍結するようにしましょう。
銀行口座の口座凍結の手続きは銀行によって異なるので、銀行のホームページを確認するか、直接問い合わせてみてください。
取引履歴を調べて預貯金の使い込みを確認する
銀行でお金の預入れや引出しをした場合、銀行にその取引内容が登録されます。
その取引内容を精査して、預貯金の使い込みが疑われるものがないかを確認してみましょう。
長期間、通帳の記帳がない場合、通帳の記載がまとめられてしまいますが、まとめられた部分について取引履歴の照会を行うことで確認することが可能です。
預貯金の使い込みがある場合には取り戻して遺産分割をする
預貯金の使い込みがあった場合、使い込まれた分を取り戻して遺産分割を行います。
使い込んだ預貯金を隠されてしまうおそれがある場合には、保全手続きによって相手の財産を移転できないようにできます。
取り戻しに応じない場合には、不当利得返還請求として民事訴訟を起こしましょう。
不動産を独り占めしているような場合
実家などの不動産を相続人で共有としているにもかかわらず、相続人の一人が独り占めして利用している場合があります。
そういった場合には、賃料に相当する金銭の支払いを求めることや共有持分を売却することも検討しましょう。
遺言書が無効であることを主張する
他の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合、遺言書の無効を主張できる場合があります。遺言書を無効にできるケースとしては、以下があります。
- 遺言書の方式を満たしていない
- 遺言能力を欠いた状態で遺言書作成が行われた
遺言書の方式にはいくつかの種類がありますが、遺言者が文章を自筆しなければならない自筆証書遺言は、方式を満たしていない可能性が特に高い方法です。
また、遺言書を作成するには遺言能力(遺言書の内容や遺言書によってどのような結果が生じるかを理解する能力)が必要です。
認知症などの状態で遺言書を作成した場合、遺言能力が認められず、遺言書が無効になる可能性があります。
遺言書が無効になるような事情がある場合は、弁護士に相談したうえで遺言の無効を主張しましょう。
遺留分侵害額請求をする
一定の法定相続人には遺産の最低限の取り分を受け取る権利が認められています。
これを遺留分といいます。
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち被相続人の配偶者・子ども(直系卑属)・父母(直系尊属)です。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害するような相続をした相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。
特定の相続人に遺産を独り占めされた場合は、遺留分侵害額請求を検討しましょう。
強引な遺産分割を主張する場合には遺産分割調停を利用
特定の相続人が「親と同居して世話をしていたのは自分だから、自分が全ての遺産を相続する権利がある」など主張することがあります。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員が同意しなければなりませんが、強引な主張をして譲らない場合、協議が成立しません。
相続人だけで話し合いをしてもまとまらない場合、裁判所の手続きである遺産分割調停という方法があります。
遺産分割調停は、裁判官と調停委員という公正中立な立場の第三者を交えて話し合いをして、遺産をどのように分割するかを決める手続きです。
公正中立な立場の第三者を交えて話し合いをすることで、客観的な視点から状況を把握できるようになり、スムーズに協議を成立させることが期待できるでしょう。
さいごに
相続では感情的な主張が優先されがちですが、法律に基づく公平な手続きを行うのが原則です。
母や長男が遺産を独り占めしようとする場合でも、正当な相続権を守るための方法はあります。
相続放棄の強要や勝手な協議書作成など、不当な対応に直面した際は、冷静に対処し、早めに弁護士に相談しましょう。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.27相続手続き代行遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?注意点は?
- 2025.10.22成年後見任意後見制度のメリット・デメリットについて解説
- 2025.09.19遺産分割協議母や兄弟が遺産を独り占めする場合の典型的な手口と法的な対処法
- 2025.08.25相続全般会社経営者(社長)が亡くなった場合の相続手続きはどうなる?