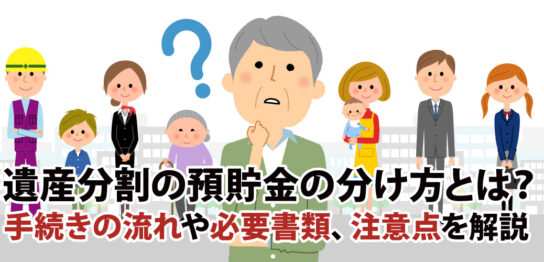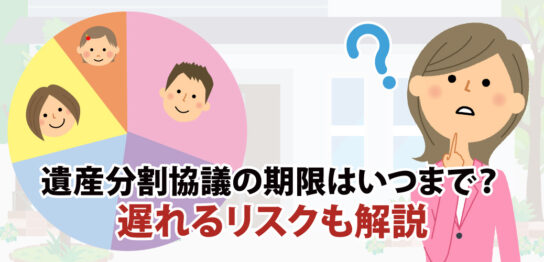- 遺産分割と相続の違いとは?
- 遺産分割の方法とは?
- 遺産分割の流れとは?
【Cross Talk】遺産分割と相続の違いはどこにあるのでしょうか?
遺産分割と相続は、どこが違うのでしょうか?
遺産分割は相続が発生した後に行う相続手続きです。
遺産分割と相続の違いについて、教えてください。
家族が亡くなり複数の相続人が財産を引き継いだ場合には、遺産分割が必要となることがあります。遺産分割と相続という言葉は、一見すると似ていますが、厳密には意味が異なります。それでは、遺産分割と相続の違いとは何なのでしょうか?遺産分割の方法や具体的な分け方、遺産分割の流れはどのようなものなのでしょうか?
この記事では、このような疑問点について、弁護士が解説していきます。
遺産分割とは?

- 遺遺産分割とは?
- 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある
遺産分割とはどのようなものなのでしょうか?
遺産分割とは、遺産を相続人の間で分配する手続きのことです。
遺産分割は、相続が発生した際に、故人の遺産を相続人の間で具体的に分配する手続きです。相続人が1人しかいない場合には、被相続人の遺産は全て相続人が承継し、相続人が2人以上いる場合には、相続人の間で遺産を分け合います。
故人が遺言書を作成していた場合には、原則としてその内容に従い遺産が分割されますが、遺言書がない場合や、遺言書で全ての遺産の分割方法が指定されていない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、双方の合意が必要です。
この話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれ、相続人全員の合意によって成立します。
遺産分割協議では、誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するのかを具体的に決定します。遺産分割は、相続人が複数いる場合に、遺産を公平に分配し、相続人の間のトラブルを防ぐために重要な手続きです。
遺産分割の対象となるのは、故人が所有していた全ての財産です。現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。これらの財産を全て調査し、評価したうえで、相続人の間でどのように分割するかを決定します。
関連記事:遺産分割とは?4つの分割方法や注意点などについて確認
相続とは?

- 相続とは?
- 相続は、相続人の意思とは無関係に発生する
相続とは、どのようなものなのでしょうか?
ここでは、相続の意味や概要について解説していきます。
相続とは、人が亡くなった際に、その方が生前に所有していた財産や権利、義務などを、一定の身分関係にある者が引き継ぐことです。
法律上、相続は故人の死亡と同時に開始され、相続人は、故人の死亡時に存在した財産や権利、義務を全て引き継ぎます。これには、現金や預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続人は、これらの財産を無条件に引き継ぐ単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認、全ての財産を放棄する相続放棄のいずれかを選択できます。
相続は、法律用語としては、故人の財産や権利義務を承継することを意味しますが、一般的には、相続手続き全体や、法定相続分に基づく財産承継など、より広い意味で使用されることがあります。
遺産分割と相続の違い

- 遺産分割と相続の違いとは?
- 相続が発生した後に、遺産分割を行うことになる
それでは、遺産分割と相続とはどこが違うのでしょうか?
ここでは、遺産分割と相続の違いについて解説していきます。
相続と遺産分割は、どちらも故人の財産を引き継ぐ手続きですが、その性質は大きく異なります。相続は、故人の財産や権利義務を包括的に承継する法律上の制度であり、故人の死亡と同時に発生します。一方、遺産分割は、相続人が複数いる場合に、遺産を具体的にどのように分配するかを決定する手続きです。
相続が発生すると、遺産は一旦、原則的に相続人全員の共有財産となります。この状態では、各相続人は遺産全体に対して自身の相続分に応じた権利を持ちますが、個別の財産を自由に処分することはできません。例えば、不動産を売却したり、預貯金を引き出したりするには、相続人全員の同意が必要です。
遺産分割は、この共有状態を解消し、各相続人が個別の財産を取得するための手続きです。相続は遺産を引き継ぐこと自体を指し、遺産分割は引き継いだ遺産を具体的に分けることを指します。遺産分割は、相続手続きの一環として行われる重要な手続きであり、相続人の間で発生する可能性があるトラブルを防ぎ、円満な財産承継を実現するために不可欠です。
遺産分割の2つの方法

- 遺産相続の方法とは?
- 遺言書に従う方法と遺産分割協議による方法
遺産は分け合うためには、どのような方法があるのでしょうか?
遺言書に従う方法と、遺産分割協議による方法があります。
遺言書に従った遺産分割
相続が発生し、遺産を分割する際には、故人の遺言書の有無によって大きく手続きが異なります。 故人が有効な遺言書を残していた場合、遺産は原則として遺言書の内容に従って分割されます。
遺言書は、故人の最終的な意思表示として尊重されるため、法定相続分よりも優先されますが、遺言書の内容が全ての相続人の合意を得られているとは限りません。特に、特定の相続人に偏った遺産分割を指定している場合や、遺留分を侵害している場合は、相続人の間で争いが生じる可能性があります。
この遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の遺産取得分のことで、遺言書によっても奪うことはできません。そして、遺言書の内容に納得できない相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。 また、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。
遺産分割協議に従った遺産分割
故人が遺言書を残していなかった場合、または遺言書で全ての遺産の分割方法が指定されていなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するため、一人でも反対する相続人がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、協議を成立させることができません。
遺産分割協議では、法定相続分にとらわれず、相続人全員が納得できるまで話し合いを行い、自由に遺産の分け方を決めることができます。
しかし、相続人の間で意見が対立し、協議が難航することもあるでしょう。この場合には、弁護士などの専門家に相談したり、家庭裁判所に遺産分割調停や審判をすることも検討する必要があります。
具体的な遺産の分け方

- 具体的な遺産分割のやり方とは?
- 現物分割・代償分割・換価分割・共有分割を解説
遺産を具体的に分けるにはどうすればいいのでしょうか?
ここでは、具体的な遺産の分け方について解説していきます。
現物分割
現物分割は、個々の財産をそのままの形で相続人に分配する方法です。
例えば、不動産は長男が、預貯金は長女が相続するといったものです。この方法は、各相続人が希望する財産を具体的に取得できるというメリットがありますが、財産の評価額が均等にならない場合や、不動産のように分割が難しい財産がある場合には、不公平感が生じる可能性があります。
代償分割
代償分割は、特定の相続人が特定の財産を多く取得する代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払う方法です。
例えば、長男が自宅を相続する代わりに、長女と次男にそれぞれ一定の金額を支払うといったものです。
この方法は、特定の財産を特定の相続人に集中させたい場合に有効ですが、代償金の金額設定や支払い方法について、相続人の間で合意形成が難しい場合があります。
換価分割
換価分割は、相続財産を売却し、売却代金を相続人の間で分配する方法です。
例えば、不動産を売却し、売却代金を相続人の間で均等に分配するといったものです。この方法は、財産の評価や分割が難しい場合や、相続人の間で公平な分配を実現したい場合に有効ですが、売却に伴う税金や手数料が発生する点や、売却価格が予想を下回る可能性がある点に注意が必要です。
共有分割
共有分割は、相続財産を相続人全員の共有名義にする方法です。
例えば、不動産を相続人全員の共有名義にするといったものです。この方法は、相続人の間で財産の分割方法について合意形成が難しい場合に一時的に選択されることがありますが、共有状態が続くと、将来的に財産の管理や処分について相続人の間で意見が対立し、トラブルに発展する可能性が高いため、できる限り避けるべきでしょう。
遺産分割の流れ

- 遺産分割の流れとは?
- 話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停を利用する
遺産分割はどのように進んでいくのでしょうか?
ここでは、遺産分割の流れについて解説していきます。
遺言書の有無を確認する
まず、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書は、故人の最終的な意思を示す重要な書類であり、遺産分割の基準となります。
遺言書は、自宅や貸金庫、公証役場などに保管されている可能性があるため、遺言書の種類によっては、家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があります。
相続人・相続財産の調査
遺言書がない場合や、遺言書で全ての遺産の分割方法が指定されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのためには、まず誰が相続人であるかを確定しなければなりません。
戸籍謄本などを収集し、法定相続人を調査します。また、遺産分割の対象となる財産を全て調査し、財産目録を作成します。これには、不動産、預貯金、有価証券、動産、債務などが含まれます。
遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、各相続人がどの財産をどれくらいの割合で取得するかを話し合い、合意を目指します。
具体的な協議は、対面で行うだけでなく、電話やオンライン会議、書面などで行うことも可能です。
遺産分割調停・審判を申立てる
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。 調停では、調停委員が相続人の意見を聞き、合意形成を支援します。調停でも合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定します。
関連記事:遺産分割調停の必要書類について解説
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で合意に至った場合、または調停や審判で遺産の分割方法が決定した場合、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は、相続手続きに必要な書類であり、相続人全員が署名・捺印します。
まとめ
相続と遺産分割は、どちらも故人の財産を引き継ぐ手続きですが、その性質は大きく異なります。相続は、故人の財産や権利義務を包括的に承継する法律上の制度です。相続が発生すると、遺産は一旦、相続人全員の共有財産となります。遺産分割は、この共有状態を解消し、各相続人が個別の財産を取得するための手続きです。
遺産分割を行うためには、相続人全員の同意が必要となり、1人でも反対する人がいる場合には、分割することができません。
相続人同士の仲が悪くて揉めそうという場合や、実際に遺産分割で揉めている場合には、弁護士に相談することで、スムーズに遺産分割を進められる可能性があります。当事務所には、相続問題に強い弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.27相続手続き代行遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?注意点は?
- 2025.10.22成年後見任意後見制度のメリット・デメリットについて解説
- 2025.09.19遺産分割協議母や兄弟が遺産を独り占めする場合の典型的な手口と法的な対処法
- 2025.08.25相続全般会社経営者(社長)が亡くなった場合の相続手続きはどうなる?