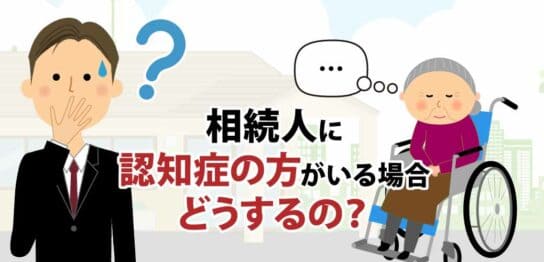はじめに
将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、「任意後見制度」の活用を考える方も少なくないでしょう。
任意後見人には大きな権限が与えられるため、不正を防ぐための監督役が必要になります。
本記事では、任意後見監督人の役割や選ばれ方、報酬、就任の制限などをわかりやすく解説します。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、被相続人の判断能力がなくなったときに財産管理や療養介護のための契約を行う後見人を、被相続人の判断能力があるうちに選んでおくことができる制度のことです。
契約などの法律行為をするための判断能力がない者の行為は無効とされています。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
これらの人の財産管理や療養介護のために、後見制度が定められています。
任意後見制度を利用して選ばれた後見人のことを任意後見人と呼びます。
任意後見監督人とは
任意後見監督人とは、任意後見人を監督し、定期的に家庭裁判所に報告する人のことをいいます。
任意後見監督人の職務は、任意後見契約に関する法律によって以下と定められていいます。
一 任意後見人の事務を監督すること。
二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
引用元:任意後見契約に関する法律 | e-Gov 法令検索
任意後見によって与えられる権限は大きいため、任意後見人が不正をしないか監督するために選任されます。
任意後見監督人の選び方
任意後見監督人選任の申立てをする際に、候補者を推薦することができるようになっています。
ただし、その人が必ず選ばれるわけではなく、本人や候補者の状況に応じて決定します。
そして、最終的に候補者の中から裁判所が決定します。
弁護士や社会福祉法人などの専門家が選ばれることもあります。
任意後見監督人になれない人
任意後見監督人になることができない人については、次のようなものが規定されています。
引用元:任意後見契約に関する法律 | e-Gov 法令検索
任意後見受任者または任意後見人の配偶者や直系血族・兄弟姉妹などは、任意後見人が不正を働いた場合に見て見ぬふりをするおそれがあるからです。
任意後見監督人への報酬
任意後見監督人に就任した人には、被相続人の遺産から報酬が支払われます。
報酬は一律ではなく、任意後見契約の内容によって決定されます。
報酬の目安としては、以下となります。
| 管理財産の額 | 報酬の額(月額) |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 1万円~2万円 |
| 5,000万円を超える | 2.5万円~3万円 |
任意後見監督人選任の手続きの流れ
任意後見監督人を選任する手続きは、以下の流れとなります。
- 任意後見契約の締結
- 任意後見監督人の選任申立て
任意後見契約の締結
まず、任意後見契約の締結をします。
任意後見契約は、法律によって公正証書で行うことが決められています。
引用元:任意後見契約に関する法律 | e-Gov 法令検索
任意後見契約によって、任意後見人を決定し、その内容が登記されます。
任意後見監督人の選任申立て
任意後見契約を締結後、被相続人の判断能力が衰えてきたときに任意後見監督人の選任申立てを行います。
申立ては、被相続人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者が行います。
引用元:任意後見契約に関する法律 | e-Gov 法令検索
申立てをするのは、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
申立てには、申立書・添付書類、収入印紙800円分(手数料)と1,400円分(任意後見の登記のための手数料)、郵便切手(金額は裁判所によって変わる)が必要です。
申立書・添付書類については、管轄の家庭裁判所で取得するか、裁判所のホームページでダウンロードしてください。
さいごに
任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備える有効な手段ですが、任意後見人には大きな権限が与えられるため、第三者による適切な監督が不可欠です。
任意後見監督人は、任意後見人の業務を監視・報告する重要な役割を担い、家庭裁判所によって慎重に選任されます。
制度を正しく理解して、安心できる終活の準備をしましょう。

- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.29相続全般不動産を相続した場合の名義変更はすべき?変更する方法やリスクについて
- 2026.01.28相続全般代襲相続できない場合とは?注意点や対処法を解説
- 2025.10.27相続手続き代行相続人の廃除をしたい場合は遺言書ですればいい?
- 2025.10.27相続全般相続における悩み別の解決方法を確認