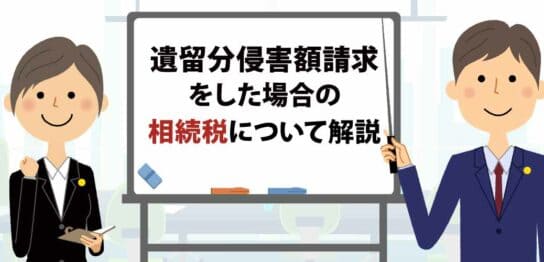親が亡くなった際に、入院費の清算や葬式費用などで大きな出費をすることも少なくありません。
また、親の遺産を相続する場合は相続税なども支払わなければなりません。
相続をするまでにかかった費用が控除されるのか疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では、相続にかかった費用のうち、どこまでが「経費」として遺産から控除できるのかを解説します。
また、親の遺産を相続する場合は相続税なども支払わなければなりません。
相続をするまでにかかった費用が控除されるのか疑問に思う方もいるでしょう。
本記事では、相続にかかった費用のうち、どこまでが「経費」として遺産から控除できるのかを解説します。
目次
遺産から控除してもらえるものとは?
どういった費用が相続税の計算から控除されるのか、またされないのかということを解説します。 相続税法には以下のように記載されています。
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
相続は死亡によって開始するので、「被相続人の債務で被相続人の死亡の際に現に存するもの」というのが前提になります。
したがって、被相続人の死亡の際に現に存するとはいえないものや、被相続人自身の債務とはいえないものは、該当せず控除は認められません。
ほかの相続人や遺産の調査費用や相続税申告のための税理士費用などは、基本的に被相続人が亡くなったあとに発生したものであり、被相続人の債務でもありませんので、控除の対象にはなりません。
葬式にかかった費用の控除に関する注意点
葬式に関連してさまざまな費用がかかりますが、なかには葬式費用でも控除対象に含まれないものがあります。たとえば、香典返しは葬式費用に含まれません。
葬儀に関連する費用には、さまざまな性質のものが含まれます。
✓斎場の使用料
✓遺体の運搬料
✓火葬にかかる費用
✓お寺への謝礼
✓会食(通夜ぶるまい、精進落とし)
✓香典返し など
しかし、相続税法では「葬式費用」と定めるだけで、葬儀に関連するどのような費用が「葬式費用」に含まれるかが明らかではありません。
国税庁では以下のようなものが「葬式費用」になると考えられています。
(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
引用元:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
これに対して、次のようなものは「葬式費用」に含まれません。
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
引用元:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
引用元:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
香典返しは葬儀に関連する費用ではないかと思う方もいるかもしれません。(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
引用元:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
しかし、香典は喪主(葬儀の主催者)に対する贈与であり、遺産ではないと考えるのが一般的です。
そうなると、香典に対する返礼である香典返しも遺産から切り離して考えるべきでしょう。
控除される債務について
葬式費用のほかに遺産から控除される対象として、被相続人の債務があります。 ただ、控除の対象になるのは相続を開始したときに確実に存在したといえる債務に限られます。代表的なものとしては、金融機関からの借入金、公租公課、入院・入所していた病院・施設の費用などが挙げられます。 しかし、被相続人自身が借入をしたのではなく第三者の債務を保証している場合は、借入をした本人(主債務者といいます)が約定どおりに弁済をすればいいわけですので、原則として控除の対象になりません。
ただし、相続開始時に主債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその保証債務を履行しなければならない場合で、かつ、主債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主債務者が弁済不能の部分の金額を保証債人の債務として控除することが認められています。
(保証債務及び連帯債務)
14-3 保証債務及び連帯債務については、次に掲げるところにより取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
(2) 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(以下14-3において「弁済不能者」という。)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。
引用元:第13条《債務控除》関係|国税庁
14-3 保証債務及び連帯債務については、次に掲げるところにより取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
(2) 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(以下14-3において「弁済不能者」という。)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。
引用元:第13条《債務控除》関係|国税庁
また、被相続人の生前に購入した墓地、墓碑、仏壇等の代金が未払いになっている場合でも、代金の支払 債務を控除することはできません。
3 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
(墓碑の買入代金)
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないのであるから留意する。
引用元:第13条《債務控除》関係|国税庁
これらの遺産は、祭祀財産といって遺産とは異なる扱いをされており、相続税の課税価格に参入されません。
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないのであるから留意する。
引用元:第13条《債務控除》関係|国税庁
(相続税の非課税財産)
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
そのため、これらの遺産の未払い代金のみを遺産から控除することはできないのです。
第十二条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索
さいごに|控除されるものとされないものを正しく理解しよう
遺産から控除される経費について解説しました。 控除されるもの、控除されないものを正しく理解して、適正な相続税の申告をするようにしてください。 判断に迷った場合は、相続に詳しい弁護士または税理士に相談することをおすすめします。
遺言や相続でお困りの方へ

分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。

- 相続税対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続税について相談できる相手がいない
- 税務署に調査されないように申告をしたい
- 税務署から通知が届いて困っている
初回相談
無料
無料
法律問題について相談をする
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.06.20遺産分割協議遺産分割協議成立後に新たな相続人が発覚!協議はやり直しになる?
- 2025.06.13遺留分侵害請求生命保険は原則として遺留分の対象ではない?例外ケースや基準を解説
- 2024.05.20相続手続き代行相続登記に必要な相続関係説明図とは?書き方は?
- 2024.04.20遺留分侵害請求兄弟が相続人になる場合とは?相続分・遺留分とともに解説