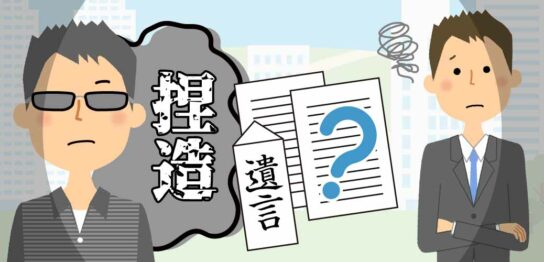- 遺言能力がない、遺言書の形式・要件を満たしていない場合は無効になる
- 遺言書を無効だと主張する場合はまず相続人全員で話し合う
- 意見がまとまらない場合には、調停・訴訟へ発展する
【Cross Talk 】日付が書かれていない遺言書は無効にできる?
母が亡くなり自宅で遺言書が見つかりましたが、日付が書かれていません。法的に有効なのでしょうか?
自筆証書遺言の要件を満たしていないので無効となります。無効にしたい場合は、まず相続人全員で話し合うことになります。
詳しく教えてください!
遺言書は遺言能力がある方が書き、法的な要件を満たしたものが有効となります。 よって、認知症で判断能力が低下している方が作成した遺言書や、遺言者の署名・押印がない遺言書は無効にすることができます。 本記事では遺言書が無効になる2パターンと無効にしたい場合の手続方法について解説いたします。
遺言書が無効になる場合

- 認知症など判断能力が低下している状態で書かれた遺言書は無効となる可能性がある
- 民法に規定された形式・要件で作成されていない遺言書は無効にできる
遺言書が無効になる場合を教えてください。
遺言者に遺言能力がない、民法の規定を満たしていない場合には無効となる可能性があります。
遺言能力がない場合※1
民法963条では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」との規定があります。加えて、同法961条では「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」という文言があります。 基本的に15歳以上の方は遺言書を書くことができますが、「遺言能力」は年齢だけではありません。 自身が遺言書に書いたことが実行されるとどのようなことが起こるのか、判断する能力を有している必要性があります。よって、高齢や認知症により、遺言書の有効性が問われる場合もあります。遺言書の形式を満たしていない
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があり、それぞれ民法で定められた形式や内容で作成しなければなりません。こちらの記事でも詳しく解説しているので、気になる方はこちらもご確認ください。 そんなに難しくない?自筆証書遺言の書き方(メリット・デメリット)
なお、遺言書が法的に無効であるからという理由で「遺言書通りの相続ができない」という訳ではありません。相続人全員が遺言者の意向を汲み遺言者の内容通りに相続することに納得している際には、遺言書に沿った相続も可能です。遺言書の内容が不明確
遺言書の中に内容が不明確な条項がある場合、その条項は無効となります。
例えば、遺産に複数の不動産が含まれる場合に「○○に不動産を相続させる」という遺言書が作成されたとすると、どの不動産を相続させるのか特定できず、その条項が無効になる可能性があるのです。
偽造されている
文書の作成名義人ではない方が、名義人の名を騙って文書を作成することを「文書の偽造」といいます。
他人の名を騙って他人名義の自筆証書遺言を偽造した場合、遺言者が全文を自書するという自筆証書遺言の要件を満たさないので、遺言書は無効となります。
関連記事:遺言が偽造・変造されたかも?遺言当事者としてどのように争う?
遺言書を勝手に開封すると無効?

- 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続をしなければならない
- 勝手に開封しても遺言書が直ちに無効になるわけではない
封筒に入った遺言書を見つけた場合、内容が気になってつい開けてしまいたくなりますが、勝手に開封してもいいのでしょうか?
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続をしなければならず、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人やその代理人立ち会いの下で開封することとされています。そのため、勝手に開封してはいけません。もっとも、開封したことを理由に直ちに遺言が無効になるわけではありません。知らずに開封してしまった場合には速やかに家庭裁判所に検認の請求をしてください。
自筆証書遺言の要件は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することですが、実際には作成した遺言書を封筒に入れ、封じ目に遺言書作成に使用した印章で押印する(封印する)のが一般的です。
封印された自筆証書遺言を保管、発見した場合、遺言書の内容が気になってつい無断で開封してしまう方も少なくありません。
自筆諸所遺言の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければならないとされています。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封することができません。
もし家庭裁判所への遺言書の提出を怠ったり、家庭裁判所外で開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
もっとも、「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではないとされています。
参照元:裁判所「遺言書の検認」
そのため、勝手に開封してしまったとしても、そのことから直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
なお、検認の手続が必要であることを知らずに開封してしまった場合であっても、その後の遺言書の改変を防止するために、検認の請求をしなければなりません。
遺言書を無効だと主張する場合の手続き

- 遺言書を無効だと主張する際にはまず相続人全員で話し合う
- 話合いがまとまらないときには調停や訴訟を検討する
相続人全員で遺言書について話し合いましたが、意見が分かれています。
相続人全員が合意に至らないときには、調停や訴訟を検討してみましょう。
相続人の間で話し合い
遺言書の有効性について、相続人の間で話し合います。 遺言書が無効であることに相続人全員が合意したうえで、遺産をどう分けるかまとまれば、協議が成立します。一方で、意見がまとまらない場合には調停で話し合いを行います。 家事事件(離婚や相続など家庭内の紛争)は基本的に「調停前置主義」が採用されており、いきなり訴訟をするのではなく、まずは、調停手続きで、当事者・調停委員・裁判官を交えて話し合いでの解決を試みることになります。 それでも話がまとまらない場合には、訴訟手続きに移行します。もっとも、多くの場合、遺言書が無効であることを話し合いで解決できることはほとんどないと思います。 話し合いでの交渉が難しそうであれば、弁護士に依頼した上で、すぐに調停・訴訟を検討する方が良いでしょう。
なお、明らかに調停が成立する見込みがない場合には、いきなり訴訟を起こすことも可能です。調停の申立て
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停手続では、遺言書の有効性を含め、遺産分割について話合いができます。 調停委員と裁判官が当事者間から事情を聴く、資料を提出してもらうなどの方法で事情を把握し各当事者の意向を聞いた上で解決策の提示や助言などを行います。遺言書の有効性に関して、例えば遺言者が高齢・認知症で無効であると主張する場合には医師の診断書といった参考資料を提出する可能性があります。 調停では遺言書の有効・無効に関してだけではなく、全員が合意する遺産分割を目標として話し合いを進められます。
話し合いがまとまらず調停が不成立となった際には遺言無効確認訴訟を起こします。遺言無効確認訴訟
遺言無効確認訴訟の管轄は地方裁判所であり、地方裁判所に訴訟の手続を行います。 訴訟手続の進行は事案によって様々ですが、長期にわたる手続となる可能性が高い印象です。 例えば、認知症が進行した状態で遺言書が書かれたものとして遺言能力がないことから遺言無効確認訴訟を提訴した場合、当時の精神状況を裁判所が判断することになります。 医療記録を取り寄せて主張立証し、被相続人の担当医を尋問するなど複雑な過程を経ることになるためです。 難しい訴訟になりますので、遺言無効確認訴訟でなければ解決できないような場合には、弁護士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。まとめ
遺言書が無効になる場合と無効だと主張する際の流れについてお伝えしてきました。遺言者に遺言能力がない、法的な要件を満たしていない遺言書は無効となる可能性があります。 遺言書の有効・無効の判断を行うことは難しく、ただでさえやるべきことが多い相続の場面では相続人の負担となってしまうことがあります。 遺言書の有効性について疑問を感じた場合には、まず相続に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。


- 遺言書が無効にならないか不安がある
- 遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい
- 独身なので、遺言の執行までお願いしたい
- 遺言書を正しく作成できるかに不安がある
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.06.20遺言書作成・執行遺言書を無効にしたい!必要な手続きについて確認
- 2025.02.25遺産分割協議遺産分割調停の必要書類について解説
- 2024.11.05遺言書作成・執行遺言書の必要性が分かる4つのケースについて解説
- 2024.07.16相続手続き代行未支給年金は相続放棄をしても受け取れる!相続放棄のルールの確認とともに解説