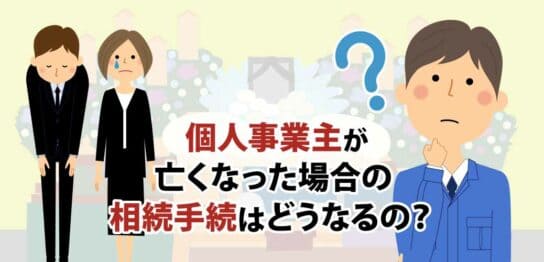はじめに
「親が入院している間に口座から生活費を引き出してもいいのか」
「亡くなる前にお金を動かすと相続で問題になるのか」
相続を控えた親がいる場合、このように悩む方は少なくありません。
預貯金は相続財産に含まれるため、生前に引き出したお金の扱いによっては、相続人同士のトラブルや法的な問題につながることがあります。
場合によっては「使い込み」とみなされ、後々に返還を求められる場合もあるため注意が必要です。
本記事では、生前に預貯金を引き出すことのリスクや法的な位置づけ、相続における扱いについてわかりやすく解説します。
親の預金は相続財産に含まれる
前提として、親の預金は相続財産に含まれます。
そのため、親が亡くなる前はもちろん、亡くなったあとも一部の相続人が勝手に親の貯金を引き出して使うことは認められていません。
親の預金を勝手におろして使うと、あとになって不当利益返還請求や賠償請求を受けるおそれがあるほか、遺産分割の際に自分の相続分が少なくなる可能性があるので注意しましょう。
なお、親が亡くなると預金口座は凍結されるため、原則として親族であっても勝手に預金を引き出すことはできません。
親が亡くなる前に預金をおろすとどうなる?
財産を管理していた方が預貯金を引き出し、病院代や施設代など亡くなった方のために使った場合、相続人の預貯金で相続人の債務を弁済したことになります。
そのため、引き出した預貯金は相続財産にはなりません。
あくまでも「親の代わりに使った」ということになるので、相続で不利になったり、他の相続人から何かしらの請求を受けたりすることもないでしょう。
引き出した方が自己のために使った場合
財産の管理を任されていた方が亡くなった方の預貯金を引き出し、勝手に自分のために使っていた場合、正当な理由なく亡くなった方の財産から利益を得ていたことになります。
そのため、他の相続人はその方に対して不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
また、遺産分割の際にすでに引き出された分の預貯金について考慮され、引き出した人の相続分が少なくなる可能性もあります。
生前に引き出した財産を死亡した方が贈与していた場合
財産を管理していた方が、生前に引き出した預貯金について亡くなった方から贈与を受けることがあります。
この場合、贈与の際に贈与契約書などが作成されており、贈与があったことを証明できれば問題ありません。
ただ、通常は財産を管理している方と亡くなった方との間には親子など親族関係があるので、贈与契約書などが作られないことも多いです。
また、財産の管理を任せるのは亡くなった方が心身に問題を抱えていることが多いことから、亡くなった方の真意に基づく贈与かどうかが争いになることも少なくありません。
さらに、仮に亡くなった方の真意に基づく贈与であったとしても、相続財産の額や贈与の額によっては、贈与によって他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。
遺留分を侵害している場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあるほか、遺留分を侵害していなかったとしても、
遺産分割協議のなかで特別受益の主張を受け、遺産分割で得られる遺産が少なくなる可能性もあるでしょう。
親の生前に預金を引き出す際の注意点
どのような理由であれ、親が亡くなる前に預金をおろすと後々トラブルに発展するおそれがあります。
そのため、生前に親の預金からお金を引き出す際は、以下のような対策を講じるのがおすすめです。
- 相続人全員に相談し、できれば許可を得ておく
- 領収書・レシートをなるべく残しておく
- 領収書・レシートを残せない場合にはメモなどを残しておく
このように、引き出したお金の用途を全員が知っていて、用途に関する客観的証拠がある状態にしておくことが望ましいです。
死亡後に預貯金を引き出す方法
親の生前に病院代や施設代を代わりに支払っていた方の中には、親の死後にもこれらの支払いが必要で、親の預貯金からお金を引き出したいという方も多いでしょう。
しかし、親の死後は預金口座が凍結されるため、親族であっても簡単にお金をおろすことはできません。
そこで、ここからは親の死後に預金を引き出す方法を解説します。
一定額の預貯金払戻し制度を利用する
いくら親の預金であっても、遺産分割を前に一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。
しかし、被相続人の生前の病院代や施設代、あるいは葬儀費用などを被相続人の預貯金で支払いたいと考える相続人は少なくないでしょう。
そこで、現在では一定の要件のもとで遺産分割前に一定の範囲の預貯金を引き出せる制度が新たに作られています。
まず、民法の改正によって新たに認められたのが、「遺産の分割前における預貯金債権の行使」です(民法909条の2)。
これによって各共同相続人は、預貯金債権の債権額の1/3に相続分をかけた額については、単独で権利を行使することができることになりました。
例えば、預貯金の額が750万円であり、Aという相続人の相続分が1/2であった場合、Aは750万円の1/3にあたる250万円に自身の相続分である1/2をかけた125万円について、単独で権利を行使することができます。
ただし、この権利行使は、債務者ごとに法務省令で定められた上限(現在は150万円)までしか認められません。そのため、上の例で預貯金の額が1,500万円であった場合、Aの権利行使が認められるのは、その1/3にAの相続分1/2をかけた300万円ではなく、上限である150万円までということになります。
次に、家事事件手続法の改正によって、遺産分割前の預貯金債権の仮分割仮処分の制度が新設されました(家事事件手続法200条3項)。
この仮処分は、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときに、他の共同相続人の利益を害しない限り、
預貯金債権の全部または一部を仮に取得させるというものです。
民法に定められた預貯金債権の行使と比較すると、以下の3点で違いがあります。
- 預貯金債権の仮分割仮処分の制度では裁判所の関与が必要であるのに対し、民法上の預貯金債権行使は裁判外で単独で行使可能である
- 預貯金債権の仮分割仮処分の制度では預貯金債権行使の必要性が要件とされるのに対し、民法上の預貯金債権行使は必要性が要件とされていない
- 預貯金債権の仮分割仮処分の制度では、事案によっては預貯金債権の全部を取得することも可能であるのに対し、民法上の預貯金債権行使には上限がある
このような両者の違いからすると、相続財産である預貯金を引き出したい場合、まず民法上の預貯金債権の行使によって迅速に預貯金を引き出すことを検討し、それでも不足する事情がある場合には預貯金債権の仮分割の仮処分を利用するというのが一般的だと考えられます。
遺産分割協議後に預貯金を引き出す
親の死後に遺産分割協議等が成立した場合は、次のような必要書類を金融機関に提出することで、預貯金を引き出せます。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名、押印のあるもの)
- 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
これらの書類によって、被相続人が死亡したことや相続人の範囲および相続人全員の協議によって預貯金の分割方法が明らかになるので、預貯金を引き出すことができるのです。
なお、相続人の間での協議ではなく、家庭裁判所の調停または審判で遺産の分割方法を決めた場合、遺産分割協議書の代わりに家庭裁判所が作成する調停調書や審判書(及び確定証明書)を提出することになります。
この場合、被相続人の死亡の事実や相続人の範囲などは、調停または審判の手続きにおいて家庭裁判所がチェックしているので、改めて金融機関から被相続人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を要求されることはありません。
さいごに
親の生前に預金を使った場合、どんな目的でお金を使ったのか次第では、他の相続人とトラブルになるおそれもあります。
そのため、親の預金から何らかの支払いを予定している場合は、事前に他の相続人も事情を説明し、証拠を残したうえで使うようにしましょう。
また、もし他の相続人から親の生前に使ったお金について、使い込みなどを疑われている場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.09.25遺産分割協議相続人以外の人が遺産分割協議に参加するケースについて解説
- 2025.09.22相続全般親が亡くなる前に預金をおろすとどうなる?預貯金の相続について弁護士が解説
- 2025.02.19相続放棄・限定承認空き家となる不動産を相続放棄する場合の注意点などについて解説
- 2025.02.19相続全般孫が相続人になる場合と注意点について解説