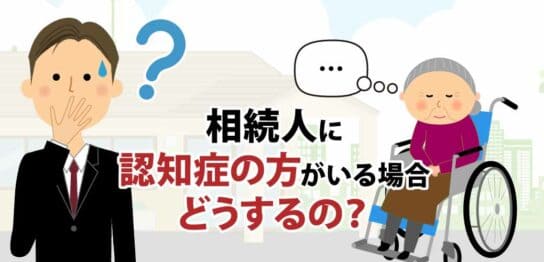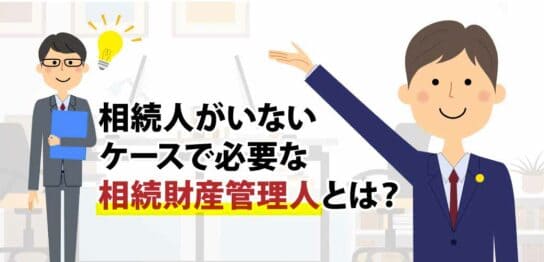はじめに
「相続人同士で遺産をどう分けるか」を決める際、避けて通れないのが「遺産分割」と「遺留分」という2つのポイントです。
遺産分割は相続財産の具体的な分け方を話し合う手続きですが、たとえ遺言があっても、一定の相続人には最低限の取り分である遺留分が法律で保障されています。
しかし、この2つの制度がどう関係するのか、実際の相続の場面でどのように影響し合うのかは、意外と知られていません。
本記事では、遺産分割と遺留分の基本的な仕組みや、それぞれの違い、そして遺留分侵害があった場合の対処法までをわかりやすく解説します。
相続トラブルを防ぐためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続が開始したあとに、被相続人の財産を相続人で分けることをいいます。
民法906条では、遺産分割に関して以下のような規定があります。
引用元:民法|e-GOV法令検索
遺産分割では遺産の種類や特性だけではなく、各相続人の生活状況や職業・年齢・健康状態にも配慮しなければなりません。
例えば、相続人の中に認知症を患っている方がいて、かかりつけの医師に判断能力が不十分と診断されたときには後見人を選任します。
また、遺産分割協議では相続人全員が同意しなければならず、一人でも欠けている場合は遺産分割自体が無効となります。
遺産分割についての詳しい内容は「遺産分割とは?遺産分割で困ったら弁護士に相談!」でも解説しているので、確認してください。
遺産分割の種類
遺産分割の方法には、遺産を現物のまま分ける現物分割、相続人のうち1人が代表して遺産を相続したうえで他の相続人には金銭または相応の遺産を譲る代償分割、遺産を売却した代金を分ける換価分割、遺産の名義を共有にする共有分割があります。
不動産・貴金属など現物の遺産を分割する際には、遺言または遺産分割協議によって、上記の4つの方法からいずれかを選択します。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の親族(兄弟姉妹を除く)に定められた遺産の最低限の取り分を指します。
例えば、相続した遺産額が認められている遺留分に満たない場合は、遺留分の額と相続した額の差額について、他の相続人に対して金銭での支払いを求めることが可能です。
ただし、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子ども(子どもが亡くなっている場合は孫)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)のみです。
兄弟姉妹は、被相続人の配偶者や子どもなどと同様に法定相続人にあたりますが、遺留分の権利はありません。
民法では、遺留分を以下のように定めています。なお、遺留分権利者の取り分は、基本的には以下の割合に法定相続分を乗じた割合になります。
| 遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 相続人が直系尊属(父母など)のみ | 遺留分算定の基礎となる財産の1/3 |
| 相続人が配偶者や子どもなど上記以外 | 遺留分算定の基礎となる財産の1/2 |
遺留分侵害額請求とは
遺言書等の内容が遺留分の額を下回っており、相続人の間の話し合いでも解決できない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てることができます。
遺留分侵害額請求の対象は被相続人による生前贈与・死因贈与や遺贈であって、遺産分割協議は含まれません。
そのため、遺留分侵害額請求の権利は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始のときから10年を経過したときに、時効によって消滅してしまいます。
期間内に遺留分侵害額請求を行う意思表示および調停申立てを行い、調停委員や裁判官を交えて解決に向けて話し合いを行いましょう。
調停でも意見がまとまらない場合には、訴訟を起こす流れとなります。
遺留分侵害額請求についての詳しい内容は「遺留分侵害額(減殺)請求権とは?行使方法は?時効は?」でも解説しているので、参考にしてください。
遺留分を侵害している場合の具体例
遺留分侵害額を算出する際は、生前贈与や相続債務を考慮するために一定の計算式を用います。
以下では、遺言に基づいた相続によって配偶者(A)が子どもの遺留分を侵害している場合について、子ども(B)が請求できる遺留分侵害額を計算してみましょう。
相続人:配偶者A、子どもB、子どもC ※子どもはいずれも成人
相続財産の価額:5,000万円
遺産の分割内容:Aが4,600万円、BとCが200万円ずつ
相続開始から1年前までの生前贈与の価額:1000万円
相続債務:400万円
まず、遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は「相続開始時の財産の価額(遺贈の分も含む)+被相続人が生前に贈与した財産の価額-相続債務」と計算します。
なお、「被相続人が生前に贈与した財産の価額」に算入される贈与は、一般的には相続開始前の1年以内のものに限定されますが、相続人に対して行われた場合は相続開始前の10年以内になされた「婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本」としてなされた贈与が含まれます。
また、贈与の当事者双方が遺留分権利者に対して侵害を与えることを知って行った贈与については、相続開始前であれば無制限に含まれます。
つまり、上記の例においては、遺留分の算定の基礎となる遺産の価額は、5,000万円+1000万円-400万円=5,600万円となります。
次に、遺留分の額は「遺留分算定の基礎となる遺産の価額×総体的遺留分×相続分割合」で算定します。
民法1042条で規定されている遺留分は遺産全体に対する割合(総体的遺留分)であり、相続人が複数いる場合には総体的遺留分に法定相続分を乗じた割合が実際の遺留分となります。
上記の例では、配偶者と2人の子どもが相続人である場合、総体的遺留分は1/2、法定相続分は、配偶者Aが1/2、子どもBと子どもCはそれぞれ1/4です。
そのため、子どもBの個別的遺留分を計算すると、5,600万円×1/2×1/4=700万円となります。
そして、遺留分侵害額は、計算した遺留分の額から遺言や遺産分割協議で決められた自身の取り分を差し引き、自身の相続債務(相続債務×法定相続分で計算されます)を加算した金額です。
よって、上記のケースにおいて、子どもBが請求できる遺留分侵害額は、700万円-200万円+(400万円×1/4)=600万円ということになります。
遺産分割と遺留分の関係
ここまで、遺産分割と遺留分について解説してきましたが、実際の遺産分割の際はどのように遺留分を考慮すべきなのでしょうか。
ここからは、遺産分割と遺留分の関係について、詳しく解説します。
遺産分割の内容が遺留分を侵害する場合でも相続人全員が合意していれば問題にならない
遺産分割の内容が1人または複数の相続人の遺留分を侵害するような不公平な分配でも、相続人全員が合意している場合には遺産分割協議は成立します。
ただし、後のトラブル回避と手続きのためには、協議後に遺産分割協議書を作成しておくことが不可欠です。
仮に口頭で遺留分を侵害した遺産分割に合意したとしても、それを証明できるものがなければ、あとになって遺留分侵害額請求をされるおそれがあるので注意しましょう。
なお、「遺留分を放棄したい」という推定相続人がいる場合、被相続人が生きているうちは、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可」を申請することも可能です。
不公平な遺産分割案を提示されたときにはどのように対応すればよいか
不公平な遺産分割案を提示されたときにはどのように対応すればよいのでしょうか。
例えば、兄弟である長男から「すでに結婚して独立した生計を立てているので、遺産分割では形見程度のもの以上の主張はしないように」と主張される場合があります。
しかし、相続人が長男ではなかったとしても、被相続人の子どもである以上は長男と同じ法定相続分があり、このような主張をされるのは不公平です。
しかし、遺産分割と遺留分は別の制度なので、長男からの遺産分割案の提示に対して遺留分侵害額請求をすることはできません。
そのため、このような主張をされた場合には、遺産分割協議において、最低でも法律で決められた分の遺産は取得したい旨をきちんと主張しましょう。
主張した結果、話がまとまらずトラブルに発展しそうな場合は、早めに弁護士に依頼して交渉を依頼したり、調停を申立てたりする方法で解決を目指すのがよいでしょう。
なお、遺産分割の際に、他の相続人から「手続きをしてしまうので実印と印鑑証明書を送ってほしい」と主張されることもあります。
このような場合、不公平な遺産分割が勝手に行われることが予想されるため、安易に実印と印鑑証明書を渡してはいけません。
不公平な遺産分割協議が成立してしまった場合、遺産分割をやり直せるか
不公平な遺産分割協議でも同意をした以上、遺留分侵害額請求はできませんが、次のような場合には遺産分割のやり直しができることがあります。
取消・無効原因がある
遺産分割の合意に取消・無効原因がある場合には、遺産分割をやり直すことができます。
遺産について重大な勘違いをしていたり、他の相続人に騙された・脅されたりしたような場合、民法95条または96条によってその遺産分割の内容を取り消してやり直すことができます。
また、協議に参加していない相続人がいたり、一部の相続人が認知症などで意思能力がなかったりした場合には、遺産分割が無効であるという主張が可能です。
無効原因があると遺産分割が成立していないことになるので、遺産分割をやり直す必要があります。
共同相続人全員の合意がある
遺産分割後でも、共同相続人全員の合意のもと、遺産分割をやり直すことはできます。
遺産分割をやり直す場合の注意点
一度決まった遺産分割を変更すると、新たな贈与や財産の譲渡とみなされ、贈与税や譲渡所得税がかかる可能性がある点に注意しましょう。
また、当初の遺産分割で第三者に譲渡された財産については、たとえやり直しが決まっても返還を求めることはできません。
さらに、相続開始から10年が経過すると、「特別受益」や「寄与分」といった主張が原則として認められなくなるため、遺産分割の見直しは早めに行うことが重要です。
遺産分割協議を申し入れた場合、遺留分侵害額請求の意思表示となるか
遺言によって相続人の遺留分が侵害されていたとしても、遺産分割協議を申し入れただけでは、遺留分侵害額請求をしたことには基本的にならないとされています。
これは、「遺産分割」と「遺留分侵害額請求」とでは、法的な仕組みや効果が異なるためです。
ただし、以下の3つの条件を全て満たすケースでは、例外的に遺留分侵害額請求の意思表示が含まれると判断されることがあります。
- ① 被相続人の全財産が一部の相続人に遺贈された
- ② 他の相続人が遺贈の効力を争わずに遺産分割協議を申し入れた
- ③ 特段の事情がない
このような状況においては、最高裁判所の判例(平成10年6月11日)により、遺留分請求の意思表示があったと見なされる可能性があります。
とはいえ、交渉中に遺留分侵害額請求の時効が過ぎてしまうリスクもあるため、トラブルを防ぐためには、明確に意思表示をすることが大切です。
特に内容証明郵便などで、時効内に遺留分請求の意思を伝えておくことが望ましい対応といえるでしょう。
さいごに
遺留分侵害額請求の権利は相続開始(もしくは遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったとき)から1年、または相続開始から10年を経過したときに消滅してしまいますので注意しましょう。
遺産分割や遺留分で疑問がある方やトラブルを避けたい方、トラブルが起きてしまった際には相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.11.26遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を行う場合の不動産の評価はどのように行うのか
- 2025.10.29相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2025.10.22遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?
- 2025.08.25成年後見成年後見人になる人・なれない人とは?資格は必要?必要な手続きについて