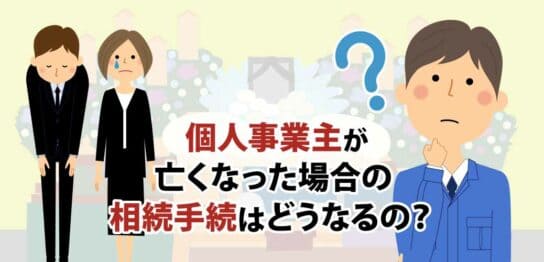はじめに
たしかに、配偶者には大きな相続税の優遇制度があるため、遺産を全て配偶者が相続することで一時的に相続税を節税することが可能です。
しかし、目先の税負担が減ったとしても、その後の相続(二次相続)でかえって税金が増えてしまう可能性があります。
さらに、遺留分などの他の相続人との遺産の分配についても注意が必要です。
本記事では、配偶者が遺産を全て相続することで得られる相続税の節税効果や、注意点などについて解説します。
相続税対策で配偶者が全て遺産を相続した場合の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは、相続や遺贈によって得た遺産の額が一定以内であれば、配偶者に相続税はかからないとする制度です。
ここでの「一定の額」とは、次の2つの額のうち多い方を指します。
• 配偶者の法定相続分相当額
配偶者の法定相続分は、以下のとおりです。
| 共同相続人 | 配偶者の法定相続分 |
|---|---|
| 子ども | 1/2 |
| 両親などの直系尊属 | 2/3 |
| 兄弟姉妹 | 3/4 |
| なし | 全部 |
の制度があるお陰で、配偶者が遺産の全てを相続する場合でも、遺産が1億6千万円以内であれば相続税はかかりませんし、遺産がいくらあっても法定相続分以内で相続をしている限り相続税はかかりません。
そのため、ほとんどの場合で配偶者には相続税がかからず、相続税対策が可能になるのです。
配偶者が遺産を全て相続して税額軽減をする要件
配偶者が税額軽減を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
・ 遺産分割が終了していること
・ 相続税申告書を提出すること
それぞれの要件について、詳しくみていきましょう。
戸籍上の配偶者である
まずひとつめの要件として、戸籍上の配偶者であることが必要です。
つまり、きちんと婚姻届を出して法律婚をしていることが求められます。
この要件を満たさないものとして把握しておくべきなのが、戸籍届を出さなさない「事実婚(内縁)」の状態です。
事実婚は、法律婚に類似する効果を与える場合もあるものの、相続においては相続権がなく、遺言で遺贈を受けていた場合でも配偶者の税額軽減は受けられません。
遺産分割が終了している
配偶者の税額軽減の制度を利用するためには、遺産分割が終了していることが必要です。
「遺産分割が終了」とは、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判のいずれかが完了していることを指します。
ただし、遺産分割調停・遺産分割審判による解決は、相続税の申告期限である10ヵ月を超える可能性が高いです。
このような場合は、いったん配偶者の税額控除を利用せずに相続税申告と納税を行い、遺産分割が終わってから更正の請求によって配偶者の税額控除による訂正を行って納付した税金を還付してもらう必要があります。
相続税申告書の提出
配偶者の税額軽減の制度を利用するためには、相続税申告書を提出する必要があります。
配偶者が税額軽減をする際の必要書類
配偶者の税額軽減をするために特別な書類は必要ありません。
ただし、遺産分割が終わっていない場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出して、後に更正の請求を行います。
配偶者が遺産を全て相続して相続税対策をする際の注意点
配偶者が遺産を全て相続することで相続税対策をする場合は、いくつか注意すべき点も存在します。
・ 遺留分に注意する
・ 兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺言書の作成を検討する
それぞれの注意点について、以下で詳しくみていきましょう。
遺産を相続した配偶者が亡くなったときの相続について考慮する
相続税対策として配偶者に遺産を全て相続させるときは、「遺産を全て相続した配偶者」が亡くなったときの相続税についても考慮しなければなりません。
仮に、夫婦のうち一方が亡くなったときに配偶者控除を利用して節税するために、配偶者が遺産を全て相続したとします。
しかしこの場合、遺産を相続した配偶者自身もいずれ亡くなるため、配偶者が亡くなった場合の相続税もあわせて考えなければなりません。
典型的な例としては、配偶者も資産を所有している場合に、相続で得た遺産と配偶者がもっている資産が合わさった結果、税率が上がる場合が挙げられます。
そのため、節税は個別の制度のみを検討するのではなく、様々な要素を加味して行うことが大切です。
「配偶者に遺産を全て相続させて相続税対策がしたい」と考えている方も、一度税理士に相談して「本当にお得なのかどうか」をよく検討するようにしましょう。
遺留分に注意する
配偶者に遺産を全て相続させる場合、遺留分にも注意しなければなりません。
遺留分とは遺産に対する最低限の取り分のことで、遺留分を有する方を遺留分権利者といいます。
遺留分権利者には被相続人の配偶者、子ども(孫)、直系尊属です。
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害したものに対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
例えば、配偶者が遺産を全て相続した場合、子どもには「頭数×1/2」の遺産が遺留分として認められます。
つまり、遺産の総額が1,000万円で子どもが2人いる場合、子どもは配偶者に対して遺産の1/4にあたる250万円を遺留分として請求することが可能です。
そのため、被相続人としては、配偶者が将来的に子どもに遺留分を請求される可能性を考慮して、あらかじめ遺留分に相当する遺産を遺言で子どもに相続させるなどの工夫が必要となるでしょう。
なお、遺留分については子どもがいる場合以外に、親や孫が相続人となるケースでも問題になります。
詳しくは、以下の記事でも解説しているので参考にしてください。
【関連記事】遺留分とは
兄弟姉妹が法定相続人の場合は遺言書の作成を検討する
被相続人に子どもがおらず、親も既に亡くなっているなどの場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、この場合に配偶者に遺産全てを相続させようとすると、遺産分割協議でトラブルになる可能性が高いので注意が必要です。
その理由として、被相続人の配偶者は兄弟姉妹からみると元々と他人であり、自分の家の相続のことで大きな顔をしてほしくないと反感を抱く場合があるからです。
法的には配偶者には法定相続分や遺留分がありますが、兄弟姉妹が感情的になっていれば話が通じにくくなります。
そして、調停や審判で決着をつけるとなると費用や時間もかかるでしょう。
そこで、配偶者と兄弟姉妹の間の相続トラブルを避けるためには、被相続人があらかじめ遺言で配偶者にどれだけの遺産を遺すか、きちんと意思表示しておくことが重要です。
この点、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので、遺留分を気にすることなく、遺言によって配偶者に全ての遺産を相続させることも可能です。
まとめ
本記事では、相続税対策として配偶者に遺産を全て相続させる場合について解説しました。
配偶者には相続税の特別控除が認められているため、遺産を全て相続させることで一時的に大きな節税効果を期待できます。
しかし、二次相続や遺留分など、配偶者に遺産全てを相続させる場合は注意しなければならない点があるのも事実です。
そのため、相続税対策に悩んでいる場合は、税理士や弁護士に相談し、本当に配偶者に遺産全てを相続させるのがよいのかどうかを検討する必要があるでしょう。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
- 東京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員
- 一見複雑にみえる法律問題も、紐解いて1つずつ解決しているうちに道が開けてくることはよくあります。焦らず、急がず、でも着実に歩んでいきましょう。喜んですぐそばでお手伝いさせていただきます。
最新の投稿
- 2025.09.19遺産分割協議遺産分割協議のやり直しはできる?期限はある?
- 2025.07.23相続全般婿養子の相続について知っておくべきことを弁護士が解説
- 2025.07.22相続全般相続税対策として配偶者が全て相続するのは得策?注意点含めて解説
- 2025.07.22相続全般お墓とか仏壇とかの相続はどうなるの?祭祀財産の相続