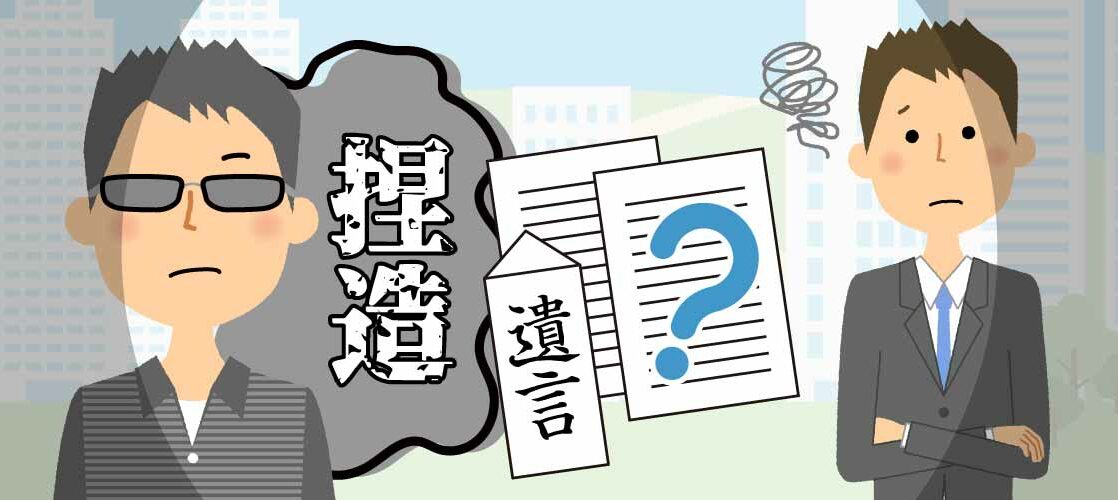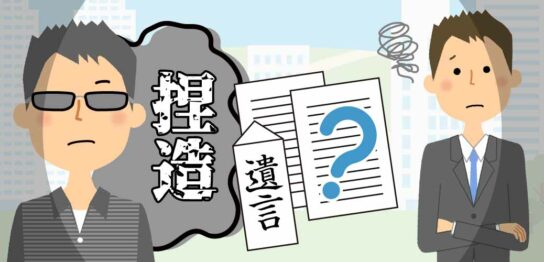相続手続きのなかで、「どうもこの遺言書はおかしい…」「故人が本当に書いたとは思えない」といった疑念が生じることがあります。
もし誰かが遺言書を捏造していた場合、それは重大な法的問題であり、他の相続人としては黙って見過ごすわけにはいきません。
では、遺言の捏造が疑われる場合、どのような主張や対応をすることができるのでしょうか。
本記事では、遺言の捏造が疑われる場合の具体的な主張方法や、法的手段として取り得る対応策について解説します。
遺言の捏造を防ぐためのポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
遺言を捏造した場合の法律関係
遺言書の捏造が発覚した場合は、遺言が無効になるだけでなく、さまざまな法律関係が生じることになります。 ここでは、遺言の捏造によって生じる法律関係について、詳しく見ていきましょう。
捏造された遺言は無効になる
まず、遺言の捏造が発覚した場合、当然その遺言書は法的に無効になります。遺言は本人が自分の意思にしたがって行わなければならないからです。
また、たとえ本人が認知症等によって意思表示をすることができない状況になっても、他人が勝手に遺言を行うことはできません。
検認によって有効になるわけではない
自筆証書遺言や秘密証書遺言がされた場合、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きが行われます。遺言の捏造と聞くと、一見この検認手続きの際に発覚するように思えますが、実はそうではありません。
遺言書の検認は、遺言書の形状や内容の確認を行うのみのため、遺言書の有効性を判断することはできないのです。
遺言書を捏造した相続人は相続欠格になる
遺言書の捏造をしたのが相続人である場合には、相続欠格となります。相続欠格とは、一部の相続人が民法が定める欠格事由に当てはまる場合に、相続をさせるのが不適切な人物として、相続人から除外する制度のことです。
なお、民法891条5号では、相続人の欠格事由について「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」としています。
そのため、相続人が自筆証書遺言や秘密証書遺言を捏造したような場合は、その相続人は相続をすることができなくなるのです。
遺言の捏造は刑事罰の対象
自筆証書遺言や秘密証書遺言を捏造した場合には、刑事事件として刑事罰が科せられる可能性があります。遺言書は私文書にあたり、捏造をした場合には、有印私文書偽造罪が成立するからです。また、捏造された遺言書を利用した場合には、有印私文書行使罪が成立します。
遺言書の破棄も相続欠格や刑事罰の対象
遺言の捏造と同様に、遺言書の破棄が行われた場合も相続欠格になります。また、遺言書の破棄については、私用文書毀棄罪が成立するため、刑事罰の対象となる点にも注意が必要です。
遺言の捏造を争うためには
遺言の捏造が疑われる際に、遺言の無効を争うにはどうすればよいのでしょうか。 ここでは、遺言の捏造が疑われる際にすべきことについて詳しく解説します。
捏造の証拠を集める
遺言が捏造されたものであることを主張するためには、それを裏付ける証拠が不可欠です。例えば、遺言当時に本人が認知症であったなどで、意思表示をすることができなかったというのであれば、遺言をした当時のカルテが証拠になります。
また、自筆証書遺言がある場合には、筆跡鑑定によって捏造を証明しなければなりません。
筆跡鑑定の際は、遺品の中に遺言者が記載した手紙や日記など、本人の筆跡が確認できるものを探して一緒に提出しましょう。
なお、遺言の捏造を証明するための証拠はケースによって異なるので、具体的な証拠の内容や集め方については、弁護士に相談するのがおすすめです。
遺言無効確認の訴え
遺言が捏造であると認定できる証拠が集まったら、裁判所に対して遺言無効確認の訴えを提起します。そして、裁判で遺言が無効であると確認されると、その遺言書を使って相続手続きをすることができなくなります。
被害届の提出刑事告訴
遺言の無効を主張すると同時に、遺言を捏造した人に対して、被害届の提出や刑事告訴をすることも検討しましょう。刑事告訴は、所轄の警察署長宛てに行います。
被害届は単に被害にあったことを申告するものですが、刑事告訴は処罰を求める意思表示を含み、警察が捜査をする義務を負うものです。
刑事告訴については受理をしてもらえないということもあるので、告訴をしたい場合は弁護士に相談をしてみてください。
遺言書の捏造によるトラブルを防ぐためには?
遺言書を捏造されるリスクを回避するには、以下のような方法が有効です。
・公正証書遺言を利用する
・自筆証書遺言書保管制度を利用する
・遺言書を専門家に預かってもらう
公正証書遺言を利用する
遺言の捏造を防ぐには、公正証書遺言を利用するのが一番です。公正証書遺言では、公証人が遺言書の原本を作成し、そのまま公証役場で原本を保管します。
遺言者も遺言書を持ち帰りますが、これは謄本なので捏造しても効力は変わりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する
自筆証書遺言書の捏造を防ぎたい場合は、法務局の遺言書保管制度を利用することを検討しましょう。自筆証書遺言書保管制度を利用すると、原本は法務局で保管されるので、捏造の心配がありません。
なお、公正証書遺言書・自筆証書遺言書保管制度をつかった自筆証書遺言書は捏造の心配がないので、遺言の検認も不要です。
遺言書を専門家に預かってもらう
自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の捏造を防ぐためには、作成した遺言書を専門家に預かってもらうのがよいでしょう。弁護士・行政書士といった遺言作成に関わる専門家は、遺言書の保管サービスを提供している場合があります。
また、遺言執行者に指定している専門家は、遺言執行を行うために遺言書を預かるのが通常です。
専門家に預かってもらうことで、捏造を防止することができます。
さいごに|遺言の捏造を疑ったら弁護士に相談を
本記事では、遺言の捏造について解説しました。
捏造された遺言は無効であることはもちろん、相続できなくなる相続欠格に該当したり、刑事罰が科せられたりといったさまざまな法律問題が生じます。
また、捏造された遺言がある場合、遺言無効確認の訴えを行う必要がありますが、そのためには遺言が捏造されたものであると認定してもらえるだけの証拠が不可欠です。
証拠の集め方や無効の訴えについて、不明な点があれば弁護士に相談することをおすすめします。
遺言や相続でお困りの方へ

分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。

- 死亡後の手続きは何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続人の範囲や遺産がどのくらいあるのかわからない
- 手続きの時間が取れないため専門家に任せたい
- 喪失感で精神的に手続をする余裕がない
初回相談
無料
無料
法律問題について相談をする
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.02.26成年後見任意後見人を選任する場合の費用について解説
- 2024.12.02相続手続き代行遺言の捏造をした方にはどのような主張をすることができるか
- 2024.06.28相続全般交通事故で死亡した場合に保険金や慰謝料は相続できる?相続人は誰?
- 2024.04.20遺産分割協議遺産を母や長男が独り占めしようとしている!その場合の対処法とは?