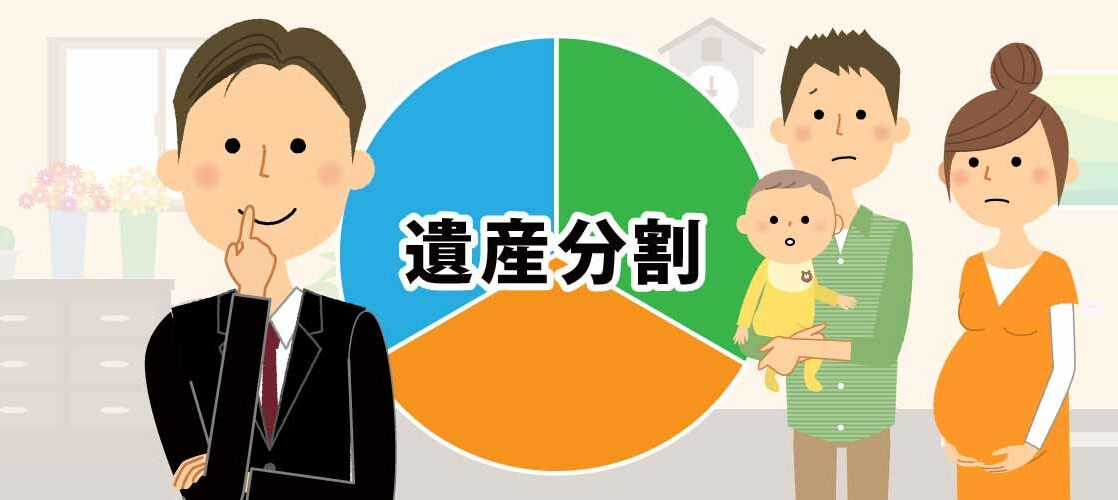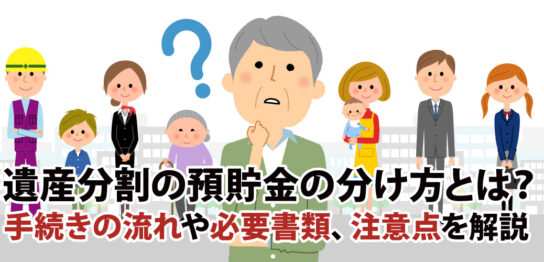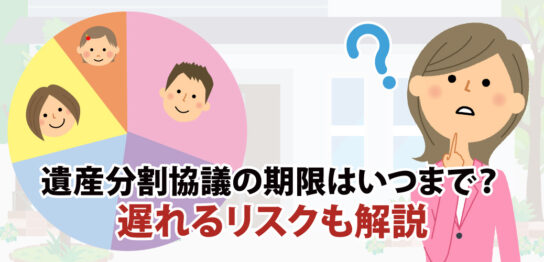はじめに
亡くなった親が遺言書を残していて、遺産相続について家族以外の人の名前が記されていたというケースもあるでしょう。
そんなとき、以下のような不安や疑問を感じる方は少なくありません。
- どのように遺産を分ければよいのだろう
- 相続人以外が遺産分割協議に参加することはあるの?
- 遺留分を侵害された場合はどうなるの?
本記事では、特定遺贈・包括遺贈の違いや相続人以外が相続に関与する場合の注意点について、わかりやすく解説します。
遺言書に書かれた受遺者は遺産分割に関与できる?
遺言によって相続を受け取ることができる人のことを受遺者と呼びます。
また、遺言によって財産を相続人以外の人や団体に譲渡することを遺贈といい、特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈の場合、受遺者は遺産分割に関与できませんが、包括遺贈の場合は相続人と同じ権利をもち遺産分割に参加することができます。
それぞれ詳しく説明します。
特定遺贈
遺言書で「所在地○番○号の不動産」「金融資産のうち○○株式会社の株式を100株」など、財産を特定する遺贈を特定遺贈と呼びます。
特定遺贈の受遺者は特定された財産を取得することは可能ですが、特定の財産以外の取得はできず、遺産分割協議に参加する義務や権利はありません。
特定遺贈が行われる財産は受遺者に所有権が移るため、原則として遺産分割協議の対象外となります。
遺言書で指定された受遺者が特定遺贈を放棄する場合、期間に制限はなく遺贈義務者や遺言執行人に対して遺贈の意思を告げることで放棄が可能です。
包括遺贈
財産の全部または一部を包括的に遺贈するもので、「全財産の○割」といった一定の割合で示されている遺贈を包括遺贈と呼びます。
包括受遺者は相続人と同じ権利をもち、債務を含めた遺産を共有することになります。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
包括遺贈には、全財産を遺贈する「全部包括遺贈」と一定の割合で遺贈する「割合的包括遺贈」があります。
全部包括遺贈の場合には、遺産分割協議にも参加する義務・権利をもちますが、協議を行う必要がないため、遺言書どおりに相続するケースでは遺産分割協議は行われません。
割合的包括遺贈の受遺者は相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加することになります。
ただし相続人とは以下の違いがあります。
① 遺留分がない
② 法人も包括受遺者となる
③ 代襲相続はない
④ 放棄があった場合には相続分は変化しない
また、包括遺贈の受遺者は被相続人に債務・借金などがある場合、マイナスの財産も受け継ぐことになります。
基本的に、マイナスの財産は共同相続人や包括受遺者が法定相続分または包括遺贈の割合に応じて負担となります。
放棄は相続開始から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことで可能です。
遺贈が遺留分を侵害する場合
遺言書によって指定された相続分を「指定相続分」と呼び、基本的には民法で定められた法定相続分より被相続人の意向を記した遺言書が尊重されます。
しかし、遺留分(遺族に定められた最低限の取り分)は遺言書による指定相続分より優先されます。
遺留分は被相続人(亡くなった方)の配偶者、子ども・孫などの直系卑属、父母などの直系尊属にあり、原則として法定相続分の1/2となります。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子ども(直系卑属) | 父母(直系尊属) |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2※1/4 | 1/2※1/4 | - |
| 配偶者と父母 | 2/3※1/3 | - | 1/3※1/6 |
| 配偶者のみ | 全て※1/2 | - | - |
| 子どものみ | - | 全て※1/2 | - |
| 父母のみ | - | - | 全て※1/3 |
兄妹姉妹とその代襲相続人(甥・姪)に遺留分はありません。
遺言書の内容が遺留分を侵害しており、受遺者が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立て、侵害された遺留分の額を受遺者に請求することができます。
相続において相続人以外の人が遺産分割に関与するケース
相続人と包括遺贈の受遺者以外にも、被相続人の特別寄与者、遺言執行者が遺産分割に関与することがあります。
相続人以外に人が遺産分割に関与するケースについて説明します。
特別の寄与をした方
相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者を特別寄与者と呼びます。
特別寄与者は遺産分割において、その寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求することができます。
特別の寄与の有無や特別寄与料に関して、相続人と意見が合わない場合には家庭裁判所で話し合う手続き(特別の寄与に関する処分調停)を行います。
遺言執行者
遺言執行者は遺言書の内容を実現する者で、財産目録の作成や遺言内容の実行などを行います。
遺言執行者は遺言書の内容を実行する権利・義務があるため、遺言書と異なる相続・遺贈を行う場合には遺言執行者の同意を得る必要があります。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
遺言執行者は、基本的に未成年者と破産者以外は誰でも就任できますが、相続人・受遺者など利害関係がある方が遺言執行者になるとトラブルに発展する可能性があります。
そのため、弁護士など第三者の専門家に依頼するケースが多いです。
遺言執行者は被相続人が遺言書で一人または複数人を指定しますが、指定されていない場合や遺言執行者が亡くなった場合には、相続人・受遺者などの利害関係者が家庭裁判所に選任を申立てることが出来ます。
さいごに|遺言書に相続人以外の名前が記されている場合は弁護士に相談
遺言書に相続人以外の名前があると、遺産分割への関与や遺留分の扱いなど、様々な懸念が生まれます。
特定遺贈と包括遺贈の違いや、特別寄与者・遺言執行者の立場を正しく理解することが、円滑な相続手続きには欠かせません。
トラブルが懸念される場合や遺言執行者に専門家を選任したい場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
参考記事:遺産分割協議は相続人以外も参加可能?

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.09.25遺産分割協議相続人以外の人が遺産分割協議に参加するケースについて解説
- 2025.09.22相続全般親が亡くなる前に預金をおろすとどうなる?預貯金の相続について弁護士が解説
- 2025.02.19相続放棄・限定承認空き家となる不動産を相続放棄する場合の注意点などについて解説
- 2025.02.19相続全般孫が相続人になる場合と注意点について解説