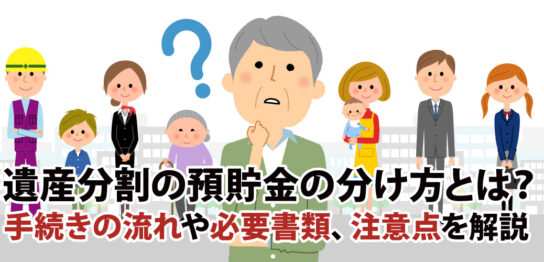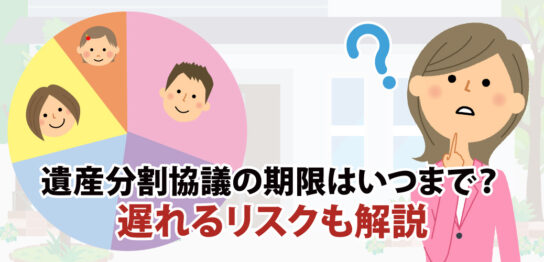はじめに
「祭祀財産の相続ってどうすればいいの?」
故人が遺した「祭祀財産(さいしざいさん)」の取り扱いについて悩んでいる方も少なくないでしょう。
祭祀財産は、遺骨や位牌、墓地、仏壇など、祖先を祀るために用いられる財産のことを指し、預貯金などの一般的な相続財産とは異なるルールで継承されます。
しかし、相続人の間で引き継ぐ人が決まらない場合や、維持・管理の負担が問題になることもあります。
本記事では、祭祀財産の定義や具体的な種類、相続との違い、継承者が決まっていない場合の対応まで、わかりやすく解説します。
遺族間のトラブルを防ぐためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
祭祀財産とは?
祭祀財とは、先祖をまつるために使用される特別な財産のことです。
代表的なものには、遺骨・墓地・仏壇・位牌などがありますが、これらは故人の供養や家系の継承に関わるものであるため、一般的な「相続財産」とは異なる扱いがされます。
民法では、祭祀財産は特定の「祭祀承継者」に引き継がれると定められており、相続人全員で分割する対象にはなりません。
そのため、誰が承継するかを事前に決めておくことが大切です。
祭祀財産の種類
民法では、祭祀財産の種類として以下3つを規定しています。
- 系譜
- 祭具
- 墳墓
それぞれどんなものが当てはまるのか、詳しくみていきましょう。
系譜
系譜とは、先祖から子孫へと続く血縁関係のつながりを表した記録や絵図です。
冊子や巻物としてその家に代々伝わっている家系図や家系譜などが当てはまります。
祭具
祭具とは、祭祀に使用される器具の総称です。
祭具として用いられる器具は宗教や宗派などによって異なりますが、以下のようなものが該当します。
- 仏像
- 位牌
- 仏壇
- 神棚
- 盆提灯
- 霊位
- 十字架
- 庭内神祠
ただし、仏間など建物の一部を構成しているものは原則として祭具に該当しません。
墳墓
墳墓とは、故人の遺体や遺骨が葬られている設備(いわゆるお墓)のことです。
具体的には、墓石、墓碑、霊屋、埋棺などが墳墓に該当します。
ただし、墳墓の敷地である墓地については、墳墓と密接不可分の関係にある範囲に限り、墳墓に含まれるので注意しましょう。
例えば、多くのお墓が存在する墓地の敷地内に墓石を設置した場合、その墓石の周囲の整理された区画だけが墳墓に含まれます。
祭祀財産と相続の関係
祭祀財産は、通常の相続財産とは異なる性質をもつことがわかりました。
では、祭祀財産は相続においてどのように扱うことになるのでしょうか。
ここからは、祭祀財産と相続の関係について、詳しく解説します。
祭祀財産は相続財産とは分けて考える
祭祀財産の承継は、相続財産の相続とは分けて考えなければなりません。
通常、被相続人が亡くなって相続が開始すると、被相続人に属していた相続財産は相続人に承継されます。
相続人が複数いる場合は相続財産を分割してそれぞれが受け継ぎ、相続財産に応じた相続税を支払う必要があります。
一方、祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を承継する者が単独で引き継ぐのが原則です。
その際、祭祀を承継して祭祀財産を引き継ぐ者のことを「祭祀承継者」といいます。また、祭祀財産は相続財産ではないため、相続税は課税されません。
さらに、相続放棄をした相続人は相続財産を相続できなくなりますが、祭祀財産は相続財産に含まれないため、祭祀承継者が相続放棄をした場合でも、祭祀財産の承継が可能です。
原則的に慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継する
祭祀承継者は祭祀財産を引き継ぐだけでなく、祭祀財産を用いて祭祀を主宰し、葬儀や法事などを代表して執り行う役割も担います。
そのため、相続において誰が祭祀承継者になるかは重要なポイントです。
その点、民法では原則として慣習に従って祭祀承継者を定める旨を規定しています。
慣習とは、社会生活上の特定の事項について、反復して行われている「ならわし」のことです。
例えば、ある家で代々長男が法事の代表となることが反復して行われている場合、一般に慣習に該当するといえます。
例外的に被相続人の指定があればそれに従う
例外として、被相続人が祭祀承継者を指定している場合は、慣習よりも被相続人の指定が優先されます。
例えば、ある家では代々長男が祭祀を承継するのが慣習であったとしても、被相続人が次男を祭祀承継者に指定した場合は、長男ではなく次男が祭祀承継者になるのです。
祭祀承継者の指定は遺言書によるのが一般的ですが、遺言書以外の文章や口頭による指定も可能です。
なお、被相続人が祭祀承継者を指定せず、祭祀に関する慣習も明らかでない場合には、管轄の家庭裁判所が祭祀承継者を選びます。
家庭裁判所がどのように祭祀承継者を選出するか、明確な基準は民法に規定されていません。
承継候補者と被相続人の関係、承継候補者の意思や能力、利害関係人全員の状況や意見などの様々な事情を総合的に考慮し、祭祀承継者を選出するのが一般的です。
祭祀財産の承継は拒否できないけど承継したものを処分することは可能
被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選定などによって祭祀承継者が決まった場合、選ばれた者は承継を拒否することは基本的にできません。
祭祀財産の維持や管理、祭祀の実施などには費用がかかりますがそれらの費用も祭祀承継者が負担するのが原則です。
また、祭祀財産に費用がかかるからといって、遺産分割でその費用分を多くもらうことも当然には認められていません。
もっとも、祭祀財産をどのように維持・管理するか、祭祀をどのように実施するかなどは基本的に祭祀承継者の自由です。
極端な話、祭祀財産を処分してもかまいません。
逆にいえば、祭祀承継者の選出を誤ると、代々伝わる祭祀財産を処分されてしまったなどのトラブルが生じる可能性もあります。
そのため、被相続人が指定する前に候補者と十分に話し合っておくなどの工夫が大切です。
遺体・遺骨の取り扱い
祭祀財産には墳墓が含まれますが、中には「お墓に埋葬されている遺骨や遺体はどうなるの?」と疑問を感じる方もいるでしょう。
ここでは、遺体・遺骨の取り扱いについて詳しく解説します。
墳墓にある遺体・遺骨
遺体・遺骨が墳墓に収められている場合、祭祀財産である墳墓と一体をなすため、祭祀財産として祭祀承継者が承継するものと解されています。
墳墓に収められる前の遺体・遺骨
一方、墳墓に収められる前の(被相続人の)遺体・遺骨が誰に帰属するかについては、諸説あるのが実情です。
具体的には、相続人に帰属する説、慣習によって当然喪主となるべき者に帰属する説、被相続人の祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)に帰属する説などがあります。
例えば、最判平成元年7月18日判決では、墳墓に収められる前の遺体・遺骨の帰属について、遺骨の所有権が慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしました。
とはいえ、これはあくまで当該事件の事実関係に基づく判断なので、事情によっては、結論が変わる可能性も十分考えられます。
祭祀財産を廻って相続争いを防ぐ方法
祭祀財産を巡っては、相続人の間でトラブルになるケースも少なくありません。
ここからは、祭祀財産を巡る相続争いを防ぐための方法について、詳しく解説します。
遺言書であらかじめ祭祀承継者を決めておく
祭祀承継者は、祭祀の主宰となるなどの負担を伴うため、「できればやりたくない」と考える方も多く、遺産分割協議で争いのきっかけになることがあります。
そのため、被相続人が遺言書であらかじめ祭祀承継者を指名しておくのがよいでしょう。
被相続人の「この人に祭祀財産を任せたい」という意思が明確になっていれば、受け入れる側も受け入れやすいといえます。
生前に話し合っておく
生前から祭祀承継者が誰であるかを話しておくのもよいでしょう。
あらかじめ祭祀承継者を決めなければならないことや、どんな負担をしているかを知ったうえで話し合いをしておけば、トラブルを防ぐことが可能です。
さいごに
祭祀財産は、遺骨や仏壇、墓地などの「系譜・祭具・墳墓」に分類される特別な財産です。
そのため、一般的な相続財産とは異なり、遺産分割の対象にはなりません。
原則として、祭祀承継者が単独で引き継ぐことになります。
祭祀承継者は被相続人の指定が最優先され、指定された者は基本的に承継を拒否できません。
ただし、祭祀財産の具体的な管理や処分については、承継者の判断に委ねられています。
相続トラブルを避けるためにも、生前に被相続人と候補者との間で話し合いを行い、適切な祭祀承継者を決めておくことが重要です。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介