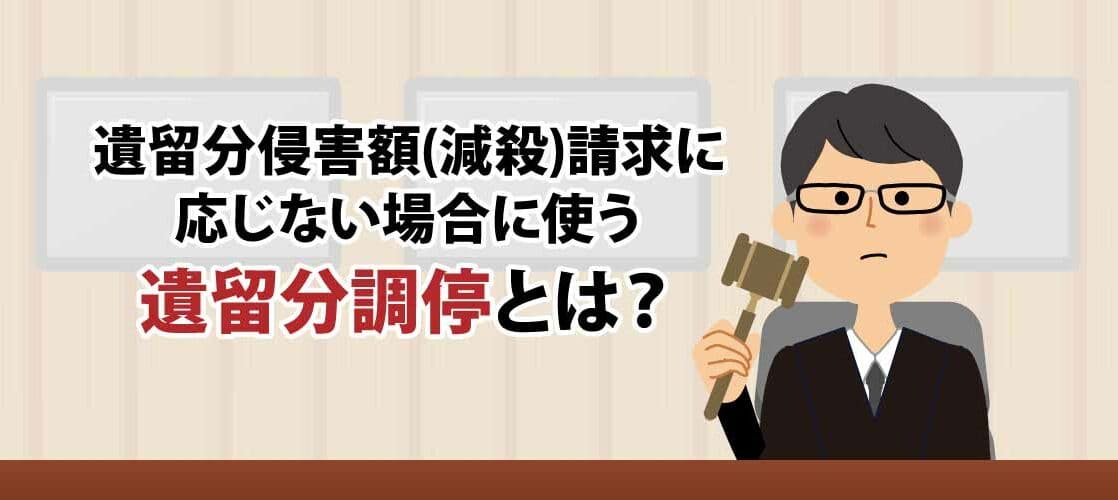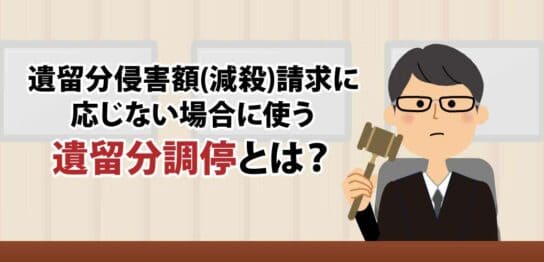はじめに
親や配偶者が遺言書で特定の相続人や第三者に多くの財産を残すと知ったとき、「自分の取り分が少なすぎるのでは」と不安になる方も少なくないでしょう。
相続人には、最低限の取り分を保障する「遺留分」が法律で認められており、侵害された場合には調停など法的手続きによって請求できます。
本記事では、遺留分侵害額請求の基礎知識から、家庭裁判所での調停手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
遺留分と遺留分侵害額請求について詳しく解説
被相続人は遺言をすることで、原則として自分の財産を自由に処分することができます。
そのため、相続人のうちの一人に全部を相続させる旨の遺言をすることや第三者に遺贈をする旨の遺言をすることも可能です。
しかし、贈与や遺贈などにより遺産を受け取れるはずだった方が遺産を一切相続できなくなってしまうと、相続人の生活保障などの観点から好ましくありません。
そこで、兄弟姉妹以外の相続人に、相続において最低限の取り分を保障しているのが遺留分です。
遺留分として保証されるのは、相続分の1/2(直系尊属のみが相続人になる場合には1/3)です。
例えば、4,000万円の遺産を母と子2名で相続した場合、法定相続分が1/2で2,000万円である母には、その1/2の1,000万円が遺留分として保障されています。
また、子どもには一人当たり500万円の遺留分が保障されます。
そして,遺留分を侵害された方が贈与や遺贈を受けた方に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権を行使するためには、相手方に対して「遺留分を支払え」と意思表示をすればよいです。
なお、遺留分侵害額請求権は、かつては遺留分減殺請求権と呼ばれる制度でした。
古い書籍やインターネット上の情報だと遺留分減殺請求権という名称になっている場合があるので、注意しましょう。
遺留分侵害額の請求調停とは?
遺留分侵害額の請求において、協議が難航したり、そもそも話し合いを拒否されたりすることがあります。
そのようなときは調停を申立てることで裁判所の関与の下で話し合いを行うことができます。
遺留分侵害額の請求調停について詳しく解説しましょう。
①当事者間で協議する
②遺留分侵害額の請求調停の申立てを行う
③調停で合意できなければ裁判を起こす
当事者間で協議する
まずは、遺留分侵害額請求を相手に行使して、支払い金額や支払い方法などについて協議をします。
遺留分侵害額の請求調停の申立てを行う
以下のような場合には、法的手段を取る必要があります。
・交渉をしても遺留分の額で合意が得られない
・支払い方法について合意が得られない
・そもそも交渉にも取り合わない
法的手段というと裁判を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、遺留分侵害額請求においては原則として、まず調停によって解決することを試みることとされています(調停前置主義)。
そのため、まず初めに遺留分侵害額の請求調停の申立てをします。
調停で合意できなければ裁判を起こす
調停で合意できない場合には裁判を起こして請求を行います。
裁判の最中に当事者間で和解を試みられますので、和解すれば和解案の内容で金銭の支払いを受けることになります。
裁判中に和解ができず判決に至った場合には、判決の内容の支払いを求めることになります。
なお、判決で遺留分侵害額請求に対して支払うべき旨が示されても支払わない場合には、強制執行することになります。
遺留分侵害額の請求調停を行うメリットは?
遺留分侵害額の請求調停を行うメリットは、主に以下の2つが挙げられます。
・お互い感情的ならずに話し合いを進められる
・解決策を提示してもらえる
詳しく解説します。
感情的ならずに話し合いを進められる
調停は調停委員会という裁判官1名・調停委員2名からなる組織が、当事者の主張を聞きながら合意を目指します。
お互いが顔を合わせて話し合うものではないので、感情的にならずに話し合いを進めることができます。
解決策を提示してもらえる
調停では当事者の意見を聞きながら、裁判官や調停委員が、第三者的な立場から解決案を提案してくれることもあります。
裁判官はもちろんですが、調停委員も相続に関する知識をもった方が就任するため、妥当な案の提案がされることで解決に向かいやすくなるでしょう。
遺留分侵害額の請求調停の手続きの流れ
遺留分侵害額の請求調停の手続きは、以下の流れで進められます。
①裁判外での話し合い
②家庭裁判所への申立て
③裁判所での話し合い
④調停の成立
⑤調停が成立しなかった場合
裁判外での話し合い
調停は当事者間での話し合いがまとまらない場合の裁判手続きですので、基本的には調停の前に裁判外での話し合いが行われます。
当事者間が直接協議する場合もありますし、弁護士が代理人として関与する場合もあります。
家庭裁判所への申立て
調停手続きを利用するためには、管轄となる家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
申立てを行うには、申立書と戸籍などの必要書類を郵送または持参して提出します。
裁判所での話し合い
調停委員を交えた話し合いが行われます。
調停委員は、申立人と相手方をそれぞれ交互に調停室に呼んでそれぞれの意向を聴取し、解決策を提示したり、解決のために必要なアドバイスを行ったりして、合意を目指します。
調停期日は何回に分けて行われます。
弁護士に依頼すれば,調停期日への参加はすべて弁護士が代理して行ってくれます。
調停の成立
調停により両当事者が合意に至れば調停成立となり、合意内容を記載した調停調書を作成します。
調停調書は判決と同じ効力がありますので、調停調書の内容どおりに金銭が支払われない場合には相手方の財産を差し押さえるなどして強制執行することが可能です。
調停が成立しなかった場合
話し合いがまとまらなければ調停は不成立となり、自動的に審判に移行します。
審判は調停のような話し合いが行われるのではなく、裁判官が事情を考慮して妥当と思われる判断をくだします。
遺留分侵害額の請求調停の申立て方法
遺留分侵害額の請求調停の申立てを行う場合には、申立書を作成し添付書類とともに提出する必要があります。
遺留分侵害額の請求調停の申立て方法について詳しく解説します。
・調停の申立方法
・申立書記載のポイント
・申立書の記載例
・請求調停にかかる費用
・請求調停に必要な書類
調停の申立方法
調停の申立ては、申立書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出して行います。
申立書は自身で作っても、裁判所のホームページからダウンロードしても、裁判所に出向いて書式をもらって記載しても問題ありません。
管轄の家庭裁判所は相手の住所地の家庭裁判所になります。
・「遺留分侵害額の請求調停の申立書」をダウンロードする
申立書記載のポイント
申立書の記載のポイントは、次のようなものがあります。・申立ての理由
・不動産について
不動産について
土地・建物についての記載事項は、不動産登記簿謄本を取り寄せて表題部に記載されている事項をそのまま記載します。取得した不動産登記簿謄本は、添付書類となります。
申立書の記載例は、 裁判所のホームページを参考にしてください。
請求調停にかかる費用
調停にかかる費用としては、以下の二種類があります。・手数料
・予納郵券
手数料は1,200円で、納入は収入印紙を購入して申立書に貼付する方法で行います。
予納郵券とは、書類の送付費として裁判所に納める郵便切手のことです。
金額は家庭裁判所によって異なるので、申立ての際に確認してみましょう。
請求調停に必要な書類
調停には、以下の書類が必要です。・申立書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・遺言書の写し
・検認調書謄本の写し
・遺産に関する証明書(預金通帳や不動産登記事項証明書など)
必要に応じて追加で必要な書類もあるので、裁判所に相談しながら進めるようにしましょう。
遺留分侵害額の請求調停の注意点
遺留分侵害額の請求調停をするにあたって、注意すべき事項には次のようなものがあります。
・相手の住所がわからない場合
・相手が出席しない場合
・テレビ会議システムの利用方法
・遺留分侵害額請求権が時効にならないように注意
・遺留分の問題を相談する弁護士の選び方
注意すべき事項について確認しましょう。
相手の住所がわからない場合
遺留分侵害額の請求調停をする場合には、相手の氏名と住所を特定する必要があります。遺言書で遺贈をするような場合には、相手を特定するために住所を記載するのが通常ですが、遺言書を作成したあとに住所が移転しているような場合もあります。
また、生前贈与をしたことが確認できても、相手の住所まではわからないケースもあるでしょう。
前の住所が分かっている場合には、住民票の除票を取得することで移転先がわかります。
また、戸籍を辿れるような場合であれば、戸籍の附票を取得することで現在の住所がわかります。
いずれも重大な個人情報で、理由なく取得することはできませんので、取得の際には遺留分侵害額請求をしようとすることを説明する必要があります。
弁護士に依頼すれば、職務上請求書というものを利用して取得することが可能になります。
相手が出席しない場合
調停が申立てられても相手が調停に出席しない場合、相手には5万円以下の過料が科せられることになっています。(不出頭に対する制裁)
第三十四条 裁判所又は調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。
引用元:民事調停法 | e-Gov 法令検索
しかし、この規定が適用されて相手に過料が科せられることはまれであり、相手が出席しないこともあります。
調停は双方の合意で成立するものであり、相手が出席しない場合には、合意ができない場合と同様に調停が不成立となります。
なお、そのあとに提起する裁判では、相手は出席しなければ敗訴することになるので、相手が裁判においても出席しなければ裁判で遺留分侵害額請求権の内容を確定することができます。
テレビ会議システムの利用方法
相続人が東京に住んでいて、大阪に住んでいる方に対して遺産が全部遺贈された場合、遺留分侵害額の請求調停は相手の住所地である大阪の裁判所に対して申立てをすることになります。
調停のたびに大阪まで出向く必要があるため、大きな手間や費用がかかります。
このような場合には、テレビ会議システムを利用することで、手間や費用を抑えることが可能です。
テレビ会議システムといっても自宅のパソコンを利用して行うわけではなく、テレビ会議システムを設置している近くの裁判所まで出向く必要があります。
なお、テレビ会議は裁判所が適当と判断した場合のみに利用できます。
必ずしも利用できるわけではないという点に注意が必要です。
遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権は遺留分の侵害を知った日から1年ないし相続開始から10年で時効により消滅します。
時効になると調停・裁判でも請求を認めてもらえません。
遺留分侵害額請求権の時効は、相手に請求を行うことで通常の金銭債権となるため、まずは請求を行って時効にならないようにしましょう。
時効を阻止する方法としては、相手に対して遺留分侵害額請求をする旨の配達証明付き内容証明を送ることです。
これによって遺留分侵害額請求をしたことと、その通知が期限内に相手に届いたことを証明できます。
弁護士の選び方の注意点
遺留分については、額がいくらになるのか、どの手続きで請求するのかなどの法的問題があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の選び方として、遺留分を含めた相続問題に取り組んでいることを示しており、相続問題に多くの実績がある事務所を選ぶようにしましょう。
相続問題に取り組んでいるかどうかは、ホームページに掲載されている相続問題の解決実績や口コミ・評判などから判断することができます。
さいごに
遺留分は法律により相続人に認められた正当な権利ですが、遺留分を侵害されても権利を行使しなければ遺留分を手に入れることはできません。遺留分侵害額請求権を行使したにもかかわらず相手方が支払いをしない場合には裁判外で交渉を行い、それでも支払いがされないときは裁判所に調停を申立てる方法があります。
弁護士に依頼すれば,調停の申立てや期日の参加もすべて任せることができます。
遺留分について悩んでいる方は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

- 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
- 遺言の内容に納得できない
- 遺留分の割合や計算方法が分からない
- 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続放棄・限定承認空き家を相続する際の話し合いのコツを確認
- 2025.10.29相続全般親が経営していた賃貸マンション・アパートを相続したときの手続きなど解説
- 2025.10.20相続手続き代行【タイプ別】遺産相続における寄与分の計算方法をわかりやすく解説
- 2025.09.22相続全般相続の寄与分と遺留分の関係を解説!トラブル防止のポイントも紹介