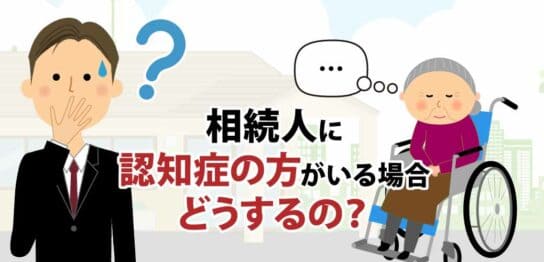- 成年後見制度の概要
- 成年後見人について
- 成年後見人になる手続き
【Cross Talk 】認知症になった母のため私は成年後見人になれますか?
私の母親が認知症になってしまい、成年後見制度の利用を考えています。 父は既に他界しており、子どもは兄である長男と私だけです。長男は母と同居しているのですが、とにかく忙しいみたいで、母の面倒は兄の妻が主にみているようです。 兄は多忙なので私が成年後見人になれますか?
誰が成年後見人になるかは最終的には家庭裁判所が決めますが、候補者として申立ての時に名乗り出れば考慮されます。
そうなんですね、成年後見についてもっと詳しくお伺いしても良いですか?
高齢や認知症などが原因で判断能力が低下し生活に支障をきたすことがあります。契約などの法律行為は生活に必須ですが、民法3条の2は意思能力を欠く法律行為は無効としています。 そのため、本人が円滑に生活を送れるようにするため成年後見制度というものがあります。 成年後見制度において成年後見人は本人の代理をしたり、本人がした法律行為を取り消したりすることができます。 このページでは成年後見人には誰がなれるのか、また、成年後見人就任までの手続きはどうなっているのかを詳しく解説いたします。
成年後見制度の概要

- 成年後見制度の概要
- 誰が成年後見人になれるのか
成年後見という制度が保護者になれるくらいの理解しかないのですが、どのような制度か詳しく教えてもらえますか?
成年後見の基本を確認しましょう。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、本人が法律行為を行うための判断能力を欠く状態となったときに、生活に困らないように成年後見人が保護者となって本人の財産管理・身上監護を行う制度のことをいいます。 医療サービスの利用、家を借りるなど、生活を送るにあたって法律行為は欠かせません。
法律行為は正常な判断ができることが前提となり、自分のした法律行為の意味を認識する能力(意思能力)がない方の行為は無効となる旨が民法3条の2に規定されています。 加齢や認知症が原因で判断能力が低下することによって、法律行為ができなくなったときに、未成年者における親権者のように、成年後見人という保護者をつけるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、民法が規定する法定後見のほかに、後見人となる方を判断能力が十分なうちに選んでおく任意後見があります。
関連記事:成年後見人になるには?誰がなれるのか手続きは?弁護士が解説
成年後見人ができること
財産の管理
成年後見人は、被後見人の預貯金、不動産、有価証券等の財産管理を行うほか、被後見人の預貯金から必要な支払い等も可能です。
これらの財産管理は成年後見人の判断で行うことができますが、居住用の不動産の売却等をする場合には、例外的に家庭裁判所の許可が必要とされています。
身上監護業務
後見人は、被後見人の日常生活に関する身上監護業務も行います。
ここでいう身上監護とは、被後見人の住居の確保や、被後見人が入院や施設に入所する際の病院や施設との契約等の手続きを行うことであり、成年後見人が被後見人の介護や身の回りの世話をするという意味ではありません。
また、成年後見人には医療同意権がないので、被後見人が手術を受けるか等については、成年後見人ではなく親族等の同意が必要です。
家庭裁判所への報告
成年後見人に選任されると、まずは被後見人の財産や収支予定等を調査して、家庭裁判所に報告する必要があります(就任報告)。
その後も成年後見人は、年に1回、その年に行った後見事務の内容や被後見人の財産や収支の変化等を家庭裁判所に報告しなければなりません(定期報告)。
最後に、被後見人の死亡等によって後見が終了した場合、被相続人の財産を相続人に引き継いだうえで家庭裁判所に終了の報告をします(終了報告)。これら以外にも、被後見人の生活状況や財産に大きな変化がある場合等は、適宜報告することがあります(臨時報告)。
資格が必要?成年後見人になれる人とは

- 民法上は成年後見人になるために何らかの資格を必要とされていない
- 事案の内容によっては弁護士、司法書士などの専門職が選任されることがある
成年後見人にはどんな方がなれるのですか?何か資格が必要になるのでしょうか?
民法上は成年後見人になるために特別な資格などは要求されていないため、法律上は誰でも成年後見人になれます。ただし、被後見人が多額の財産を持っている場合、親族間に対立がある場合、専門的知識を必要とする事務が予定されている場合などは、弁護士などの専門職が成年後見人に選任される可能性があります。
民法上、成年後見人になるために特別な資格は必要ないため、法律上は誰でも成年後見人になることができ、実際に特に資格を持たない親族が成年後見人に選任されるケースは少なくありません。
ただし、以下のケースでは、親族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任される可能性が高くなります。
- 被後見人が多額の財産を所有している場合
- 親族間に対立がある場合
- 専門的知識を必要とする事務が予定されている場合
成年後見人になれない人

- 民法が成年後見人の欠格事由を定めている
- 未成年者、後見人等を解任されたことがある者、破産者等が欠格事由に該当する
成年後見人になれる方はわかりましたが、逆に成年後見人になれない方はいますか?
民法に定める欠格事由に該当する方は、成年後見人になることができません。民法が定める欠格事由は、未成年者、過去に後見人等を解任されたことがある者、破産者、被後見人に対し訴訟をした者やその者の配偶者等、行方不明者の5つになります。
民法は、法律上当然に成年後見人になることができない欠格事由を定めています(民法847条)。
成年後見人は、被後見人の財産を管理し、身上監護に関する事務を行うため、相応の能力が求められます。
そのため、成年後見人の職務を適正に行うことが期待できない方をあらかじめ除外しておく必要があります。そこで設けられたのが欠格事由です。
民法で定める欠格事由は、次の5つです。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした方、並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない方
「免ぜられた」=「解任された」であり、過去に家庭裁判所から解任された(元)後見人等は、後見人として適性に問題があるため、欠格事由とされています。
破産者は、自己の財産の管理が不適当であった方が被後見人の財産を管理することは被後見人の利益にならないことから、欠格事由とされています。
被後見人に対して訴訟をし、またはした者等は、被後見人と利害が対立するか、感情の融和を欠くため、被後見人のために誠実に職務を遂行することが期待できないので、欠格事由とされています。
成年後見人になるための手続きの流れ

- 成年後見人になるための手続きの流れ
- 成年後見人の推薦
では具体的に成年後見人になるための手続きを教えてください。
成年後見の申立てについて確認しましょう。
本人の判断能力の低下
成年後見人になるためには成年後見制度の申立てをするところから始めます。
成年後見制度は本人が高齢や認知症などが原因となって判断能力が低下したときに利用されます。
どの程度の判断能力にまで低下すると成年後見を利用するかについては、民法7条が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と規定しています。
目安となるのが、認知機能に関する検査である長谷川式簡易知能評価スケールというもので、20点以下になると認知症の可能性が高いといわれており、10点以下になると上記の状態であると判断されることが多いといえます。
申立て
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」といえる状態になると、自動的に成年後見が始まるわけではなく、家庭裁判所に申立て、審判を経て成年後見が始まります(民法7条)。
民法7条は、本人・配偶者・4親等内の親族などの請求によって審判をすることになる旨を規定しています。
書面を作成し、資料を添付して申立てを行います。
この際に、成年後見人に候補者として推薦する人がいる場合には、その旨の書面(東京家庭裁判所の場合には後見人等候補者事情説明書)を作成して提出します。
成年後見開始の審判
申立て書類をもとに成年後見開始の審判がされると、成年後見が開始され、成年後見人としての事務が始まります。
まとめ
このページでは、成年後見人とはどのような人か、誰がなれるのか、成年後見人が選ばれる手続きなどについてお伝えしてきました。
不明な点がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

- 判断力があるうちに後見人を選んでおきたい
- 物忘れが増えてきて、諸々の手続きに不安がある
- 認知症になってしまった後の財産管理に不安がある
- 病気などにより契約などを一人で決めることが不安である
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.01.28相続全般寄与分の相場はいくら?タイプ別の計算方法を解説
- 2025.11.26遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を行う場合の不動産の評価はどのように行うのか
- 2025.10.29相続全般個人事業主が亡くなった場合の相続手続きはどうなるの?
- 2025.10.22遺言書作成・執行遺言書を紛失した場合にはどう対応すればいいか?