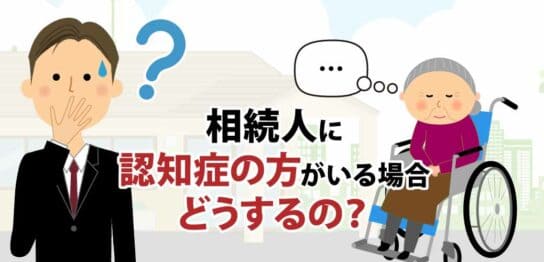- 法定相続分の計算
- 個別の事情に応じた調整
- 最終的な相続分の決定
【Cross Talk】子どもが相続する場合相続分を最終的にどうやって決めれば良いのでしょうか。
父が亡くなり、私たち子ども3人と母で相続をすることになりました。今までの知識から母が1/2残りの1/2を私たち子ども3人で分けるというのは分かるのですが、遺産には不動産や車などもあり、そんなに綺麗に割り算ができるわけではないですよね?どうやって相続分を最終的に決めているのでしょうか。
法定相続分を計算し、寄与分や特別受益で調整をして、それを参考に遺産分割協議をすることになります。
なるほど!詳しく教えてもらって良いですか?
相続において典型的な事例である子どもが相続する場合において、最終的に相続分をどのように決めていけば良いのでしょうか。 一般的な知識として、配偶者は1/2、子どもは残り1/2を頭数で分けるという知識をもっている方は多いでしょうが、遺産が全て銀行預金や現金のような分けやすいものでない限り、綺麗に分けることも難しいでしょう。 最終的な相続分が決まるまでの法律・実務的な流れを確認しましょう。
そもそも子どもとは?両親が離婚した場合や再婚した場合は?

- 法律上相続において子どもとなる人
- 離婚・養子縁組・認知されていない場合
そもそも法律上子どもとされるのはどういう人なのでしょうか。
民法772条以下の子に関する規定を確認しましょう。
相続において子となる人についてはどのような規定が置かれているのでしょうか。
相続人となる子どもとは
民法887条1項では、子どもは相続人となることが規定されています。 法律上の子どもについては、親子関係について定める民法772条以下に規定があり、子どもについては嫡出子・非嫡出子を問いません。 なお、子どもは通常既に出生した後の方についていい、まだ生まれていない胎児について含まないのですが、民法886条は相続においては例外的に既に生まれたものとみなして子どもとして扱うことが定められています。両親が離婚した場合
両親が離婚すると、子どもは一方の親権に服することになります(民法881条3項など)。 日本では多くの場合、母親が親権を獲得するのですが、この場合でも父と子の親子関係が終了するわけではありません。 両親が離婚した場合、親権者とその子どもが相続人となることはもちろん、親権者ではない親との間でも従前通り子どもとして相続人となります。両親が離婚して再婚した場合
両親が離婚して再婚した場合も、子どもは相続人となります。 離婚をして親権を相手の配偶者に渡した親が、再婚して別の家庭を持つことも多く、この場合前婚との間の子どもとは連絡をとらなくなることが多いです。 離婚や再婚によって子どもが法律上の子どもとしての地位を失う規定はなく、従来通り子どものままです。 そのため、その方が亡くなると、後婚の配偶者・子どもが相続人となることはもちろん、前婚との間の子どもも相続人として共同相続人となります。 相続争いに発展することが多いので、遺言をしておくなどのきちんとした対策をしておくことが推奨されます。養子縁組の子がいる場合
養子縁組によって法律上の親子関係が生じることになります。 そのため、養子は子として相続人となります。 なお、養子には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組では元々の親子関係は消滅しないのに対して、特別養子縁組では元々の親子関係が消滅します。 そのため、普通養子縁組をした場合、子は実親のみならず養親の遺産も相続することができるのに対して、特別養子縁組の場合は養親の遺産のみを相続することができるにとどまります。父に認知されていない子どもがいる場合
父に認知されていない子どもがいる場合、その子どもは法律上の子どもとはならないので相続人とはなりません。 もし子どもが認知の訴えを起こし、これが認容されると子どもとして相続人になります。子が相続人になるときの法定相続分

- 法定相続分のおさらい
- 代襲相続の場合
- 相続欠格・廃除があった場合の処理
まず、法定相続分について細かい話も含めたことをお伺いしてもいいですか?
代襲相続があった場合や相続欠格・廃除があった場合の処理も含めて確認しましょう。
子が相続人になるときの法定相続分について確認しましょう。
配偶者がいる場合
配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2とされています(民法900条1号)。 子が複数いる場合には、1/2の相続分を子の人数で割ります。 本件の相談者のように子が3人いるというケースでは1/2÷3で、各人が1/6ずつとなります。 子は、法律上被相続人の子供であるといえる場合であれば、たとえ前婚中の子や、婚外の子でも相続人になります。配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、子の人数で分割をします。子が3人のケースでは、1/3ずつとなります。子どもが既に亡くなっている場合
もし、親が亡くなった際に子どもがそれよりも先に亡くなっていたような場合、子どもにさらに子どもがいる(親からすれば孫)場合には、代襲相続が発生して孫が自分の親の代わりに相続します。孫が複数居る場合には親の相続分を孫の人数で割ります。 配偶者および子どもが3人いて、子どもの1人が既に亡くなっており、既に亡くなっている子どもにさらに子どもが2人いる場合には、配偶者が1/2・子ども2人が1/6ずつで、孫2人が代襲相続として1/12ずつ相続することになります。相続人になれない場合
子どもではあるものの、相続人になれない場合を知っておきましょう。 まずは、相続欠格です。 たとえば、遺産目当てに親を殺害した子どもに相続を認めるべきでないのが通常です。このように相続を認めるべきでない場合を規定し、そのような状態にあてはまる人に相続させない制度が相続欠格です(民法891条)。
次に、相続人の廃除です。 相続欠格がないような場合でも、非行を繰り返していたなど、被相続人として相続をさせたくない、という場合もあります。このような場合、家庭裁判所に相続人の廃除を申立て、これが認められればその方は相続をすることができなくなります(民法892条)。 最後に相続放棄です。 遺産がなく借金しかないような場合や、相続争いに巻き込まれたくないような場合には、相続放棄を家庭裁判所に申述することで、相続人ではなかったこととして扱われます(民法938条)。相続欠格と相続人の廃除があった場合には代襲相続が発生しますが、相続放棄の場合には代襲相続は発生しないなど、制度による違いもあります。
法定相続分の次に個別の事情に応じて調整を行う

- 法定相続分を確定してから個別の事情に応じた調整をする
- 寄与分と特別受益の概要
相続分については理解しました。ただ、私は自営だった父の後継ぎのような形で父の店の資金援助をするなどしてお店を一緒に守ってきた一方で、次男は自宅の新築費用に何千万も父に出してもらっています。これで相続分が一緒というのも少し納得がいかないのですが……。
そのような個別の事情に対応するために寄与分・特別受益という制度があります。
法定相続分についての規定を確認した上で、本件の相談者のように個別の事情に対応する規定があるので確認しましょう。
寄与分
たとえば、相続人である子の一人が親の介護を何十年もしていたような場合、親はその分長期にわたりヘルパーを雇わなくても済むことになり、多額の支出を免れたといえます。また、親が自営業をしていて、仕事を手伝っていたような場合には、お金が増えるのを手伝っていたといえます。遺産が出ていくのを抑えたり、資産を増やしたりしたような事情がある場合にはそれを相続で考慮すべきとして規定されたのが寄与分の規定です(904条の2)。詳細は「寄与分とは?親の介護をしたら相続分が増える?嫁が介護していたら?」で解説しておりますので参照してください。
特別受益
子の中には、本件の相談者のように、医学部卒業のための高額の学費を全部出してもらった、家の購入資金を贈与してもらった、結婚式のためのお金を工面してもらったなど、自分のための多額の支出を親にしてもらうようなことがあります。子供が複数いる中で一人だけそのような恩恵を受けていて、相続する際に相続分が一緒というのは不公平です。このような恩恵のことを「特別受益」といい、特別受益を受けていた者は、相続の際に具体的な相続分を差し引かれることになります。詳細は「相続の特別受益とその持ち戻しとは?学費や生命保険は含まれる?」を参照してください。
遺産分割協議で最終的な相続財産を決定する

- 最終的な相続分は遺産分割協議で決める
- 遺産分割協議が調わない場合
具体的な調整についてはわかりました。ではこれらをふまえて最終的にはどうやって相続の話を決めるのでしょうか。
まずは遺産分割協議で、遺産分割協議が調わない場合には調停・審判を利用して決めます。
上述の法律の規定によっても、綺麗に遺産を分配できるわけではありません。 法律の規定から形式的に適用される金額で絶対に分けなければならないというわけではないので、預金の一部をもらえればそれ以外の遺産に対する主張はしない、というような場合ももちろんできます。
遺産の中に居住用不動産があり、それが遺産の大部分を占めるような場合、その所有権を相続する人は他の相続人との不均衡をどう是正するかなども問題なります。誰がどの程度相続するのか、法律を参考にしながら、当事者同士の遺産分割協議で決定することになります。 もし遺産分割協議が調わない場合には遺産分割調停・審判において決定していくことになります。
子どもの遺留分

- 遺留分は法定相続分をベースに計算される
- 遺留分の額は法定相続分の1/2
遺留分は法定相続分の1/2でしたよね?
はい。法定相続分がいくらなのかは遺留分の額の計算という観点からも重要ですね。
被相続人が遺言や生前贈与で、特定の相続人や第三者に全てを遺贈するような場合があります。 このような場合、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求を行うことができます。 子どもが相続人である場合の遺留分は、子どもの法定相続分の1/2とされており(民法1042条1項2号)、遺留分の計算をするにあたって法定相続分がどれだけなのかが計算の基礎となります。 例えば、父・母・子ども2人の場合で、父が亡くなり遺産が1,000万円である場合、子の相続分は1/4となり、その1/2が遺留分となるので、遺留分は125万円となります。
子が全員相続放棄した場合の相続人と法定相続分もチェック

- 子どもが全員相続放棄した場合次順位の相続人に相続権がうつる
- 親・兄弟姉妹が相続人のときの法定相続分
子どもが全員相続放棄した場合どうなりますか?
子どもがいないと扱うことになり、親・兄弟姉妹と次順位の相続人に相続権がうつります
子どもが全員相続放棄した場合、相続人は誰になるのでしょうか。またその場合の法定相続分はどうなるのでしょうか。 相続放棄をすると、法律では最初からその相続人がいなかったものとして扱うことになっています(民法939条)。 そのため、子ども全員が相続放棄をすると、最初から子どもがいなかったことになり、次順位の相続人に相続権が移ります。 第二順位の相続人:親などの直系尊属 第三順位の相続人:兄弟姉妹 なお、配偶者も兄弟姉妹もいない場合には、相続人の不存在という手続きを経て、特別縁故者への配分や、特別縁故者がいない場合には国のものになることになります。
親が相続人となる場合と法定相続分
親などの直系尊属が相続人となる場合、配偶者との法定相続分は、配偶者2/3・親などの直系尊属が1/3となります。 両親ともに健在である場合には親の分の1/3を1/2で割ることになるので、1/6ずつが法定相続分となります。兄弟姉妹が相続人となる場合法定相続分
兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者と共同相続する場合の法定相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹が1/4で、兄弟姉妹がいる場合には1/4をその頭数で割ることになります。 例えば、夫が亡くなり妻と兄弟姉妹3人が相続人である場合には、妻が3/4兄弟姉妹はそれぞれ1/12ずつとなります。まとめ
このページでは、子供が遺産を相続する場合の相続分についてお伝えしてきました。特に寄与分がいくらなのか、特別受益がいくらなのか、については遺産分割協議で揉める可能性もあり、その揉め事が原因で遺産分割協議ができなくなるということもあります。相続分の計算や交渉が難しい場合にはぜひ弁護士にご相談ください。

- 遺産相続でトラブルを起こしたくない
- 誰が、どの財産を、どれくらい相続するかわかっていない
- 遺産分割で損をしないように話し合いを進めたい
- 他の相続人と仲が悪いため話し合いをしたくない(できない)
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29遺言書作成・執行公正証書遺言とは?作成の流れ・費用についてわかりやすく解説
- 2025.10.27遺産分割協議両親が離婚した・再婚するとどうなる?子どもが相続する場合の相続分について弁護士が解説
- 2025.10.27遺産分割協議相続人がいない場合に必要な相続財産清算人とは?
- 2025.04.18遺留分侵害請求遺留分侵害額請求を拒否できる?弁護士が解説