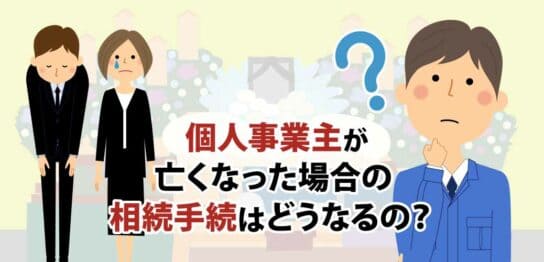- 任意後見人ができること・できないことは?
- 任意後見人をつけるメリット・デメリットとは?
- 任意後見人になれる人とは?
【Cross Talk 】任意後見人ができることはどのようなことですか?
任意後見人ができることとは、どのようなことでしょうか?
任意後見人の権限は、財産管理と身上監護です。
任意後見人のできること・できないことについて、詳しく教えてください。
ご自身の老後の生活や財産管理の不安から、任意後見人をつけることを検討されている方もいらっしゃると思います。任意後見制度は、ご自身の意思が明確なうちに将来の安心を確保しておくことができますが、具体的にどのようなことができて、誰に頼めるのかわからないという方も多いと思います。 そこでこの記事では、任意後見制度の基本から、任意後見人ができること、できないこと、任意後見人になれる人の条件などについて、弁護士が解説していきます。
任意後見人とは?

- 任意後見制度とは?
- 任意後見と法定後見の違いとは?
任意後見とはどのような制度ですか?
ここでは、任意後見制度の概要や法定後見との違いについて解説していきます。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来的に自身の判断能力が低下した場合に備え、精神的に健康で十分な判断能力があるうちに、あらかじめ「誰に」、「どのような内容で」財産管理や身上監護に関する事務を任せるかを自分で決めておくことができる制度です。この制度を利用するには、将来的に支援を受ける人と、その方から信頼された任意後見人となる人との間で、「任意後見契約」を公正証書で締結します。 この契約は、締結しただけでは効力が発生しません。本人の判断能力が実際に低下したと家庭裁判所が判断し、任意後見人が契約内容通りに職務を遂行しているかを監督する「任意後見監督人」が選任されて初めて、その効力が生じます。これにより、任意後見人は契約で委任された範囲内で、本人の代わりに様々な事務を行うことができるようになります。関連記事:任意後見制度の基礎知識・手続きの流れとその他概要について解説
任意後見と法定後見の違い
判断能力が低下した方を支援する制度として、「任意後見」と「法定後見」の二種類があります。 任意後見は、将来の判断能力低下に備えて、本人が元気なうちに自らの意思で後見人を選び、契約を結んでおく制度です。本人の意思が最大限に尊重される点が特徴です。 これに対し法定後見は、既に本人の判断能力が低下している状況において、家族などの関係者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つの類型があり、それぞれ後見人等に与えられる代理権や同意権、取消権などの権限が異なります。 特に重要な違いとして、任意後見人には原則として法律行為を取り消す「取消権」がありません。 例えば、本人が悪質な契約を結んでしまった場合でも、任意後見人はその契約を取り消すことができないため、別途法定後見の利用を検討する必要が生じる場合があります。この点が、両者の制度設計における大きな相違点といえるでしょう。関連記事:法定後見と任意後見二つの成年後見制度の違いについて解説
任意後見人ができること

- 任意後見人ができることとは?
- 財産管理と身上監護とは?
任意後見人ができることはどのようなことでしょうか?
ここでは、任意後見人の権限の範囲について解説していきます。
財産管理
任意後見人が本人を支援するために行える事務は、大きく「財産管理」と「身上監護」の二つに分けられます。財産管理とは、本人の資産を守り、適切に管理・運用していくための法律行為全般を指します。具体的な業務内容には以下のようなものが含まれます。関連記事:財産管理委任契約とは?委任できる内容やメリット・デメリット、手続きの流れ
身上監護
身上監護とは、本人の健康や生活に関する契約や手続きを通じて、日常生活を支援するための法律行為を指します。任意後見人は、本人の身体の自由を拘束したり、医療行為について同意したりすることはできませんが、以下のような業務が可能です。任意後見人ができないこと

- 任意後見人ができないこととは?
- 契約の取消しや死後事務、介護などは任せられない
それでは、任意後見人ができないことはどのようなことですか?
ここでは、任意後見人ができないことを解説していきます。
次に、任意後見契約は本人が死亡した時点で効力を失うため、本人の死後の事務を行うことはできません。 具体的には、死亡届の提出、葬儀の手配、遺品整理、相続手続きなどは、任意後見人の職務範囲外となります。これらの死後事務を任せたい場合は、別途「死後事務委任契約」を締結するなど、別の方法で手配しておく必要があります。
また、任意後見人は医療行為への同意や、病院・施設への身元保証人になることは原則できません。手術や延命治療に関する同意は本人の身体に関わる非常に重要な判断であり、法的な根拠がないため任意後見人が代行することは認められていません。
さらに、日常生活における身体介護や家事などの「事実行為」は、任意後見人の職務には含まれません。任意後見人が行うのはあくまで「法律行為」であり、例えば介護サービスの契約はできても、実際の入浴介助や食事の準備、通院の付き添いといった直接的な介護は、介護事業者やヘルパーに依頼する必要があります。任意後見人をつけるメリット

- 任意後見人をつけるメリットとは?
- 本人が後見人を選べる
任意後見人をつけるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、任意後見制度を利用することのメリットを解説していきます。
自らの意思で後見人を選定できる
任意後見制度のメリットは、本人が自らの意思で、将来の任意後見人を選べる点です。 法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも本人の希望通りの人物が選ばれるとは限りません。見ず知らずの専門家が後見人となる可能性もあり、財産管理を任せることに抵抗を感じる方も少なくありません。 しかし、任意後見では、信頼できる子どもや兄弟姉妹、友人、あるいは弁護士など、本人が最も安心できる人物を自由に選任することができます。これにより、本人の生活状況や価値観を理解し、きめ細やかな配慮をしてくれる方に、安心して将来を託すことが可能になります。関連記事:任意後見人を選任する手続きの流れと必要書類について解説
任意後見人の仕事を監督してもらえる
任意後見制度では、任意後見人が実際に職務を開始する際に、家庭裁判所によって必ず「任意後見監督人」が選任されます。
任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約の内容に従って適切に事務を行っているかを定期的にチェックし、家庭裁判所へ報告する義務を負っています。任意後見人と本人の利益が相反するような状況が発生した場合には、任意後見監督人が本人を代理するため、本人の利益が保護されるのです。契約内容がある程度柔軟に決められる
任意後見契約は、当事者間の合意に基づいて内容を決定する「契約」であるため、本人の希望に応じてその内容を比較的柔軟に定めることが可能です。 どのような財産の管理を任せるか、どのような医療・介護サービスを受けたいか、どのような生活を送りたいかなど、具体的なライフプランや価値観を契約書に詳細に盛り込むことができます。関連記事:任意後見制度のメリット・デメリットについて解説
任意後見人をつけるデメリット

- 任意後見人をつけるデメリットとは?
それでは、任意後見人をつけるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、任意後見制度を利用するデメリットを解説していきます。
判断力が低下しないと発効できない
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えるための契約ですが、実際に任意後見契約が効力を発生し、任意後見人が職務を開始するためには、本人の判断能力が実際に低下していると家庭裁判所が判断し、任意後見監督人が選任される必要があります。契約を締結しただけでは、すぐに任意後見人のサポートが始まるわけではありません。そのため、契約したらすぐに財産管理を任せたいという場合には、任意後見契約と同時に、財産管理委任契約を結ぶ必要があるでしょう。
本人の死後に権限が及ばない
任意後見契約は、本人が亡くなった時点で自動的に終了します。したがって、任意後見人は、死亡届の提出、葬儀の手配、遺品整理、相続手続きなどを行う権限を持ちません。 本人の死後にこれらの事務を特定の人物に任せたい場合は、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。この点は、任意後見制度が「生前の支援」に特化した制度であることを理解しておく上で非常に重要です。任意後見監督人選任の申立てが必要
任意後見制度を開始するには、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。 任意後見監督人は、任意後見人が職務を適正に行っているかを監督する重要な役割を担います。家庭裁判所が選任するため、親族以外の弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが一般的です。 この任意後見監督人には、本人の財産から毎年その報酬を支払わなければならないという点も経済的なコストといえるでしょう。任意後見人になれる人

- 任意後見人になれる人とは?
- 弁護士を任意後見人に指定することができる
任意後見人になれるのはどのような方なのでしょうか?
ここでは、任意後見人になれる方について解説していきます。
成年者であること
任意後見人になれる方として、成年者であることが必要です。 これは、未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、本人を支援する立場として適格ではないからです。成年者であれば、原則として任意後見人となる資格を有します。 しかし、単に成年者であるというだけでなく、実際に任意後見人として長期にわたって職務を遂行できるかどうかを慎重に検討する必要があります。法律に定められた欠格事由に該当しないこと
任意後見人になれる方には、法律で定められた欠格事由に該当しないことが求められます。具体的には、以下のいずれかに該当する人は任意後見人になることができません弁護士を任意後見人に指定することもできる
家族や親族の中に適任者がいない場合や、親族間のトラブルを避けたいと考える場合は、弁護士などの専門家を任意後見人に指定することも可能です。 弁護士は、法律に関する専門知識と豊富な実務経験を持っており、財産管理や契約手続きなど、多岐にわたる任意後見業務を適切かつ円滑に遂行することができます。財産規模が大きい場合や、親族関係が複雑な場合などには、専門家である弁護士に任意後見人を依頼することを検討してください。まとめ
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備え、元気なうちに自ら後見人を選び、財産管理や身上監護の内容を契約で定める制度です。ただし、法定後見とは異なり、取消権がない点や死後事務ができない点に留意が必要です。 メリットとしては、後見人を自分で選べること、任意後見監督人による監督があること、契約内容を柔軟に決められる点が挙げられます。任意後見人には成年者で欠格事由に該当しない人のほか、弁護士を指名することも可能です。 当事務所には任意後見に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2025.10.29相続全般相続分の譲渡とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、税金や方法について解説
- 2025.10.27遺産分割協議遺産分割協議書とは?なぜ必要なのか記載の注意点や文例などについて解説
- 2025.10.20相続全般任意後見人ができること・できないこと|なれる人の条件について
- 2025.09.25成年後見成年被後見人は遺言を作成できるのか